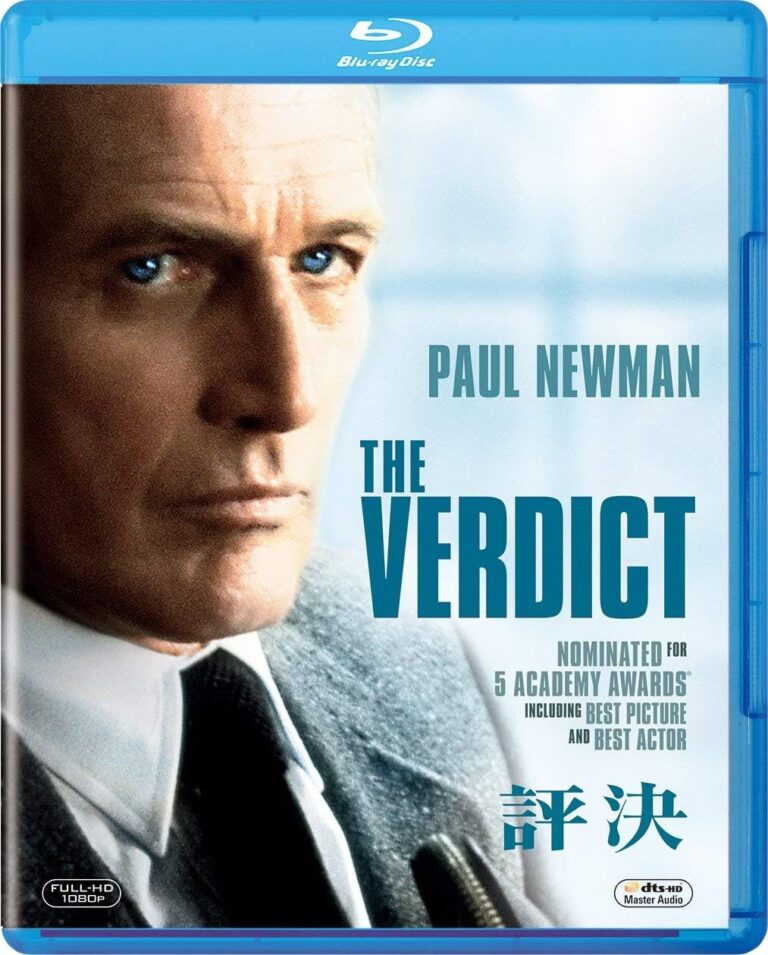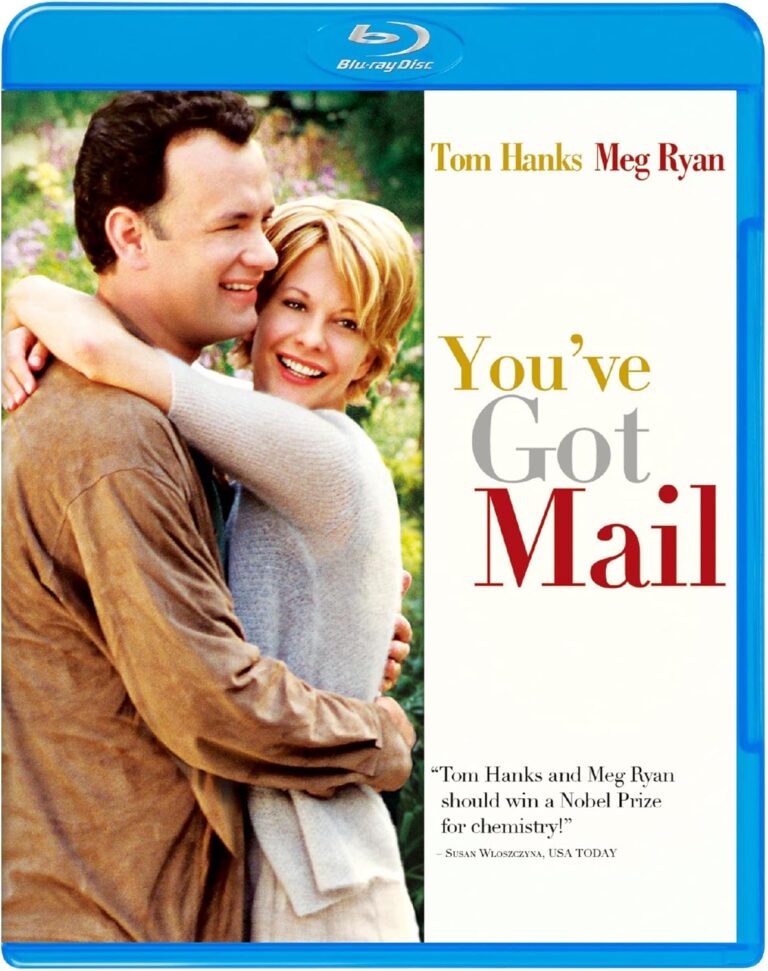『メリーに首ったけ』(1998)
映画考察・解説・レビュー
『メリーに首ったけ』(原題:There’s Something About Mary/1998年)は、かつてプロムに誘えなかった女性メリーを忘れられないテッドが、十数年後に彼女の居場所を調べるため探偵ハイモアを雇うことから始まるロマンティック・コメディ。だが調査を依頼したはずのハイモアもメリーに惹かれ、彼女の周囲には複数の男性が集まり、それぞれが思惑を抱えながら接近していく。
欲望の座標軸としてのメリー──“好かれる女”の構造
キャメロン・ディアスが演じるメリーという存在は、コメディの中心に据えられながらも、物語的には“欲望の座標軸”としての意味合いが濃い。
つきぬけるような笑顔、ある種の天真さ、そして他者を無条件に包み込む母性的な気配が並列され、男性キャラクターの視線と欲望を一身に集める。
その造形はステレオタイプに見えながら、主演の身体性が演出の枠を自然に超えてしまうことで、イメージの固定化を拒み、逆に作品全体の重力場を形成している点が興味深い。
ディアスが“少しおバカで、セクシャルに奔放で、判断基準も軽やか”というキャラ設定を引き受けるとき、彼女の身体は単なる男性視線の対象には留まらず、作品そのもののテンションを支えるエネルギー源に変換されていく。
喜劇はしばしば役者の身体の強度に依存するが、この作品におけるディアスはその典型で、下世話なギャグを次々と受け止めながらも、決して役の dignity を喪失しない。
だからこそ、彼女自身への好意と、メリーというキャラクターへの好意が型のように重なり合い、観客の感情回路にも短絡的に作用する。
物語の基底には“誰もがメリーに惚れるのは必然だった”という前提が伏在し、その必然性を可能にしているのが、ディアスの演技が持つ透明度と反射率の高さなのだ。
彼女は物語に漂う卑俗さや過剰なテンションを吸収し、光に変えるプリズムのような役割を担っている。彼女がベン・スティラーという“負け組”に属する男性を最終的に選ぶ構造も、ロマンティック・コメディが長らく利用してきた“救済の物語”の変奏として理解できる。
差異化された男女像、格差、欲望の非対称性。そのすべてを、メリーという存在が軽やかに統合してしまう。
下品さの操作とファレリー兄弟の暴力的ユーモア
ファレリー兄弟が得意とする“下品さの操作”は、本作でも極端な形で露出している。
動物虐待スレスレのギャグ、障害者を巡る過激なネタ、そしてジェル代わりに精液を髪につけるという象徴的ともいえる過剰描写。それらは表層的には“低俗な笑い”として機能しているように見えるが、内部には明確な構造がある。
彼らのコメディは、社会的規範から外れた事象を場に投げ込み、観客の倫理感を揺さぶることで笑いの境界を露呈させるタイプの“暴力的ユーモア”だ。笑いの構造に対して観客がどう反応するかは、作品そのものの価値判断とは別の領域で発生する。
だからこそ、キャメロン・ディアスがこの手の極端なギャグを喜々として受け止める様子は、作品を支えるもうひとつの軸として機能している。
彼女は羞恥や嫌悪といった通常の反応を笑いへ変換する“媒介者”として働き、ギャグの粗さと役者のプロフェッショナリズムの落差が、作品のテンションを生み出す。
マット・ディロンの扱いにも同様の構造が見られる。かつて『ビューティフル・ガールズ』で“かつての悪ガキ”というセルフイメージを演じた彼が、ここではイケてない探偵役として身体を投じることで、役者本人のキャリア像を茶化すようなレイヤーが生まれる。
キャリアの光と影、過去の栄光と現在の軽み。それらがコメディの中に織り込まれ、ディロンという俳優の“変質可能性”が可視化される。
このように、作品自体の下世話さは、俳優の身体とキャリアが持つイメージの層とぶつかり合うことで、単なる悪ふざけではなく、奇妙な“反物語的な厚み”へ変換されている。
虚構を走査する音楽と、90年代後期アメリカの空気
ジョナサン・リッチマンが物語の端々に狂言回しのような形で登場し、音楽を通して心象風景を代弁する手法は、コメディとしては異例の“内的声の可視化”と言えるだろう。
語り手が物語の外側から介入し、キャラクターの心情や作品のムードを音楽的に拡張していく姿は、喜劇の枠を越えてメタ的な構造を帯びる。
ファレリー兄弟の“脳天気さ”は、80年代ウェストコースト的な明るさの残滓を引っ張り込みつつ、90年代後期のアメリカに漂っていた“過剰な楽観主義”をそのままフィルムに焼き付けている。
R指定であろうが、倫理的に問題があろうが、映画は常に前へ進み続ける。規範や配慮よりも、テンションと快楽を優先した物語の進行は、90年代アメリカ映画が抱えていた価値観の揺らぎと同期している。
冷戦後の空白、ITバブルの初期段階、資本と欲望が膨張していく過渡期の空気。それらの社会背景が、作品の“アホ丸出し”のムードと気持ちよく噛み合っている。
この無軌道なエネルギーこそ、当時のアメリカ映画が持っていた特性であり、ファレリー兄弟の作品はその特性を露骨な形で結晶化している。
本作が“アメリカの懐の深さ”として讃えられるのは、下品さを包含する許容量の問題ではなく、文化的多様性を笑いの形式に落とし込む“耐性”がまだ強かった時代の空気が、作品全体に濃密に封じられているからだ。
規範が揺らぎ、欲望が形を変え、映画というメディアがまだ軽やかに暴れる余白を持っていた時代。その空気が、この作品の笑いの背後で強く振動している。
- 原題/There's Something About Mary
- 製作年/1998年
- 製作国/アメリカ
- 上映時間/119分
- 監督/ピーター・ファレリー、ボビー・ファレリー
- 脚本/エド・デクター、ジョン・ジェイ・ストラウス
- 製作/フランク・ビドア、マイケル・スタインバーグ、チャールズ・ビー・ウェスラー、ブラッドレイ・トーマス
- 撮影/マーク・アーウィン
- 音楽/ジョナサン・リッチマン
- キャメロン・ディアス
- マット・ディロン
- ベン・スティラー
- リー・エヴァンス
- クリス・エリオット
- ジェフリー・タンバー
- マーキー・ポスト
- リン・シェイ
- ジョナサン・リッチマン
- キース・デヴィッド

![メリーに首ったけ/ファレリー兄弟[DVD]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/71952EWux-L._AC_SL1259_-e1754545375916.jpg)