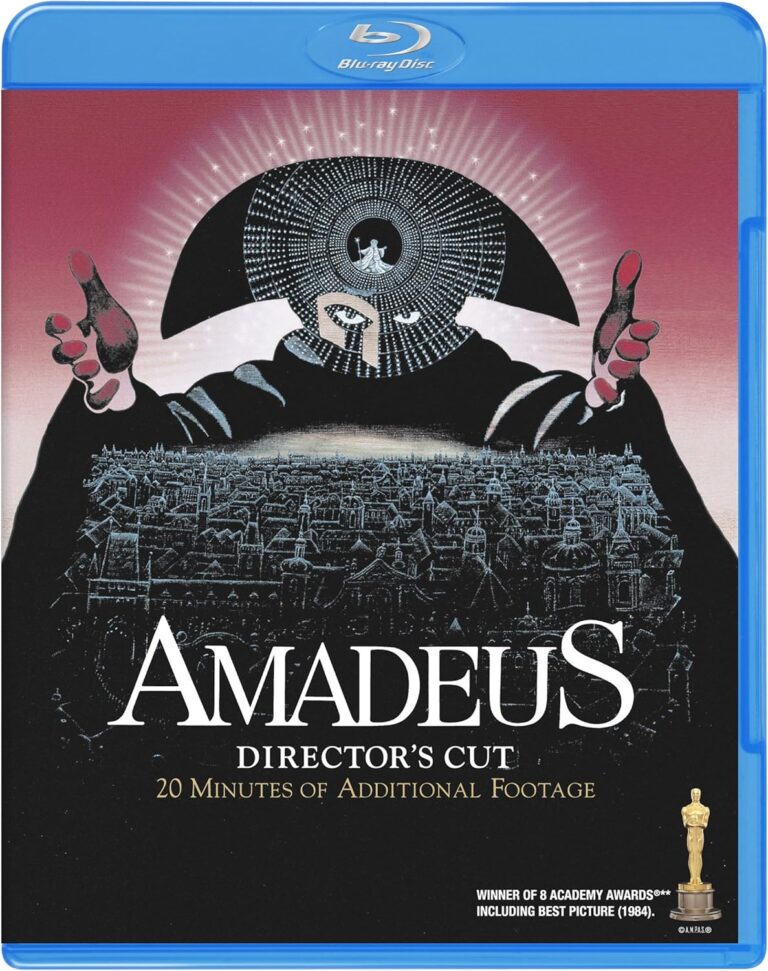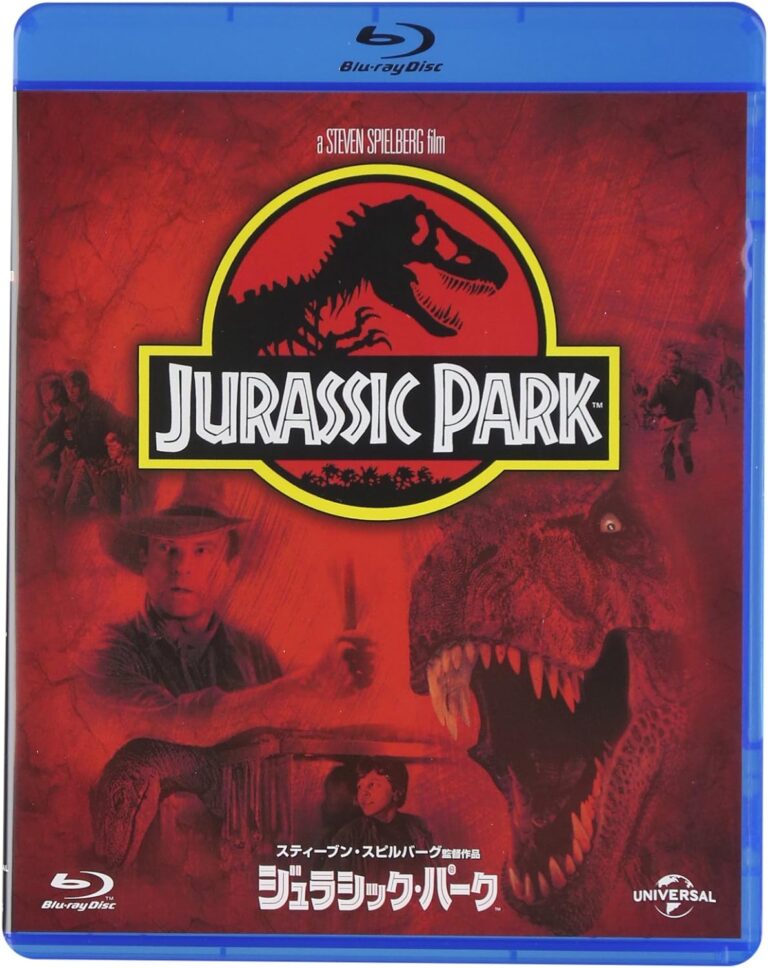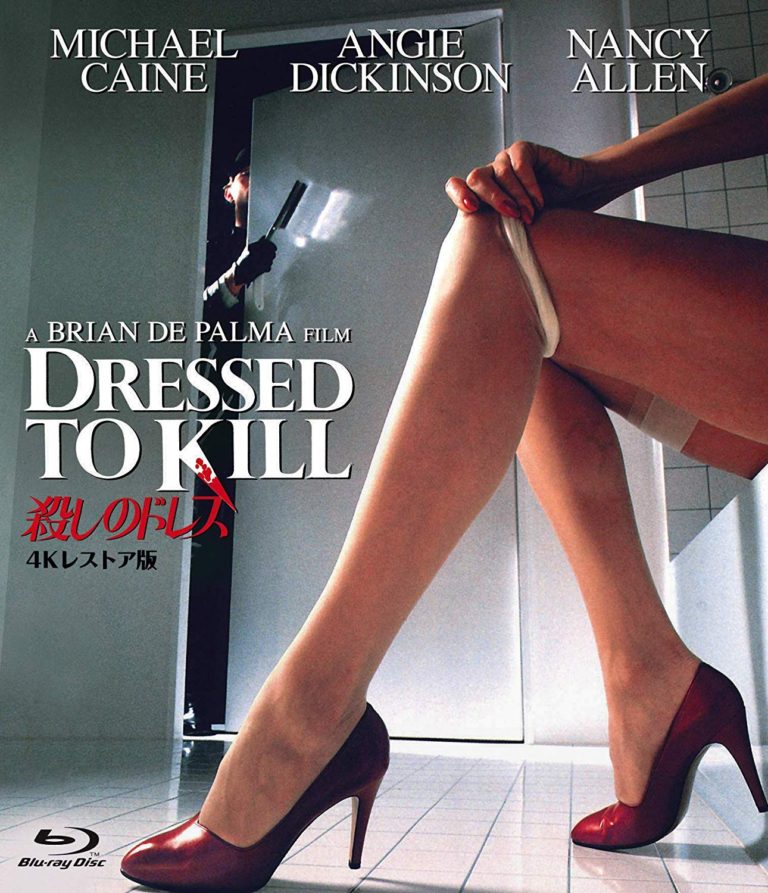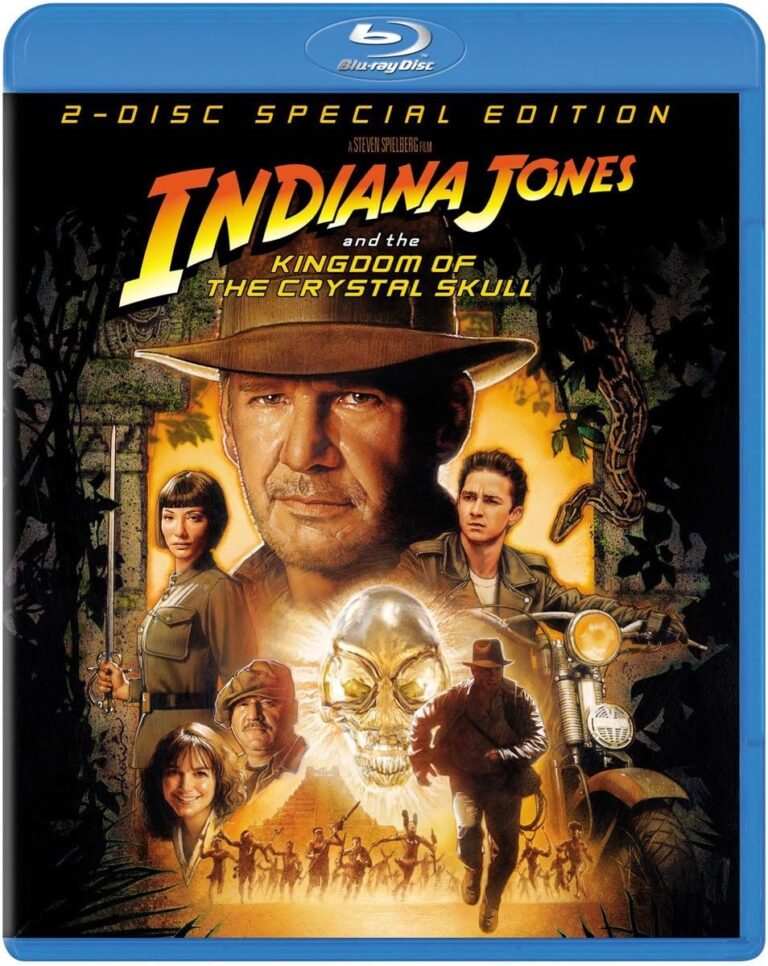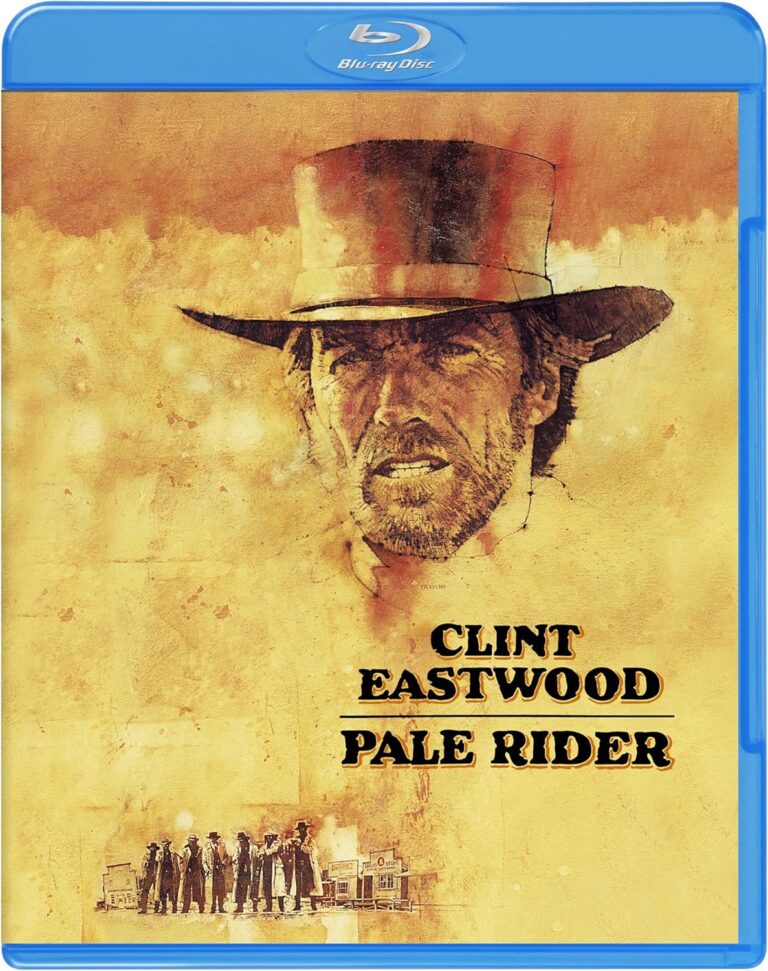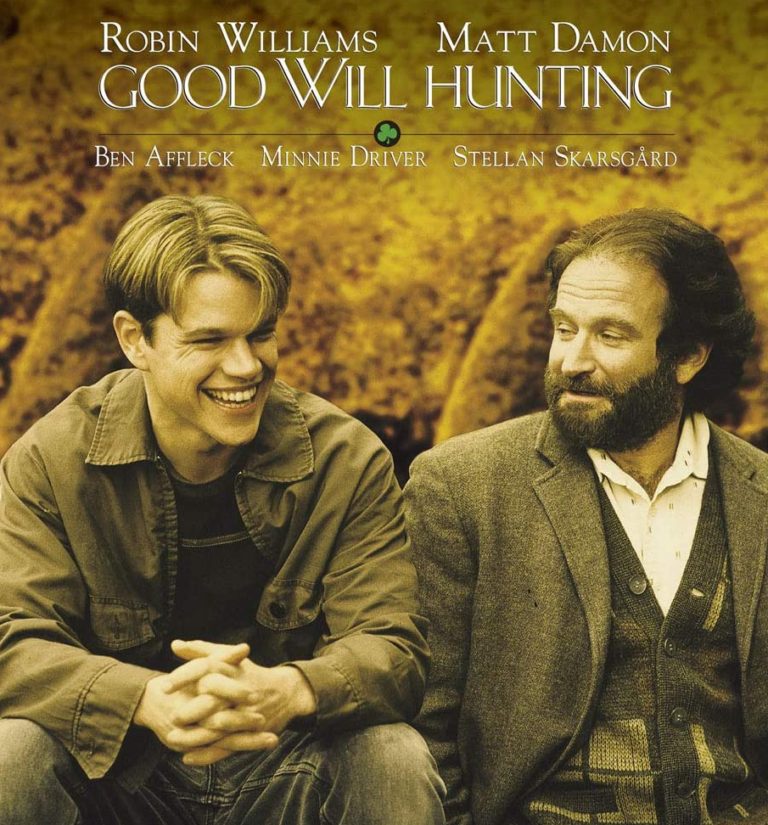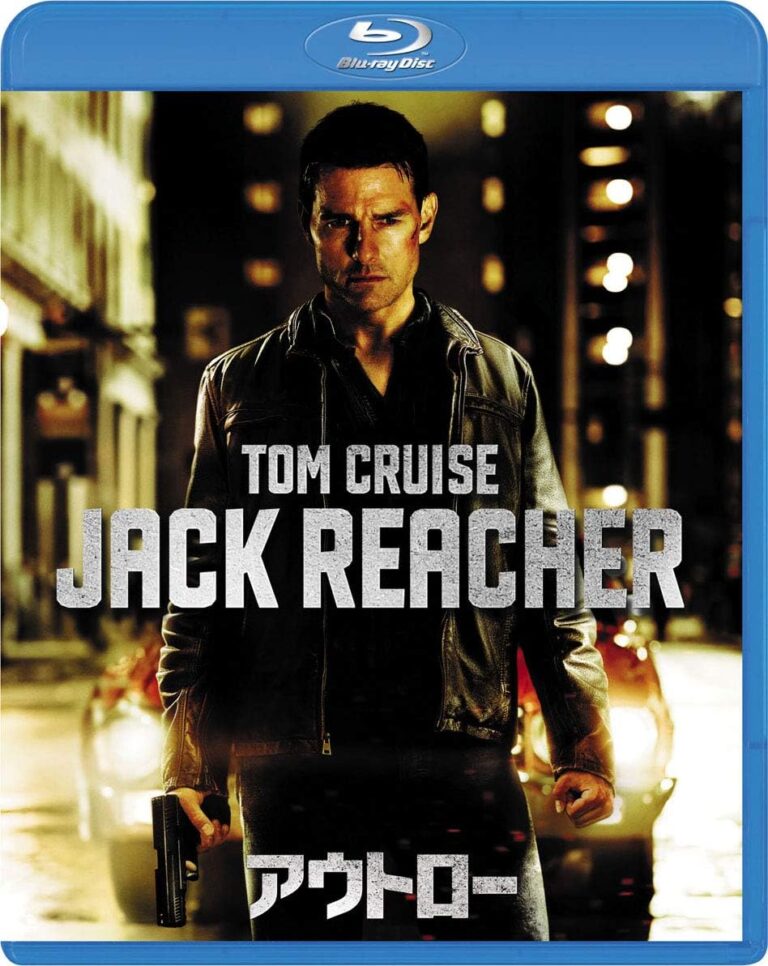『ブリジット・ジョーンズの日記』(2001)
映画考察・解説・レビュー
『ブリジット・ジョーンズの日記』(原題:Bridget Jones’s Diary/2001年)は、ロンドンの出版社に勤める32歳の独身女性ブリジット(レニー・ゼルウィガー)が、恋と仕事に奮闘しながら日記に自分の失敗と願望を綴る物語。上司ダニエル(ヒュー・グラント)との関係に翻弄されつつ、幼なじみマーク(コリン・ファース)との再会が彼女の運命を揺るがせる。
肥大する自己像──“普通の女”が抱える滑稽なリアリティ
酒もタバコもやめられず、ダイエットは三日坊主。仕事ではヘマばかりで、恋人はいない。そんな32歳の等身大の女性・ブリジットを描いたヘレン・フィールディングの小説は、90年代のイギリス女性たちにとってのバイブルとなった。
『ブリジット・ジョーンズの日記』(2001年)はその映画化である。舞台はノッティングヒル。『ノッティングヒルの恋人』(1999年)でヒュー・グラントが演じた“甘い皮肉屋”が再び登場し、この街が完全にラブコメ的幻想の舞台へと変貌していく過程を象徴している。
ブリジットの部屋にはワインと日記帳、そして孤独がある。テレビの前でチョコレートをかじりながら、“理想の恋”を夢想する姿は、すでにメディアに飼いならされた消費者としての女性像である。
彼女の自虐的なモノローグは、セルフ・ヘイトと自己愛が同居する90年代的ナルシシズムの結晶だ。つまりこの映画は、“自分探し”という名の自己肯定ビジネスの幕開けでもあった。
物語の構造は超シンプル。セクシーな上司(ヒュー・グラント)に翻弄されながら、最終的には誠実で地味な男(コリン・ファース)を選ぶ──それは恋愛映画の古典的法則「灯台もと暗し理論」に他ならない。
だが、この“鉄板構造”が21世紀の入口で再び機能したこと自体が重要である。『ブリジット・ジョーンズの日記』は、ポストフェミニズム時代における“ロマンティック・コメディの逆襲”だった。
“弱さ”や“滑稽さ”を肯定する新たなリアリズム
80〜90年代に『ワーキング・ガール』(1988)や『テルマ&ルイーズ』(1991)が提示したのは、女性が社会の中で主体性を獲得し、自らのキャリアを通して自己を確立するという“闘う女”の物語。そこには、男社会を相手取っても自分の人生を自分で設計する、という明確な理想があった。
しかし2000年代に入ると、そうした“強さの物語”はある種の完成と疲弊を迎える。フェミニズムの理念が商業文化に吸収され、「自立する女性像」はすでに広告やテレビドラマが量産する商品的イメージへと変質していった。観客は、理念よりも感情に、正しさよりも親密さに惹かれはじめる。ブリジット・ジョーンズは、まさにその文脈に生まれた“弱いヒロイン”である。
彼女は自立しているようで、仕事にも恋愛にも不器用で、社会的な成功を目指すよりも“自分が愛される”ことを夢見る。だがそれは退行ではない。完璧さを装うことに疲れた90年代女性たちにとって、ブリジットの不完全さはむしろ救済の形だった。
ポストフェミニズムとは、女性が社会的権利を得た後に訪れる“感情の領域”の政治であり、そこでは「愛されたい」という欲望が、再び正当な自己表現として許される。
『ブリジット・ジョーンズの日記』はその転換点を象徴する作品であり、ロマンティック・コメディという“軽さ”のジャンルが、再び女性の生を語るプラットフォームとして機能し始めた瞬間だった。
つまりこの映画の“逆襲”とは、フェミニズムの理想を否定することではなく、それを一度脱構築し、“弱さ”や“滑稽さ”を肯定する新たなリアリズムを提示した点にある。
マイク・ニコルズやリドリー・スコットが描いた“戦う女”の時代が終わり、レニー・ゼルウィガーが演じる“笑う女”の時代が訪れた。笑いはここで抵抗ではなく、共感の言語となる。『ブリジット・ジョーンズの日記』は、フェミニズムの第二章をロマコメの形式で語り直した稀有な映画なのだ。
この構造は、安野モヨコの『ハッピー・マニア』(1995〜2001年)に近い。このマンガが描いた自己啓発と恋愛依存のループを、ブリジットはそのまま映画的フォーマットに移し替えている。
ヒュー・グラント演じる上司は、セクシュアリティの象徴であり、同時に女性の幻想を利用する“欲望の代理人”。対してコリン・ファースは、性的魅力よりも“誠実”という擬似道徳によって女性を救済する存在として登場する。
つまりこの映画において“恋愛の勝利”とは、理想の男性を得ることではなく、現実を受け入れるための自己暗示なのだ。ブリジットが最後に選ぶのは“愛”ではなく、“安心して失敗できる場所”である。
可愛さの政治学
この映画を決定的に成功させたのは、ブリジットを演じたレニー・ゼルウィガーの存在だ。ふっくらした体型で、どこか間の抜けた笑顔。それでいて、下品にならないキュートさを放つ。
彼女は“女性の欠陥”を笑いに変換できる数少ない女優である。たとえば、バニーガール姿でパーティに現れても、観客はそこに性的な挑発ではなく“痛々しい頑張り”を見出す。
下着姿で雪の中を駆けるクライマックスも、エロティシズムではなく“意地らしさ”として受け取られる。それは、レニー自身が身体的な不完全さを武器にしているからだ。
完璧な美ではなく、不器用な可愛さ。それこそがこの映画のコメディ的核心であり、90年代以降の“女性像のアップデート”を象徴している。ジュリア・ロバーツやキャメロン・ディアスでは成立しなかったであろう“庶民的ヒロイン”像を、レニー・ゼルウィガーは完全に体現した。
彼女はスターではなく、“観客の友人”である。観客が自分の延長線上にヒロインを見出せたとき、ロマンティック・コメディは再びリアリティを獲得する。
しかしながら、『ブリジット・ジョーンズの日記』が描く“キャリアウーマン像”は、70年代フェミニズムの成果を明らかに逆行している。彼女の成長は、仕事や自己実現によってではなく、恋愛によって回復する。
物語の終盤、ブリジットが仕事を失っても、悲劇にはならない。恋があれば生きていける──この安易なロジックこそ、ポストフェミニズムの甘美な罠である。
『アリー my Love』(1997〜2002)や『セックス・アンド・ザ・シティ』(1998〜2004)は、キャリアと恋愛の両立を模索したが、『ブリジット・ジョーンズの日記』は“失敗する女”を肯定することでそのバランスを放棄する。
彼女の仕事は、人生の中心ではない。恋が主で、仕事は従だ。しかも、彼女の成功は“男に選ばれること”によってしか証明されない。これはロマンティック・コメディが内包する保守性そのものであり、同時に観客が最も求める幻想でもある。
ブリジットの笑いは、女性の敗北を包み隠す柔らかなカーテンのようだ。吉本ばなな的な“自己肯定の詩学”と、消費社会的な“幸福の演出”がここで融合する。
だがその裏で、社会は確実に個人を孤立させていく。恋愛がもはや救済ではなく、自己防衛の物語として描かれている点に、この映画の時代性がある。
「日記」という檻──語ることと笑うことの間で
ブリジットが日記に書きつけるのは、恋の進捗でも仕事の記録でもない。彼女は“語ることでしか存在できない女性”である。書くという行為は、彼女にとって現実と自己をつなぐ仮の装置だ。日記は自意識の鏡であり、同時に彼女を閉じ込める檻でもある。
『ブリジット・ジョーンズの日記』は、女性の解放を謳いながら、言葉と笑いの中に彼女を再び幽閉してしまう。映画のラスト、ブリジットは恋人を追いかけ雪の街を駆ける。そこにはもはや“社会的存在”としての彼女はいない。残るのは、幸福を演じる一個の身体だけだ。
ロマンティック・コメディとは、幸福の演技を見せるジャンルである。観客が求めるのは現実ではなく、現実を一瞬だけ忘れさせてくれる幻想だ。だからこそこの映画は、軽やかで、危険で、そして限りなく切ない。
笑いながら自分の傷を見つめる女性たちのために、『ブリジット・ジョーンズの日記』は存在する。
- 原題/Bridget Jone's Diary
- 製作年/2001年
- 製作国/イギリス
- 上映時間/97分
- 監督/シャロン・マグワイア
- 脚本/ヘレン・フィールディング、アンドリュー・デイヴィス、リチャード・カーティス
- 製作/ティム・ビーヴァン、エリック・フェルナー、ジョナサン・カヴェンディッシュ
- 原作/ヘレン・フィールディング
- 撮影/スチュアート・ドライバ
- レニー・ゼルウェッガー
- ヒュー・グラント
- コリン・ファース
- ジェンマ・ジョーンズ
- ジム・ブロードベント
- シャーリー・ヘンダーソン
- サリー・フィリップス
- ジェームズ・コリス

![ブリジット・ジョーンズの日記/シャロン・マグワイア[DVD]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/51Vd69KYGJL._AC_UL640_FMwebp_QL65_-e1761133046235.webp)