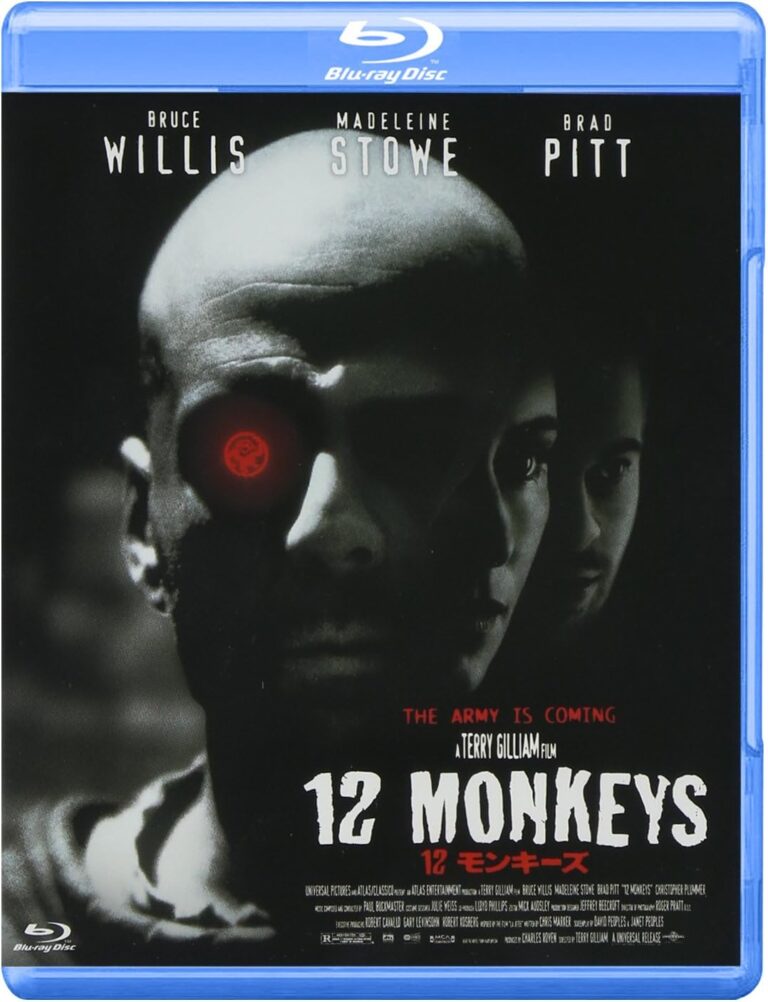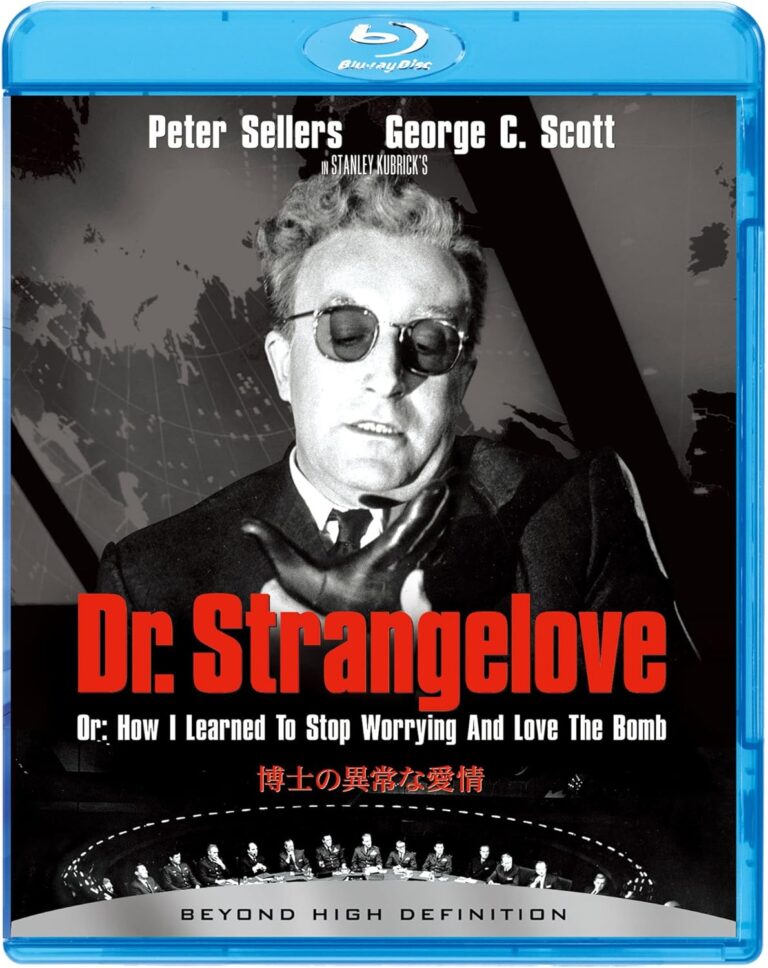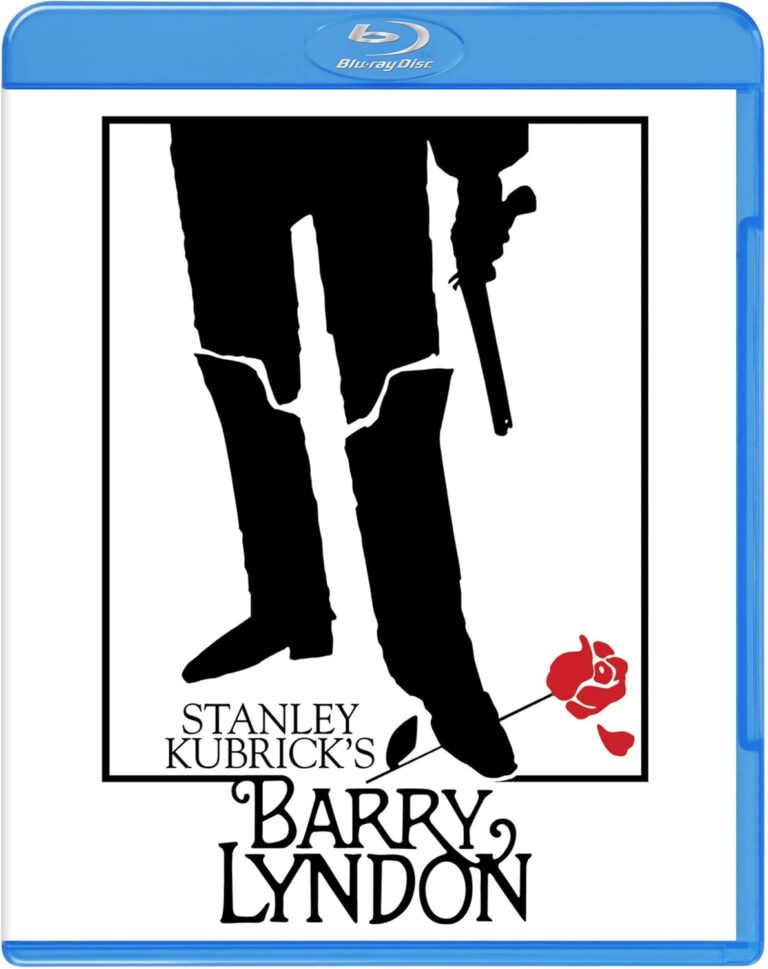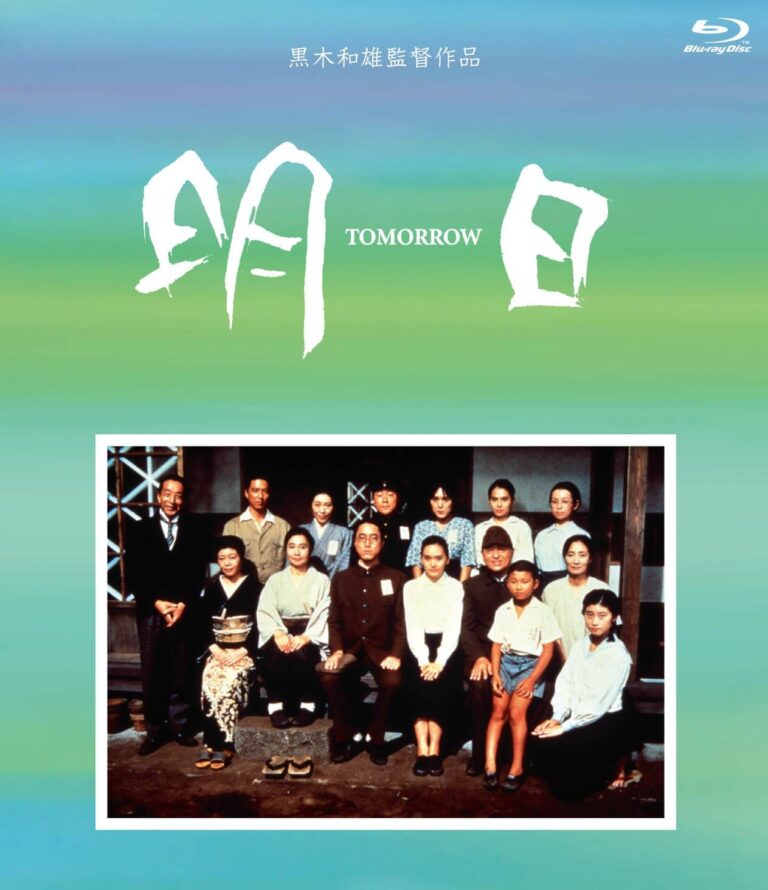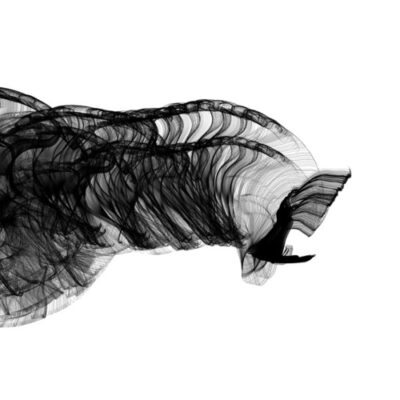『バッファロー’66』──ヴィンセント・ギャロが撮った「自分を赦すための映画」
『バッファロー’66』(原題:Buffalo ’66/1998年)は、ヴィンセント・ギャロが監督・脚本・主演・音楽を手がけたセルフポートレート的映画。無実の罪で服役した男ビリー・ブラウンが、他者と再びつながろうとする過程を描く。共演はクリスティーナ・リッチ、アンジェリカ・ヒューストン、ベン・ギャザラ。1998年サンダンス映画祭でプレミア上映され、インディペンデント・スピリット賞撮影賞にノミネートされた。
虚勢の鎧──愛されたい男の拒絶
ヴィンセント・ギャロ演じるビリー・ブラウンは、どうしようもない男だ。虚勢を張って威張り散らすが、実際は臆病で小心。無実の罪で5年間服役し、出所後は自暴自棄な日々を送る。「俺に触るな」、「俺をじろじろ見るな」、「握手で我慢しろ」。彼の口から飛び出すのは、他人を遠ざけるための言葉ばかり。
だがその暴言の裏には、どうしようもなく「愛されたい」という渇望が潜んでいる。拒絶は救済の形を変えたものにすぎない。彼は小学生のように、「好きな子にキライだと言う」しか能がない男だ。
「生きられない……」と漏らす瞬間、彼の虚勢は崩壊を始める。怒鳴り、泣き、母親に罵られ、愛を乞う。ギャロは“男のかっこ悪さ”を一切ごまかさない。『バッファロー’66』は、そんな痛々しい男が自己憎悪を脱ぎ捨てるまでの「感情の解体劇」だ。
レイラ(クリスティーナ・リッチ)は、ビリーに誘拐される形で登場するが、彼女の存在は物語を超えて“赦しの象徴”となる。太めの体躯とベビーフェイス、幼さと官能の同居──ギャロは彼女を「母と恋人の融合体」として描く。レイラがビリーを愛する理由は明示されないが、それが重要なのだ。愛は説明できない“降臨”であり、神話的な救済なのである。
ボウリング場でのタップダンス・シーン。青白い光が満ちる中、レイラがひとり踊り出すと、映画はリアリズムを離れ、時間が凍る。キング・クリムゾンのようなプログレ的リズムが流れ、観客は夢と現実の狭間へ引きずり込まれる。あの瞬間、ビリーは初めて“赦される”。その赦しは恋ではなく、母のまなざしに近い。
アンジェリカ・ヒューストンとベン・ギャザラが演じる毒親は、愛情の不在を象徴している。母はフットボールに夢中で息子を無視し、父は暴力的な沈黙で支配する。
ビリーがレイラに求めるのは、恋人ではなく“再び母親になる誰か”。ギャロは、母性を「男が再び世界と接続するための回路」として描いている。
ヴィンセント・ギャロという神話──自己を演じる男
ギャロは、1961年ニューヨーク州バッファロー生まれ。貧困と家庭不和の中で育ち、10代から音楽と絵画に救いを求めた。70年代にはアヴァンギャルドなアートシーンに出入りし、ニューヨークのアンダーグラウンド・カルチャーに身を置く。俳優として『アリゾナ・ドリーム』(1993)で注目されるも、商業映画には馴染まず、自らの手で「自分自身を撮る」決意をした。
『バッファロー’66』は、そんなギャロの“人生の再演”である。彼はこの作品を「自分を赦すための映画」と呼び、監督・脚本・編集・音楽・主演すべてを手がけた。つまりこれは映画の形をした懺悔録なのである。
ギャロはインタビューでこう語っている。「この男は誤った犠牲者だ。彼が変わるのは、自分の人生に責任を取るときだけだ」。彼にとって映画とは救済の場であり、同時に罰の場でもある。だからこの作品には“演出の完璧さ”ではなく、“生き延びるための記録”としての荒さが残っている。
彼の映像には、クエンティン・タランティーノ的引用精神と、デヴィッド・リンチ的悪夢が同居している。照明が突如変わり、音楽が割り込み、血がストップモーションで凍る。
すべてが「現実を誤魔化すための演出」でありながら、その嘘が異様なリアリティを帯びる。ギャロは、自分の内側にある「救われなさ」を、様式と演技の境界線で晒している。
音楽的自意識──リズムで語る愛の構造
音楽家でもあるギャロは10代の頃からバンド活動を行い、フランク・ザッパやプログレッシヴ・ロックの影響を公言してきた。『バッファロー’66』のサウンドトラックでは、イエス、キング・クリムゾン、ギャロ自身の作曲などを織り交ぜている。音楽は単なるBGMではなく、感情の代替言語として機能している。
たとえばボウリング場のダンス・シーンでは、カメラはリズムに合わせて揺れ、編集が音楽の呼吸で動く。ギャロの演出は音楽的構造を持つ。メロディではなく、テンポと間で感情を語る。
彼の“映像=音楽”感覚は、デヴィッド・リンチの『ロスト・ハイウェイ』やジム・ジャームッシュの『ナイト・オン・ザ・プラネット』に連なる90年代アメリカ・オルタナティヴ映画の中核を成す。
音楽の使い方が特異なのは、感情の過剰を言葉で語らず、音響で“言葉にならない痛み”を伝えるためだ。ギャロにとって映画とは、視覚よりも聴覚の記憶であり、音が傷の深さを可聴化するメディウムである。レイラの沈黙、ビリーの荒い呼吸、そして雪の上で鳴る微かな足音。すべてが“音の映画”なのだ。
プライベート・ムービーとしての祈り
『バッファロー’66』は、インディペンデント・フィルムという形式を超えた「私映画」である。照明が唐突に変わり、シナトラの歌が響き、血が宙に浮いて止まる。ボウリング場の幻想、モーテルの沈黙、雪の町の虚無──どれもが「現実の痛みを誤魔化すための夢」だ。しかしその夢の中でこそ、ビリーは生き直す。
ギャロの“下手なロマンティシズム”は、むしろ真実だ。構成の粗さも、セリフのぎこちなさも、作り手の“生”をそのまま映している。芸術として整えるよりも、傷を残すことを選んだ映画。つまりこの作品は、映画という手段で自分を抱きしめるための「祈り」なのだ。
ビリー・ブラウンは、世界でいちばんダメな男だ。だが、その男にも天使は舞い降りる。『バッファロー’66』は、愛によって再生する物語ではない。愛されることによって、ようやく「壊れた自己を受け入れる」物語だ。
ギャロは語る。「救済なんて存在しない。でも、誰かに抱きしめられた瞬間だけは、世界が少しやさしくなる」。「最悪の俺に、とびっきりの天使がやってきた」──それは宣伝コピーではなく、ヴィンセント・ギャロという男の、人生そのものの告白なのである。
- 原題/Buffalo’66
- 製作年/1998年
- 製作国/アメリカ
- 上映時間/118分
- 監督/ヴィンセント・ギャロ
- 脚本/ヴィンセント・ギャロ、アリソン・バグナル
- 音楽/ヴィンセント・ギャロ
- 製作/クリス・ハンリー
- 製作/クリス・ハンレー
- 撮影/ランス・アコード
- 美術/ギデオン・ポンテ
- 編集/カーティス・クレイトン
- ヴィンセント・ギャロ
- クリスティーナ・リッチ
- アンジェリカ・ヒューストン
- ベン・ギャザラ
- ロザンナ・アークエット
- ミッキー・ローク
- ジャン・マイケル・ヴィンセント
![バッファロー'66/ヴィンセント・ギャロ[DVD]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/71sp4CuCx6L._AC_SL1500_-e1758931578861.jpg)