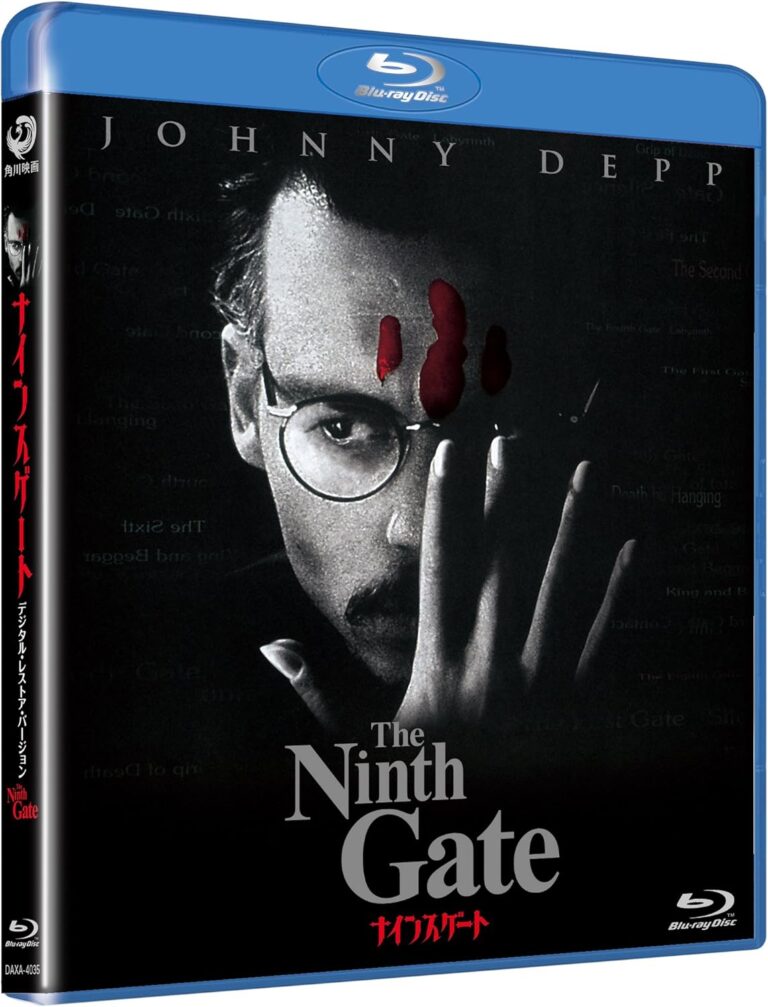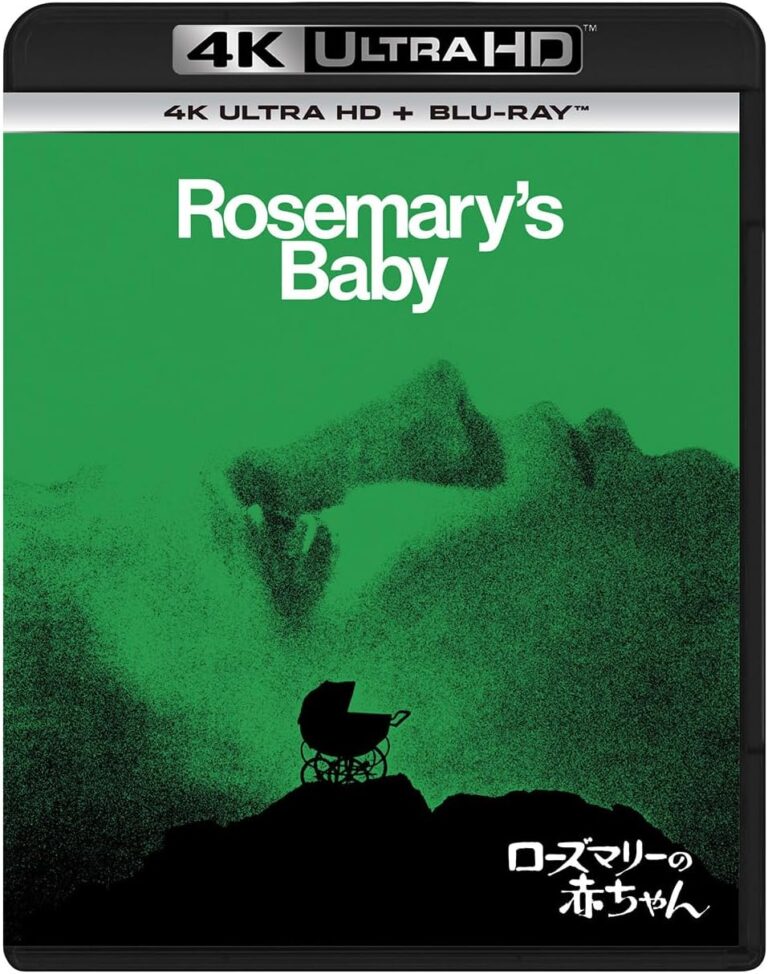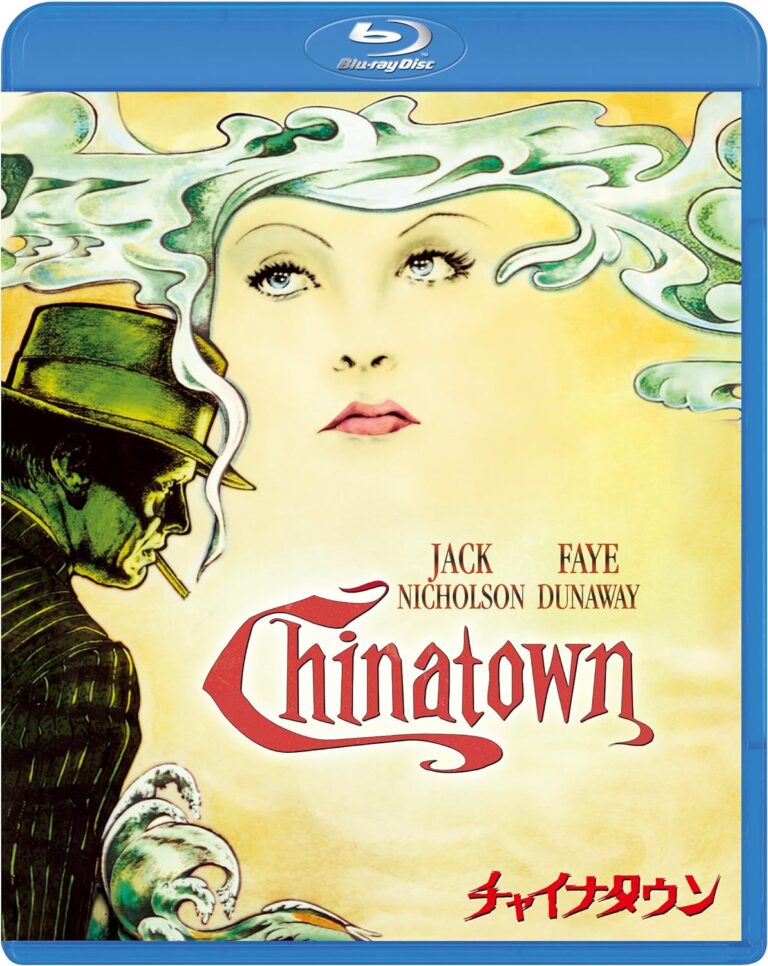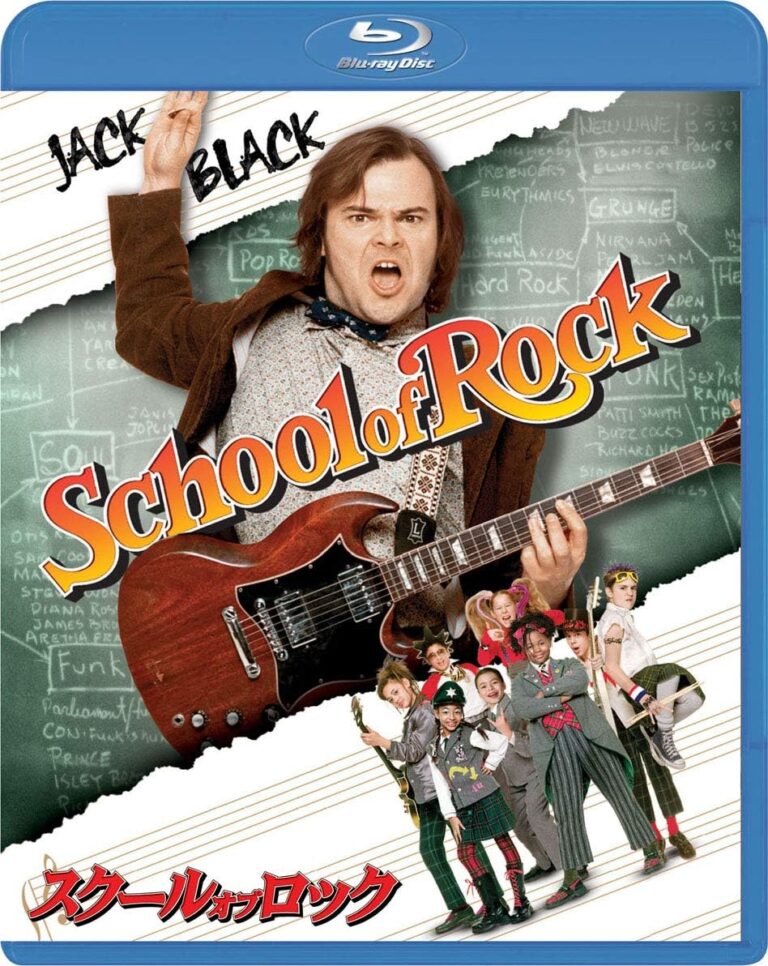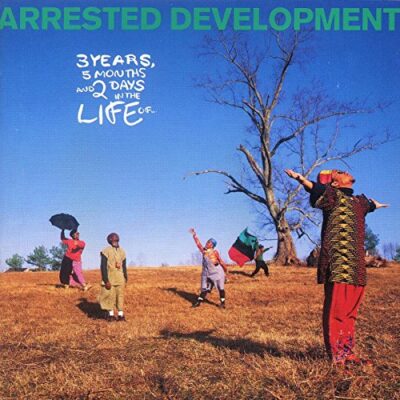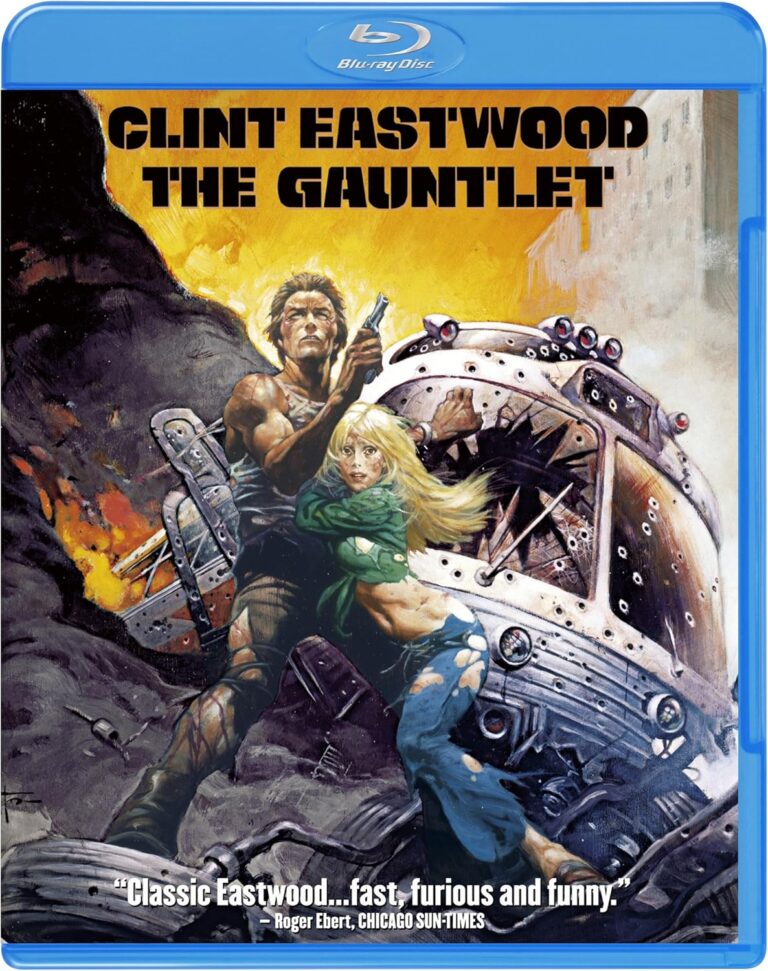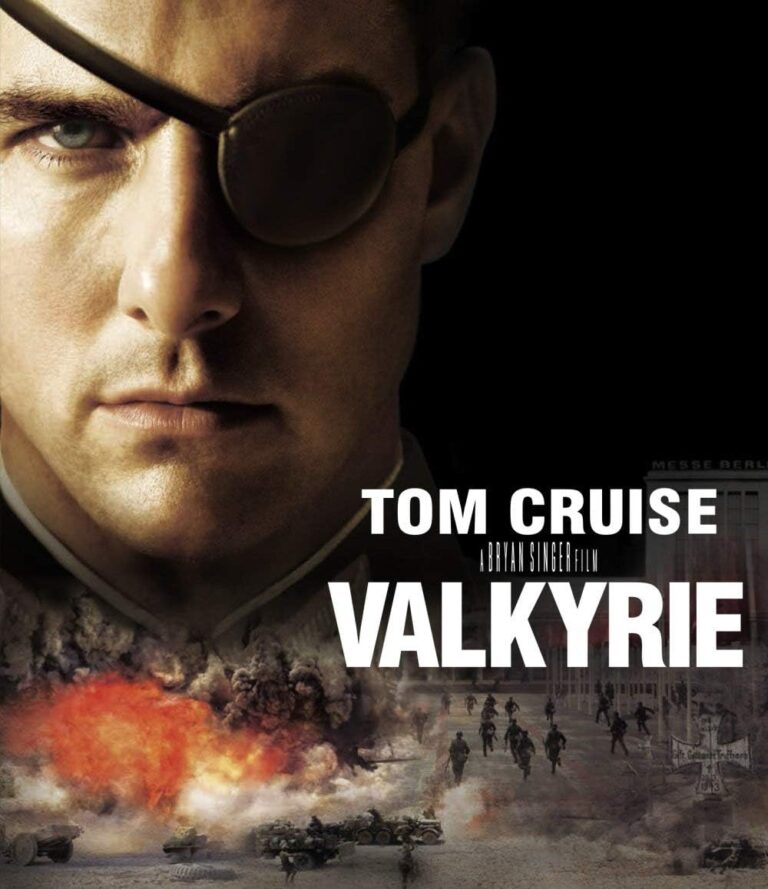『おとなのけんか』──密室で崩壊するブルジョワの理性
『おとなのけんか』(原題:Carnage/2011年)は、ロマン・ポランスキー監督がヤスミナ・レザの舞台劇を映画化した心理コメディである。ニューヨーク・ブルックリンの一室に集まった二組の夫婦が、子供同士の喧嘩をきっかけに互いの理性を失い、礼節の仮面が剥がれていく。会話が次第に暴力へと変わり、80分間の密室が人間関係の縮図となる。
ブルジョワの仮面を剥ぎ取る「80分間の密室デスゲーム」
巨匠ロマン・ポランスキーが仕掛けた『おとなのけんか』(2011年)は、まさに映画の皮を被った人間解体ショーだ。
舞台はニューヨーク、ブルックリンのとあるアパートの一室。子供同士の喧嘩を平和的に解決しようと集まった二組の夫婦。最初は「良識ある大人」として、上品な言葉を使い、高級なチューリップを飾り、手作りケーキを囲んで微笑み合っている。
だが、そこはポランスキーの独壇場。カメラが一度部屋に入れば、そこはもう逃げ場のない「心理的監獄」だ。冒頭、公園のいさかいを遠くから見せるロングショットで、僕たちは強制的に「目撃者」に仕立て上げられる。
そこから一歩も外へ出さない、この執拗なまでの閉鎖性。『ローズマリーの赤ちゃん』(1968年)で観客の背筋を凍らせたポランスキーの「当事者に引きずり込むトラップ」は、老境に入っても全く衰えていない。
実はこの映画、ブルックリンが舞台でありながら、撮影はすべてフランスのスタジオで行われている。かつての事件による法的問題で、アメリカに入国できないポランスキーが、パリのセットの中に「完璧なニューヨークのアパート」を構築したのだ。この「偽りの箱庭」という設定自体が、登場人物たちが守ろうとする「偽りの良識」と見事に共鳴している。
監督自身が物理的な国境という監獄に縛られながら、カメラという凶器を使ってブルジョワジーの精神的監獄を暴き立てる。この皮肉すぎる構造こそが、映画に異様なまでの密度と緊張感を与えているのだ。
ポランスキーの脳内に刻まれたゲットーの悪夢
なぜ、ポランスキーはこれほどまでに「部屋」という閉鎖空間に執着するのか。その答えは、彼の血塗られた幼少期にある。
ナチス占領下のポーランド、クラクフ・ゲットー。幼いポランスキーは、周囲を高い壁に囲まれた「監獄」の中で、明日の命も知れぬ逃亡生活を強いられた。
壁の向こうへ逃げ出そうとしても、常に誰かの視線に晒され、理不尽な暴力が降り注ぐ。この時、彼の脳内に刻み込まれた「閉所恐怖症的な不安」と「加害者がいつ被害者になるか分からない不条理」こそが、本作の、そして彼の全作品の原動力なのだ。
『おとなのけんか』のリビングルームは、一見セレブな安息の地に見える。だが、ポランスキーの目を通せば、そこはかつてのゲットーと同じ「出口のない絶望の箱」に他ならない。
劇中、何度も部屋を出ようとしては戻ってくる夫婦たちの姿。あれは単なる脚本の都合ではない。ポランスキーの深層心理にある「壁からは逃げられない」という呪縛の現れなのだ。
彼にとって「部屋」とは、人間の文明が試される場所ではなく、剥き出しの生存本能が激突する戦場だ。このあまりに重すぎる伝記的背景を知れば、優雅なティータイムが阿鼻叫喚の地獄絵図へと変貌する様も、もはや必然としか言いようがない。
『死と処女』から続く「権力逆転」の連鎖
ここで、ポランスキーの「密室三部作」とも呼ぶべき系譜に触れないわけにはいかない。本作『おとなのけんか』で見られる、被害者と加害者の立場がクルクルと入れ替わるドロドロの権力ゲーム。これは、かつて彼が描いた『死と処女』(1994年)や『毛皮のヴィーナス』(2013年)の正統な進化形といえる。
『死と処女』では、かつての拷問被害者が、偶然現れた「加害者かもしれない男」を椅子に縛り付け、言葉の銃弾で処刑しようとした。そこにあるのは、密室という逃げ場のない空間で、優位に立った者が「正義」の名を借りて他者を蹂躙する残酷な快感だ!
本作のリビングでも、同じことが起きている。最初は「被害者の親」として道徳的優位に立っていたジョディ・フォスターが、いつの間にか「加害者の親」であるケイト・ウィンスレットを糾弾する独裁者へと変貌する。
だが、酒が入り理性が溶け出すと、その支配構造は一瞬で崩壊し、加害者が被害者を嘲笑い、被害者が加害者を呪うというカオスな地獄絵図が完成するのだ。
この「座る位置」や「台詞の受け渡し」一つで権力の天秤がグラグラと揺れる様こそ、ポランスキーが半世紀かけて磨き上げた変態的演出の真髄。誰が正しいかなど、この密室ではどうでもいい。
ただ「今、誰が誰を支配しているのか」という原始的なパワーゲームが、僕たちの動物的な本能を刺激して止まないのだ。
ジェンダーの崩壊線
ジョディ・フォスター、ケイト・ウィンスレット、クリストフ・ヴァルツ、ジョン・C・ライリーといった、当代随一の名優たちによる演技合戦も凄まじい。顔面演技のインフレが凄まじすぎて、画面が熱を帯びているほどだ。
例えば、ジョディ・フォスター演じる“アフリカを憂う正義の味方”ペネロピ。彼女の「私は正しい、あなたたちは野蛮だ」という高慢なリベラル精神が否定された瞬間、顔を真っ赤にして理性を飛ばす芝居は、まさにオスカー級の怪演。
対するケイト・ウィンスレットは、夫への不満を酒と共にかき回し、豪快に家庭の均衡を破壊していく。この「女の意地」が火花を散らす一方で、男たちは実に情けない。クリストフ・ヴァルツは携帯が水没しただけで幼児のように狼狽し、ジョン・C・ライリーは良き夫の仮面の下にあるミソジニー(女性蔑視)を露呈させる。
夫婦対夫婦というタッグマッチは、いつの間にか「男女対決」になり、最後には「個人対個人」の醜い生存競争へと分解されていく。ここにはポランスキーが初期作品『水の中のナイフ』から描き続けてきた「パワーゲームの逆転」という批評軸が、最高にブラックなユーモアと共に鎮座している。
親は子供のために戦っているつもりで、実は自分のエゴをぶつけ合っているだけ。この過程こそが、現代の結婚観やジェンダー役割がいかに脆い砂上の楼閣かを、容赦なく暴き出す。
私生活のスキャンダルで世間を騒がせた巨匠だが、そんな彼だからこそ、この「人間なんて一皮剥けば皆ゲス野郎だ」という人間喜劇をこれほど軽やかに、残酷に撮り切れたのだろう。この映画は、とんでもない猛毒の心理劇である。
- 監督/ロマン・ポランスキー
- 脚本/ヤスミナ・レザ、ロマン・ポランスキー
- 製作/サイド・ベン・サイド
- 原作/ヤスミナ・レザ
- 撮影/パヴェル・エデルマン
- 音楽/アレクサンドル・デスプラ
- 編集/エルヴェ・ド・ルーズ
- 美術/ディーン・タヴォウラリス
- 衣装/ミレーナ・カノネロ
![おとなのけんか/ロマン・ポランスキー[DVD]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/81vgAeei6OL._AC_SL1500_-e1758355417615.jpg)
![ローズマリーの赤ちゃん/ロマン・ポランスキー[DVD]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/71eSDdAxtZL._AC_SL1250_-e1751524926589.jpg)