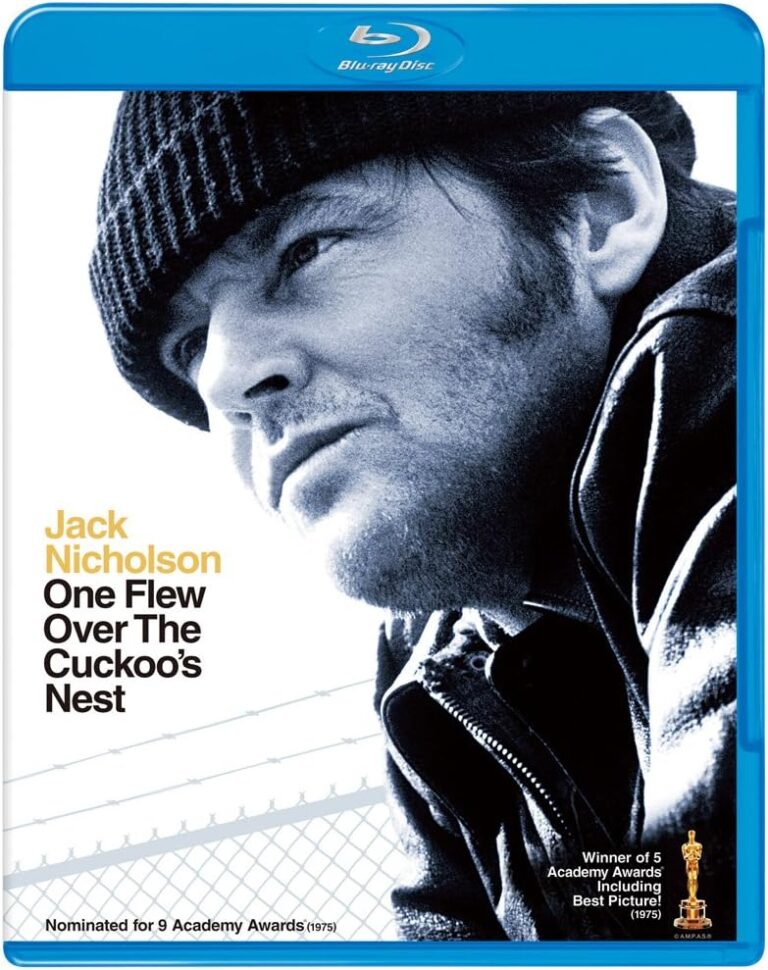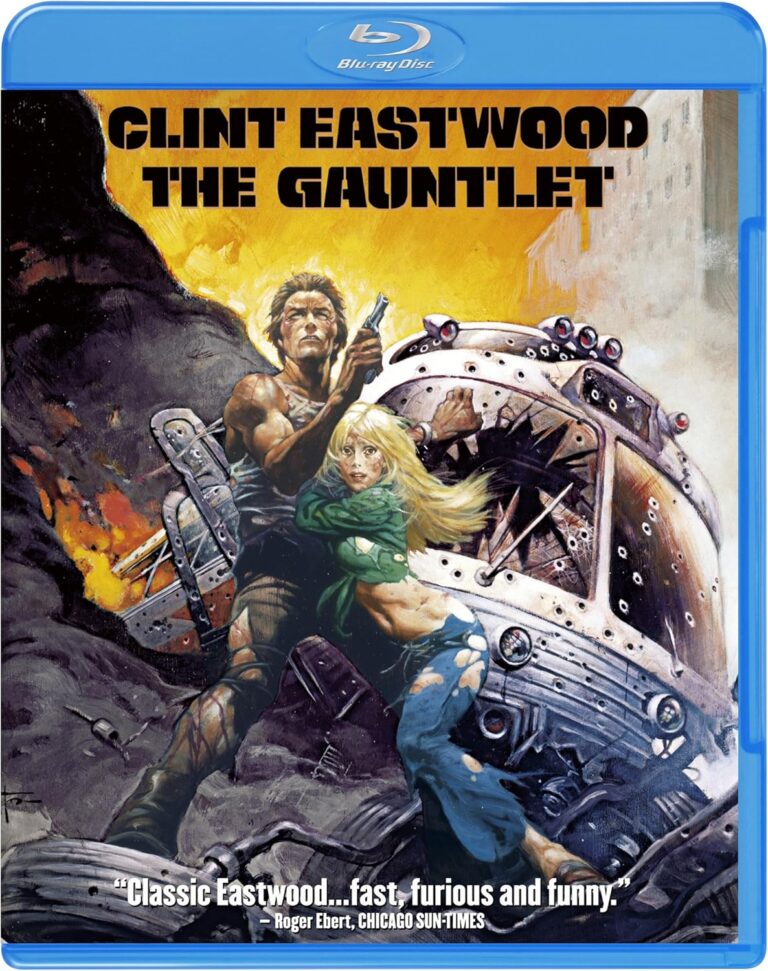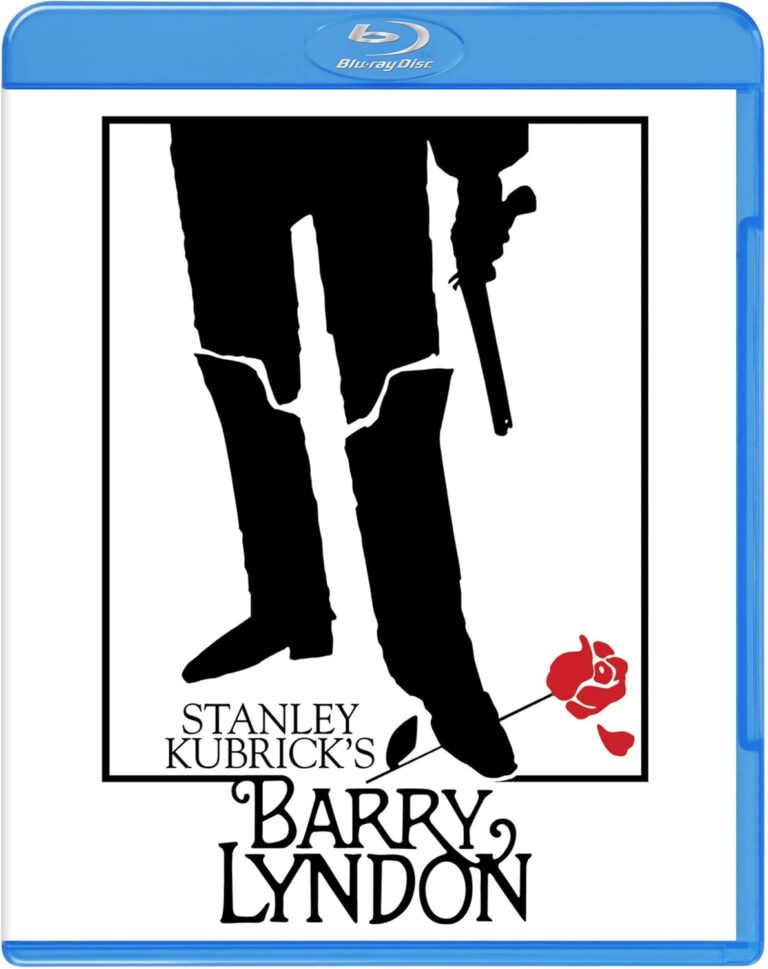清涼感とファンタジーに包まれた少女たちの物語
視点の揺らぎと物語の変質
『花とアリス』(2004年)という映画について語るとき、決まり文句のように繰り返されるキャラクター紹介がある。「奥手で引っ込み思案な花と、恋愛に積極的なアリス」。だが、本当にそうだろうか。
実際にスクリーンに映し出される二人は、そんな記号的な分類に収まるものではない。少なくとも僕にとって花もアリスも「お転婆だが根は純情で素直な女の子」であり、その無邪気さと直情さが物語全体を突き動かしているように見える。
岩井俊二自身が
「最初は花から見たアリスを描こうとしていたけれど、だんだんと両者の関係が拮抗して、物語が変わっていったんです」
と語っているように、この映画はもともと片方の少女の視点を中心に据えるはずだった。しかし、制作の過程で二人のキャラクターが拮抗し、振り子のように視点が揺れ動く作品へと変質していった。この変化は単なるストーリー上の修正ではなく、映画そのものの構造を変える大きな出来事だったと言える。
花は、自分を「今カノ」と信じて疑わない宮本先輩の存在を通じて自らを規定する。つまり恋愛というファクターを媒介にして「自分」を確かめようとする少女だ。だからこそ、彼女は嘘をつく。その嘘は淡い恋心から生まれた悪戯というよりも、むしろ自分の存在を証明するための通過儀礼であり、彼女の不安定な自我を裏付ける行為なのである。
一方のアリスは、恋愛を自ら積極的に招き入れることを避けている。それは、男性遍歴の激しい母親への反発が根底にあるのだろう。彼女はオーディションに参加し、芸能界という不確かな未来を模索することによって自分のアイデンティティを築こうとする。
だからこそ最後のバレエシーンには、一瞬だけ少女から大人へと移ろう姿が垣間見える。花とアリス、それぞれの「自分を自分たらしめるもの」の違いが、家庭環境の描写の濃淡としてスクリーンに刻まれているのだ。
岩井作品における少女像の変遷
こうした二人の姿は、岩井俊二がそれまで描いてきた少女像の延長線上にあるようでいて、大きく異なっている。『打ち上げ花火、下から見るか?横から見るか?』(1993年)に登場するヒロインは、少年たちの幻想的な憧れとして造形されていた。
『Love Letter』(1995年)では、亡くなった恋人の記憶と重なり合う少女の存在が、物語をロマンティックに彩った。さらに『リリイ・シュシュのすべて』(2001年)においては、インターネット時代の闇に呑み込まれる十代の少女が、圧倒的な痛みとともに描かれた。
その流れを踏まえると、『花とアリス』は180度転換した作品と言える。岩井作品に共通する陰鬱さや幻想性は薄れ、清涼感と軽妙さに包まれたスラップスティック・コメディーに仕上がっている。
だが、それは決して能天気な青春映画というわけではなく、二人の少女が「自分は誰か」を模索する物語であるという点において、従来の岩井作品と同じ根を共有している。
コメディとしての異化効果
本作の大きな特徴は、随所に仕掛けられた“異化効果”にある。
たとえば、花が「別れましょうか」と切り出す教室の後ろで、巨大な鉄腕アトムの風船がゆらめいている場面。あるいは宮本先輩に真相を告白するシーンで、尻を丸出しに絶叫する落研の先輩とのカットバックが挿入される場面。いずれもシリアスな感情の場面に唐突な異物が侵入し、観客に奇妙な笑いをもたらす。
また、アジャコングやテリー伊藤、ルー大柴といった強烈な個性を持つ人物がそのまま映画の中に現れるのも、岩井らしい“あざとさ”だ。ルー大柴主演の番組タイトルが『サルとルー』というのは直球すぎて笑うしかない。こうした演出は一見すると悪ノリのようだが、実際には「青春の滑稽さ」を可視化する装置として機能している。
そして極めつけは、鈴木杏の泣き顔アップである。ラーメンズの片桐仁も映画パンフレットで触れていたが、執拗なまでにクローズアップされるその表情は、少女漫画なら「うえーん」の吹き出しひとつで済むはずの感情を、実写ならではの異様な質感で観客に突きつける。
蒼井優なら自然に流れていくであろう場面が、鈴木杏の「巧さ」によってどこか引っかかりを残し、笑いと違和感へと転化する。この仕掛けが意図的であれ偶発的であれ、映画に独特のリズムを与えているのは間違いない。
少女漫画的フォーマットと男性視点
こうして見ていくと、『花とアリス』は伝統的な少女漫画のフォーマットを巧みに換骨奪胎した作品であることが分かる。淡い恋愛、友情、成長の物語──その全てが「少女の世界」の内部で展開される。
だが同時に、これはあくまで岩井俊二という男性監督が描いたファンタジーである。少女たちへの盲目的なイノセンス信仰が結実した、非肉感的青春映画。今どきの女子高生が本当に「愛している」と大人の男性に告げるだろうか、というツッコミは無意味である。これは現実ではなく、フィクションだからだ。
ここで重要なのは、このフィクションが観客にどう受容されてきたかという点だ。『花とアリス』は多くの男性観客にとって「理想化された少女像」を消費する装置であり、同時に女性観客にとっては「自分の成長の物語」を重ね合わせる余地を残す作品でもある。その両義性こそが、本作を単なる青春映画以上の存在へと押し上げている。
清涼感と余韻
『花とアリス』は、青春期特有の不安定さと無邪気さを同時に描き出すことに成功している。花は嘘を通じて自分を確かめ、アリスは未来を探ることで自分を形づくる。
二人の姿はまるで鏡のように対照的でありながら、根底には同じ純情さが流れている。岩井俊二が意図した以上にアリスが物語を牽引した結果、映画は二人の成長譚として開花した。
前作『リリイ・シュシュのすべて』が10代の暗黒面を抉り出したとすれば、『花とアリス』はその裏返しとして、清涼感とスラップスティックに彩られた光の側面を映し出す。だが、その軽やかさの裏には、岩井俊二が一貫して描いてきた「自分とは誰か」という問いが脈打っているのだ。
だからこそ、何も考えずに楽しむのも一興だが、細部を観察することで見えてくる仕掛けの数々に気づけば、この作品が単なる青春コメディーに留まらないことを実感するだろう。
『花とアリス』は、清涼感とファンタジーに包まれながらも、少女たちの成長の痛みと輝きを同時に刻み込んだ稀有な映画である。
- 製作年/2004年
- 製作国/日本
- 上映時間/135分
- 監督/岩井俊二
- 脚本/岩井俊二
- プロデューサー/岩井俊二
- 美術/種田陽平
- 撮影/角田真一
- アソシエイトプロデューサー/前田浩子
- ラインプロデューサー/中山賢一
- 照明/樋浦雅紀、中須岳士
- 録音/益子宏明、岸直隆
- 鈴木杏
- 蒼井優
- 郭智博
- 相田翔子
- 阿部寛
- 平泉成
- 木村多江
- 大沢たかお
- 広末涼子
- ルー大柴
- アジャ・コング
- 伊藤歩
- テリー伊藤