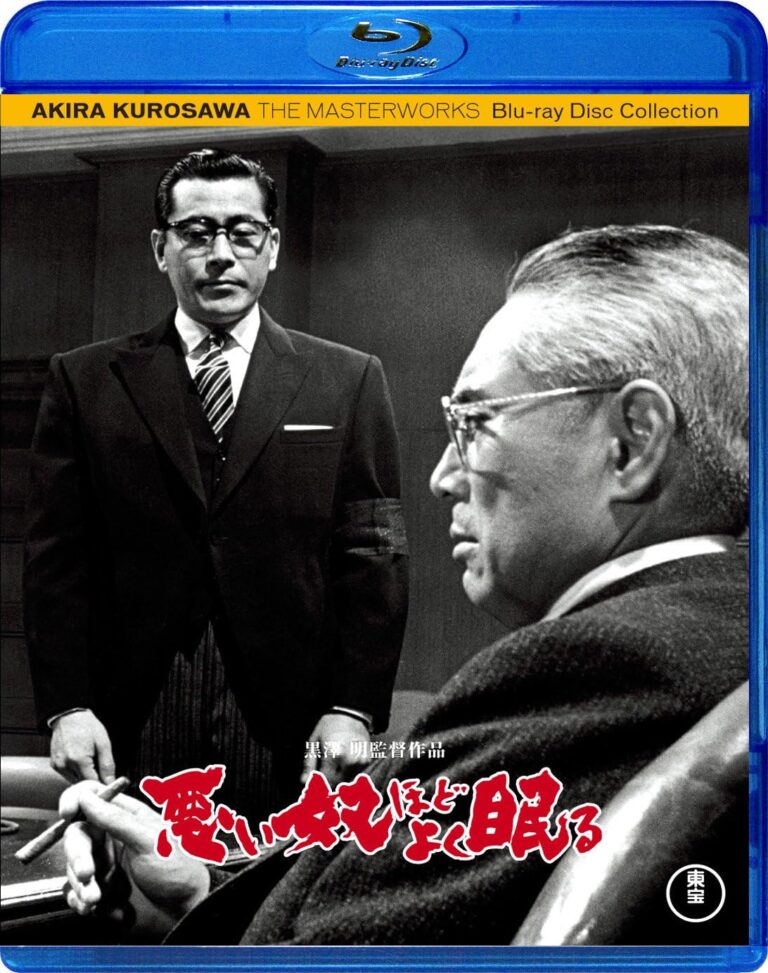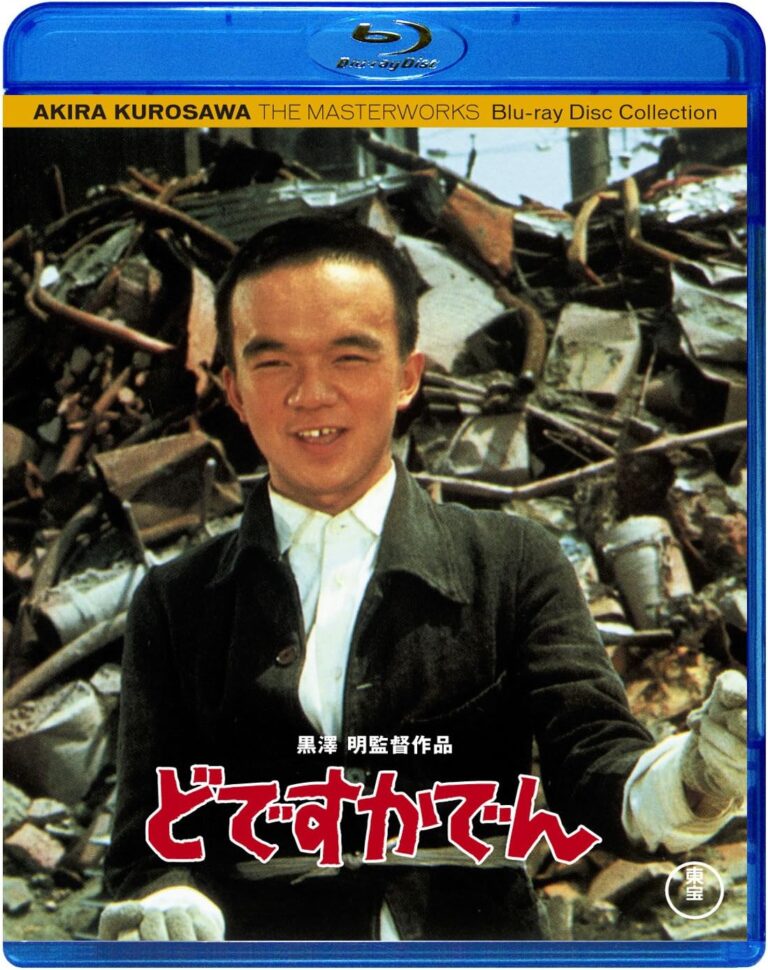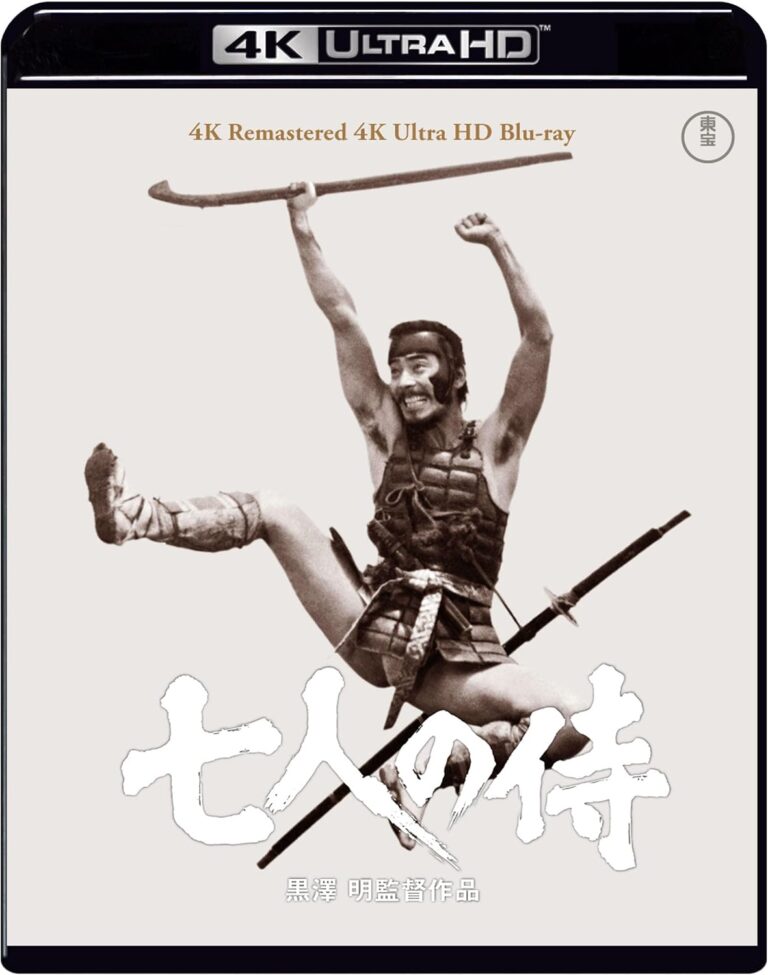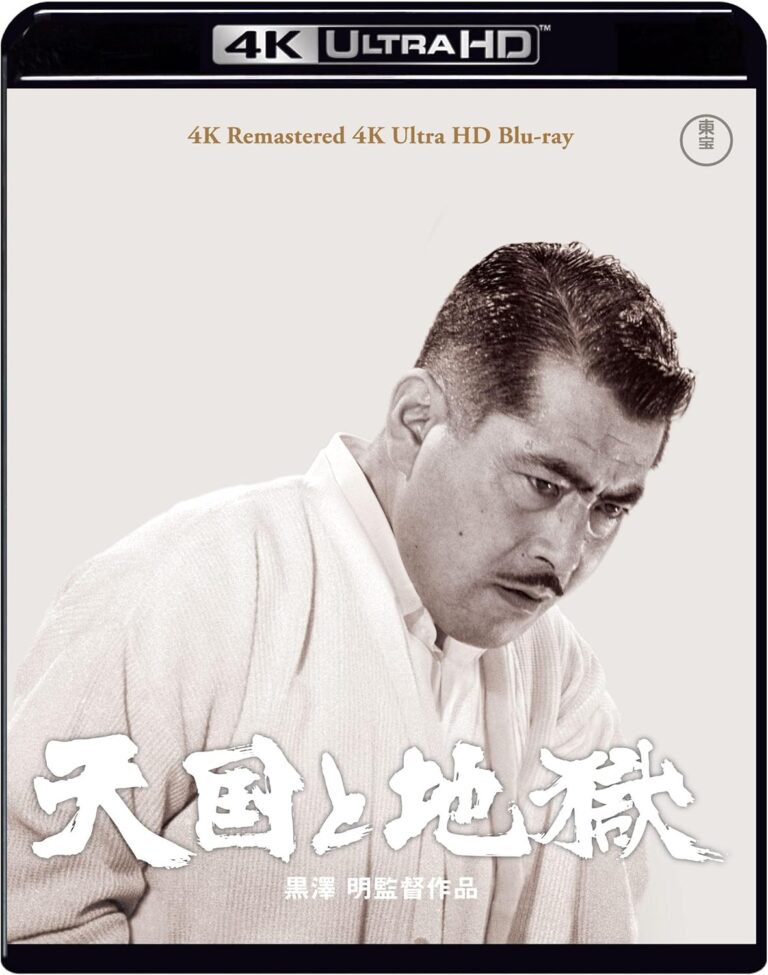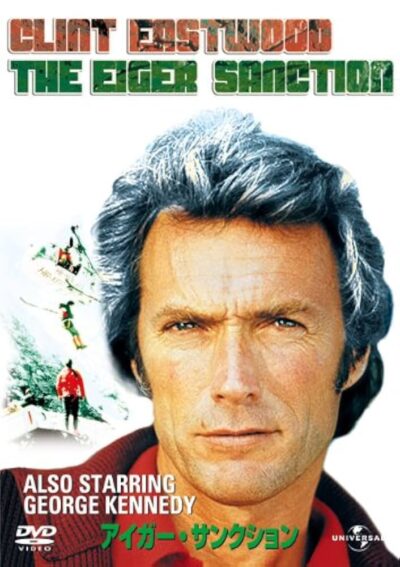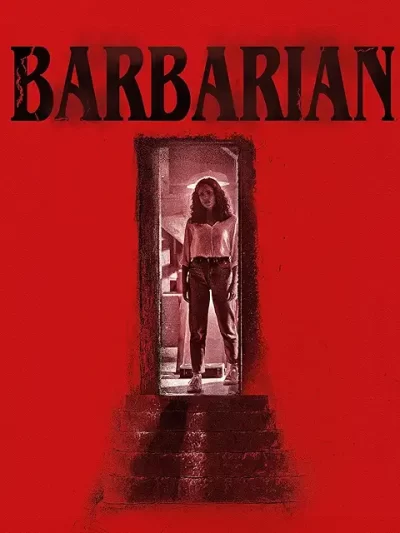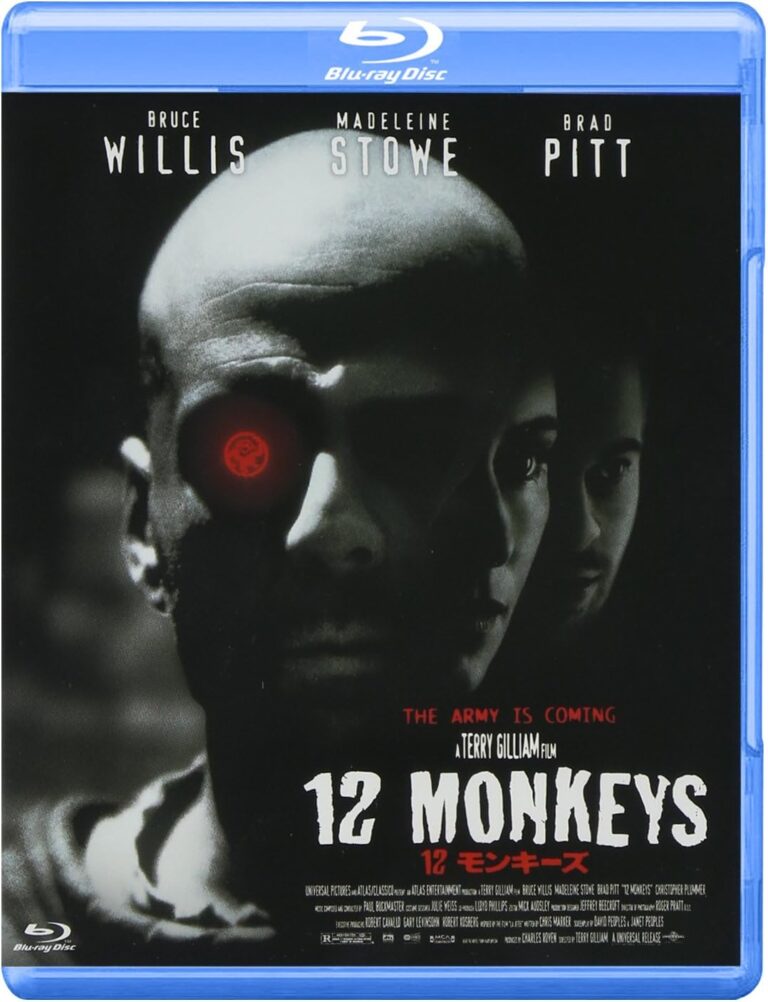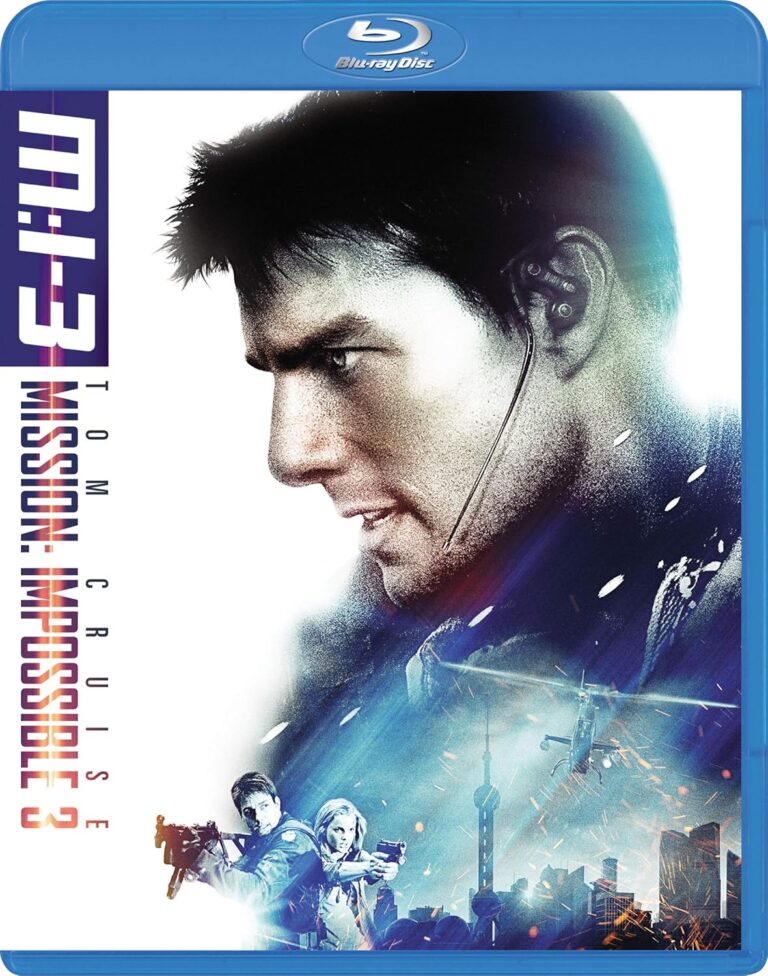『野良犬』(1949)
映画考察・解説・レビュー
『野良犬』(1949年)は、黒澤明監督による刑事スリラーの名作。拳銃を盗まれた新人刑事・村上(三船敏郎)が、自らの失態を取り戻そうとする焦燥感の中で、鏡合わせの存在である犯人・遊佐(木村功)の孤独を理解していく。戦後日本の焦土から立ち上がる混沌と、その中で「正義」という名の重い十字架を背負った男たちの姿を、圧倒的な映像言語で描き出した。
コルトという去勢とドッペルゲンガー
スクリーンから熱気が噴き出してくるような猛暑の中、新人刑事・村上(三船敏郎)が汗だくになって走る。満員のバスの中でスリに遭い、商売道具であり、国家権力の象徴であり、男根のメタファーでもあるコルトの拳銃を盗まれてしまったからだ。
『野良犬』(1949年)は、拳銃紛失事件を描いたサスペンスであると同時に、戦争によってアイデンティティを剥奪された一人の青年が、自分自身の影を追いかけ、東京という地獄を巡礼する、魂の去勢と回復の物語である。
黒澤明が本作の着想を得たのは、ジョルジュ・シムノンのジュール・メグレ警視シリーズ。シムノンの小説が犯人の心理への同化を描くように、黒澤もまた、刑事と犯人を光と影の関係として構築した。
村上刑事と、彼から銃を奪い、強盗殺人を繰り返す犯人・遊佐(木村功)。二人は、共に復員兵であり、戦争で全てを失い、帰る場所を持たないという点で、鏡合わせの存在といえる。
劇中、ベテラン刑事の佐藤(志村喬)は「一皮むけば、お前と遊佐は同じだ」と語る。このセリフこそが、本作の核だ。村上は、自分が一歩間違えれば遊佐になっていたかもしれないという恐怖に突き動かされている。彼が必死に銃を探すのは、強烈な当事者意識と、自己嫌悪からなのだ。
村上が闇市を彷徨うシーンでの、あの飢えたような、それでいて怯えたような三船敏郎の目。彼は刑事の顔をしていない。タイトル通り、行き場を失った一匹の野良犬の目をしている。
戦後という時代は、誰もが野良犬だった。国家という飼い主を失い、価値観が崩壊した焼野原で、ある者は法を守る犬になり、ある者は人に噛みつく狂犬となったのである。
本作が制作された1949年が、まだGHQの占領下にあったことも重要だ。警察官が銃を持つこと自体が特別な意味を持っていた時代、それを奪われるという失態は、単なる職務怠慢を超えて、戦後日本の無力な去勢感と直結している。
村上の焦燥感は、当時の日本人男性が抱えていた劣等感や焦りと同期していたからこそ、これほどまでに観客の胸を締め付けるのだ。
本多猪四郎のゲリラ撮影と汚れた東京
『野良犬』が同時代の日本映画と一線を画しているのは、その圧倒的なドキュメンタリー的リアリズムにある。冒頭から中盤にかけて、村上が銃を探して上野のアメ横や浅草の闇市を歩き回るシークエンスは、実際の1949年の東京の風景だ。
この撮影を敢行したのは、後に『ゴジラ』(1954年)を監督することになる黒澤の無二の親友、本多猪四郎。彼は隠しカメラを使い、浮浪児、パンパン、傷痍軍人、そして汗まみれで商売をする人々を、盗み撮り同然のゲリラ撮影でフィルムに焼き付けた。
黒澤はこの素材を見て唸ったという。作り物のドラマの中に、制御不能な現実のノイズが混入することで、映画はフィクションの枠を超え、時代の証言記録へと変貌した。
特に印象的なのが、当時のファッションや風俗の描写。犯人の遊佐は、貧しい生活をしているはずなのに、真っ白な麻のスーツを着ている。それは、汚れた世界に対する彼なりの精一杯の虚勢であり、同時に汚れやすさ(=堕ちやすさ)の象徴でもある。
対する村上は、薄汚れたランニングシャツ姿で、汗を拭うこともせずに歩き回る。画面の端々から、当時の日本の蒸し暑さと、腐敗した生ゴミの臭いまでもが漂ってくるようだ。
黒澤は、この不快指数を意図的に高めることで、登場人物たちの精神的圧迫感を視覚化した。扇風機が回る音、ハエがたかる音、そして人々の怒号。不快なノイズの集積こそが、戦後日本のリアリティだったのだ。
『野良犬』は音響演出においても革新的だった。犯人のアジトで流れるラジオから、陽気なラテン音楽「ラ・パロマ」が流れるシーン。あるいは、緊張感あふれる尾行シーンで、場違いなほど明るい野球中継の音が重なるシーン。
これらは、悲劇的な状況と相反する音をぶつけることで、悲劇性を際立たせる対位法の手法だ。世界は個人の悲劇になど無関心であり、残酷なまでに日常は続いていく。その冷徹な対比が、村上の孤独をより一層深める。
極めつけは、犯人の情婦である踊り子・並木ハルミ(淡路恵子)の楽屋裏の描写。当時16歳だった淡路恵子の、あのふてぶてしくも妖艶な存在感!彼女は戦後派の象徴として登場し、古い道徳に縛られる村上を翻弄する。
彼女たちが生きる夜の東京の毒々しさと、村上が守ろうとする昼の正義の脆さ。このコントラストを、本多猪四郎の記録映像が下支えすることで、『野良犬』は単なる刑事ドラマを超えた、都市論としての強度を獲得している。
バディ・ムービーの始祖と、泥まみれの号泣
本作は、性格の異なる二人の刑事がコンビを組む、バディ・コップ・ムービーの元祖の一つとしても評価されている。
若く、情熱的だが危なっかしい村上と、老練で冷静だが人情味あふれる佐藤。この黄金の組み合わせは、後の『セブン』(1995年)のブラッド・ピットとモーガン・フリーマンや、『踊る大捜査線』の織田裕二といかりや長介など、無数のフォロワーを生んだアーキタイプだ。
志村喬の演技は、まさに父性そのもの。焦る村上を自宅に招き、冷やしたビールを飲ませ、「まあ、落ち着け」と諭す。ここで描かれるのは、先輩後輩の枠を超えた、疑似的な父子関係だ。
戦争で父や兄を失った世代(村上)に対し、生き残った旧世代(佐藤)が、どうやって生きるべきかを背中で教える。『野良犬』が単なるサスペンスで終わらないのは、この人間ドラマの厚みがあるから。
佐藤が犯人に撃たれ、瀕死の重傷を負ったとき、村上の怒りは頂点に達する。それは「銃を取り戻す」という目的が、「父(佐藤)の仇を討つ」というより根源的な動機へとスライドする瞬間だ。
そして迎えるクライマックス。場所は、皮肉にも平和の象徴のような、花が咲き乱れる郊外の原野だ。激しい格闘の末、村上と遊佐は泥まみれになり、どちらが刑事でどちらが犯人かもわからない状態で倒れ込む。
ここで黒澤は、劇的なBGMを一切流さない。聞こえてくるのは、近くの民家から、たどたどしいピアノの練習曲が聞こえてくるだけだ。遊佐の口から漏れるのも、悪党の捨て台詞ではなく、悲痛なうめき声と号泣だ。
泥にまみれて泣く遊佐を見下ろす村上の目には、勝利の喜びはない。あるのは、「そこにいたのは、自分だったかもしれない」という、深い悲しみと共感だ。
黒澤明は、安易なカタルシスを徹底的に拒絶する。犯人を捕まえても、銃が戻っても、戦争が残した傷跡は癒えないし、社会の貧困も解決しない。
花畑の中で響くピアノの音は、これから訪れる平和な時代の予兆かもしれないが、泥にまみれた彼らにとっては、あまりにも遠い世界からの騒音でしかない。
『野良犬』は、戦後日本が抱えた解決不能な問いを、そのままフィルムに定着させた。だからこそ、この映画は70年以上経った今も、古びるどころか、現代社会の格差や断絶を映す鏡として、我々の前に立ちはだかっている。
![野良犬/黒澤明[DVD]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/61pBEKC8BPL._AC_UL640_FMwebp_QL65_-1-e1769089672999.webp)
![メグレ警視のクリスマス[本]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/41L-QRTDgRL.jpg)
![ゴジラ/本多猪四郎[DVD]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/81gAu9SkxSL._AC_UL640_FMwebp_QL65_-e1771242881788.webp)
![セブン/デヴィッド・フィンチャー[DVD]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/61lj5Vqd5TL._AC_SL1263_-e1759018786744.jpg)