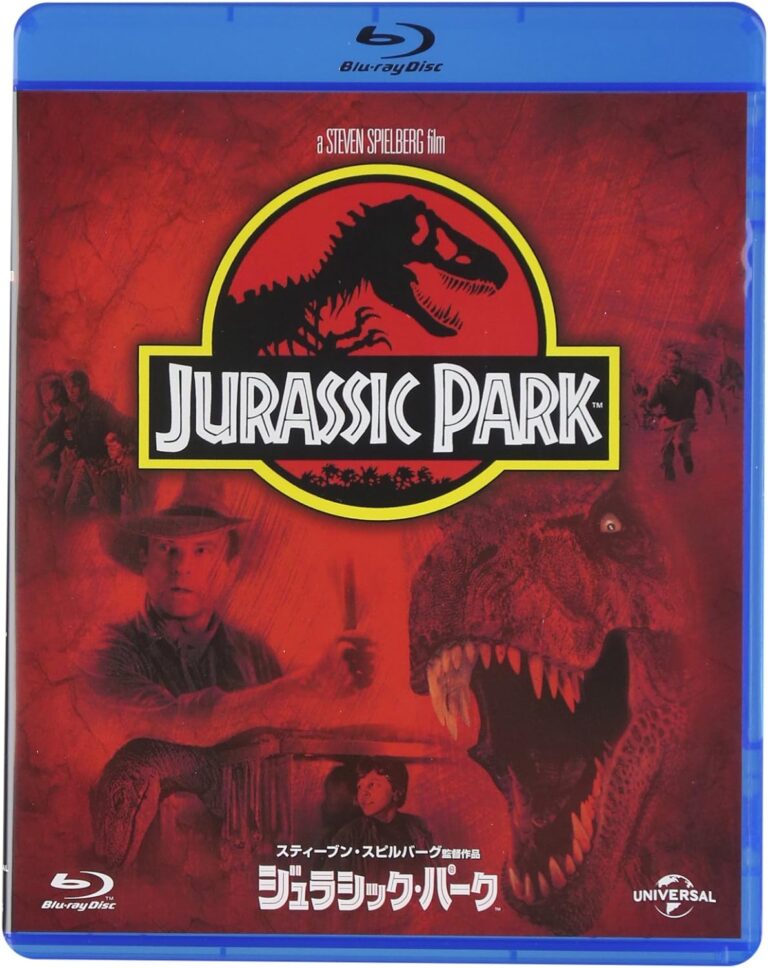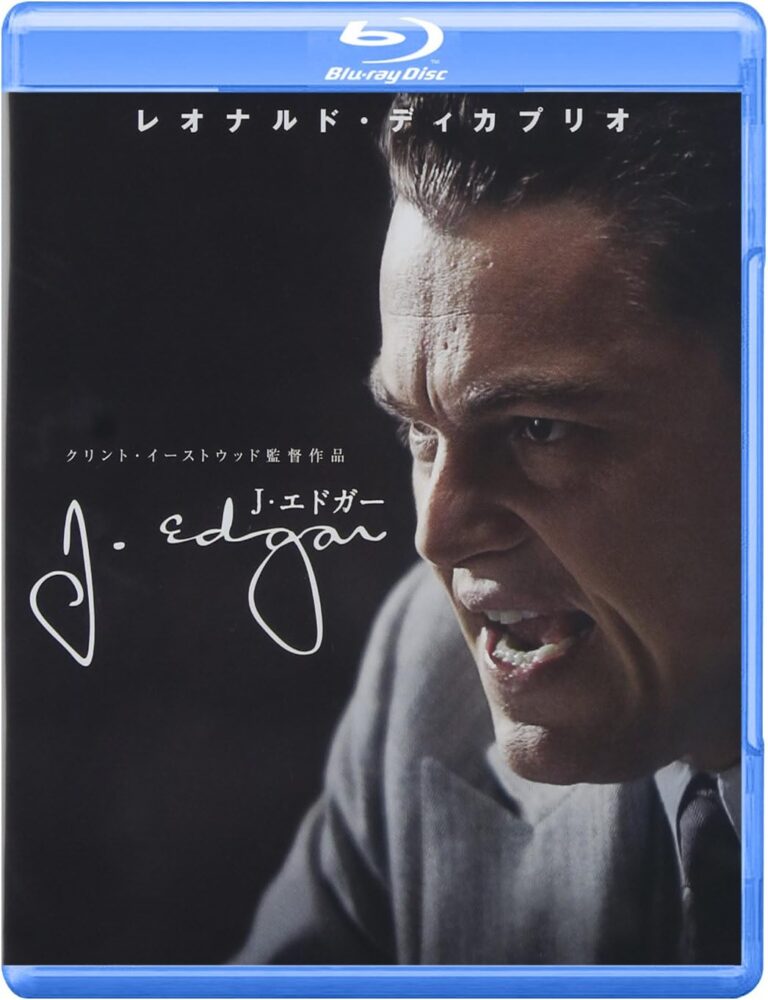『スピード』──純度100%のアクション主義
『スピード』(原題:Speed/1994年)は、ロサンゼルスで発生した連続爆破事件をめぐるサスペンス・アクションである。SWAT隊員のジャックと乗客アニーが、爆発の危機を前に走り続ける。止まることの許されない車内で、彼らは恐怖と勇気の狭間に立たされる。
物語を捨てた映画
『スピード』(1994年)は、脚本の時点からすでに潔い。人物描写や舞台背景などはほとんど無視され、あるのは「動く」「止まらない」「爆発する」という三つの動詞だけ。
ハリウッドのマッチョ主義を極限まで研ぎ澄まし、映画を“行動そのもの”へと還元した結果、ここには心理も主題も存在しない。あるのはただ、爆発音と緊張の連続である。
ここまでして“カツドウシャシン”に徹した潔さの前では、「人間が描かれていない」という批判など無意味だ。映画とは本来、動きの芸術なのだという信念がここに貫かれている。
監督のヤン・デ・ボンは、『ダイ・ハード』(1988年)や『リーサル・ウェポン』(1987年)などで撮影監督を務めてきた映像職人。彼はドラマ演出には不器用だが、爆発と速度の撮り方を熟知している。
だからこそ、本作では“物語を演出する”のではなく、“カメラで状況を設計する”という異端のアプローチを取った。ドラマの欠如は計算された空白であり、彼が狙ったのは「映像だけで観客を支配すること」だった。
特筆すべきは、縦・横・水平という三方向の運動を連鎖的に展開させるアクション設計だ。エレベーター(縦のアクション)、バス(横のアクション)、地下鉄(水平のアクション)。
この三重構造によって、映画全体が“運動の図形”として組み立てられている。デ・ボンのカメラは決して観客を休ませない。動く密室の連続が、観客の呼吸までも奪っていく。
ステレオタイプの極北
キアヌ・リーブス演じるSWAT隊員ジャック・トラヴェンは、キャラクターというより“装置”に近い。彼は思考せず、ただ反応する。
ブルース・ウィリスが『ダイ・ハード』で見せたような皮肉や人間臭さは一切排除され、代わりに“行動の純粋形”として存在する。言い換えれば、ジャックは人間の皮を被った“アクションの擬人化”である。
一方、デニス・ホッパーが演じる爆弾魔は、理由もなく悪であり続ける。彼にドラマは不要だ。もはや背景などどうでもよく、彼の存在は狂気そのものとしてスクリーンに刻まれている。
年老いたサイコ親父が笑いながら暴走する姿は、映画的時間の暴力を体現している。ホッパーが老いとともに凶暴さを増す様は、ハリウッドが生んだ“終末のピエロ”のようだ。
そんな狂騒の中で、サンドラ・ブロックの存在が唯一の呼吸孔として機能する。彼女が演じるアニーは、単なるヒロインではなく、観客の代理として“常識”を担う人物だ。
恐怖と混乱の中で見せる一瞬の笑顔、軽口、涙。それらが映画全体のテンションを微妙に調律し、作品に人間的リズムを与えている。ブロックはこの作品で一気にスターダムへ駆け上がったが、それは単なる偶然ではない。
彼女の存在が、冷たいアクションの構造に温度をもたらしているのだ。
“考えるな、走れ”──運動の哲学
『スピード』は、思考を拒絶する映画である。観客に問うでも、説くでもなく、ただ「見よ、感じよ」と命じる。哲学の代わりに加速度があり、心理の代わりに衝撃波がある。
だが、ここまで徹底されると、それはもはや“愚直”ではなく“純粋”だ。ヤン・デ・ボンは、ドラマを削ぎ落とすことで逆説的に“映画の本質”をあぶり出した。
バスが爆走する。ブレーキは効かない。観客のまぶたも止まらない。物語など不要だ。ここにはただ、映像の運動と時間の流れだけがある。『スピード』は、アクション映画というジャンルを一度“ゼロ地点”に還元した作品であり、その潔さこそが最高の美学である。
頭を空にして観ること──それがこの映画の正しい鑑賞法だ。考えるな、走れ。それだけで十分だ。
- 原題/Speed
- 製作年/1994年
- 製作国/アメリカ
- 上映時間/ 115分
- 監督/ヤン・デ・ボン
- 製作/マーク・R・ゴードン
- 製作総指揮/イアン・ブライス
- 脚本/グラハム・ヨスト
- 撮影/アンジェイ・バートコウィアク
- 音楽/マーク・マンシーナ
- 美術/ジャクソン・デ・ゴヴィア
- 編集/ジョン・ライト
- キアヌ・リーヴス
- デニス・ホッパー
- サンドラ・ブロック
- ジョー・モートン
- ジェフ・ダニエルズ
- アラン・ラック
- グレン・プラマー
- リチャード・ラインバック