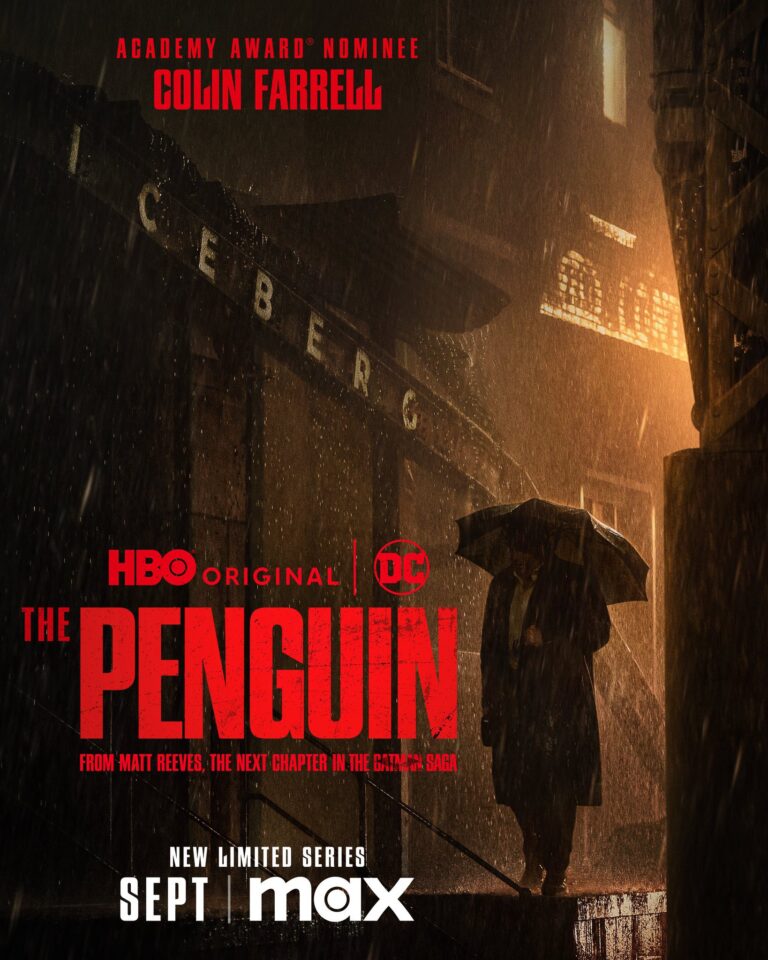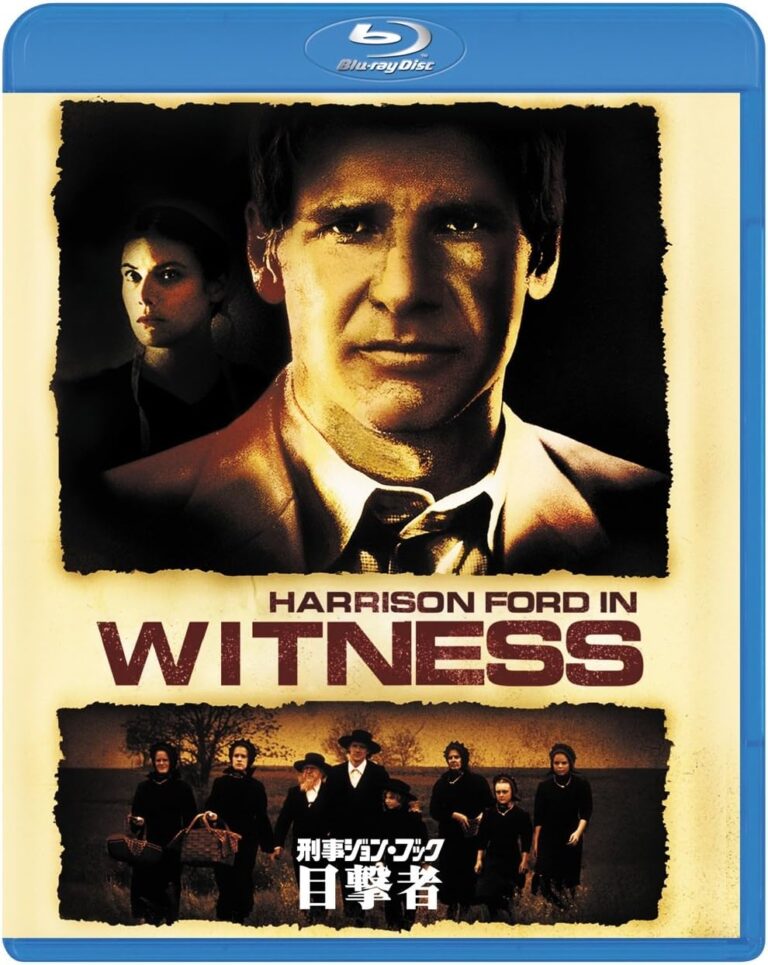『スパイダーマン2』──ヒーローが「普通に戻りたい」と願うとき
『スパイダーマン2』(原題:Spider-Man 2/2004年)は、サム・ライミ監督によるシリーズ第2作。大学生となったピーター・パーカーが、ヒーローとしての使命と日常生活の板挟みに苦しみながら、愛するMJや友人との関係に葛藤する。新たな敵ドック・オクとの対決を通じて、“責任”の意味を改めて問う青春ドラマ。
男が泣ける映画
何でも巷では、「スパイダーマン2は男が泣ける映画だ」という風評が、まことしやかに流れているらしい。
この言説は誇張ではない。むしろ「責任を引き受ける」という主題が、現代社会に生きる人々の切実な経験と共鳴しているからこそ生じた文化的現象である。仕事、家族、恋愛──あらゆる側面で重荷を背負わされる社会人男性にとって、「普通の人間に戻りたい」と嘆くピーター・パーカーの姿は、そのまま自分自身の鏡像に他ならなかった。
このモチーフは、古典神話からすでに存在する。英雄ヘラクレスは半神半人の力を持ちながらも、普通の人間として生きることを望んだ。近代文学においても、特別な力を持つ主人公がその力を拒む場面はしばしば描かれる。
しかし『スパイダーマン2』は、このモチーフを物語全体の推進力として徹底化した。ピーターは学業やアルバイトに追われ、友人との関係も壊れ、恋愛は実らない。つまり、彼の「普通でいたい」という欲望は単なる気まぐれではなく、日常生活そのものから必然的に生じた切実な叫びなのである。
この欲望は、日本のアイドル文化に近接している。1970年代後半から1980年代にかけて、キャンディーズをはじめとするアイドルたちは「普通の女の子に戻りたい」と宣言して引退した。これはファンにとって大きな感情的カタルシスを伴う儀式であり、アイドルにとっても夢から降りる唯一の方法だった。
ピーターの欲望も同じ構造を持つが、彼の場合は夢から降りることが許されない。彼が「普通」に戻れば、ニューヨークは危機に陥る。この矛盾が物語を青春悲劇として構造化し、観客の共感と涙を誘うのだ。
青春映画としての『スパイダーマン2』
本作を青春映画として位置づける視点は、批評史的に重要だろう。アメコミ映画はしばしば勧善懲悪の物語として語られるが、ライミ版『スパイダーマン2』はむしろ青春コメディ/青春ドラマの構造を踏襲している。
ピーターの苦難は、恋人とのすれ違い、学業の不振、経済的困窮、社会的役割の重圧といった、ごく凡庸な問題で構成されている。観客が涙するのは、彼が超人だからではなく、彼があまりにも「普通の青年」だからだ。
この点で『スパイダーマン2』は、『アメリカン・グラフィティ』(1973年)の青春群像劇や、『フェリスはある朝突然に』(1986年)の無責任な冒険譚と地続きにある。つまり本作は、ヒーロー映画のフォーマットを借りながらも、実態としては「青春映画の系譜」に属しているのだ。
キルスティン・ダンスト演じるMJは、青春映画的文脈における女性像の転換を示したものだといえるだろう。『ヴァージン・スーサイズ』(1999年)において彼女は不可触の幻想的ヒロインだった。しかし『スパイダーマン2』では、現実に悩み、選択を迫られる等身大の女性として描かれる。
この変化は2000年代初頭のハリウッド全体の傾向と一致する。夢の中の少女像から、現実を引き受けるパートナー像へ。MJはその象徴的存在だったのだ。
市民に救われるヒーローの革新性
『スパイダーマン2』をヒーロー映画と考えたとき、物語のクライマックスで描かれる「電車のシーン」は、映画史に残る革新的瞬間といえるのではないか。スパイダーマンが必死に電車を止め、力尽きて倒れる。その素顔を市民が目にしながらも秘密を守り、彼を抱きかかえて守る場面は、観客に深い感動をもたらす。
ここで描かれているのは、ヒーローと共同体の新しい関係だ。従来のヒーローは孤高の存在であり、市民を守る側に立ってきた。だが『スパイダーマン2』では、市民がヒーローを守る。この逆転は、ヒーローが「共同体の一員」として承認される瞬間を意味していた。
この場面が9.11以降のアメリカ社会において特に大きな意味を持ったことは疑いない。崩壊する都市、瓦礫の中で互いを助け合う市民の姿を経験した観客にとって、このシーンは希望の寓話であり、共同体再生の物語として機能したのである。
ドック・オクの鏡像性と悲劇性
悪役ドック・オクは、従来のアメコミ映画の悪役像とは異なる人間的厚みを備えている。科学者としての理想を追い求めながらも、自らの発明に飲み込まれ、責任を放棄してしまう彼は、ピーターのもう一つの可能性を体現する存在である。
ここにおいて、ライミは「悪役を鏡像として描く」という古典的手法を巧みに活用している。ピーターが責任を選ぶのに対し、オクは責任を放棄する。両者の対比は単なる勧善懲悪を超え、「責任を果たすとは何か」という倫理的テーマを浮かび上がらせる。
アルフレッド・モリーナの演技は、怪物的誇張よりも人間的弱さを前景化させた。観客は彼を単なる悪役ではなく、「失敗した大人」として見る。だからこそオクとの戦いは倫理的葛藤として観客に響くのである。
ライミ三部作の位置づけ
『スパイダーマン』三部作を通観すると、『2』はその核心に位置する。第一作は「力を得ること」、第三作は「力を濫用すること」に焦点を当てた。対して第二作は「力を失うこと」と「責任を再確認すること」を描いた。三部作の中で最も人間的で、最も普遍的なテーマを扱った作品である。
『3』がサブプロット過多で批評的評価を落としたことを考えれば、『2』の構造的洗練は一層際立つ。批評史的にも『スパイダーマン2』は三部作の頂点であり、21世紀スーパーヒーロー映画の金字塔として位置づけられる。
この流れは、後続のスーパーヒーロー映画と比較してみるとわかりやすい。クリストファー・ノーランの『ダークナイト』(2008年)は、よりシリアスで政治的なバットマン像を提示し、スーパーヒーローを現実政治のメタファーへと昇華した。MCUは逆に、シリーズ横断的にキャラクターを配置し、共同体の物語を壮大に拡張した。
一方、ザック・スナイダーの『マン・オブ・スティール』(2013年)や『バットマン vs スーパーマン』(2016年)は、ライミ的青春悲劇ともノーラン的リアリズムとも異なる「神話的ヴィジョン」を強調した。
これらと比較することで、『スパイダーマン2』の位置はより鮮明になる。本作は、神話的誇張と政治的リアリズムの中間に位置する「青春の物語」として独自の輝きを放っている。
「泣ける映画」としての必然
『スパイダーマン2』は、単なるヒーロー映画でも、単なる青春映画でもない。責任と承認をめぐる物語として、9.11以降のアメリカ社会の要請に応え、スーパーヒーロー映画を新たな段階へと導いた。
ピーター・パーカーは「普通の男の子に戻りたい」と願いながらも責任を選び、市民は彼を守り、悪役は鏡像として彼を試し、ヒロインは現実を生きる女性像へと変容する。ライミはホラー映画の文法を青春映画の枠組みに接続し、スーパーヒーロー映画の批評史的転換点を築いた。
この映画が「男が泣ける映画」として語られるのは、単なる偶然でも風評でもない。それは社会的・文化的・映画史的必然に支えられた評価であり、21世紀スーパーヒーロー映画の礎を築いた事実を示している。
- 原題/Spider-Man2
- 製作年/2004年
- 製作国/アメリカ
- 上映時間/127分
- 監督/サム・ライミ
- 製作/ローラ・ジスキン、アヴィ・アラド
- 製作総指揮/スタン・リー
- 脚本/アルビン・サージェント
- 撮影/ビル・ホープ
- 音楽/ダニー・エルフマン
- 美術/ニール・スピサック
- 編集/ボブ・ムラウスキー
- トビー・マグアイア
- キルスティン・ダンスト
- アルフレッド・モリーナ
- ジェームズ・フランコ
- ローズマリー・ハリス
- J・K・シモンズ
- ディラン・ベイカー
- ビル・ナン
- テッド・ライミ
- エリザベス・バンクス