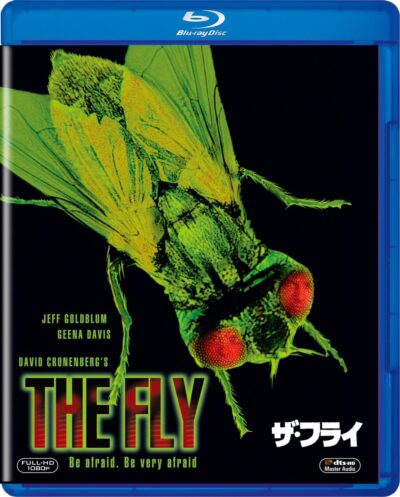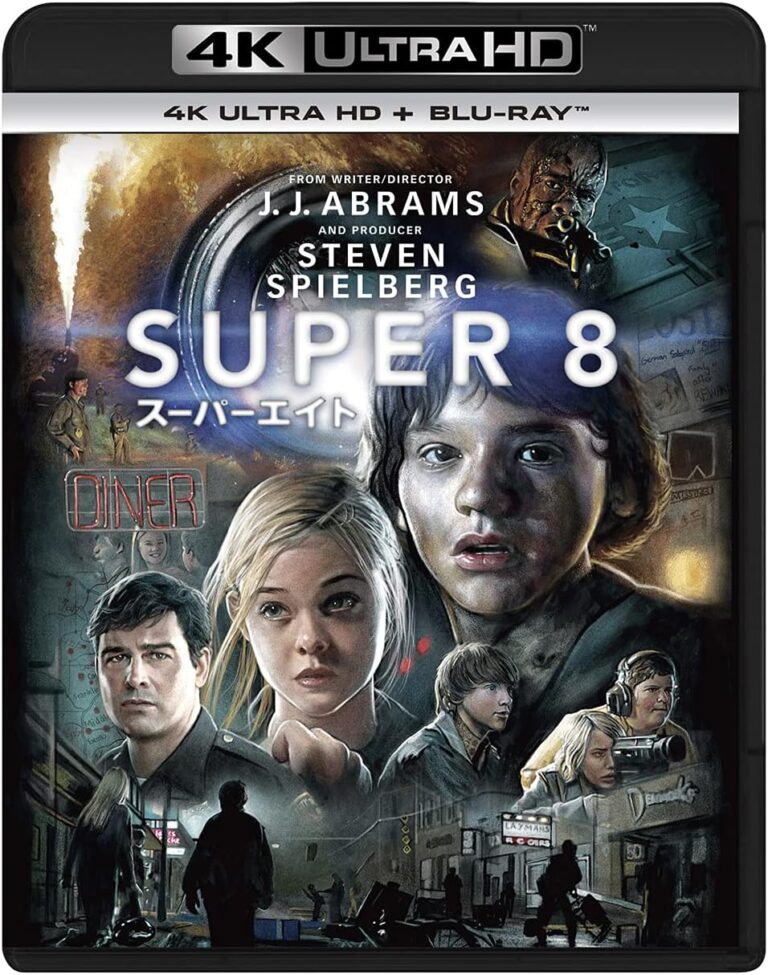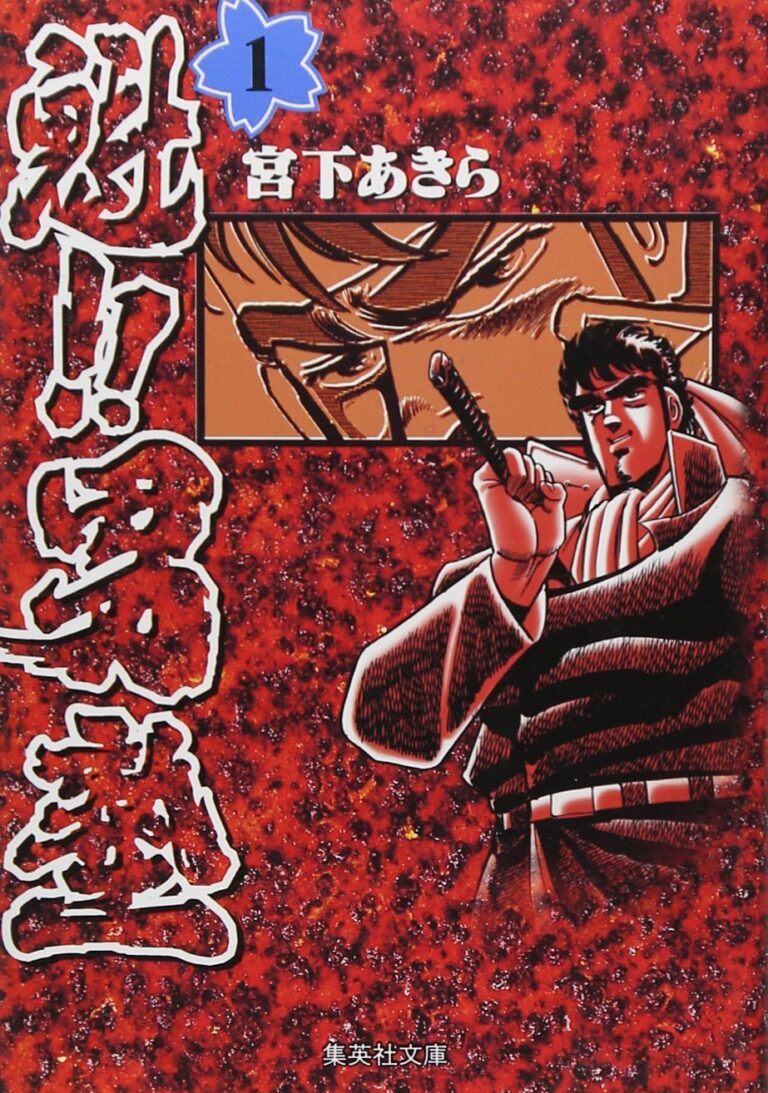『ザ・フライ』(1986)
映画考察・解説・レビュー
『ザ・フライ』(原題:The Fly/1986年)は、科学者セス・ブランドルがテレポート実験中にハエと融合し、次第に人間性を失っていく物語。デヴィッド・クローネンバーグ監督が、肉体の変化を通じて愛と科学の境界を描く。グロテスクな変身の奥に、愛と救済の悲劇が静かに息づく。
科学と愛の融合!理系グロテスクが描く究極のラブストーリー
SF映画の古典『蠅男の恐怖』(1958年)を、あのデヴィッド・クローネンバーグがリメイクする。1986年にこの企画が発表された時点で、すでに異常な化学反応の匂いがプンプンと漂っていた。
物質を転送するテレポーテーション実験の最中、一匹のハエが装置に紛れ込む。ジェフ・ゴールドブラム演じる天才科学者セス・ブランドルは、あろうことかハエと遺伝子レベルで融合してしまうのだ。
あらすじだけをなぞれば、明らかにB級トランスフォーメーション系のボディホラー。だがクローネンバーグの真の狙いは、突発的な変身ではなく、緩やかで不可逆的な変化にある。
人間の身体がドロドロに崩壊していく過程を、顕微鏡のように冷徹に観察する。そしてその背後にひっそりと潜む、切実な愛の構造を容赦なく暴き出す。
科学の傲慢と人間の情念が真っ向から衝突する、痛切な寓話。そう、本作はSFホラーの形式を借りた、理系グロテスク・ラブストーリー(そんなジャンルないけど)なのだ。
彼が描くグロテスク描写は、ダリオ・アルジェントやジョージ・A・ロメロのような、悪趣味アトラクション演出とは違う。彼のカメラは肉体の変質を、逃れられない内的論理として冷淡に描き出す。
皮膚がボロボロに剥がれ落ちる。指がポロリと欠け落ちる。歯が抜け、関節が異常な角度にひん曲がっていく。クリス・ウェイラスが手がけたこの凄まじい特殊メイクのプロセスは、恐怖のギミックではなく生物学的現象として我々の前に提示される。
観客はスクリーンに向かって悲鳴を上げる余裕すらない。ただただ息を呑んで、その悲惨な崩壊を観察し続けることを強いられる。クローネンバーグのグロテスクは極めて理性的であり、倫理的ですらあるのだ。
血と粘液の匂いが充満する密室の実験室。そこでは科学は、もはや取り返しのつかない進化の暴走として機能している。神の領域への無謀な越境を試みた者の傲慢。その残酷な報いとしての肉体崩壊が、見事に重ね合わされているのだ。
セスの肉体変化は、人間性の限界そのものを痛々しく可視化したプロセスである。クローネンバーグは恐怖を描くためではなく、人間であることの定義を問うために、変身というガジェットを用いたのだ。
クローネンバーグが暴く肉体の限界
リトアニア系ユダヤ人の家庭に生まれたクローネンバーグは、大学で生物学と生化学を本格的に学んだ経歴を持つ。その後、ビート文学とアンダーグラウンドな実験映画に激しく傾倒していった。
理系と文系。科学の冷徹さと文学の情念。彼の特異な作品世界は、常にこの二つの項目の交差点に存在している。本作『ザ・フライ』は、その二重螺旋が見事に融合した象徴的作品だ。
科学実験の失敗によって生じたグロテスクな悲劇を、彼はあくまで一つの美しい詩として語り抜く。テレポート装置が生み出したのは、人間の存在構造そのものに潜む致命的なバグだ。
セスが異形のアントニー(ハエ男)へと変化していく過程は、創造と破壊、理性と欲望が等価に並置された現代の神話といえる。クローネンバーグはシャーレの上に置かれた細胞を覗き込むように人間を観察し、その変容を冷ややかにフィルムへと記録していく。
だがその冷徹な視線の奥底には、観察対象への深い愛情と哀憫が確かに支えとして存在している。科学的思考と文学的感性の奇跡的なマリアージュ。それが彼の映画を異常なまでに人間臭くしている最大の理由といっていいのではないか。
主人公セスを演じたジェフ・ゴールドブラムの存在が、この映画の体感温度を決定づける。彼の演技は常に過剰で、異常に神経質で、観客の精神的な耐性を執拗に試してくる。端的に言ってしまえば、顔のルックスも含めてとにかくクドいのだ。だがその強烈なクドさこそが、セスの崩壊を観念的なお遊びに留めず、観客の感情の奥底へとダイレクトに接続する。
彼は実験に狂信的にのめり込む科学者であると同時に、愛する女に溺れ切る一人の男でもある。変身のプロセスが進行するにつれ、その二面性が肉体的なレベルでドロドロに融合していく。科学への異常な執念と恋人への粘着質な執着が完全に同化し、やがて救いようのない破滅を迎えるのだ。
おそらくクローネンバーグは、この俳優が放つ特有の熱を計算し尽くしていた。ゴールドブラムのクドすぎる芝居は、理性的なSFの物語を生々しい情動へと転換させる最強の触媒。だからこそ、理屈では絶対に説明できない悲劇の次元へと引き上げていく。
観客が彼の醜い変化に対して、単なる嫌悪感や恐怖ではなく深い哀れみを抱いてしまうのはなぜか。それは俳優の過剰な熱量が、圧倒的な感情のリアリティを生み出しているからだ。ここにこそ、クローネンバーグという映画作家の底知れぬ演出の巧みさが隠されている。
変身の詩学と悲劇のラスト
この凄絶な物語の中核を最後まで支え続けるのは、セスとジーナ・デイヴィス演じるヴェロニカとの恋愛関係だ。狂気の科学暴走を描くSF映画でありながら、実はこの映画の骨格は極めてシンプルで純粋な恋人たちの物語として構築されている。
セスはハエの遺伝子との融合によって、人間としての理性も肉体も完全に失っていく。だが、彼を想うヴェロニカの愛だけは最後まで決してブレることはない。
皮膚が溶け落ち、指が折れ曲がり、声が奇怪なノイズに変わっても、彼女はその醜悪なバケモノの中に、かつて愛した男の魂を必死に見出そうとするのだ。
そこに生まれるのは、海よりも深い慈悲の心。クローネンバーグはこのラストシークエンスを、一切の救いがない徹底的な悲劇として撮り切った。
完全にハエの怪物と化して苦しむセスが、無言のまま恋人にショットガンの銃口を自らの頭に向けさせる。ヴェロニカは泣き叫びながら、愛する者のためにその引き金を引く。
その残酷な瞬間、観客はこの凄惨な死の解放を、究極の愛の延長線上にあるものとして受け入れるしかない。頭を撃ち抜かれることが、これほどまでに美しく悲しい映画が他にあるだろうか?
『ザ・フライ』は、恋愛の究極の到達点を殺しの美学として描き切った奇跡の映画だ。ここでは死は永遠の別れを意味するものではない。呪われた肉体からの絶対的な救済として成立している。
クローネンバーグがスクリーンに叩きつける過激な残酷さは、実は彼が人間に対して抱く限りない優しさの裏返しに他ならない。セスの身体が完全に崩れ落ちたとき、そこにはただ純粋な愛の記憶だけが残される。
科学の力が肉体を無惨に破壊し、愛の力が精神を永遠に救済する。この強烈なパラドックスこそがクローネンバーグの真の美学だ。愛することは、他者と融合し、自らの自我を完全に喪失すること。セスがハエと一体化して崩壊していくプロセスは、まさに恋の極致としての自己喪失の完璧な比喩である。
クローネンバーグは、血と粘液と遺伝子の奥底に、誰も見たことのない究極の愛の形を見つけ出したのだ。
- 監督/デヴィッド・クローネンバーグ
- 脚本/チャールズ・エドワード・ポーグ、デヴィッド・クローネンバーグ
- 製作/スチュアート・コーンフェルド
- 原作/ジョルジュ・ランジュラン
- 撮影/マーク・アーウィン
- 音楽/ハワード・ショア
- 編集/ロナルド・サンダース
- ザ・フライ(1986年/アメリカ)