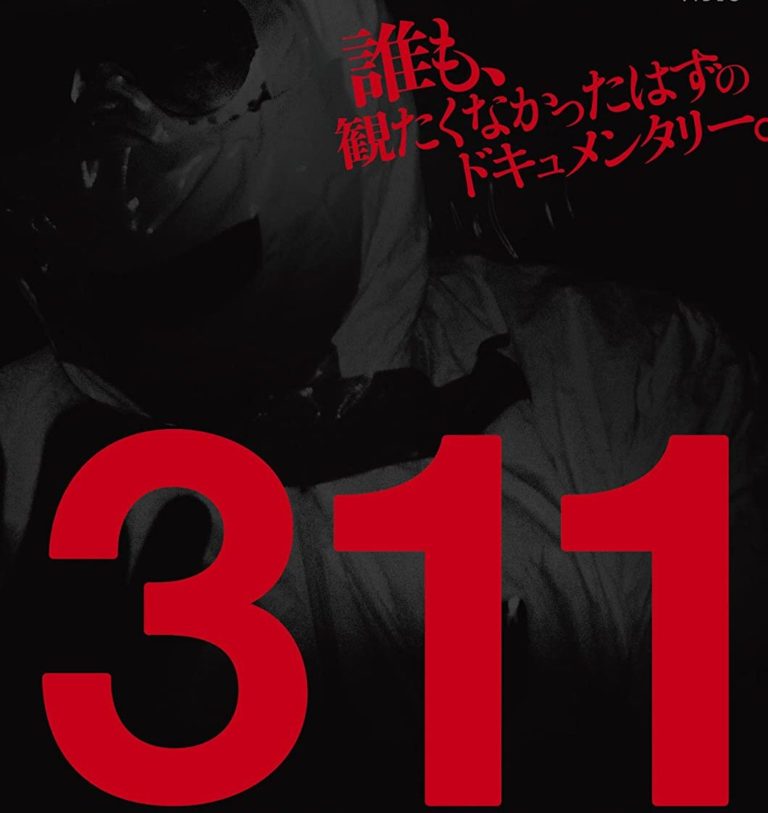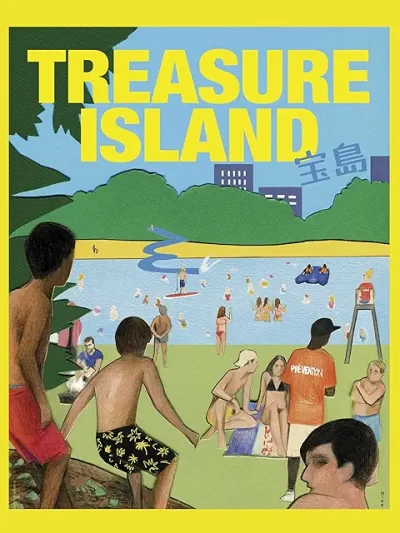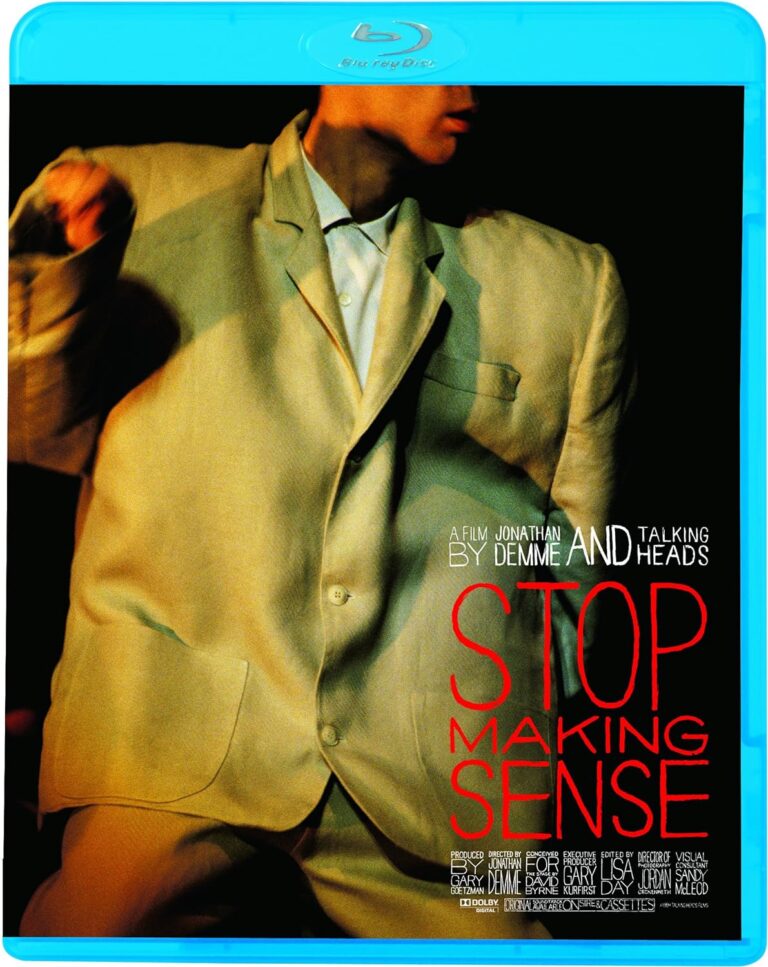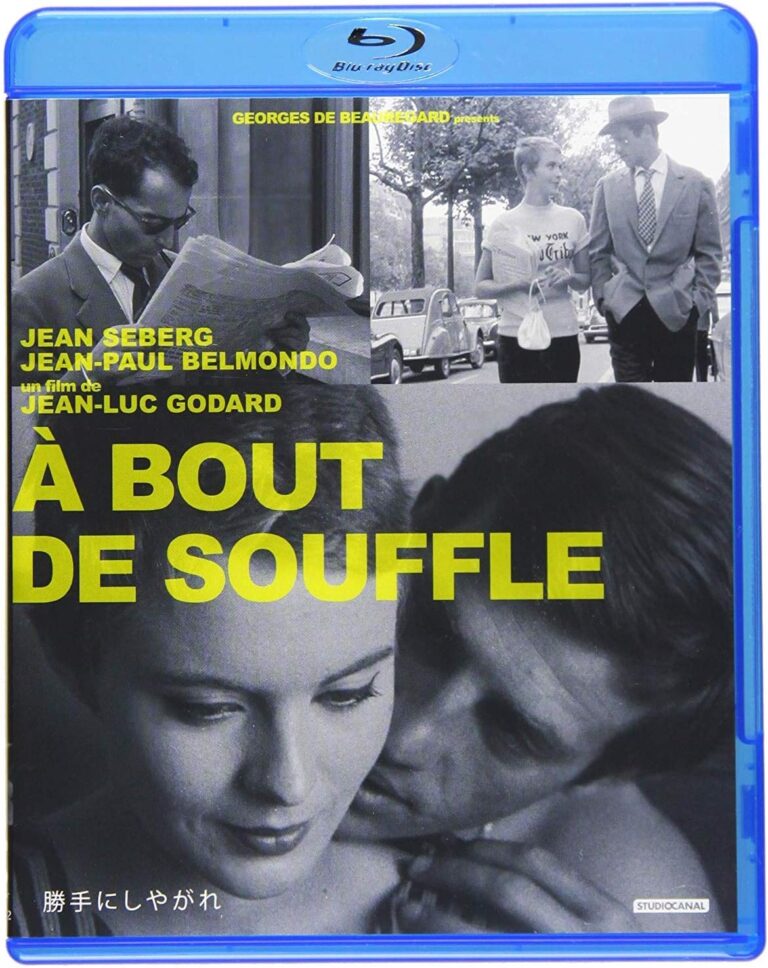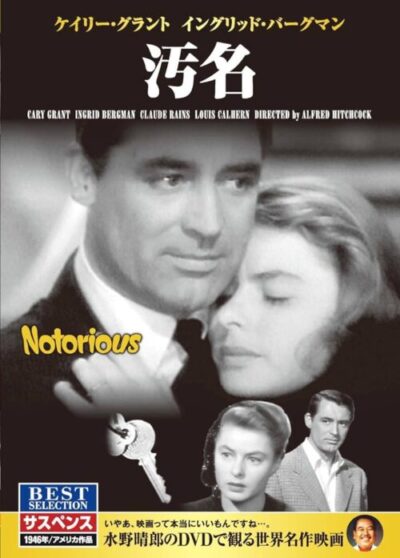『ゆきゆきて、神軍』(1987)
映画考察・解説・レビュー
『ゆきゆきて、神軍』(1987年)は、原一男監督が実在の元兵士・奥崎謙三を追ったドキュメンタリーである。太平洋戦争末期のニューギニア戦線で起きた上官による部下射殺事件の真相を暴こうと、奥崎が戦友を訪ね歩く過程を記録する。取材はやがて告発の枠を超え、撮る者と撮られる者の対立が、倫理と暴力の境界を浮かび上がらせていく。
原一男と奥崎謙三──暴力としての映画
強烈な個性を持った被写体を、同じくらい強烈な個性を持った監督が執拗につきつめて撮りあげた、驚天動地のドキュメント。それが『ゆきゆきて、神軍』(1987年)である。
その被写体は、激ヤバ・アナーキスト奥崎謙三。かつて天皇陛下にパチンコ玉を撃ち込んだ「天皇パチンコ事件」で知られる男だ。戦後日本にあって、彼ほど一貫して国家と暴力を自らの肉体で体現した人間はいない。
監督は、激ヤバ・ドキュメンタリー監督の原一男。『極私的エロス』や『全身小説家』で知られる、徹底的に“人間の奥底”を覗き込むフィルムメーカー。『ゆきゆきて、神軍』とは、彼ら二人の衝突そのものが映画化された、戦慄の作品なのだ。
原のカメラは単なる記録ではない。そこには撮影者自身の暴力が宿っている。奥崎が上官の家を訪ね、拳を振り上げるその瞬間、原のカメラもまた“殴っている”。
被写体と撮影者が互いに暴力を放ち合う。そのフレームの中でしか、この作品は成立しない。映画とは何か。倫理とはどこにあるのか。原はそれを問うために、撮るという行為そのものを極限まで露出させた。
カメラが撃つ、信念が返す──“撮る”と“撮られる”の戦場
『ゆきゆきて、神軍』の最大の恐ろしさは、カメラが“現実の武器”として機能している点にある。
奥崎は、ただの告発者ではない。彼はカメラの存在を知覚し、それを利用して自己を劇化する。つまり彼は“撮られることによって”自らの信念を世界に突き立てるのだ。撮影現場は、被写体と撮影者の協働的暴力の現場となる。
原一男のカメラは、しばしば無慈悲なまでに被写体を追い詰める。だが、その冷徹さの裏には、撮る者自身が“奥崎に取り憑かれている”ような奇妙な陶酔がある。
カメラは観察の装置であると同時に、感染の装置でもある。奥崎の狂気はレンズを通じて原に伝播し、さらに観客にまで波及していく。観客もまた、倫理の壁を越えて、暴力の現場に巻き込まれていくのだ。
ドキュメンタリーとは、本来「記録する」営為である。だが原の手にかかると、それは「介入」へと変わる。彼のカメラは状況を変化させ、撮影対象を破壊し、現実そのものを組み替える。
そこに立ち現れるのは、真実ではなく、真実が生成される瞬間。『ゆきゆきて、神軍』は、ドキュメンタリーというジャンルを倫理の地平から突き落とす、映画史上稀有な作品である。
奥崎謙三を単なる狂人として片付けるのは容易だ。だが彼の狂気は、個人の病理ではなく“戦後日本の残響”である。
ニューギニア戦線で起きた射殺事件を掘り返す彼の執念は、戦後社会が忘却しようとした戦争責任そのものへの告発。戦争が終わっても、戦争は終わらない──その矛盾の体現者が奥崎だった。
彼の怒号と暴力は、戦後民主主義の裏面に巣食う偽善を撃つ。国家の記憶は制度によって管理され、戦争は「過去」として封印された。しかし奥崎は、あえてその蓋をこじ開け、腐臭を放つ真実を曝け出す。彼の狂気とは、社会が葬り去った真実を“代わりに記憶する”行為なのである。
この映画が放つ痛烈なリアリティは、戦後日本の記憶装置としてのカメラが、どれだけ倫理的に危険な存在であるかを示している。原一男がこの被写体を選んだこと自体が、戦後社会への批評行為なのだ。
彼は奥崎という鏡を通して、日本という共同体の狂気を撮った。『ゆきゆきて、神軍』とは、国家が忘却した暴力の記録であると同時に、記録行為そのものが暴力であることの証明でもある。
ドキュメンタリーの限界線──倫理を超えた場所へ
『ゆきゆきて、神軍』のクライマックスでは、もはや映画と現実の境界が崩壊する。奥崎は上官を罵倒し、暴力をふるい、原のカメラはそれを止めようともしない。撮影者もまた共犯者である。
だが、その“共犯関係”こそが本作の倫理的核心だ。ドキュメンタリーにおける真実は、撮影者がどこまで現実に介入するかで決まる。原はその線を越える。越えたうえで、なおもカメラを回し続ける。そこに彼の映画作家としての信念がある。
この信念の純度は、後年の『全身小説家』(1994年)や『れいわ一揆』(2019年)へと連なっていく。原一男にとってドキュメンタリーとは、被写体を描くことではなく、自らの存在を賭けることだ。カメラは告発の道具であると同時に、自己の倫理を測る刃でもある。
『ゆきゆきて、神軍』を観終えたあと、観客に残るのは“撮る”ことへの畏怖だ。真実を記録することは、他者を傷つけることに等しい。だが、その傷を恐れては、映画は成立しない。
原一男はその矛盾を抱え込み、なおもカメラを構え続ける。奥崎謙三はその鏡像であり、暴力と信念の極限で交わる二人の存在が、戦後日本の倫理の限界を照らし出す。
『ゆきゆきて、神軍』とは、映画そのものが戦場であり、カメラが銃であり、倫理が弾丸であることを証明する作品である。原一男は撃ち、奥崎謙三は撃ち返す。観客はその弾丸の飛跡を、ただ見つめるしかない。
戦後という名の虚構の上で、映画だけがまだ、生きた暴力を記録している。
- ゆきゆきて、神軍(1987年/日本)
![ゆきゆきて、神軍/原一男[DVD]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/61ymZhRg2lL._AC_SL1500_-e1759052879422.jpg)