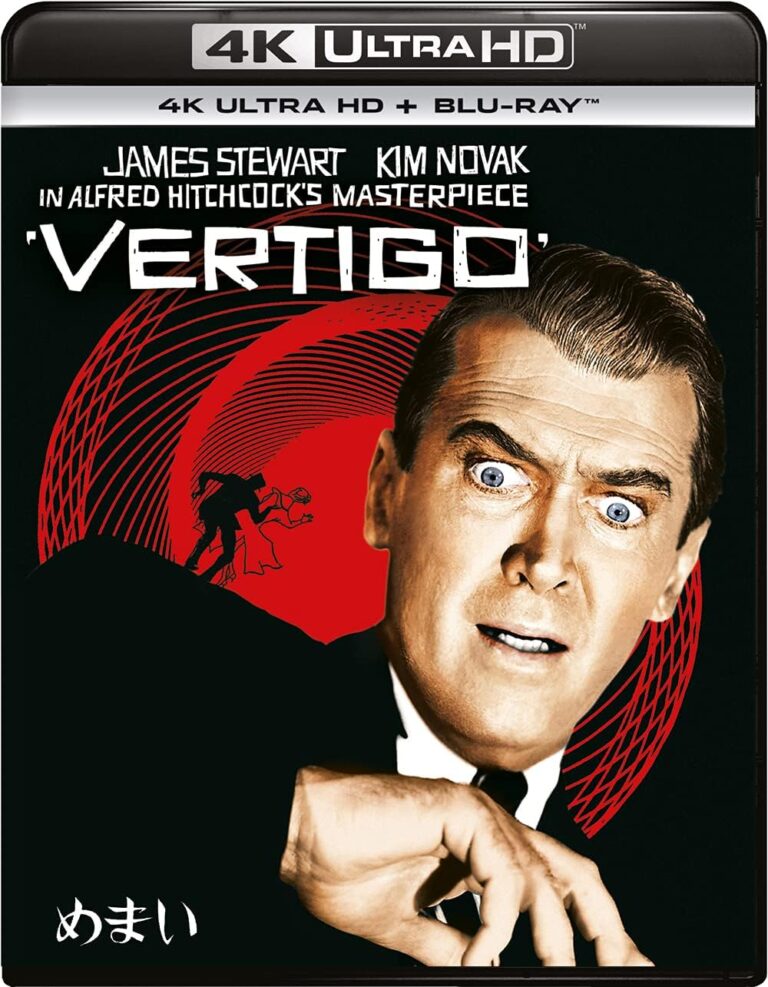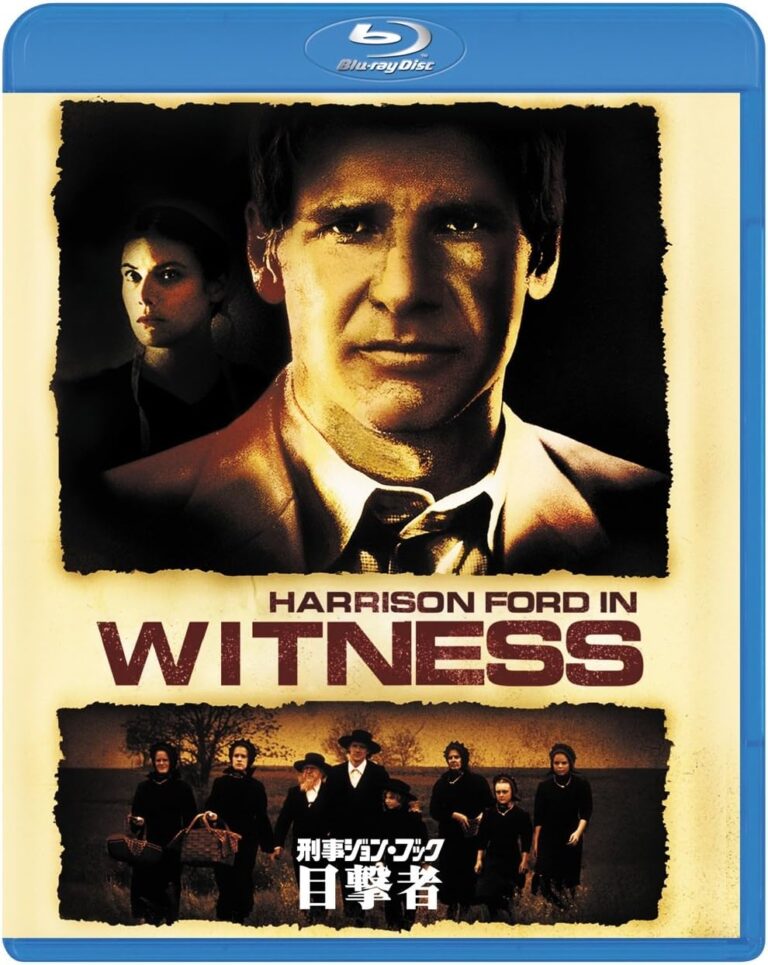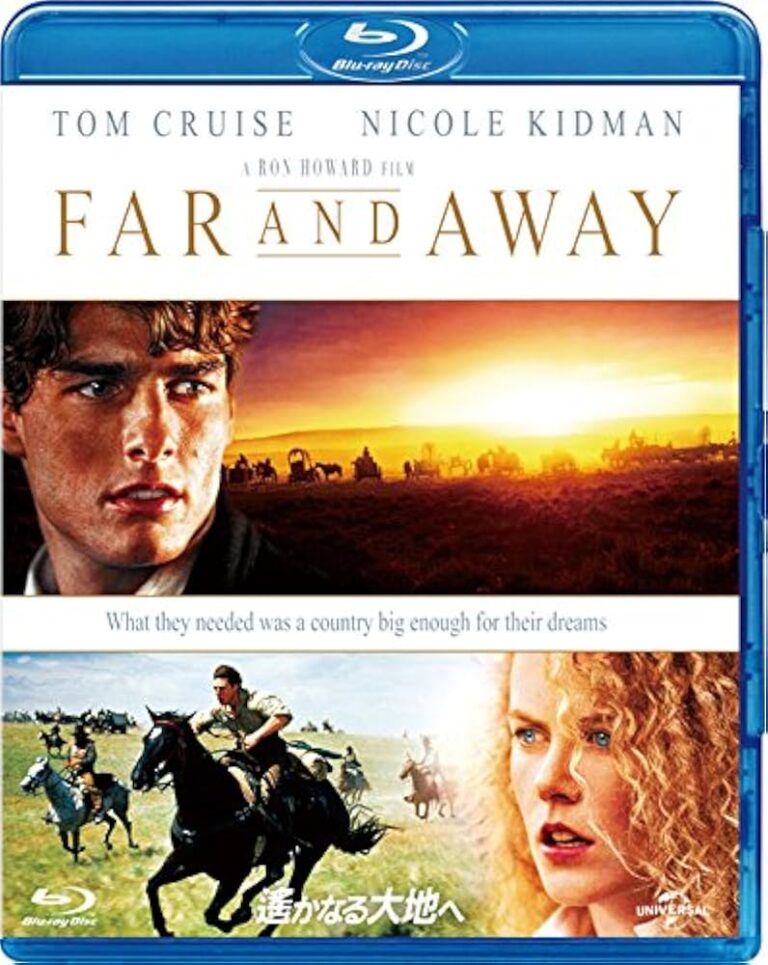『チャイナ・シンドローム』(1979)
映画考察・解説・レビュー
『チャイナ・シンドローム』(原題:The China Syndrome/1979年)は、ジェームズ・ブリッジズ監督が手がけた社会派サスペンスの傑作。テレビキャスターのキンバリー(ジェーン・フォンダ)が原子力発電所で重大事故寸前の瞬間を目撃し、技師ジャック(ジャック・レモン)、カメラマンのリチャード(マイケル・ダグラス)とともに真実を追う姿を描く。本レビューではネタバレを含めてストーリーを解説し、スリーマイル島事故と“予言的”に呼応した歴史的背景、そして娯楽映画としての演出やジャーナリズム映画としての意義について考察する。
神が仕組んだ戦慄のプロモーションと、冷戦下の核の夢
十数年前、渋谷・東急本店の前で、山本太郎とすれ違った。かつてメロリンQとして、あるいは気のいいアンちゃんとしてお茶の間を沸かせた彼は今、険しい表情で社会の不正と対峙している。
その背中を見送りながら、ふと思った。我が国の巨大な災厄が、人の人生を、そして社会の形を、こうも劇的に変えてしまうものなのか、思わずその足でTSUTAYAに向かい、僕は『チャイナ・シンドローム』(1979年)を手に取った。3.11を経験した我々の無意識下には、常に制御不能なテクノロジーへの根源的な恐怖が刻印されているからだ。
本作の全米公開は1979年3月16日。当時は冷戦の真っ只中であり、原子力は石油危機を救う夢のエネルギーとして、国家レベルで推進されていた。
電力会社や保守派メディアは、この映画を「荒唐無稽なSF」、「左翼の妄想プロパガンダ」と鼻で笑い、徹底的なネガティブ・キャンペーンを展開する。
だが、歴史は残酷なシナリオを用意していた。公開からわずか12日後の3月28日、ペンシルベニア州のスリーマイル島で、映画のプロットをなぞるかのような炉心溶融事故が発生したのである。フィクションが現実に追いつかれたというよりも、現実が映画の最悪のシミュレーションを後追いしてしまった。
「チャイナ・シンドローム」とは、核燃料が炉心を溶かし、地殻を突き抜けて地球の裏側の中国まで達してしまうという、ブラックジョークのような仮説。
物理学的にはあり得ないこの比喩が、事故当日のニュースキャスターたちの口から語られ、一瞬にして全米のトラウマ用語となった。映画が描いた計器の誤作動による水位の誤認や現場のパニック、そして何よりも事実を矮小化しようとする企業の隠蔽体質、これらすべてが、45年後の今もなお、我々の目の前にあるリアルな恐怖として横たわっている。
もし山本太郎がこの映画を観ていたら、彼はジャック・レモン演じる技師の姿に、今の自分を重ね合わせるだろうか?
マイク・ダグラスの野心と音の革命
本作でプロデューサーを務めたのは、出演も兼任したマイケル・ダグラス。当時、偉大な父カーク・ダグラスの影に隠れていたマイケルは、この企画に自らのキャリアの全てを賭けていた。
彼が目指したのは、堅苦しい社会派ドキュメンタリーではなく、『カッコーの巣の上で』(1975年)のような人間ドラマと、一級のサスペンスを融合させること。そのための最大の戦略が、徹底した音の排除と、リアリズムの追求である。
驚くべきことに、本作には劇伴がほとんど存在しない。通常のパニック映画なら、危機が迫れば不穏なストリングスが鳴り響き、観客の感情を誘導することだろう。だが、ここにあるのは、制御室の環境音、計器が弾き出す冷たい電子音、タービンの唸り、そして人間の荒い息遣いだけ。
冒頭、取材中の制御室で事故が起きるシーンでは、コーヒーカップの水面が微かに揺れ(これは『ジュラシック・パーク』より14年も早い演出だ)、やがて激しい振動へと変わる。
その時、聞こえてくるのはブーンという低い地鳴りと、けたたましいアラーム音のみ。音楽による感情のガイドラインがないため、観客はスクリーンの中の登場人物と同じレベルで、何が起きているのか分からない不安と恐怖を共有することになる。
さらに特筆すべきは、美術監督ジョージ・ジェンキンスによる制御室(コントロールルーム)のセットの異常な精巧さだ。実際の原発取材が拒否されたため、元技術者の記憶と証言を頼りに再現されたその空間は、公開後に本物の原子力技術者が「どこかのプラントでロケをしたのか?」と見紛うほどの完成度だったという。
この圧倒的なリアリズムがあったからこそ、中盤の政治的な駆け引きや、終盤のカー・チェイスといった映画的な嘘が、説得力を持って機能するのだ。
ジャック・レモン演じる技師ゴデルが、不正の証拠となるX線写真の偽造を見抜くシーンの静かな緊張感。派手な爆発などなくても、一枚のフィルムだけで世界がひっくり返るスリルを描けることを、本作は証明してみせたのである。
道化から闘士へ、そしてメディアの敗北
この物語の核にあるのは、個人の覚醒という熱いテーマと、それを冷徹に見つめるメディア批判の視点だ。
ジェーン・フォンダ演じるTVキャスターのキンバリーは、当初動物園のレポートやイベントの盛り上げ役といった「毒にも薬にもならない」ニュースを担当する、いわゆるお飾りアナウンサーとして登場する。
赤い髪をなびかせ、愛想笑いを振りまく彼女は、視聴率至上主義に毒されたテレビメディアの象徴。当時、すでにベトナム反戦運動でハノイ・ジェーンとして知られていた活動家の彼女が、あえてこの軽薄なキャスターを演じるというメタ構造も面白い。
だが、「見てはいけないもの」を見てしまった瞬間から、彼女の内面で何かが砕け散り、再構築されていく。フォンダの演技の素晴らしさは、その変化のグラデーションにある。
最初はおどおどとし、上司の圧力に屈していた彼女が、カメラマンのリチャード(マイケル・ダグラス)の熱量に感化され、やがて自らのキャリアを賭して真実を報道しようと決意する。その瞳に宿る光が、恐怖から怒り、そして使命感へと変わっていく様は圧巻だ。
だが、本作のラストは、安易なハッピーエンドを許さない。ゴデルはSWATの突入によって射殺され、彼が命を賭して訴えようとした真実は、テレビ局の意図的な操作によって一時的にかき消されそうになる。
キンバリーの必死のレポートによって辛うじて現場の真実は伝わるものの、映画はすぐに日常の放送(コマーシャル)へと切り替わって終わるのだ。
これは、個人の勇気を称賛しつつも、それを消費し、すぐに次の娯楽へと移ろっていく“テレビというメディアの残酷さ”をも鋭く風刺している。
彼らは英雄なのか、それとも巨大なシステムに押し潰された犠牲者なのか。『チャイナ・シンドローム』は、45年の時を超えて、今なお我々にその答えを問い続けている。
- 監督/ジェームズ・ブリッジス
- 脚本/マイク・グレイ、T・S・クック、ジェームズ・ブリッジス
- 製作/マイケル・ダグラス
- 製作総指揮/ブルース・ギルバート
- 撮影/ジェームズ・A・クレイブ
- 音楽/スティーヴン・ビショップ
- 編集/デヴィッド・ローリンズ
- 美術/ジョージ・ジェンキンス
- チャイナ・シンドローム(1979年/アメリカ)
![チャイナ・シンドローム/ジェームズ・ブリッジス[DVD]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/81y0y5ERojL._AC_SL1500_-e1758922277474.jpg)
![カッコーの巣の上で/ミロス・フォアマン[DVD]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/717BMPHVe4L._AC_SL1000_-e1759984618696.jpg)