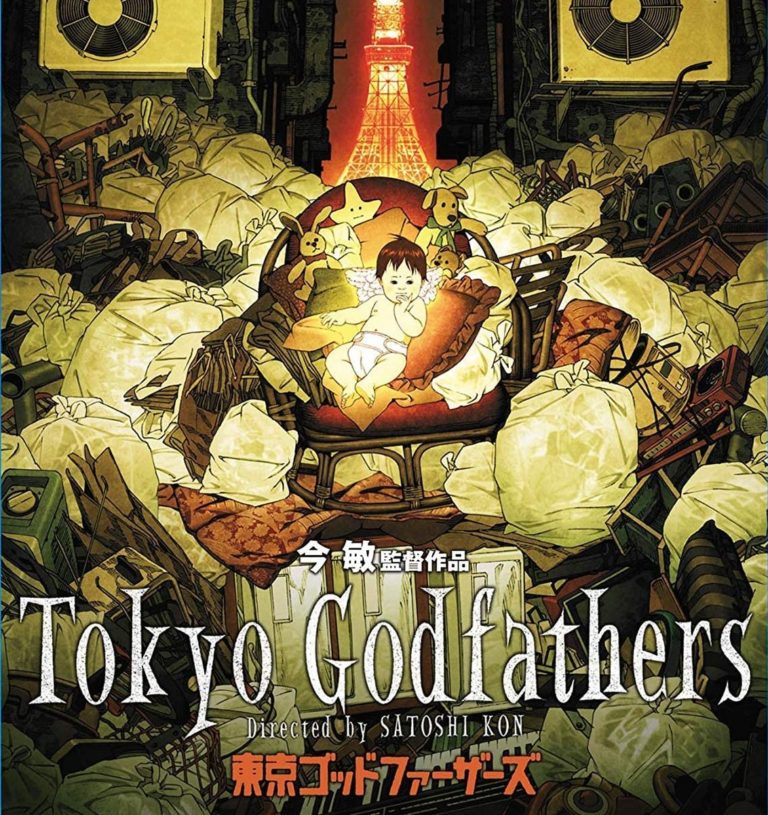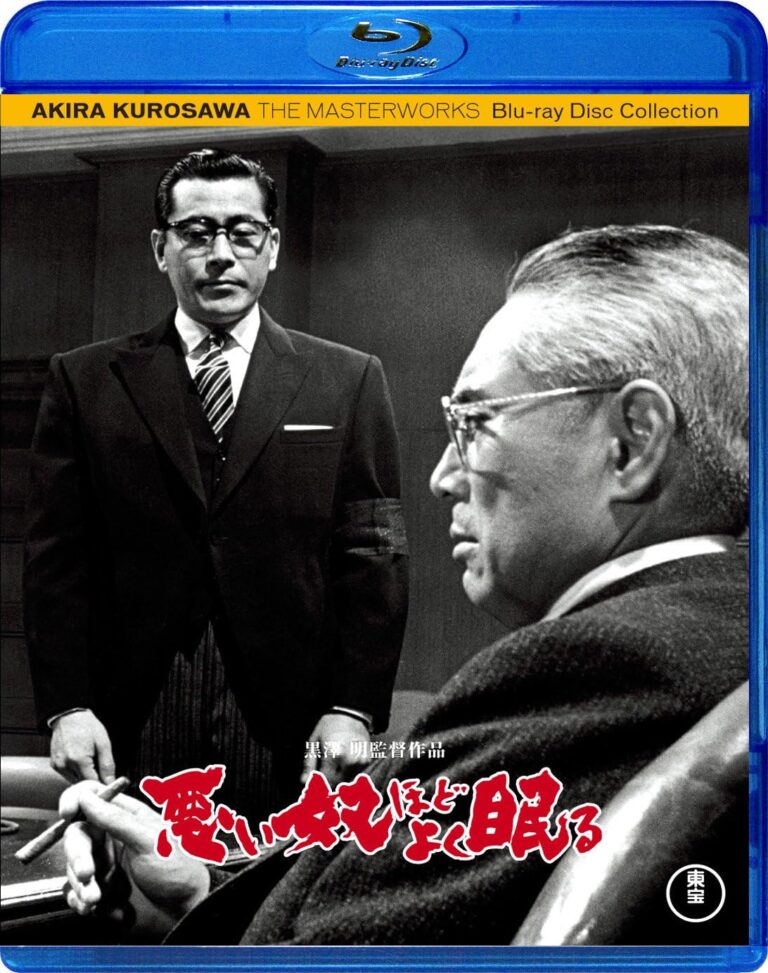『デトロイト・メタル・シティ』──渋谷系とデスメタルが衝突する場所
『デトロイト・メタル・シティ』(2008年)は、若杉公徳の同名漫画を原作に、李闘士男が監督した音楽コメディ。渋谷系を愛する青年・根岸崇一は、事務所の方針でデスメタルバンド「DMC」のボーカル・クラウザーIIとして活動することに。理想と現実の乖離に苦しみながらも、彼は二つの音楽世界を行き来し、笑いと狂気の境界に立たされる。
バラエティ出身監督の映像言語
かつて渋谷系に憧れて上京した若者が、なぜか事務所の方針によりデスメタルバンドのヴォーカルに仕立て上げられる──『デトロイト・メタル・シティ』(2008年)の導入は、冗談のように軽い。だが、その笑いの奥には、音楽文化の二重構造と自己表現の悲喜劇が潜んでいる。
渋谷系は90年代日本の都市的知性の象徴であり、洗練とおしゃれを装う“東京的欲望”の形だった。だが、その裏側には常に、血と唾液の匂いが混じる原始的な音楽衝動が潜んでいる。
渋谷のカフェでボサノヴァを鳴らす夢を抱いた青年が、真っ黒なペイントで「地獄に堕ちろ!」と叫ぶ現実に立たされる。この乖離こそ、現代のアイデンティティが抱える滑稽な悲劇だ。
作者・若杉公徳が描いたこの物語を映画化したのは、李闘士男。彼の経歴──『とんねるずのみなさんのおかげです』『SMAP×SMAP』といったバラエティ番組演出──が示す通り、この映画は“テレビ的笑い”の言語を借りて、音楽という抽象表現をコメディとして再構築した異色作である。
李闘士男の演出は、明確にテレビ的だ。PV出身監督がカットを細かく割り、映像の速度で笑いを作るのに対し、彼はカメラを動かさず、空間の中で俳優の“間”と“呼吸”を生かす。
笑いの発生源は構図ではなく、演技の間合いに宿る。遊園地のトイレで、クラウザーII(松山ケンイチ)が後輩のポップな渋谷系ナンバーに思わずノリノリで踊り出す場面などは、まさにその典型だ。
ここでの笑いは、演出家が仕掛けたギャグではなく、“現場で偶発的に生まれる間”をカメラがすくい取ったもの。李闘士男が長年培ってきた“バラエティ的即興性”が、映画のリズムそのものを決定している。
彼は映画を舞台としてではなく、“笑いの現場”として設計する。つまり、『デトロイト・メタル・シティ』は物語的リアリズムではなく、“笑いの物理法則”によって動いているのだ。
「動かないカメラ」としてのリミテーション
李闘士男の最大の武器は、俳優の身体を“笑いのメディウム”として使うことにある。松雪泰子演じるデスレコード社長は、ドSキャラとしての権力性をデフォルメしながら、暴力と母性を往復する奇妙な存在に仕立てられる。
秋山竜次の変態ドラマーは、もはや人間を超えた肉体的ノイズとして、映像にリズムを与える。大倉孝二のフリーター・オタク的追っかけも、笑いの狂気を補完する歯車として完璧に機能している。
ここには“抑制された笑い”という概念がない。すべてがメーターの針を振り切る瞬間に爆発する。李闘士男のギャグ演出は、編集ではなく“テンションの総量”によって成立しているのだ。
テレビの世界では、笑いの瞬間を編集で“切り取る”が、映画では“維持する”。この映画が他のコメディ映画よりも異様に熱を帯びているのは、笑いの瞬間を逃さない撮影構造──固定カメラによる圧縮的フレーム──にある。
そして李闘士男は、自身が“カメラを動かすことのできない監督”であることを、誰よりも理解しているように見える。広角レンズを多用し、極端な遠近感を作り出すことで映像に圧を与えるが、トラッキングやドリーショットといった映画的ダイナミズムには踏み込まない。
代わりに、照明と色彩で“映像的カタルシス”を演出する。赤、黒、金──デスメタルのステージが過剰にヴィヴィッドな色で塗りつぶされる瞬間、李闘士男の演出はまるでテレビのスタジオセットのように機能する。
そこでは現実感よりも“演出の快楽”が優先される。映画的な運動性を欠くかわりに、彼が選んだのは“舞台的演出”という閉じた空間のなかで笑いを封じ込める方法だった。これこそが、李闘士男が持つテレビ出身監督としての宿命──動かないカメラが生む、笑いと不条理の密度──である。
松山ケンイチというカメレオン的身体
この映画を支えているのは、紛れもなく松山ケンイチの身体だ。彼は『デスノート』(2006年)でLを演じたときと同様、演技を“仮面としての身体”に昇華させる稀有な俳優である。
根岸崇一というナイーブな青年と、ヨハネ・クラウザーIIという極悪デスメタルの化身──この二つの人格を、彼は驚くほど自然に往復する。松山の演技は二重性そのものであり、“内面の分裂”を笑いへと転化する技術を持つ。
笑いと狂気は紙一重であり、彼のパフォーマンスはその狭間で観客を引きずり回す。渋谷系の甘ったるいメロディを口ずさむ根岸と、ステージで下品な罵詈雑言を叫ぶクラウザーIIは、同一人物でありながら、異なる文化の化身である。
つまり、松山ケンイチの身体が“音楽ジャンルの衝突”を演じているのだ。ここにこそ、『デトロイト・メタル・シティ』という作品の真のテーマがある。笑いとは、異なるコードが同一空間で共鳴する瞬間に生まれるノイズであり、彼はその“ノイズの中心”に立っている。
Ⅵ. テレビと映画の境界線を笑いで踏み越える
李闘士男の『デトロイト・メタル・シティ』は、テレビの語法で映画を撮るという矛盾に満ちた実験だ。カメラを固定し、構図を変えず、演者の身体だけを暴走させる。その結果、映画はバラエティの延長線上にありながら、どこか異様に“映画的”な手触りを獲得している。
笑いが映像の運動性に置き換わったとき、コメディはアクションになる。デスメタルの過剰な暴力性と、渋谷系の繊細なロマンティシズムという二項を、李闘士男は“笑い”という共通言語で同一化させた。
笑いは暴力の浄化であり、同時に暴力の模倣でもある。この映画のクラウザーIIは、観客を笑わせながら、同時に破壊する。暴力が笑いに変換される瞬間、そこに映画的快楽が発生する。
『デトロイト・メタル・シティ』は、音楽映画でもコメディでもない。“笑いという暴力装置”をめぐるメタ映画である。
- 製作年/2008年
- 製作国/日本
- 上映時間/104分
- 監督/李闘士男
- 脚本/大森美香
- エグゼクティブプロデューサー/市村南、塚田泰浩、山内章弘
- 企画/川村元気
- プロデューサー/樋口優香
- 撮影監督/中山光一
- 照明/武藤要一
- 美術/安宅紀史
- 録音/郡弘道
- 編集/田口拓也
- ラインプロデューサー/鈴木嘉弘
- 音楽/服部隆之
- 松山ケンイチ
- 加藤ローサ
- 秋山竜次
- 細田よしひこ
- 鈴木一真
- 高橋一生
- 宮崎美子
- 大倉孝二
- 岡田義徳
- ジーン・シモンズ
- 松雪泰子
![デトロイト・メタル・シティ/李闘士男[DVD]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/51SUtgxzfYL._AC_UL640_FMwebp_QL65_-e1761047210919.webp)