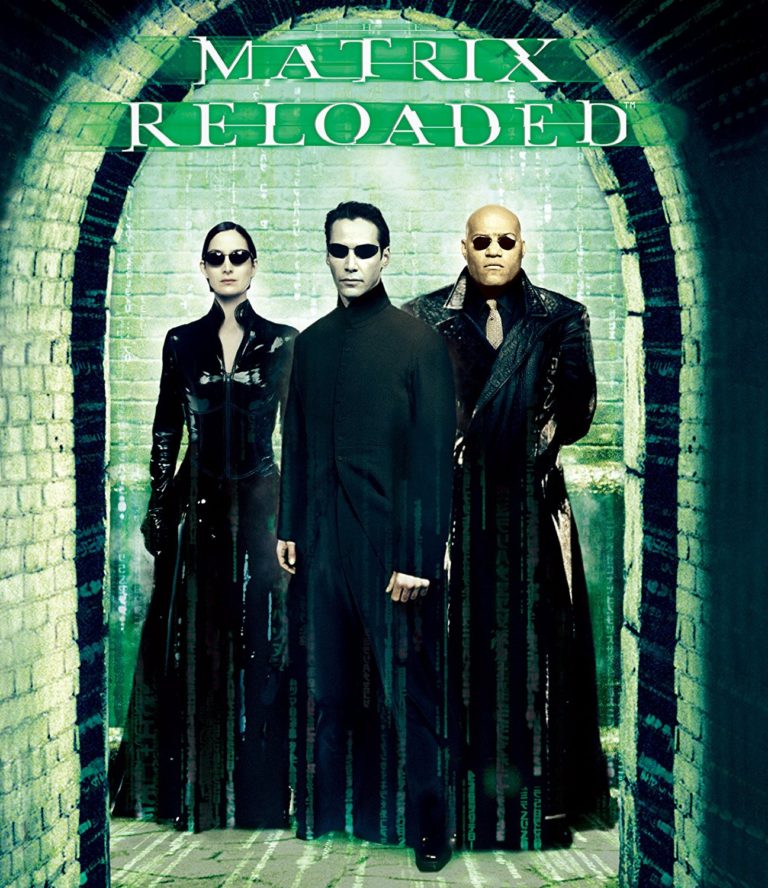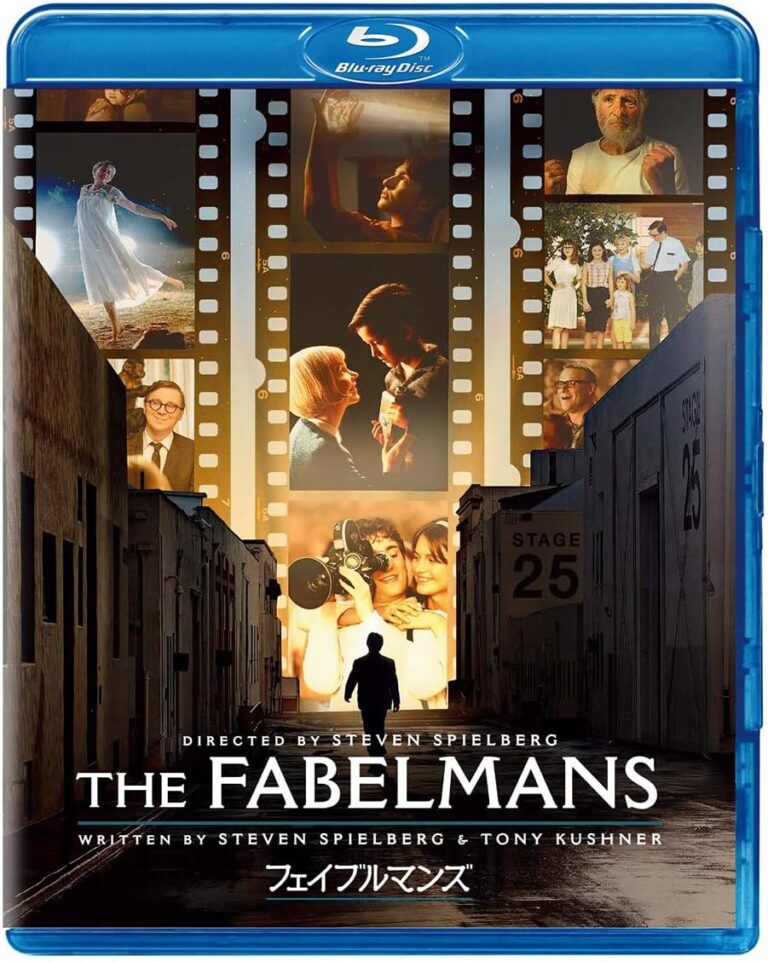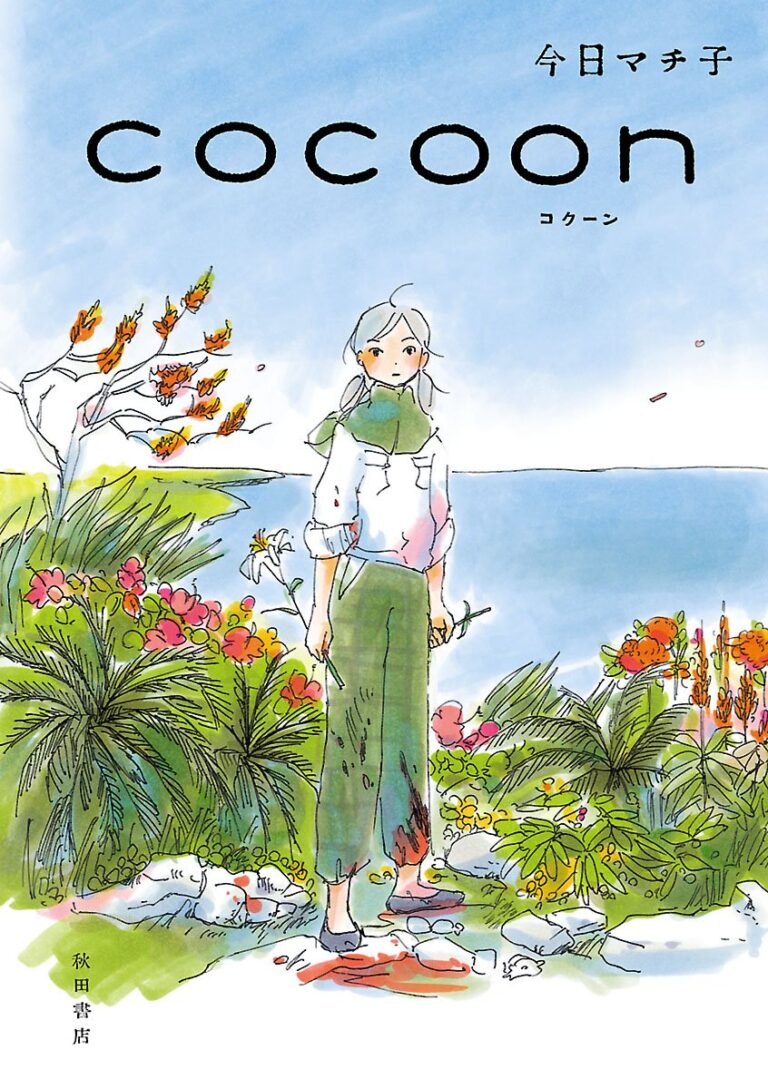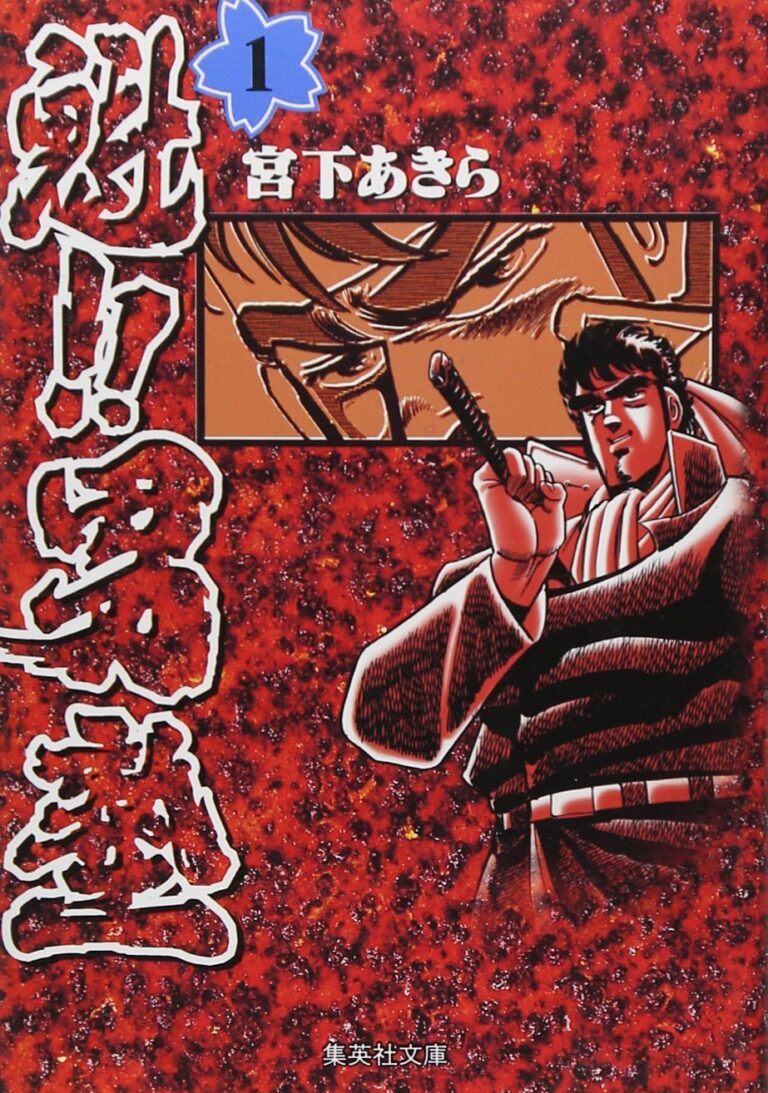『甘い生活』(1960)
映画考察・解説・レビュー
『甘い生活』(原題:La Dolce Vita/1960年)は、フェデリコ・フェリーニがローマを舞台に描いた十八の断章から成る物語。作家志望から転じてゴシップ記者となったマルチェロは、華やかな夜の社交界と退廃の空気のなかを漂い続け、享楽と倦怠のあいだで自らの居場所を見失っていく。次々と現れる人々との出会いや祝祭的な場面の連続が、都市に渦巻く虚無と人間の迷走を映し出し、明確な物語を欠いた風景そのものが彼の人生を形づくっていく。
ストーリーの不在が生む“無重力”
18に分割されたエピソードを数珠つなぎにした『甘い生活』(1960年)には、明確なプロットも中心的なドラマも存在しない。だがこの“物語の欠落”こそが、本作の根幹的な魅力であり、フェリーニの企み。彼はここで、ひとつの物語を語るのではなく、物語が失われた時代の風景そのものを描こうとしたのである。
ローマを舞台に、虚無と享楽が循環するように流れ続ける映像。そこには重力が存在しない。登場人物は浮遊し、時間は閉じた円環を形成する。観客はただその渦の中を漂うしかない。
ゆえに、この映画の最良の鑑賞法は、煙草を燻らせながらソファに沈み、意識を半分眠らせることだ。それって最高に贅沢な睡眠導入剤じゃないですか!
主人公マルチェロ(マルチェロ・マストロヤンニ)は、作家を志してローマに出てきたものの、その志を捨ててゴシップ記者として魂を切り売りしている。
彼の周囲には、アニタ・エクバーグ、アヌーク・エーメ、マガリ・ノエルらが入れ替わり立ち替わり現れ、華やかで退廃的な夜の饗宴へと誘う。映画の中で語られるのは“ドラマ”ではなく、ただひたすらに“堕落していく時間”そのものなのだ。
マルチェロが体験するのは、都市の歓楽に溺れながらもそこに満たされないという、近代知識人の病理だ。娼婦とベッドを共にし、噴水で美女と抱擁し、ブロンドの恋人に子供のようにじゃれつく。
眠らない都市ローマで、享楽は終わることなく繰り返される。「あなたを愛してあげるのは私だけよ」という台詞が虚しく響くのは、すでに彼の中で“愛”という概念が消費され尽くしているからだ。
フェリーニはこの空虚な祝祭の只中で、自らの分身であるマルチェロに“生きる倦怠”を刻印する。精神の支えであった友人スタイナーの自殺によって、彼の内なる理想主義は音を立てて崩壊する。
知性も道徳も信仰も、もはや救いの拠り所とはならない。残るのは、快楽と退廃だけ。この構造は、完全にフェリーニ自身の自己告白にほかならない。
『道』(1954年)や『カビリアの夜』(1957年)で“神の沈黙”を描いた彼は、『甘い生活』でその沈黙の中に“笑い”を見出す。精神の死を悲劇としてではなく、享楽的な祝祭として提示する――これこそがフェリーニ流の、逆説的で強烈な楽天主義なのだ!
象徴としての魚──救済の不可能性と“見ること”の終焉
終盤に登場する、巨大な魚の死骸。これは、『甘い生活』という映画の全構造を凝縮した、決定的なイメージである。腐りかけた銀色の皮膚、濁った眼、潮に晒された巨大な躯体──それは、祝祭の夜を過ごしてきた登場人物たちの、内なる腐敗を可視化したものだ。
マルチェロがその魚を見つめる視線には、もはや驚きも恐れもない。彼はただ“見ることしかできない人間”になっている。報道写真家として、虚飾と退廃を見つめ続けた男の末路が、ここで象徴的に描かれるのだ。
魚の眼は開かれているが、何も見ていない──その姿は、マルチェロ自身が“見る主体”でありながらも、もはや世界に意味を見出せないという存在論的な限界を示している。サッパリ分からない、そうつぶやきたくなるほどの虚無だ。
フェリーニはここで、“視覚の終焉”=“認識の終焉”を提示している。『甘い生活』における退廃は、官能の果てに訪れる倦怠ではなく、見ることの意味が失われた世界に他ならない。マ
ルチェロは目を開いたまま、何も感じることができない。彼の視線が死を見つめても、それはもはや現実を映すものではなく、映像を映すだけの空洞だ。フェリーニはこの瞬間、映画そのものの“終わり”を予感しているのではないか。
その死骸の直後に現れるのが、ポニーテールの少女。彼女は純粋で、まだ“見ること”ができる存在だ。彼女の眼差しは透明であり、マルチェロを赦すでも裁くでもない。ただ「こちらへ」と呼びかける。しかし、彼にはその声が届かない。“聞こえない”という事実こそが、救済の断絶を示している。
この場面でマルチェロが見つめる少女の姿は、現実の少女というより、かつて彼が失った“無垢”そのものの具現だろう。だがその無垢に戻る道は閉ざされている。彼はもう、彼女の言葉を理解する言語を持たない。フェリーニはここで、「純粋さは常に失われた後にしか想起されない」という残酷な真理を突きつけるのだ。
したがって、この映画の結末は、宗教的救済を拒絶した人間の、最後の視線の物語として読むことができる。フェリーニのカメラは、罪を清める神を描かない。かわりに描くのは、赦しを求めながらも決して赦されない人間の滑稽な姿である。
魚は死んでいる。しかし、それを見つめる人間もまた“内側で死んでいる”。この二重の死が交錯する地点にこそ、フェリーニ的モラルが宿るのだ。彼にとっての救済とは、もはや“救われること”ではなく、“救われないことを自覚すること”なのである。
永遠の祝祭──“甘い生活”の終わらない夜
『甘い生活』は、ローマという都市が孕む“生の祝祭”と“死の倦怠”を同時に描いた作品である。そこではエロスも信仰も、すべてが同じ平面上で回転している。
18の断章は、バラバラでありながら一つのリズムを奏でる。退廃と欲望、理想と挫折、笑いと絶望。フェリーニはそれらを“祝祭”という形式で包み込み、虚無の中に生命の火花を散らす。
マストロヤンニが演じるマルチェロは、知性を装いながらも堕落を止められない“永遠の中年”であり、フェリーニの分身であり、同時に我々観客そのものではないか!ラストに映る朝の光――それは救済の兆しではなく、“終わらない夜の後に訪れる、もうひとつの虚無”である。
最後にひとつ、トリビアを。劇中でマルチェロが「ニコ!」と呼びかけるモデル風の美女は、『The Velvet Underground and Nico』(1967年)で知られるニコ本人だ。
あのアンニュイな微笑が、映画のすべてを凝縮しているようで最高デス!
- 原題/La dolce vita
- 製作年/1960年
- 製作国/イタリア
- 上映時間/174分
- 監督/フェデリコ・フェリーニ
- 脚本/フェデリコ・フェリーニ、エンニオ・フライアーノ、トゥリオ・ピネリ、オテロ・マルテリ
- 製作/ジュゼッペ・アマート
- 撮影/オテッロ・マルテッリ
- 音楽/ニーノ・ロータ
- 美術/ピエロ・ゲラルディ
- 甘い生活(1960年/イタリア)
![甘い生活/フェデリコ・フェリーニ[DVD]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/819ejwcKp2L._AC_SL1500_-e1759056144368.jpg)
![カビリアの夜/フェデリコ・フェリーニ[DVD]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/71QgfFJlY9L._AC_UL640_FMwebp_QL65_-e1770502448977.webp)
![The Velvet Underground & Nico/ヴェルヴェット・アンダーグラウンド[CD]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/LDV9011-e1707467703712.jpg)