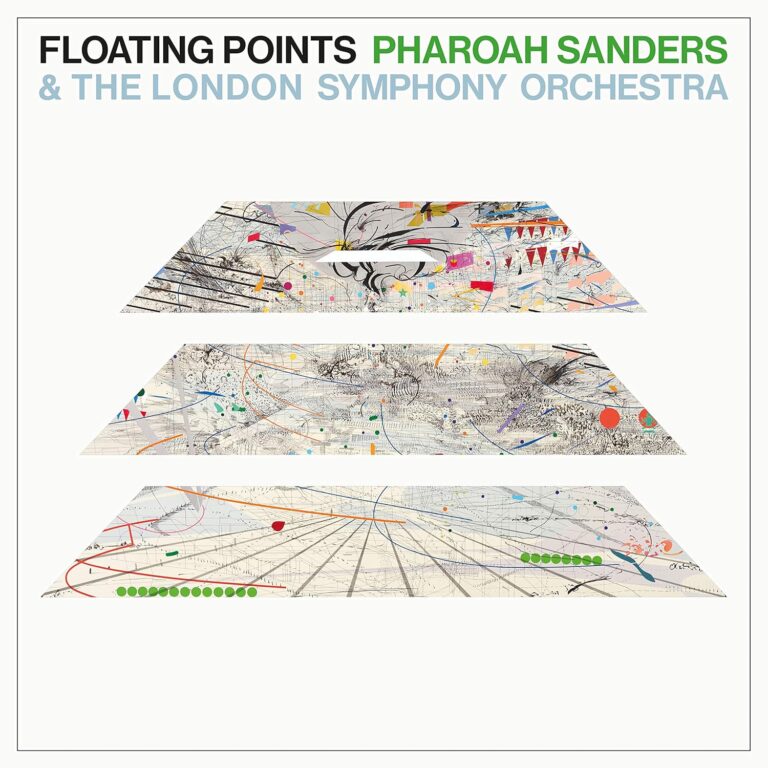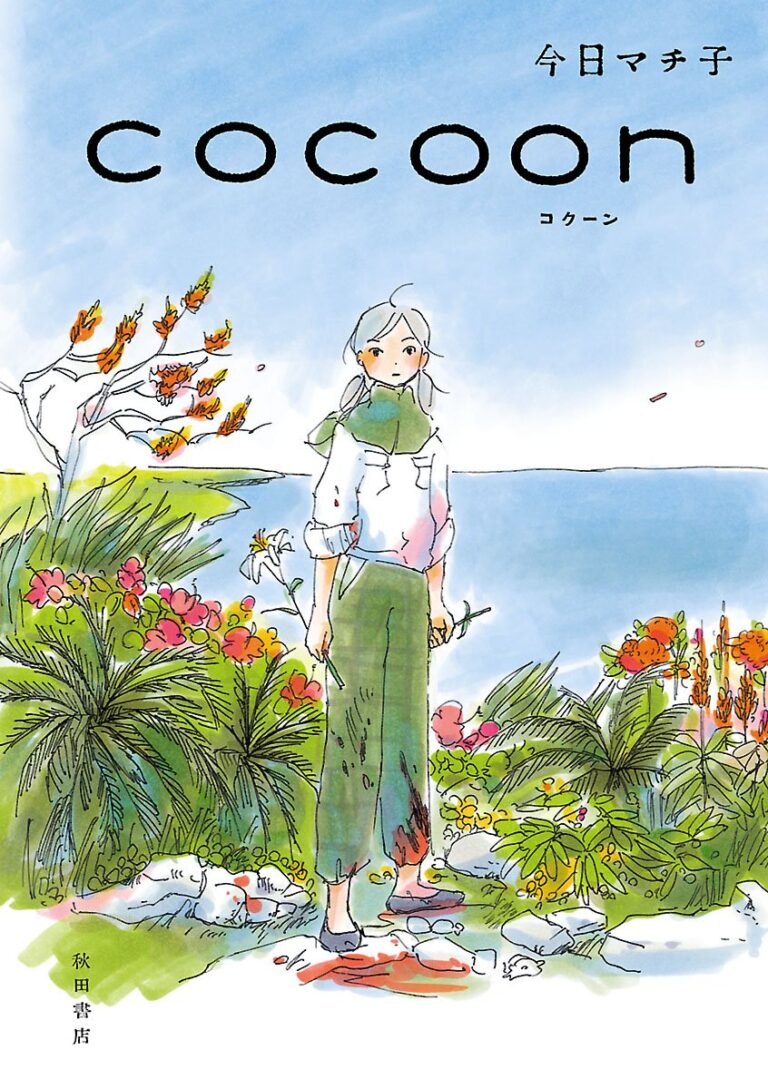『マルサの女』(1987)
映画考察・解説・レビュー
『マルサの女』(1987年)は、伊丹十三監督が国税局査察部の実態を独自の観察眼で描き出した社会派サスペンスである。バブル経済が膨張する中、査察官・板倉亮子(宮本信子)は悪徳ラブホテル経営者・権藤(山崎努)の巧妙な脱税を追うが、資本と権力が絡み合う巨大な構造に呑み込まれていく。 painstakingな捜査手順、制度に縛られた人間の欲望、正義の孤立──国家装置と個人の攻防が緊張感とユーモアを交差させながら、バブル期日本の“見えない作動原理”を鮮烈に浮かび上がらせる。
制度を撮る作家──伊丹十三の出発点
『お葬式』(1984)、『タンポポ』(1985)によって興行・批評の双方で成功を収め、映画監督として順調に軌道に乗っていた伊丹十三。その三作目にあたる『マルサの女』(1987)は、国税局査察部という、一般には最も地味な官庁を主題に選んだ作品である。
選択の理由はきわめて個人的だ。自身の映画のヒットによって得た利益が税金として徴収され、「自分の金がどこへ消えていくのか」を知りたくなった──その動機が発端だったという。
この軽い憤懣が、結果として日本映画史上稀有な「制度映画」の誕生へとつながる。伊丹が描いたのは“税金の物語”ではなく、“国家装置の物語”である。
脱税を摘発する査察官たちは、法の番人ではなく、社会構造の内部を歩く観察者であり、同時にその内部に呑み込まれていく被観察者でもある。『マルサの女』はその二重の視点を通じて、国家と個人、権力と欲望の境界を鮮烈に浮かび上がらせる。
ディテールの美学──“HOW TO”としての制度劇
伊丹の脚本は、徹底したリサーチを基盤としている。マルサの捜査手順、帳簿の読み方、ペーパーカンパニーの仕組み、金の流れのトレース──それらは単なる背景ではなく、映画の“文体”として機能する。伊丹にとって、ディテールとは装飾ではなく構造そのものなのだ。
「映画を観て悪用されたら困る」として、実際の捜査技術の一部は省略されているといわれるが、その精度の高さは疑いようがない。『マルサの女』は、“税務捜査のHOW TO”を装いながら、実際には“人間観察のHOW TO”である。
伊丹の映画術は、「神は細部に宿る」という信念に貫かれている。情報の微粒子が集まって人物像を形成し、物語の説得力を支える。ここにおいて、社会的リアリズムは心理描写よりも重要な叙述法となる。
すなわち、“国家”という抽象的存在を映像化するために、彼はディテールを物語化するのだ。
接近の映画──カメラの倫理と欲望の構図
伊丹の映画的スタイルは、“対象に寄る”ことに尽きる。彼はロングショットを極力避け、クローズアップを好む。理由は単純だ──登場人物に少しでも近づきたいからである。だが、その“近さ”は共感ではなく、解剖に近い。
彼のカメラは、クールな観察者であると同時に、対象の皮膚に触れようとするフェティッシュな視線を帯びている。金銭、書類、料理、汗、肉体、欲望。すべてが接写され、画面は触覚的な密度を獲得する。
特にセックス描写の生々しさは、観客の倫理を試すような不快さを孕む。だがその不快こそ、伊丹映画の“真実の接触”。宮本信子の〈おかっぱとソバカス〉、山崎努の〈片足の不自由さ〉といった外形的ディテールが、伊丹の接近的演出によって異様なまでに生々しく変容していく。
俳優の身体そのものが、社会の寓意を担う彫刻的素材へと変化するのだ。伊丹は、登場人物を描くのではなく、“観察される身体”としてフレームに配置する。
金と欲望──構造的ドラマの核心
物語は、悪徳ラブホテル経営者・権藤(山崎努)を脱税容疑で追う国税局査察官・板倉亮子(宮本信子)の執念を軸に展開する。だが、この構図は単なる善悪の対立ではない。伊丹が描くのは、正義と悪が共に“金銭という宗教”に支配されている社会である。
板倉は正義の体現者でありながら、職務の正当性という制度的欲望に取り憑かれている。権藤は金の亡者であると同時に、国家権力の裏側を知る“もう一人の観察者”でもある。彼らは対立するが、同じ欲望の構造に属している。伊丹はそのアイロニカルな関係を、冷徹な視線で解体していく。
この作品において“金”は単なるモチーフではない。金は社会の言語であり、倫理を超えたコミュニケーションの手段である。伊丹はその流通のプロセスを丹念に追うことで、資本主義というシステムの“物語的機能”をあばき出す。
金は人間の意志を中継し、関係性を規定し、やがて人間そのものを形式化してしまう。『マルサの女』は、その“金という構造の物語”を描いた最初の日本映画である。
リアリズムと演技──社会を演じる身体
伊丹映画の魅力は、キャスティングの緻密さにもある。主役から端役に至るまで、すべての俳優が制度の歯車として配置されている。
宮本信子の演技は、感情よりも手続きに忠実であり、その“無表情さ”がむしろ現代社会の無機質なリアリティを強調する。山崎努の権藤は、悪人である以前にシステムの産物として描かれ、その存在そのものが“経済の人格化”である。
この関係性を通して、伊丹は〈演技=制度の模倣〉という命題を提示する。俳優はキャラクターを演じるのではなく、“制度の役割”を演じる。したがって、『マルサの女』における演技は、心理的リアリズムを超えた社会的記号として機能する。
伊丹十三の“観察映画”──ディテールから国家へ
伊丹十三の映画は、常に“社会制度を観察する映画”である。『お葬式』では葬儀という儀礼を、『タンポポ』では食文化を、そして『マルサの女』では税制度を。それらはすべて“日本社会の作動原理”を可視化するための装置であり、伊丹はそれを娯楽のフォーマットの中に仕込む。
彼の観察は冷酷だが、決して無感情ではない。対象を愛しているがゆえに、徹底的に解剖する。だからこそ、その“寄り”は時に過剰であり、観客にとって不快ですらある。だが、その不快は倫理の領域ではなく、真実の領域に属している。
伊丹は、社会という生体をカメラで解剖する医師である。彼のメスは笑いを装いながら、常に現実の奥へと切り込んでいく。『マルサの女』において、その切開はもっとも精密で、もっとも美しい。
観察者の倫理──伊丹映画の到達点
『マルサの女』は、笑いの映画であると同時に、倫理の映画である。笑いは社会を赦すためのものではなく、観察を続けるための距離の取り方なのだ。伊丹十三は、社会を糾弾するのではなく、観察し続ける。その冷徹な凝視の中に、真の人間理解がある。
本作で完成された“観察の美学”は、後の『マルサの女2』『ミンボーの女』『スーパーの女』へと連なっていく。制度を観察し、人間を観察し、そして観察する自分自身をも観察する──その無限ループこそが、伊丹十三の映画的思想の核心である。
ちなみに権藤という名前は、山崎努が24年前に出演した黒澤明の『天国と地獄』(1963)で、三船敏郎が演じた靴会社の社長と同じ。貧しい医学生が富豪となり、やがて脱税の容疑者となって追われる──この偶然の連鎖は、まるで日本映画史そのものの寓話のようだ。
- 『マルサの女』(1987)金銭と欲望のリテラシー(1987年/日本)
- マルサの女2(1988年/日本)
![マルサの女/伊丹十三[DVD]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/71ml6hmlfHL._AC_SL1156_-e1758813666634.jpg)