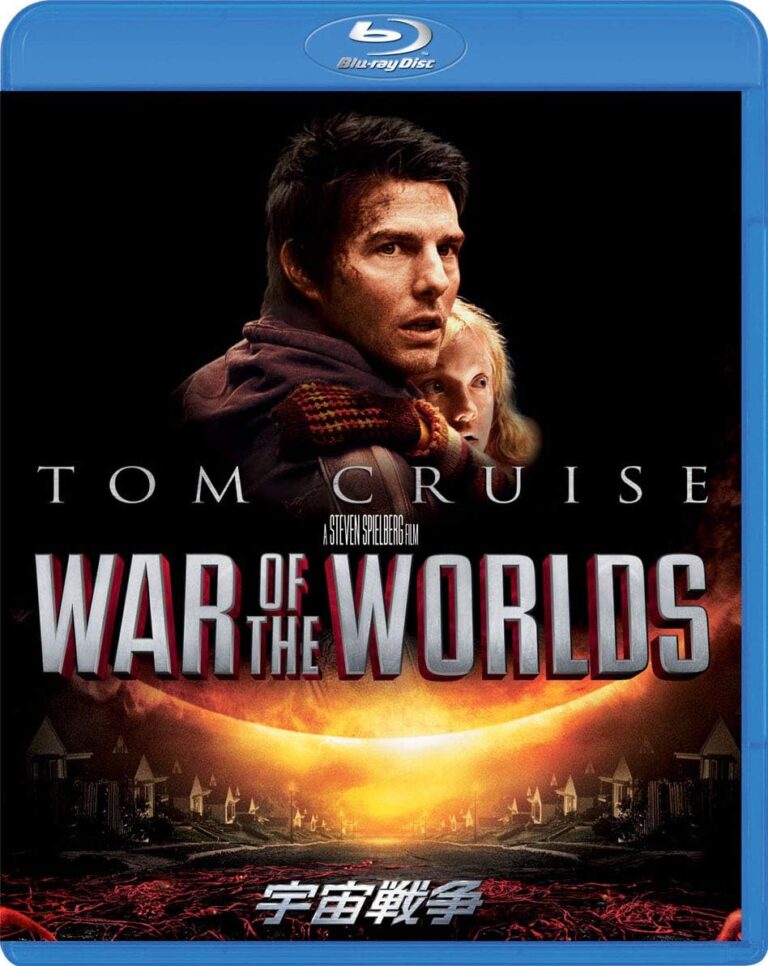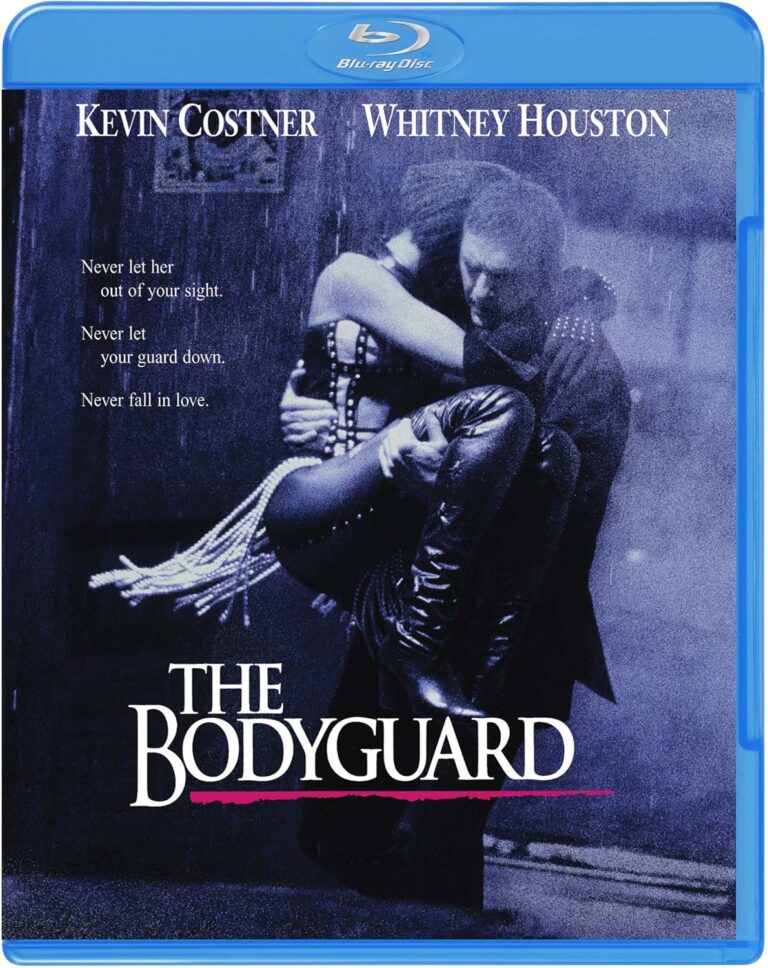『ポエトリー、セックス』(2001)
映画考察・解説・レビュー
『ポエトリー、セックス』(原題:The Monkey’s Mask/2001年)は、オーストラリアの詩人ドロシー・ポーターの長編詩小説をもとに、サマンサ・ラング監督が映画化した心理サスペンス。失踪した女子大生を追う私立探偵ジル(スージー・ポーター)が、被害者の残した官能的な詩の断片を手掛かりに捜査を進める。やがて大学教授ダイアナ(ケリー・マクギリス)との関係が事件と交錯し、詩と性愛が混じり合う危うい真相が浮かび上がる。
詩と欲望のあいだ──サマンサ・ラングの問題設定
オーストラリアの詩人ドロシー・ポーターによる長編詩小説『Monkey’s Mask』を映画化したのが、サマンサ・ラング監督による『ポエトリー、セックス』(2001年)である。
『女と女と井戸の中』(1997年)で知られるラングは、女性の欲望と抑圧を主題化する作家だが、本作では詩と性愛、そして死を媒介にしたサスペンスへと踏み込む。
行方不明となった女子大生ミッキーの捜索を依頼される女探偵ジル。彼女が手にするのは、被害者が残した官能的な詩の断片のみ。詩的言語が唯一の手がかりであるという構成は、文学的モチーフを映画的サスペンスに転換しようとする試みといえる。
しかし、ラングの演出は形式主義的で、詩の象徴性を映像的に翻訳するには至っていない。詩の中に潜む倒錯や官能は、映像化された途端に説明的になり、詩的余白が失われてしまう。
その結果、本作は「詩的サスペンス」としての独自性を志向しながらも、実際にはジャンル映画としての強度を欠くという矛盾を抱えている。
女性探偵の造形──ノワール・ヒロインの変奏
ジルというキャラクターは、典型的なハードボイルド探偵の女性版として設定されている。
アルコールに依存し、社会的権威に反発し、そして依頼人の女性と肉体関係を持つ。こうした設定は、古典的フィルム・ノワールの男性探偵像――たとえばハンフリー・ボガートのような孤独な観察者――を女性に転倒させた構造である。
だが、ラングのアプローチは単なるジェンダーの置き換えに留まらない。ジルは“女性の身体を通して世界を捜査する存在”として描かれる。彼女が事件の真相に近づくほどに、その身体は欲望と不安の媒介となり、倫理と官能の境界が曖昧化していく。
この点で『ポエトリー、セックス』は、レズビアン映画というよりも、“女性身体を軸としたノワールの再構築”を試みた作品と見るべきだろう。
ただし、その野心に見合うだけの脚本的精度はない。事件の動機や構造の解明が弱く、観客が期待する「探偵による真相の発見」は曖昧なまま終わる。結果として、作品は心理劇にもミステリーにもなりきれず、印象的な主題を提示しながらも未消化に終わる。
詩的言語と映像言語の乖離
原作『Monkey’s Mask』は、詩の断片を通じて登場人物の心象と事件の輪郭を浮かび上がらせる構造詩だった。そのリズムと省略が生み出す余白が、読者に想像の自由を与えていた。
しかし、映像化された『ポエトリー、セックス』では、その余白が消え去る。詩的表現をそのまま映像に置き換えようとした結果、詩は単なる“情報”へと転化し、物語の進行を説明する手段に堕してしまう。
さらに、作品全体に漂うエロティシズムも、詩的比喩ではなく視覚的刺激として処理されている。性愛の描写が人物心理の深化に繋がらず、むしろサスペンスを希薄化させてしまう。
つまり、ラングが挑戦した“文学と映画の融合”は、理論的には興味深いが、実際の映像設計においては十分に機能していない。詩的モチーフを保持したまま物語を駆動させるには、より抽象的な演出言語が必要だった。
ミステリーの鍵を握る大学教授ダイアナを演じるのは、ケリー・マクギリス。『トップガン』(1986年)や『刑事ジョン・ブック/目撃者』(1985年)で知的で洗練された女性像を演じた彼女だが、本作では中年期特有の疲弊と退廃を体現している。
その変貌は単なる加齢の結果ではない。マクギリスの身体が、作品の主題と呼応している点に注目すべきだ。彼女の肉体は、かつてのヒロイン像を脱構築し、女性の老いを性的まなざしの外に置く。
この意味で、ラングはマクギリスの身体を“詩的象徴”として扱おうとした。だが、その意図は必ずしも成功していない。演出が写実的すぎるため、象徴的身体が単なるリアリズムの老女へと変わってしまうのだ。
結果として観客は、マクギリスの存在を主題的記号としてではなく、単なる“変わり果てたスター”として受け取ってしまう。
ノワールの構造を持たないサスペンス
映画全体を通して最大の問題は、物語構造の緩さである。観客の大半が早い段階で犯人の見当をつけられてしまう脚本は、サスペンスの根幹を失っている。
ノワールとは、謎解きではなく、真実を暴く過程で主人公が破滅していく構造を持つジャンルである。だが、『ポエトリー、セックス』はその“破滅の必然性”を描けていない。
事件も恋愛も、主人公にとって致命的な帰結をもたらさないため、物語に緊張が生まれない。欲望の炎が倫理を焼き尽くす瞬間こそノワールの醍醐味であるが、ラングの演出はどこか安全圏に留まっている。
その慎重さが、女性監督によるフェミニズム的距離感として理解できなくもないが、ジャンル映画としての切れ味を鈍らせているのは否めない。
『ポエトリー、セックス』は、女性監督によるノワール再解釈という点で意義深い試みではあった。だが、文学性とエロティシズム、サスペンスの融合という難題に挑んだ結果、いずれの要素も中途半端に終わっている。
本作が提示したのは、女性が主体的に欲望し、捜査し、語るという“ポスト・ノワール的視点”だったが、それを支える映画的形式は確立されていなかった。
もしこの作品が後年リメイクされるならば、詩の構造そのものを脚本構成の骨格に据えるような、よりラディカルな映画言語が必要になるだろう。
『ポエトリー、セックス』は失敗作ではある。しかし、女性映画史の中で、女性主体のノワールを試みたという一点において、確かな問題意識を刻んだ実験的作品だった。
![ポエトリー、セックス/サマンサ・ラング[DVD]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/51aPLhqJqL._UF8941000_QL80_-1-e1760009573634.jpg)