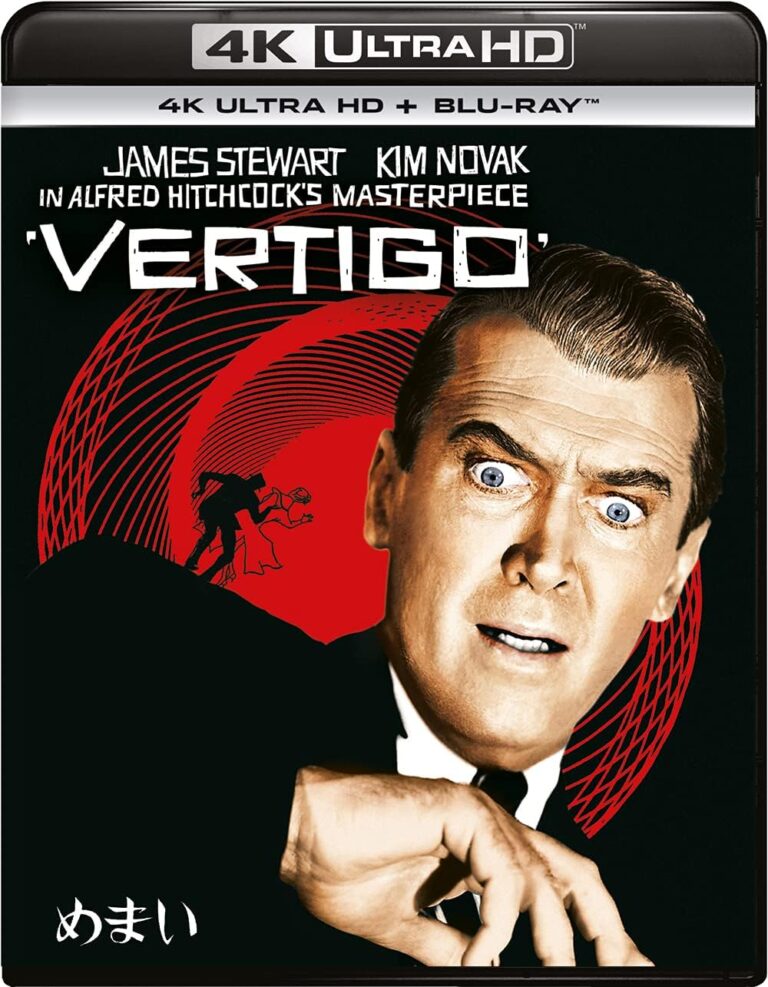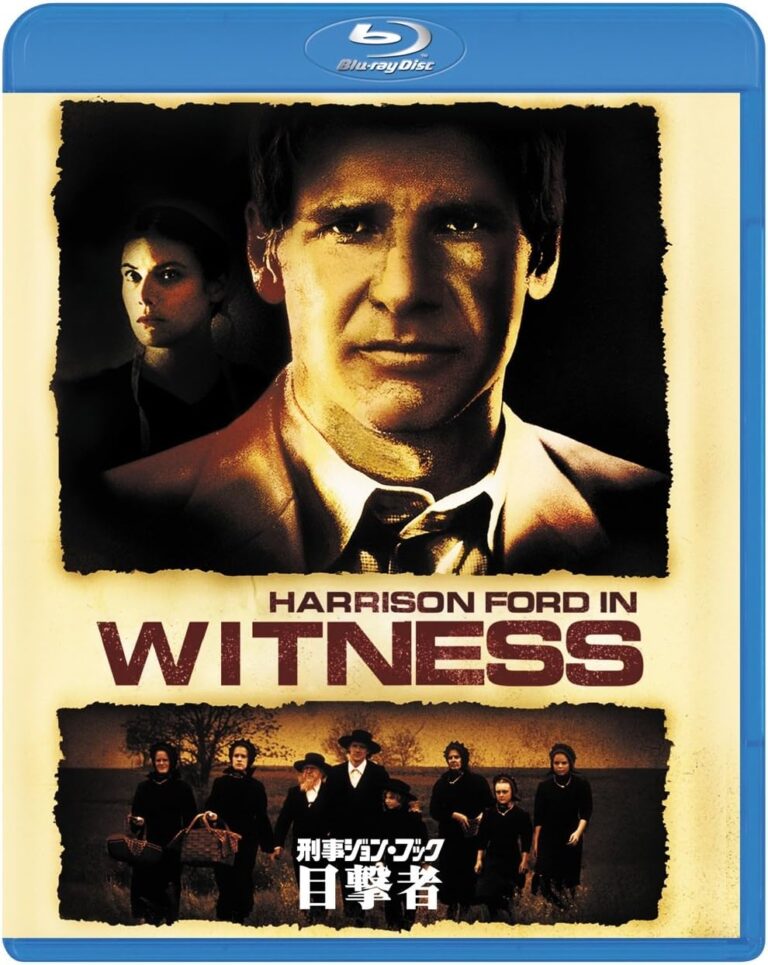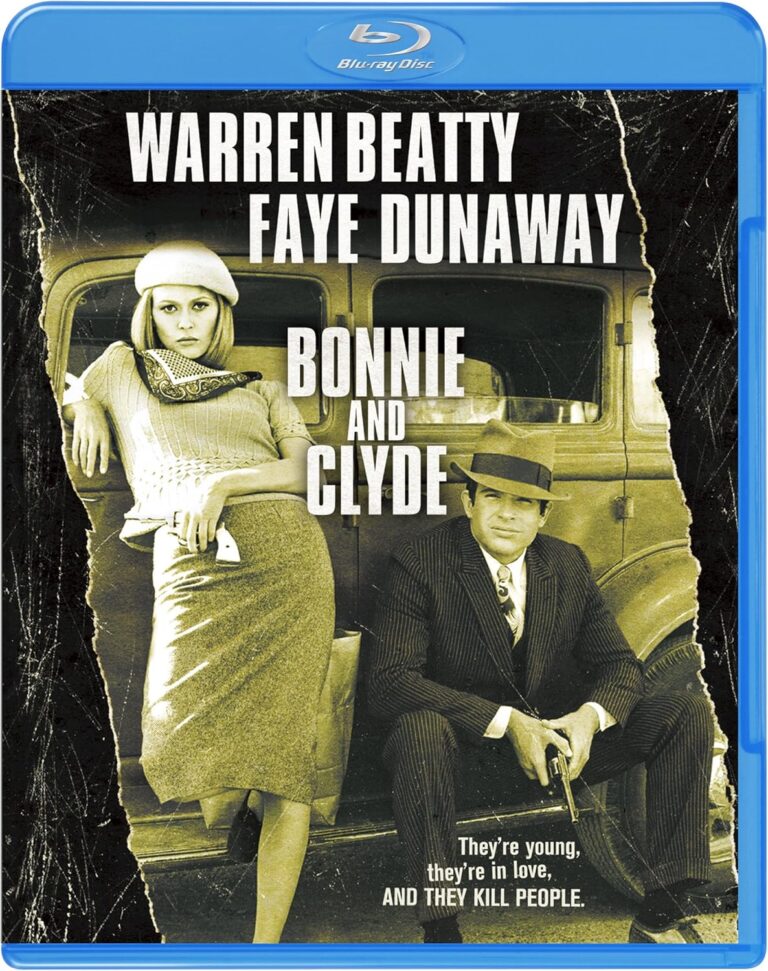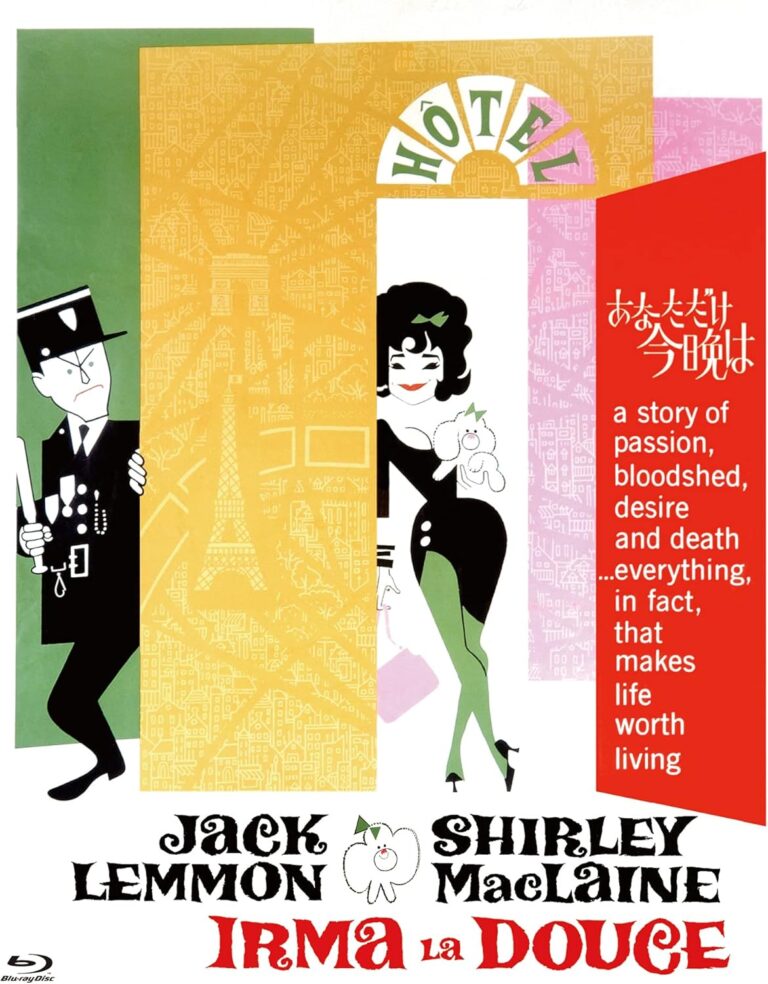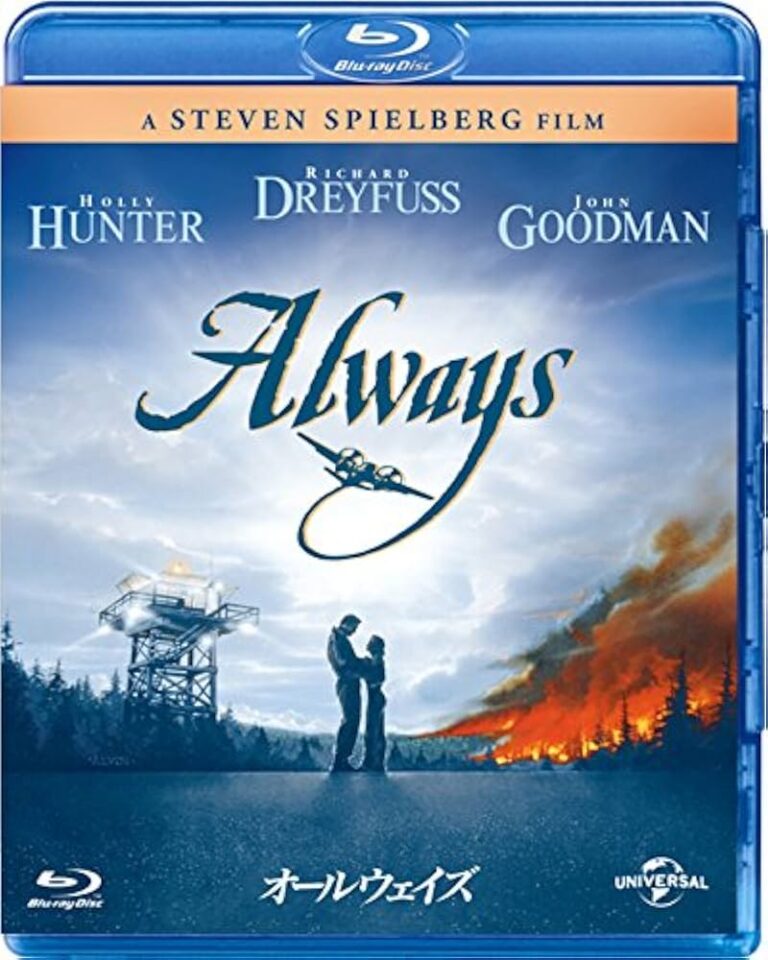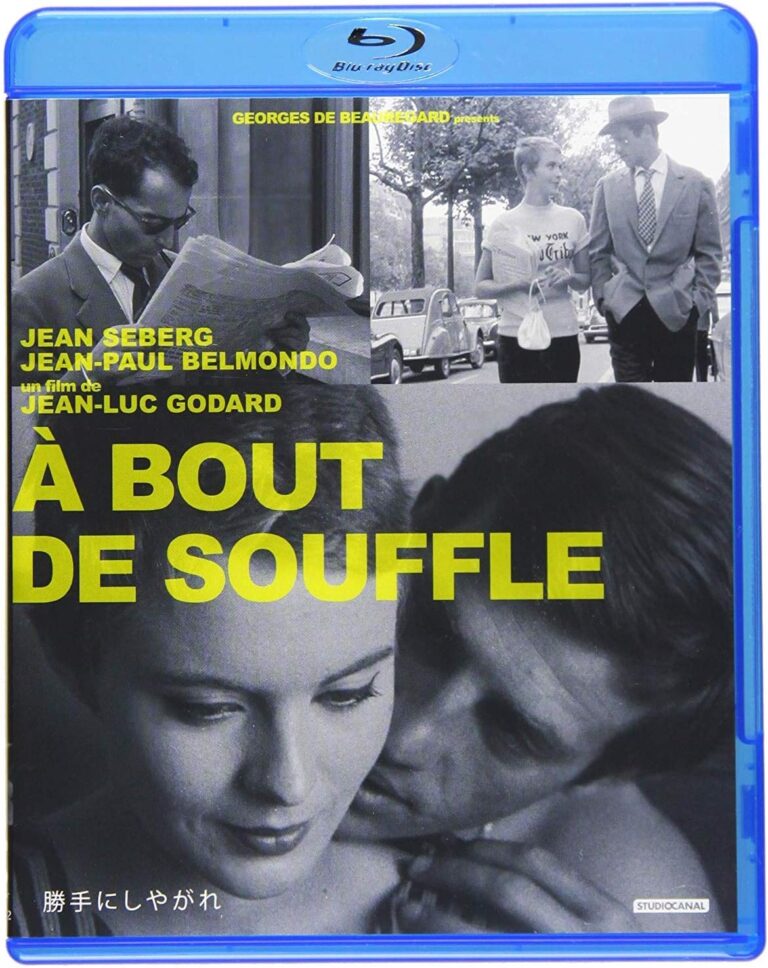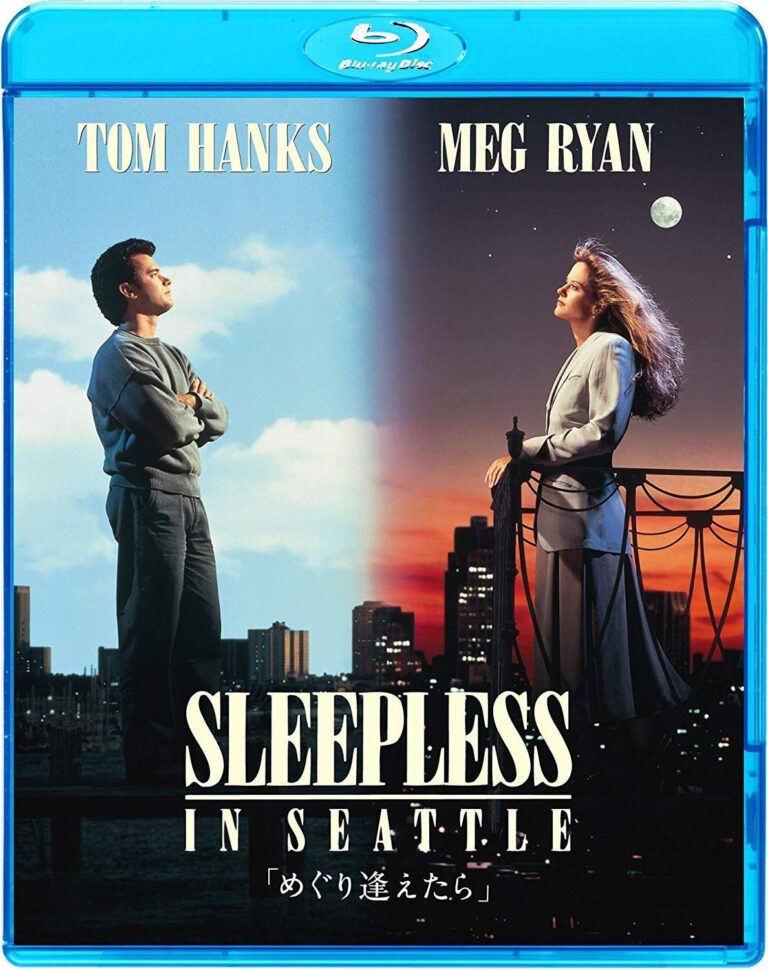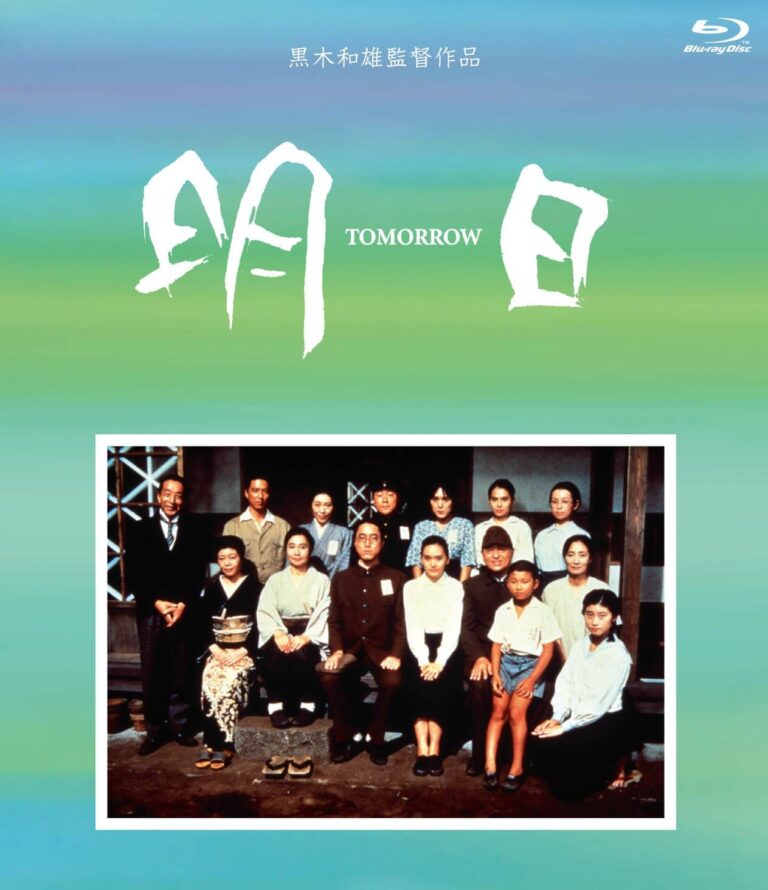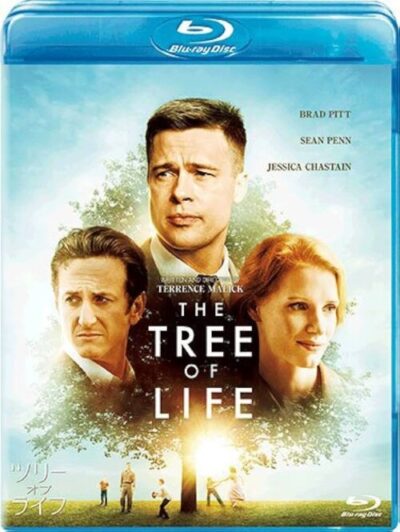『世界にひとつのプレイブック』(2012)
映画考察・解説・レビュー
『世界にひとつのプレイブック』(原題:Silver Linings Playbook/2012年)は、怒りと衝動を制御できないパット(ブラッドリー・クーパー)と、孤独と喪失を抱えるティファニー(ジェニファー・ローレンス)が、ダンスを通して“生きるリズム”を取り戻していく再生の物語である。精神の揺らぎを繊細に描いたデヴィッド・O・ラッセル監督の演出が、ふたりの不安と希望の往復運動をやわらかく照らし出す。
制御不能な“カオス”を愛するための、狂気と祈りの戦術書
『世界にひとつのプレイブック』(2012)は、メンタルヘルスを扱った良作でもなければ、アカデミー賞女優を生んだサクセスストーリーでもない。
デヴィッド・O・ラッセル監督が、自身の“制御不能な人生”と、双極性障害を抱える愛息への“祈り”をフィルムに焼き付けた、血の通ったドキュメンタリー的パンク・ロマンスなのだ!
原題は、『Silver Linings Playbook』。「Silver Linings」とは、厚い雲の向こう側にある“希望の光”。「Playbook」はアメフトの作戦図。
直訳すれば、「絶望の淵で、一筋の希望を掴み取るための作戦書」となる。だが、この映画に描かれているのは、冷静な作戦などではない。理性をぶっ飛ばした、感情と感情の交通事故だ。
まず、この映画の制作背景そのものが、劇中のパット(ブラッドリー・クーパー)の精神状態のように躁的。当初、主役の座にはマーク・ウォールバーグが、ヒロインにはアン・ハサウェイが座るはずだった。だが、ハサウェイはラッセルとの「クリエイティブな相違」(という名の衝突)で降板。ウォールバーグも去った。
普通ならプロジェクト崩壊の危機。だが、ラッセルはこの「予期せぬ事態」こそを燃料に変えた。彼は現場でゴッド・マイクと呼ばれる拡声器を使い、テイクの最中でも俳優に罵声に近い指示を飛ばし、音楽を爆音で流し続け、役者の理性を麻痺させたという。
「考えさせるな、感じさせろ」。その結果、クーパーの瞳には演技を超えた“本物の焦燥”が宿り、予定調和な会話劇は、呼吸すら許さないライブ・セッションへと変貌した。
ラッセル監督自身が、業界きってのトラブルメーカーであり、情動を制御できない人間であることは有名だ(ジョージ・クルーニーと殴り合いかけた逸話は伊達ではない)。
つまり本作は、「自分で自分をコントロールできない監督」が、「自分で自分をコントロールできない男」を描くという、狂気的なメタ構造によって成立しているのだ。
だからこそ、画面から漂う“危うさ”が嘘ではない。観客は、整えられた作り物ではなく、今にも崩壊しそうな人間の“均衡”を目撃することになる。
スカイプから現れた21歳の怪物、ジェニファー・ローレンス
この“制御不能なカオス”に、たった一人で対峙し、ねじ伏せた存在がいる。当時まだ21歳だったジェニファー・ローレンスだ。
夫を亡くした未亡人ティファニーを演じるには、彼女はあまりに若すぎた。オーディションはケンタッキー州の実家から、なんとスカイプで行われたという。画質も荒く、距離も離れたPC画面の向こう側。
しかし、ラッセルはそのモニター越しに「捕食者」の目を見た。
彼女が演じたティファニーは、傷ついたヒロインではない。相手の傷口に塩を塗り込みながら、同時にその痛みを共有しようとする、暴力的な天使だ。
37歳のクーパーに対し、16歳も年下の彼女が対等、いやそれ以上に渡り合えたのは、彼女の演技が技術ではなく、動物的な直感に基づいていたからに他ならない。
劇中、パットはスティーヴィー・ワンダーの『My Cherie Amour』を聴くとパニックを起こす(原作のケニー・Gから変更されたこの選曲も絶妙)。だが、ティファニーはそのパニックを否定しない。ただ、彼女なりのステップで踏み込んでくる。
クライマックスのダンスシーン。彼らの得点は「5.0」で、平均点だ。だが、彼らはまるで優勝したかのように狂喜乱舞する。なぜなら、そもそもこの映画は「10点満点」の完璧な人間になることを目指していないから。
社会的には「5点」の不完全な人間同士が、互いの欠けた部分を補い合い、その不格好なダンスを踊り続けること。それこそが、ラッセルが見出した“Silver Lining”の正体なのである。
父の祈り──「ハッピーエンド」という名の抵抗
なぜ、これほどまでに激しい映画が、最後には温かい涙を誘うのか? そこには、監督の個人的な“祈り”が隠されている。
ラッセルの息子マシューは、双極性障害と強迫性障害を抱えている。劇中、パットの家を訪ねてくる「取材したがる近所の少年」としてカメオ出演しているのが、そのマシュー本人だ。
原作小説の結末は、もっとビターで、映画のような爽快なハッピーエンドではない。しかし、ラッセルはあえて結末を変えた。
現実世界は厳しい。私の息子のような人々にとって、現実はあまりに過酷だ。だからこそ、せめて映画の中だけでも、彼らに“奇跡”を与えたかった
この改変を、ハリウッド的なご都合主義と批判するのは野暮というもの。これは、過酷な現実を知り尽くした父親が、フィクションという武器を使って世界に叩きつけた希望の捏造であり、魂の救済措置なのだから。
パットとティファニーがラストで見せる安堵の表情。それは、病気が治ったからではない。自分たちの“狂気”を受け入れ、それを共有できる相手を見つけたからだ。
私たちは誰もが、多かれ少なかれPlaybook(作戦)通りにいかない人生を生きている。計画は崩れ、愛は壊れ、感情は暴走する。だが、それでいい。『世界にひとつのプレイブック』はそう語りかける。
- 監督/デヴィッド・O・ラッセル
- 脚本/デヴィッド・O・ラッセル
- 製作/ブルース・コーエン、ドナ・ジグリオッティ、ジョナサン・ゴードン
- 製作総指揮/ブラッドリー・クーパー、ジョージ・パーラ、ボブ・ワインスタイン、ハーヴェイ・ワインスタイン
- 撮影/マサノブ・タカヤナギ
- 音楽/ダニー・エルフマン
- 編集/ジェイ・キャシディ
- 世界にひとつのプレイブック(2012年/アメリカ)
![世界にひとつのプレイブック/デヴィッド・O・ラッセル[DVD]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/71e8qdYz7ZL._AC_SL1240_-e1759056741724.jpg)