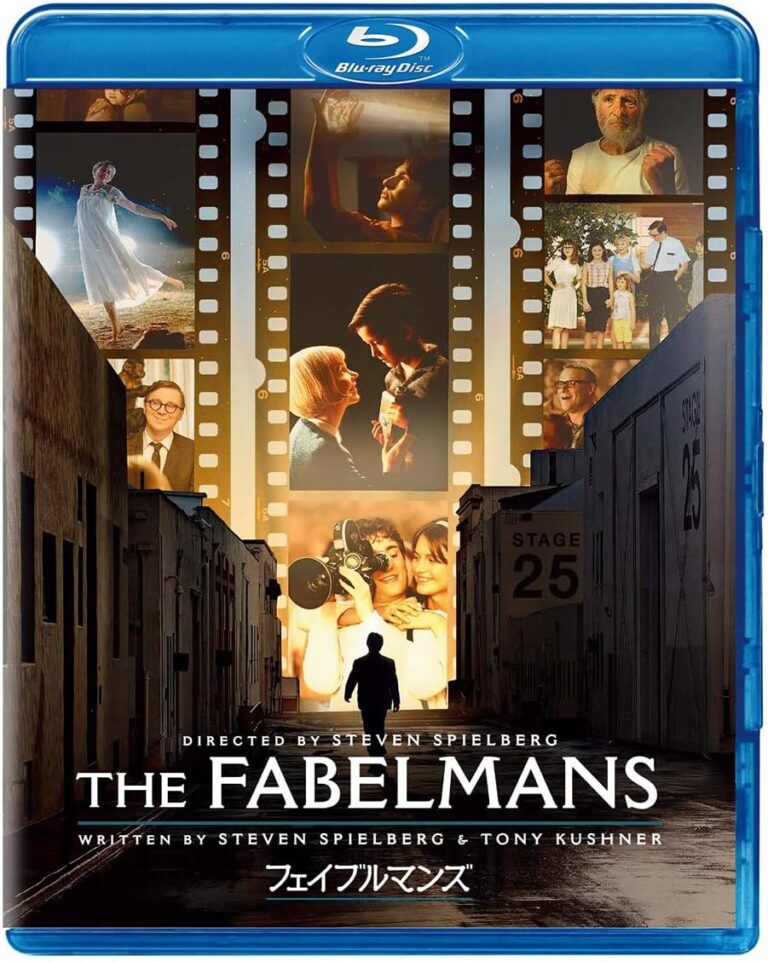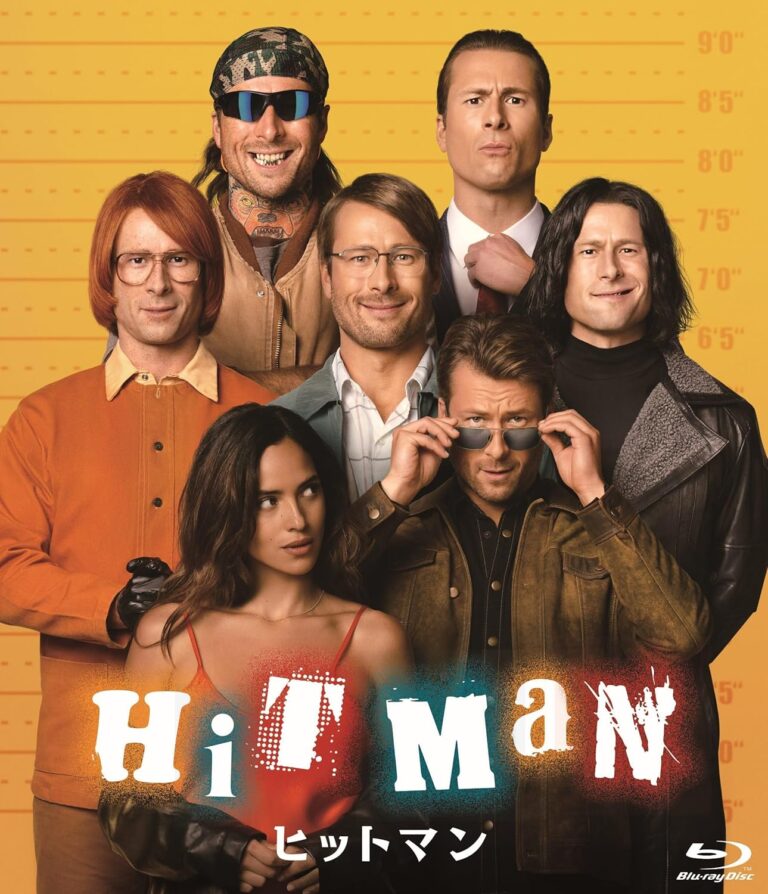『時をかける少女』──原田知世が駆け抜けた、恋と喪失の尾道トライアングル
『時をかける少女』(1983年)は、大林宣彦が監督を務め、筒井康隆の同名小説を映画化した青春ファンタジー。舞台は尾道。理科室で謎の香りを嗅いだ高校生・芳山和子は、時間を超える能力を身につけてしまう。親友の吾朗や深町一夫との関係の中で、その力の意味を探りながら、繰り返される時間と初恋の記憶に翻弄されていく。やがて和子は、未来から来た少年との別れを経て、自らの記憶を消す決断を迫られる。原田知世が初主演を果たし、角川映画の象徴的存在となった作品である。
変態の美学──大林宣彦という装置
大林宣彦という監督は、映画という装置を通して“変態”という言葉を美学へと昇華させた稀有な存在である(キッパリ)。
ここでいう変態とは、性的倒錯ではなく、世界を常識の回路からずらし、日常に潜む異物を感情とイメージの反転によって露わにする行為のことだ。
彼はCMディレクターとして培った映像的フェティシズムを、フィルムという媒介に転写し、現実を夢に、夢を現実に変質させた。『転校生』(1982年)、『さびしんぼう』(1985年)と並ぶ“尾道三部作”の第二作である『時をかける少女』(1983年)は、その変態性がもっとも繊細かつ透明な形で結晶化した作品といえる。
ここでまず指摘すべきは、本作が筒井康隆の同名SF小説(1967年『角川文庫』刊)を原作としている点である。原作は、中学三年生の少女・芳山和子が理科室で不思議な薬品の匂いを嗅ぎ、時間を跳躍する能力を得る──という筋立てで、科学的想像力と思春期の心理を融合させたジュブナイル小説だった。
筒井は“時間SF”の嚆矢として、日常の中に突然開く異界を描き、後の日本SF文学に大きな影響を与えた。だが大林は、この物語を単なる時間旅行譚ではなく、“時間の質感を映像として体験させる寓話”に変換したのである。
その経緯は、角川映画のプロデューサー角川春樹によるオファーに端を発する。角川は当時、原田知世を新しいスクリーン・アイドルとしてデビューさせる戦略を練っており、彼女のイメージを成立させるために、青春と幻想を往還する題材を求めていた。
そこで白羽の矢が立ったのが、筒井康隆の『時をかける少女』。大林は『転校生』で尾道という舞台と思春期の転生モチーフを用いて成功しており、その延長線上で“少女が時間を越える”という物語を映画的に展開することが決まった。
彼は筒井に直接会い、脚本段階で「原作をそのままではなく、映画として再誕生させたい」と伝えたという(※筒井自身も後年インタビューで、「大林監督の映画は原作を越えた」と述べている)。この原作と映画の関係こそ、大林作品特有の“現実と虚構の転写”を象徴している。
角川春樹プロデュースのもと、原田知世という無垢なアイドルのデビュー作として製作された本作は、表層的には清冽な青春ファンタジーの装いをしている。
だがその内側には、少女が大人になる瞬間──性的覚醒と時間の不可逆性というテーマ──が埋め込まれており、大林はその二重構造を隠すことなく露わにしている。
彼が撮る“美少女”とは、決して受動的な存在ではない。むしろ世界を感受する装置としての肉体、時間の流れを通じて変質していく感情の受容体として描かれるのだ。
大林のレンズは、少女の肌を撫でる風や光の粒子さえも性的なニュアンスを帯びさせる。それは露骨なエロティシズムではなく、成長の痛みとしての官能である。
生理とまなざし──青春映画の中の隠された欲望
『時をかける少女』においてもっとも印象的なのは、物語の進行とは無関係に挿入される生理の暗示だ。実験室で倒れた原田知世演じる芳山和子を介抱した女性教師が、去り際に「生理…」と呟き、岸部一徳演じる教師がその後ろ姿をいやらしい視線で見送る。
その一連の流れは、明示的なエロスではなく、“視線の倫理”をめぐる寓話として機能する。女性の身体に宿る生理的変化を、男性の欲望と無関係に描きながら、同時にその欲望をカメラの位置に重ねる。
この二重構造こそがオオバヤシイズムの本質だ。彼の映画では、常に“見る者”の存在が前景化する。教師の視線は、観客のそれと重なり、我々自身の覗き見的衝動をスクリーンに映し返す。
大林はその構造を意図的に露出させ、映画という媒介そのものの変態性を提示する。つまり、『時をかける少女』は青春映画の形式を借りながら、実は“見ることの罪”を描いているのだ。
原田知世の演技が一本調子であり、高柳良一の台詞が拙く棒読みであることさえ、この作品の内部では意味を持つ。未熟な演技がもたらすぎこちなさこそ、時間に取り残された“成長の前段階”としてのリアリティを担保している。
そこではプロの演技よりも、言葉にならない沈黙や視線の逸れ方が、より深い感情の地層を示している。
時間と記憶の断絶──「その後」を描く青春の残酷さ
大林宣彦が他の青春映画作家と決定的に異なるのは、彼が“時間”を決して肯定的なものとして扱わない点にある。
『時をかける少女』の後半で、時間を超えて恋人を救おうとした和子は、記憶の消去という代償を支払う。彼女は愛を成就させる代わりに、自らの感情の履歴を失う。
大林はこの結末を、ノスタルジーの反転として描く。すなわち、青春の輝きはその喪失によってしか確定しない。大学院の廊下ですれ違う二人──かつての恋人である深町一夫と和子──は互いを認識できない。
そこにあるのは、記憶を失った者の孤独ではなく、時間という非情なシステムが個人の感情を削ぎ落としていく残酷さ。大林は“時をかける”という超常的行為を、SF的な奇跡としてではなく、人間の成長に伴う不可逆な断絶として描く。
だからこそ、この映画は甘美な青春ファンタジーではなく、時間に取り憑かれた存在の悲劇である。原田知世の表情から、幼さが抜け落ちた瞬間、彼女はもはや“少女”ではなくなり、同時に映画の中心的モチーフも消滅する。
時間の流れそのものが、青春というジャンルの墓碑銘となっている。
アイドル映画の変容──純粋さと虚無の狭間で
本作は明らかに角川映画的戦略のもとに成立したアイドル映画だが、大林はその枠組みを内部から転覆する。原田知世という存在を、単なる消費可能な偶像としてではなく、“時間の受け皿”として機能させる。
彼女の無垢さは、商業的純粋さと物語的虚無の間で引き裂かれている。高柳良一とのぎこちないやり取り、唐突に挿入される「桃栗三年柿八年」の歌のシーンもまた、物語の流れを中断する異物として作用し、観客を映画の外へと弾き出す。
大林はリズムの破綻を恐れない。それどころか、破綻を通して映画の構造そのものを可視化する。映像の中に漂う空気の粒子、音の揺らぎ、人物の配置──それらが一体となって“時間の感触”を再構成する。
彼にとって映画とは、物語を語るメディアではなく、時間を触知させる装置なのだ。だからこそ、彼の作品には常に“終わりの気配”が漂う。『時をかける少女』のラストで描かれるのは、恋の成就ではなく、不可逆な時間の支配である。ハッピーエンドを拒絶するその姿勢は、むしろ現実への誠実さの証明にほかならない。
同じ角川映画の系譜に位置づけられる作品群──たとえば薬師丸ひろ子主演の『セーラー服と機関銃』(1981年)や『探偵物語』(1983年)、渡辺典子の『伊賀忍法帖』(1982年)、『晴れ、ときどき殺人』(1984年)──はいずれも、アイドルの魅力を“物語の中心”として構築していた。
すなわち、角川映画とは企画段階から「アイドルを売るための映画」であり、彼女たちの存在がスクリーンを支配していた。薬師丸が演じたヒロインたちは、少女と大人の狭間に立ちながらも、常に〈社会の外側〉にある“守られる存在”として描かれ、観客の視線に守護される構図の中で神聖化される。
彼女が「カ・イ・カ・ン」と銃を撃つ瞬間でさえ、その行為は暴力の快楽ではなく、純粋さの儀式として消費されていたのだ。
それに対して、大林宣彦が手がけた『時をかける少女』は、明確に“アイドル映画の反転”として設計されている。原田知世は、観客の視線によって完成するアイドルではなく、時間の流れによって消耗する存在だ。
彼女の可憐さは瞬間的に輝くが、それは次の瞬間に失われていく運命を内包している。つまり彼女の魅力は「記憶の中でしか生きられない」という宿命に支配されているのだ。
薬師丸や渡辺典子のキャラクターが“社会の物語”に属するのに対し、原田知世の和子は“時間の物語”に閉じ込められている。ここに、大林の映像思想と角川映画の商業主義が激しく衝突する接点がある。
角川映画の多くが、“アイドルの瞬間的な消費”を目的にしたパッケージ化された青春だったのに対し、大林は“時間の中で消えゆく存在の記録”を撮った。
これは同時代の商業映画としては異端であり、角川春樹自身がのちに「大林は角川映画を文化にしてしまった」と述懐したほどである。原田知世が劇中で見せる素朴で未完成な演技は、演技力の不足ではなく、映画という時間の流れに対して無防備であることの証明。
彼女は「役を演じる」よりも「時間に触れられる」存在であり、だからこそ彼女の表情には〈記録ではなく記憶〉の質感が宿る。
さらにいえば、『時をかける少女』が提示する“虚無の手触り”は、同じ年に公開された『探偵物語』の終盤のきらめきと正反対に位置する。
そこでは都会のノスタルジーが甘美に演出されていたのに対し、大林の尾道は湿度を帯びた記憶の層として立ち上がる。角川映画が一般的に提示した“アイドル=永遠の少女像”を、大林はあえて終わらせる。
彼は“成長”を物語のクライマックスではなく、“喪失”として描く。映画の中で原田知世が少しずつ表情を硬化させ、声のトーンを落とし、姿を消していく過程そのものが、角川アイドル映画の神話に終止符を打つ儀式になっている。
変態としての叙情──大林映画の終着点
『時をかける少女』は、大林宣彦の変態性がもっとも美しい形で結実した作品だ。彼の“変態”とは、世界を愛しすぎるあまり、現実をそのまま受け入れられず、フィルム上で異化してしまう行為である。
彼にとって少女とは、性の象徴ではなく、永遠に失われ続ける時間そのものだ。だからこそ、彼のカメラは彼女たちを見つめるのではなく、“見送る”のである。
ラストシーンで原田知世が振り返ることなく去っていく姿は、観客に対する別れの視線だ。そこには、記憶を奪われた者の悲しみと同時に、未来へと歩み出す者の覚悟がある。
大林宣彦は、青春という瞬間を永遠化するのではなく、その不可逆性を映画という記録装置の中に封じ込めた。変態とは、現実の痛みをロマンチックに変換する能力であり、それゆえに彼の映画は常に詩的でありながら冷酷だ。
『時をかける少女』は、アイドル映画でありながら、時間と記憶、欲望と倫理、青春と死という普遍的テーマを内包する異形の作品である。大林宣彦はこの映画を通じて、変態こそが最も誠実な叙情であることを証明した。
- 製作年/1983年
- 製作国/日本
- 上映時間/104分
- 監督/大林宣彦
- 製作/角川春樹
- プロデューサー/山田順彦、大林恭子
- 原作/筒井康隆
- 脚本/剣持亘
- 脚色/大林宣彦
- 撮影/阪本善尚
- 音楽/松任谷正隆
- 編集/大林宣彦
- 録音/稲村和己
- 原田知世
- 高柳良一
- 尾美としのり
- 津田ゆかり
- 岸部一徳
- 根岸季衣
- 内藤誠
- 入江若葉
- 上原謙
- 入江たか子