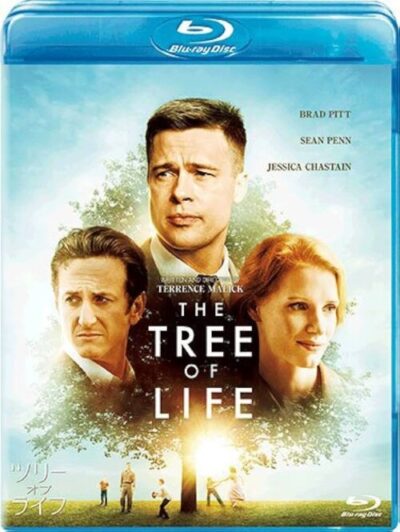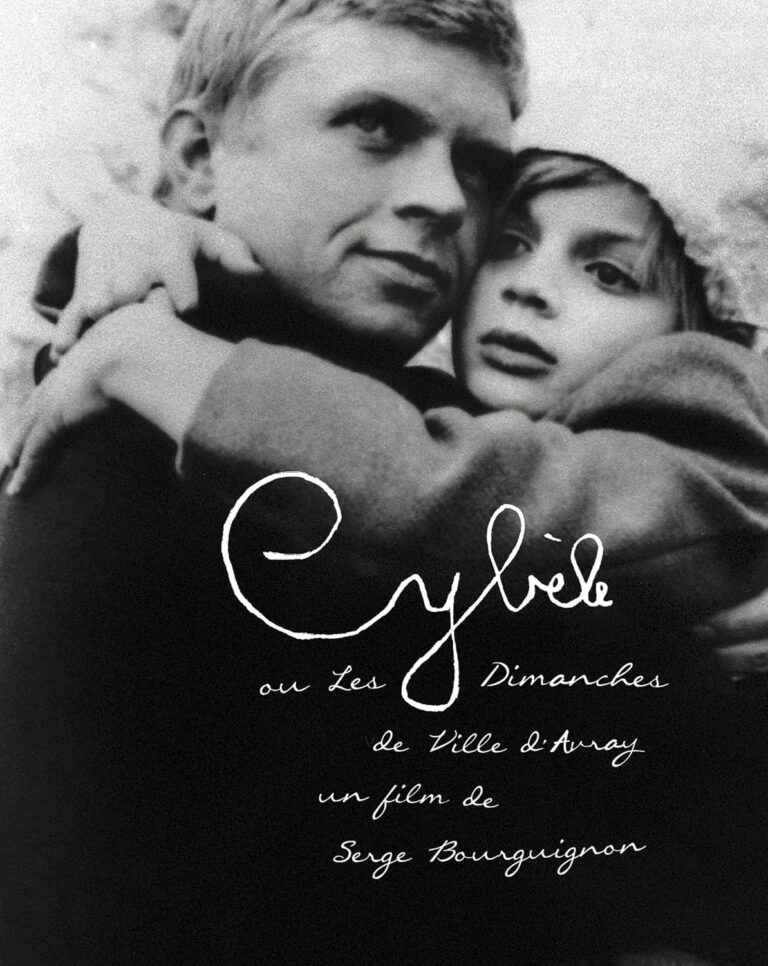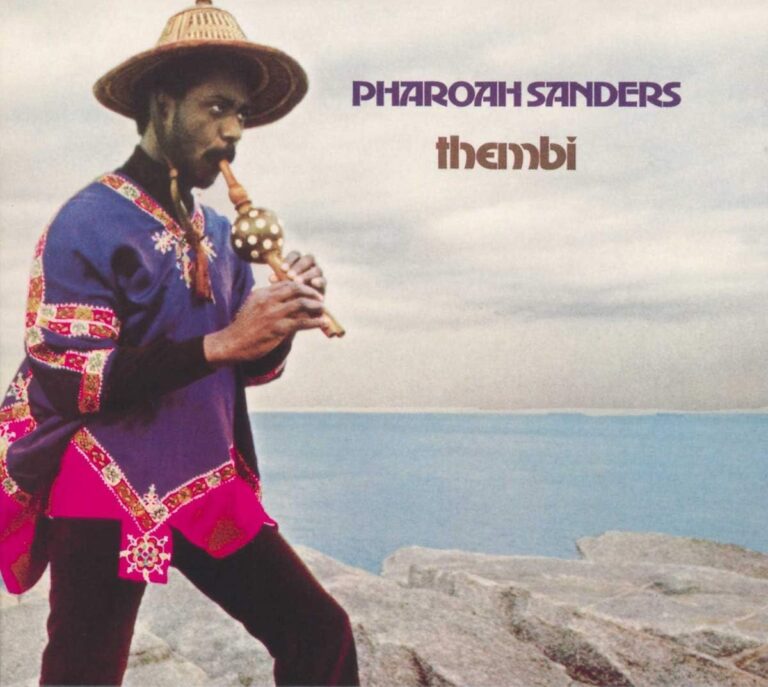『ウォール・ストリート』(2010)
映画考察・解説・レビュー
『ウォール・ストリート』(原題:Wall Street: Money Never Sleeps/2010年)は、オリバー・ストーン監督が前作から23年を経て再び金融界を描いた社会派ドラマ。服役を終えた元トレーダーのゴードン・ゲッコー(マイケル・ダグラス)が、金融危機後のニューヨークで復帰を試みる。若き投資家ジェイコブ(シャイア・ラブーフ)との関係を通じ、時代の変化と欲望の倫理が交錯していく。
時代の変奏──23年後の“ウォール街”
前作『ウォール街』(1987年)から23年。オリバー・ストーンは再び同じ場所にカメラを戻した。1987年といえば、世界経済を震撼させたブラック・マンデーが発生した年であり、金融資本主義の「倫理なき熱狂」が露わになった時期である。
そして2010年──世界はサブプライムローンに端を発する金融危機の爪痕に喘いでいた。このタイミングでの続編制作は偶然ではない。ストーンは常に時代の臨界点に反応する作家であり、経済という抽象的システムの裏に潜む“人間の欲望”を見つめてきた。
『ウォール・ストリート』(2010年)は、その延長線上にある「倫理の更新」の物語である。
ゲッコーの変奏──“強欲は善”から“家族の徳”へ
「強欲は善(Greed is good)」という言葉は、80年代アメリカの象徴であり、同時にマイケル・ダグラス演じるゴードン・ゲッコーの代名詞となった。
だがストーンは、この続編でそのアイコンを反転させる。長い服役を経たゲッコーは、かつての帝王ではなく、時代に取り残された亡霊として登場する。
出所時に手渡される巨大な携帯電話──それは単なる小道具ではない。技術革新の速度と人間の取り残され方を、わずかなカットで語る優れた演出である。
家族を失い、孤独を抱えたゲッコーが「人生で最も大切なのは家族」と語る場面は、一見すると更生の物語に見える。だが、オリバー・ストーンはそんな安易な救済を信じていない。
結末でゲッコーは再び欲望に身を投じ、観客に“道徳”と“資本”の関係を逆転させてみせる。善意が悪を包み込み、悪が善を模倣する──それが現代資本主義の構造そのものだ。
映像としてのウォール街──電子的空間のダイナミズム
本作の見逃せない美点は、ストーンの演出センスにある。彼は社会派というレッテルを貼られながらも、常に映像表現そのものに革新を求めてきた。出所シーンのミニマルな演出、スプリット・スクリーンによる会話のテンポ、情報の錯綜をデジタル空間で視覚化する編集──いずれも今日的な“情報の速度”を映し出している。
株価のグラフが摩天楼のシルエットと重なり、光の帯が都市の神経を駆け抜けるオープニングは、資本主義そのものを巨大な電子生命体として描いた詩的メタファーだ。
80年代のウォール街が“金と欲の神殿”だったとすれば、2010年代のウォール街は“情報と電脳の迷宮”である。
オリバー・ストーンという作家──過剰と反省の狭間で
ストーンは政治的映画作家であると同時に、過剰なスタイリストである。
『Uターン』(1997年)や『エニイ・ギブン・サンデー』(1999年)に見られるように、彼は常に現実を誇張し、映像的エネルギーを炸裂させる。本作でもその傾向は健在だ。複層的な編集と音楽のカットインが、現代社会の分裂したリズムを可視化している。
トーキング・ヘッズの楽曲を再び使用したのは、彼自身の映画史的回帰でもある。音と映像の同期が、80年代的享楽と2010年代的空虚を架橋し、資本主義の“循環する快楽”を体現する。
ストーンの映画はいつも、社会批判とスタイルの快楽の狭間で揺れている。
倫理なき時代の青年──物語の限界とリアリズムの不在
難を言えば、主人公ジェイコブ(シャイア・ラブーフ)の人物像があまりにも直線的であることか。彼は誠実で正義感の強い青年として描かれるが、現代の金融資本主義を舞台にするには清潔すぎる。葛藤の欠如は、明らかに物語のダイナミズムを奪っている。
前作のチャーリー・シーンが〈理想と欲望〉の狭間で引き裂かれていたのに対し、ジェイコブにはその内的闘争がない。善人であることに疑いを持たない彼は、資本主義の“曖昧な倫理”を体現できていない。結果として、ゲッコーの陰影と対比が弱まり、映画はやや予定調和的に終わる。
それでも、キャリー・マリガン演じる娘の存在が作品に一抹の温度を与えている。彼女の素朴な透明感は、ゲッコーという怪物の物語にかすかな救済を添える。
中盤で登場するチャーリー・シーンのカメオは、映画史的メタ・ジョークとして機能しており、かつての青年の“その後”を見せる冷たいギャグでもある。
“強欲”の彼方にある空虚
『ウォール・ストリート』(2010年)は、単なる続編ではない。資本主義の物語が終焉したあとに何が残るのか──その問いを映像で描いた試みである。
かつて「強欲は善」と叫ばれた時代は去り、今や“強欲”そのものが倫理の中に吸収されている。善悪の境界が溶解した世界で、オリバー・ストーンは再びゲッコーを蘇らせる。
この映画は告発でも教訓でもない。むしろ、我々自身がゲッコーの再来であることを静かに告げる。資本主義の終わりとは、強欲が悪でなくなる瞬間のことなのだ。
- 監督/オリバー・ストーン
- 脚本/アラン・ローブ
- 製作/エドワード・R・プレスマン、エリック・コペロフ
- 製作総指揮/セリア・コスタス、アレックス・ヤング、アレサンドロ・キャモン
- 撮影/ロドリゴ・プリエト
- 音楽/クレイグ・アームストロング
- 編集/ジュリー・モンロー、デヴィッド・ブレナー
- 美術/クリスティ・ズィー
- 衣装/エレン・マイロニック
- ウォール街(アメリカ)
- JFK(1991年/アメリカ)
- ウォール・ストリート(2010年/アメリカ)
- ウォール街(アメリカ)
- ウォール・ストリート(2010年/アメリカ)
![ウォール・ストリート/オリバー・ストーン[DVD]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/71pWZxM0hiL._AC_SL1000_-e1759749798391.jpg)