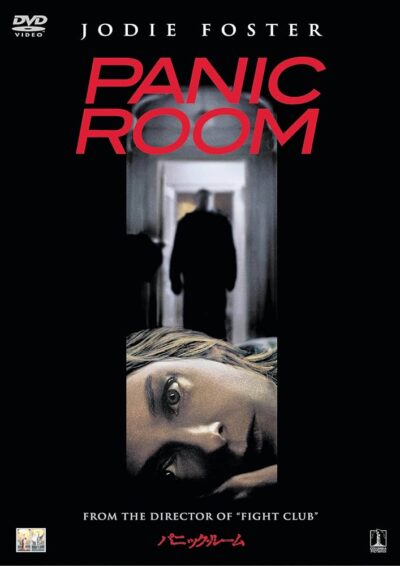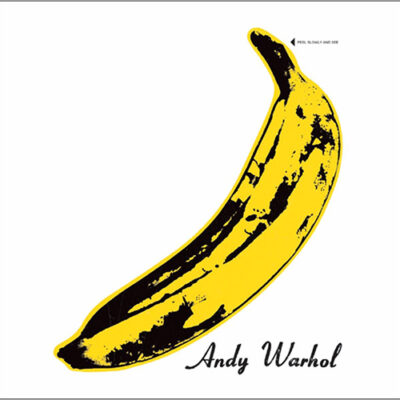『ベンジャミン・バトン 数奇な人生』(2008)
映画考察・解説・レビュー
『ベンジャミン・バトン 数奇な人生』(原題:The Curious Case of Benjamin Button/2008年)は、逆に年を取る男の生涯を描いたデヴィッド・フィンチャー監督の叙事的ファンタジー。第一次大戦後のアメリカを背景に、老いて生まれ若返りながら人生を歩むベンジャミンと、踊り手デイジーとの愛の軌跡が綴られる。原作はF・スコット・フィッツジェラルドの短編小説で、第81回アカデミー賞で13部門にノミネート、うち3部門を受賞した。
スピルバーグが夢見た光を、フィンチャーが影で塗り潰した日
『ベンジャミン・バトン 数奇な人生』(2008年)の企画は、古くは1990年代初頭、スティーヴン・スピルバーグが「老いて生まれ、若返りながら死ぬ」というマーク・トウェインの逆説的な幸福論を、映画化しようとしたことに始まる。
スピルバーグなら、きっとこれを『世にも不思議なアメージング・ストーリー』のように、失われた若さを取り戻す「奇跡の寓話」として、黄金色の光り輝く魔法のように撮ったはずだ。実際当時はトム・クルーズ主演で、若返る喜びを謳歌するファンタジーとして企画が進められていたのだから。
だが、実際にこのメガホンを取ったのは、ハリウッド屈指の構築主義者であり、完璧主義者のデヴィッド・フィンチャーだった。彼はスピルバーグ的な希望をいっさいがっさいゴミ箱に放り込み、代わりに「時間という名の絶対的な暴力」をスクリーンの中心に据える。
プロデューサーに、キャスリーン・ケネディやフランク・マーシャルといったスピルバーグの愛弟子たちを揃えながら、フィンチャーはあえて彼らの温もりから距離を置いた。
彼が描きたかったのは、魔法ではなく「肉体が老いる、あるいは若返る」という物理的な現象が、いかに人間を孤独に追い込み、愛する者との距離を広げていくかという、残酷なまでのリアリズムだったのだ。
脚本を担当したのは『フォレスト・ガンプ/一期一会』(1995年)で世界を泣かせたエリック・ロス。20世紀のアメリカ史を横断する叙事詩的な構成は確かに似ている。
しかし、『フォレスト・ガンプ/一期一会』が「偶然を肯定し、歴史の流れに溶け込む」物語だったのに対し、ベンジャミン・バトンは「時間に翻弄され、歴史の流れからはじき出される」孤独な男の物語。
フィンチャーはロスの脚本から感傷的な台詞を削ぎ落とし、代わりに映像の「質感」で語ることを選んだ。彼にとって人生の意味とは、心や魂といった曖昧な場所ではなく、皮膚のシワ、肉のたるみ、血管の浮き沈みといった、逃れようのない「肉体的時間」にこそ宿るものなのだ。
80歳の赤ん坊を創り出した、デジタル・バイオロジー
本作の特異点は、若返りという奇想を単なる物語のギミックにせず、徹底的な肉体的現実として捉えている点にある。
フィンチャーは「コンツアーシステム」と呼ばれる、当時の限界を突破したVFX技術を駆使し、ブラッド・ピットの頭部をフルデジタルで作成。驚くなかれ、映画の前半52分間、ブラッド・ピット本人は一度も画面に映っていないのだ。
150人以上のデジタル・アーティストが155,000時間以上を費やし、ピットの表情の動きを120種類以上のデジタル・シェイプに解体・再構築した「老いた虚像」がそこに立っている。これはもはや特撮ではなく、デジタルによる生命の創造だ。
この圧倒的なテクノロジーの目的は、単なる見世物ではない。フィンチャーが最終的に到達したのは、デジタルがアナログ(肉体)を再発見す」瞬間だった。
老いたベンジャミンが次第に若返り、生身の肉体を取り戻していく過程は、彼が『ファイト・クラブ』(1999年)で誇示した「筋肉という自己証明」の裏返しである。
あの映画では肉体は暴力の象徴であり、自己を破壊するための手段だった。だが本作では、肉体は時間に侵食され、やがて愛の器として崩壊していく。デジタルが肉体を超越する時代に、彼は逆説的に「肉体こそが逃げられない唯一のリアルである」と冷徹に語るのだ。
対を成すケイト・ブランシェットの身体もまた、フィンチャーのカメラにおいて、時間の器として描かれる。撮影監督クラウディオ・ミランダが、19世紀の絵画のようなデジタル撮影と、当時最新のLED照明を組み合わせて捉えた彼女の肌の質感を見よ。
バレエを踊る彼女が「身体のラインが大事なの」と語る瞬間、その柔らかな動きは単なる台詞を超えて、「今、この瞬間にしか存在しない生」の輪郭を描き出す。
若返る男と老いていく女。二人の身体が一瞬だけ重なり、再び離れていく。その刹那に刻まれる感触が、映画全体の情動を支配している。
ブランシェットの肉体は象徴ではなく現象であり、照明が彼女の肌に触れるとき、観客は抽象的な「老い」を超えて、死へと向かう生命の「温度」を直接感じてじまう。
ブラッド・ピットが到達した無の演技
もしスピルバーグがこの作品を撮っていたなら、ラストは涙なしには見られない、再会と救済の感動のフィナーレになっていただろう。
だがフィンチャーは、安易な幸福を徹底的に拒絶することで、作品に永遠の命を与えた。彼にとって、物語が提示する「幸福」や「感動」など、構造的な欺瞞にすぎない。
撮影現場でフィンチャーはピットに対し、「表情で感情を説明するな。ただそこにいろ」と厳命したという。その結果生まれたのが、本作を象徴する、感情の真空だ。
若返ったベンジャミンが、老いた恋人を見送るシーンを思い出してほしい。テレビを観ながら何の感慨もなく「さよなら」を告げるその無表情……。これこそがフィンチャー作品に通底する、冷徹な観察者の視点だ。
内面が一切滲み出ない顔。そこに宿るのは無垢ではなく、むしろ「時間という巨大なシステムの一部」としての人間の根源的な孤独。フィンチャーはこの冷たさを、誰よりも愛している。
彼は「愛」を甘い言葉としてではなく、老いた皮膚が若返る皮膚に触れるとき、あるいはその逆の瞬間に生じる「物理的な摩擦」として描いた。そこに宿る切なさは、どんな涙の演技よりも深く、観客の肺を圧迫する。
ベンジャミンが若返るほどに、世界は彼を置き去りにし、やがて彼は知性も言葉も失い、赤ん坊へと退化していく。そこにカタルシスなど存在しない。あるのは、時間という絶対的な法に支配された肉体の、静かなる敗北の記録だけだ。
『ベンジャミン・バトン 数奇な人生』は、アメリカ的な感動大作の皮を被りながら、その実体は「肉体という現実を通してしか時間を語れない」というフィンチャーの冷徹な信仰が詰まった、恐るべき肉体の映画である。
時間が進むたびに若返る男。その数奇な生は、皮肉にも「死に向かう生命」そのものを、世界で最も美しく、そして最も残酷に可視化してしまったのである。
- 監督/デヴィッド・フィンチャー
- 脚本/エリック・ロス
- 製作/キャスリーン・ケネディ、フランク・マーシャル、セアン・チャフィン
- 撮影/クラウディオ・ミランダ
- 音楽/アレクサンドル・デスプラ
- 編集/カーク・バクスター、アンガス・ウォール
- 美術/ドナルド・グレアム・バート
- 衣装/ジャクリーン・ウェスト
- セブン(1995年/アメリカ)
- ゲーム(1997年/アメリカ)
- ファイト・クラブ(1999年/アメリカ)
- パニック・ルーム(2002年/アメリカ)
- ベンジャミン・バトン 数奇な人生(2008年/アメリカ)
- ドラゴン・タトゥーの女(2011年/アメリカ)
- ゴーン・ガール(2014年/アメリカ)
- Mank マンク(2020年/アメリカ)
- ザ・キラー(2023年/アメリカ)
![ベンジャミン・バトン 数奇な人生/デヴィッド・フィンチャー[DVD]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/81WH-hgV4tL._AC_SL1500_-e1759017866813.jpg)
![フォレスト・ガンプ/一期一会/ロバート・ゼメキス[DVD]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/71vWPqPbi9L._AC_SL1209_-e1718507309266.jpg)
![ファイト・クラブ/デヴィッド・フィンチャー[DVD]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/51ltwfwxY0L._AC_UF8941000_QL80_-e1759018047940.jpg)