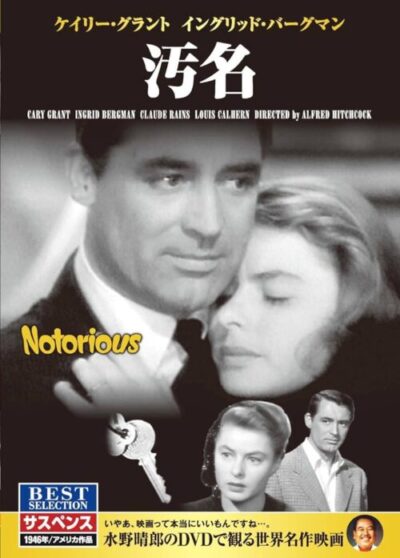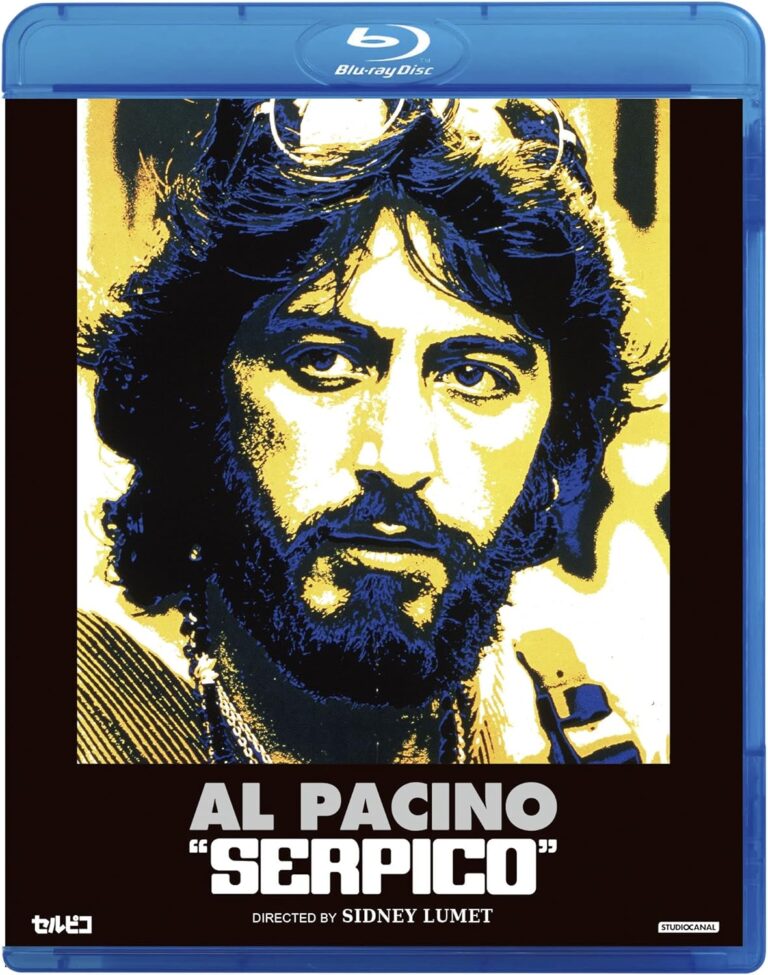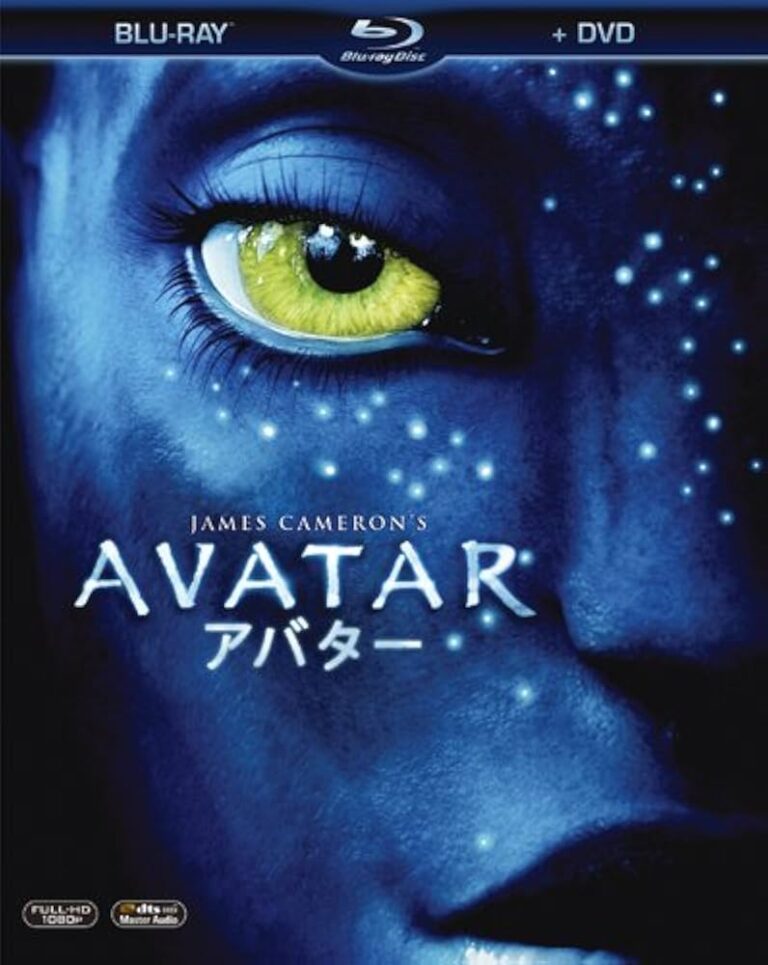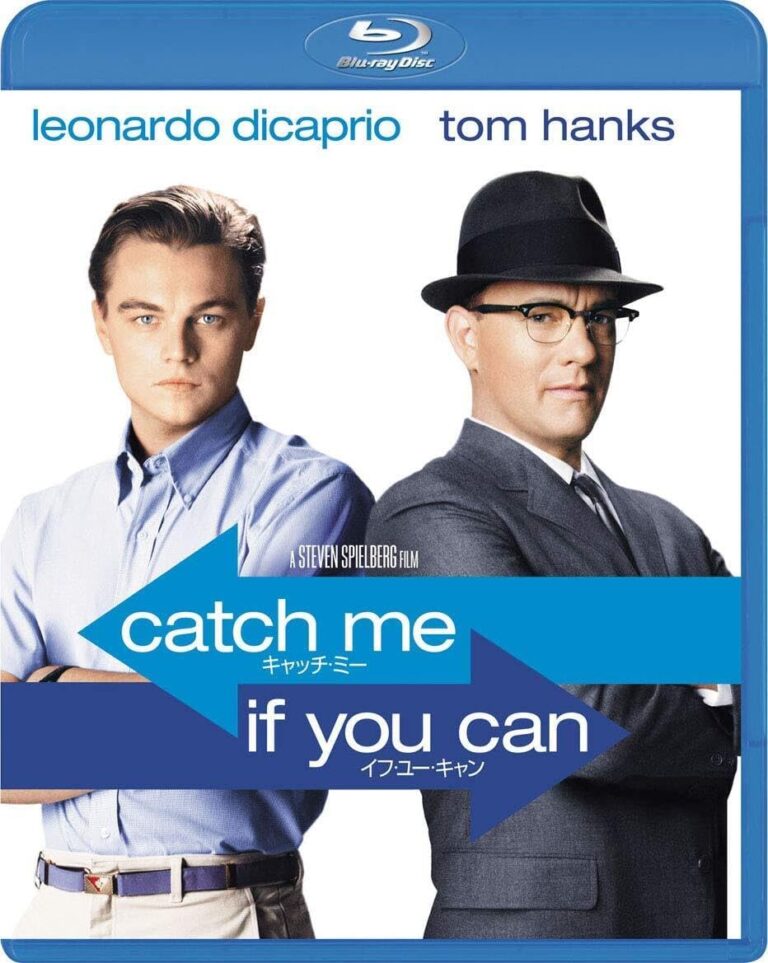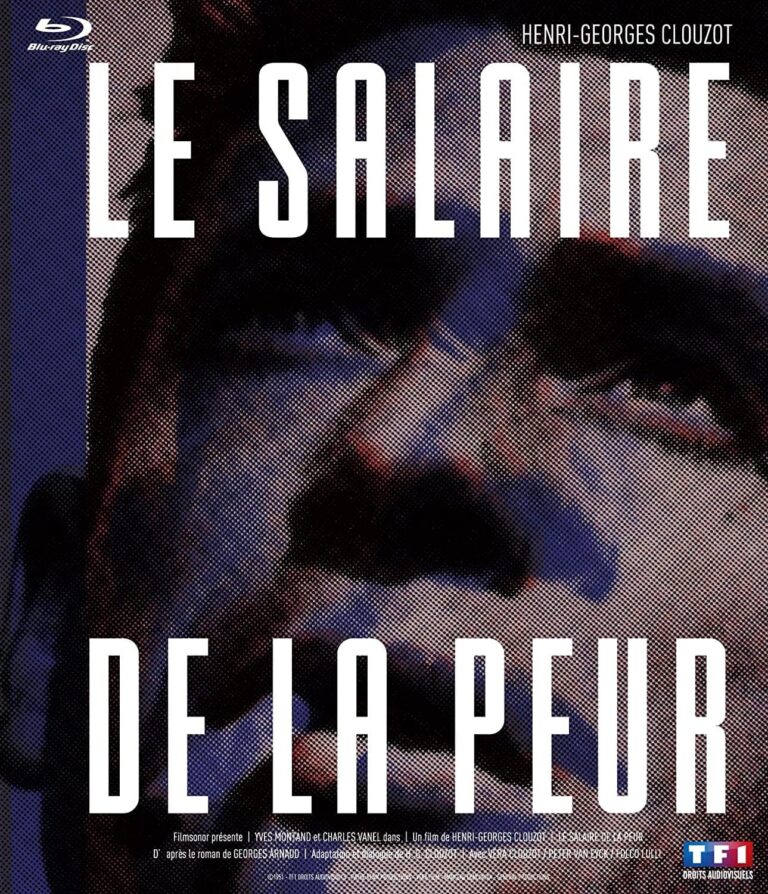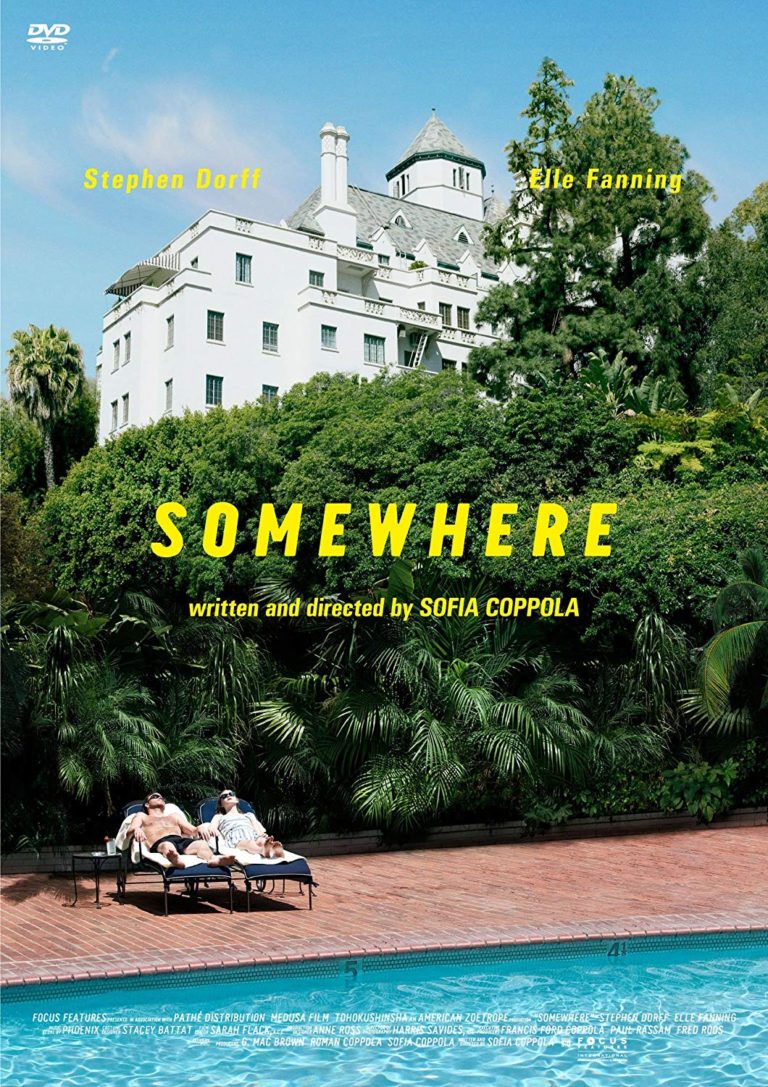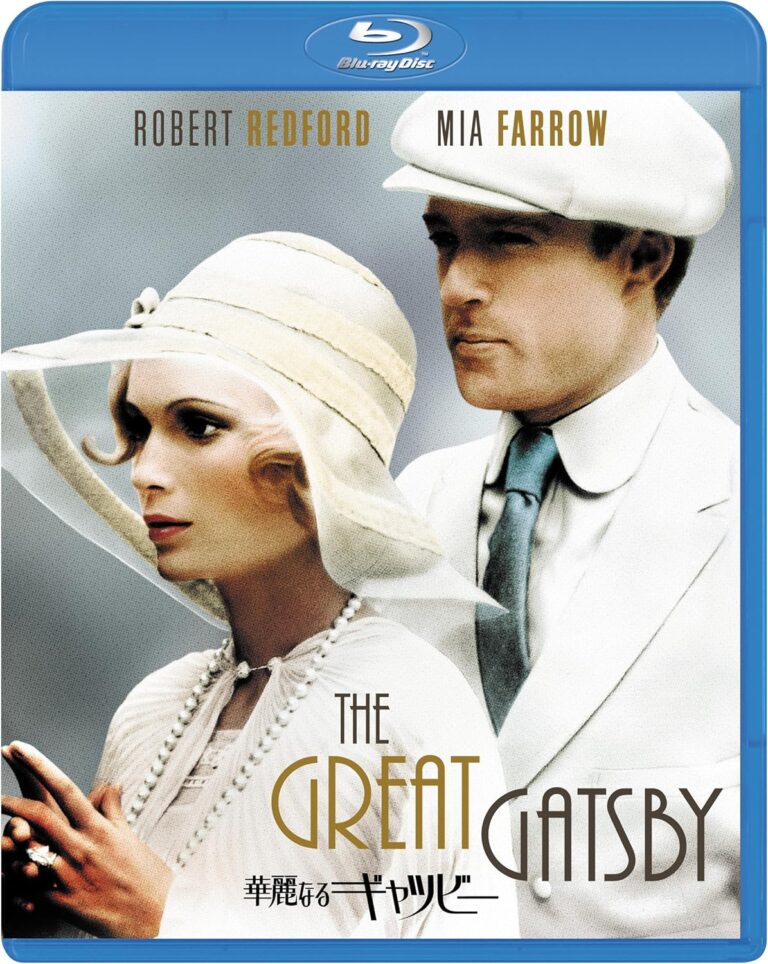『時計じかけのオレンジ』──暴力と快楽のあいだで笑う悪魔
『時計じかけのオレンジ』(原題:A Clockwork Orange/1971年)は、暴力を美として提示し、倫理と自由意志をめぐる根源的な問いを突きつけたスタンリー・キューブリックの衝撃作。未来都市を舞台に、快楽と支配の狭間で人間性が機械化していく過程を描く。
最も論争的で、挑発的で、そして最もキューブリック的な作品
1960年、作家アンソニー・バージェスは医師から「脳腫瘍で余命一年」と診断された。残される妻の生活を守るため、彼は猛烈な勢いで執筆に取り組む。その成果のひとつが、1962年に刊行された近未来小説『時計じかけのオレンジ』である。
診断は誤りであり、バージェスはその後30年以上生きることになるが、「死を目前にした作家が人間存在の暴力性と自由意志を描き切ろうとした」というエピソードは、この小説をより陰影深いものにしている。背景には、戦時中に彼の妻が米兵に暴行を受けた体験が影を落としていたともされる。
この小説を映画化したのが、スタンリー・キューブリックだ。1971年公開の『時計じかけのオレンジ』は、彼のフィルモグラフィーの中でも最も論争的で、挑発的で、そして最も「キューブリック的」な作品となった。
アレックスという「未来世紀のミック・ジャガー」
主人公アレックス(マルコム・マクドウェル)は、享楽に生きる若者だ。ナッドサットと呼ばれる未来のスラングを操り、エドワード朝風の衣装に身を包み、ベートーヴェンを崇拝する。彼はセックスと暴力を純粋な快楽として求め、街を徘徊する。
その姿は、まるで「未来世紀のミック・ジャガー」。社会的には明らかに「悪」であるにもかかわらず、観客の目には抗いがたいカリスマとして映る。ここにこそ本作の危うさと魔力がある。
このアレックス像は、映画が公開された1971年という時代を背景にして初めて説得力を持つ。当時の欧米社会は、ベトナム戦争の泥沼と反体制文化の昂揚に揺れていた。
イギリスではモッズやロッカーズ、さらにはフーリガンが社会問題化し、若者の享楽的暴力は「モラル・パニック」として糾弾されていた。社会学者スタンリー・コーエンの言う「悪魔化された若者像」が、まさにアレックスに重なる。
同時に、音楽シーンではローリング・ストーンズのミック・ジャガーが「悪魔的な反逆者」の象徴として君臨していた。1968年の名曲〈悪魔を憐れむ歌(Sympathy for the Devil)〉において、ジャガーは「悪魔の声」で歴史の暴力と人間の欲望を歌い上げ、観客を陶酔と恐怖に巻き込んだ。
そのステージパフォーマンスは、カリスマと危険が紙一重であることを証明していた。アレックスは、こうしたロックスター的イメージを映画の中に取り込み、若者文化のアイコンとして再構築されたのである。
さらに時代はやがてパンクへと雪崩れ込む。セックス・ピストルズのドラマー、ポール・クックが「本はあまり読まないけど、『時計じかけのオレンジ』はクールで大好きだ」と語ったのは象徴的だ。
アレックスは、パンク世代にとっての反逆的カリスマの原型だった。ジョニー・ロットンが「アナーキー・イン・ザ・UK」で叩きつけた反社会的エネルギーは、すでにアレックスの暴力的享楽の中に予告されていたのである。
言い換えればアレックスとは、享楽的な暴力と性的エネルギーを通じて「管理社会に抗う身体の記号」だったのだ。彼が観客に魅力的に映るのは、単なる不良少年だからではなく、時代が抑圧してきた欲望そのものをカリスマ化したからにほかならない。
社会学的背景──享楽的若者と管理社会
1960年代後半から70年代初頭、欧米社会は若者文化の激変期を迎えていた。戦後の豊かさを背景に育った「ベビーブーム世代」は、もはや親の価値観を継承するのではなく、享楽と反抗を通じて自己を主張するようになった。イギリスではサッカー場を暴力で支配するフーリガンがメディアを騒がせ、アメリカではヒッピーと反戦運動が街頭を埋め尽くした。
社会学者スタンリー・コーエンが指摘した「モラル・パニック」は、こうした現象に正確に当てはまる。若者の逸脱行動はメディアによって過剰に恐怖化され、社会秩序崩壊の前兆として糾弾された。アレックスはその典型であり、バージェスとキューブリックは享楽的若者の姿を戯画化しつつ、背後に潜む社会の緊張をあぶり出している。
さらにフーコー的に言えば、アレックスは「規律訓練社会」と「逸脱の身体」の衝突を体現している。権力は若者の身体を監視し、従順にしようとするが、アレックスは快楽の消費によってそれを拒絶する。彼の存在は、管理社会に突きつけられた抵抗の記号なのだ。
また、ボードリヤール的に解釈すれば、アレックスの暴力や性的行為は、もはや「意味ある行為」ではなく、記号化されたシミュラークルである。暴力は実際の社会変革をもたらすのではなく、映像や音楽に接続された「消費される快楽」へと転化している。まさにポップ・カルチャーの暴力なのである。
キューブリック流「暴力の美学」
キューブリックは一貫して「人間に内在する暴力」を描いてきた。『突撃』(1957年)では第一次世界大戦の理不尽な軍法会議を通じて、暴力が制度に内在することを示した。『スパルタカス』(1960年)では奴隷反乱を大規模な戦闘シーンで描き、圧政と自由のせめぎ合いに血のリアリズムを刻んだ。
『博士の異常な愛情』(1964年)では核兵器という「システム化された暴力」が人類破滅をもたらす滑稽さを風刺した。そして『2001年宇宙の旅』(1968年)では、人類進化の始まりを「猿人が骨で仲間を殴り殺すシーン」として描き、暴力を人間存在の原点として位置づけた。
こうした系譜を経て、『時計じかけのオレンジ』に至る。ここでキューブリックは、暴力をもはや社会批評や歴史の寓話としてではなく、観客の感覚そのものを揺さぶる「美」として提示する。
有名な「雨に唄えば」シーン。マルコム・マクドウェルが即興で歌い踊りながら作家夫人を襲う場面は、悲惨さとポップさが背徳的に結びつく。観客は嫌悪と高揚のあいだに突き落とされる。
また、セックスシーンを早回しでコミカルに、暴力シーンをバレエのように振り付ける演出は、倫理的な抑制をすり抜け、「暴力の美」を提示する。観客は「暴力は悪い」と説教されるのではなく、「暴力が美しい」と感覚的に経験してしまうのだ。
ここに至って、暴力は倫理や社会の枠組みを離れ、芸術的な形式美へと昇華される。これはキューブリック流の究極的挑発であり、彼の暴力描写の到達点といえる。
音楽と暴力──電子音楽が生んだアイロニー
この映画に欠かせないのが音楽である。電子音楽の先駆者ウェンディ・カーロス(当時はウォルター名義)が、ベートーヴェンやロッシーニをシンセサイザーで編曲し、暴力のシーンに貼り付けた。重低音の粘着質な電子音は、スクリーンの残虐性を倍加させると同時に、観客の倫理的立脚点を崩す。
クラシックの荘厳さは、ここでは犯罪と結びつき、観客に強烈なアイロニーを浴びせる。ベートーヴェン第九の歓喜が、アレックスにとっては「強姦と破壊のBGM」として鳴り響く。高尚と卑俗が反転し、暴力はアートに、アートは暴力に転化する。
この逆転こそキューブリックの狙いだ。暴力を排除した「道徳的に正しい映画」をつくるのではなく、暴力が人間にとって「快楽と切り離せない」ことを、音楽を通じて感覚的に体験させる。つまり音楽は、観客を暴力の加害者に共犯化する装置となっているのだ。
自由意志と管理社会の寓話
物語の後半、アレックスはルドヴィコ療法という心理的去勢を施される。暴力や性欲を抱くと激しい吐き気をもよおすよう条件づけられた彼は、社会にとって「模範的市民」となる。しかし、それは自由意志の完全な剥奪であり、人間を「時計じかけの機械」に変えてしまう。
釈放されたアレックスは、かつての被害者たちから逆襲を受ける。暴力を抑制された結果、彼はただの弱者と化し、痛めつけられるしかない。この矛盾を突きつけることで、バージェスもキューブリックも「暴力そのものが悪なのか、それとも自由を奪うことが悪なのか」という倫理的難問を観客に投げかけている。
『2001年宇宙の旅』で人類の進化を描き、『博士の異常な愛情』で核戦争の狂気を風刺したキューブリック。だが『時計じかけのオレンジ』こそ、彼の作家性が最も凝縮した作品だと断言できる。
暴力と美、自由と管理、快楽と倫理。あらゆる矛盾が過剰に増幅され、観客は拒絶と陶酔の両方を強いられる。これはまさに「キューブリキズム」の極北であり、真性の鬼畜映画である。
「この映画って暴力礼賛で嫌い」という人に出会ったら、アレックスよろしく殴っちまえ。殴ってよし!
- 原題/A Clockwork Orage
- 製作年/1971年
- 製作国/イギリス
- 上映時間/137分
- 監督/スタンリー・キューブリック
- 製作/スタンリー・キューブリック
- 脚本/スタンリー・キューブリック
- 原作/アンソニー・バージェス
- 撮影/ジョン・オルコット
- 音楽/ウォルター・カーロス
- 美術/ラッセル・ハッグ、ピーター・シールズ
- 編集/ビル・バトラー
- マルコム・マクドウェル
- パトリック・マギー
- ウォーレン・クラーク
- ジェームズ・マーカス
- マッジ・ライアン
- マイケル・ベイツ
- エイドリアン・コリ