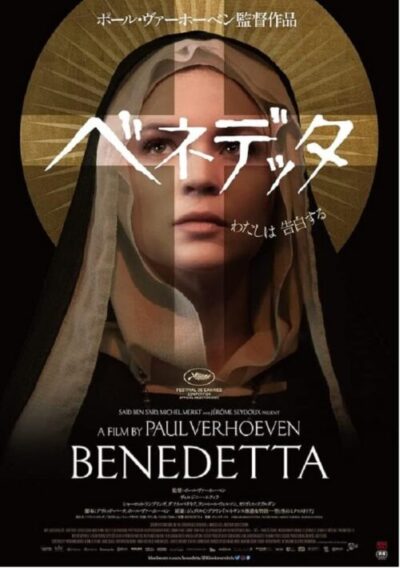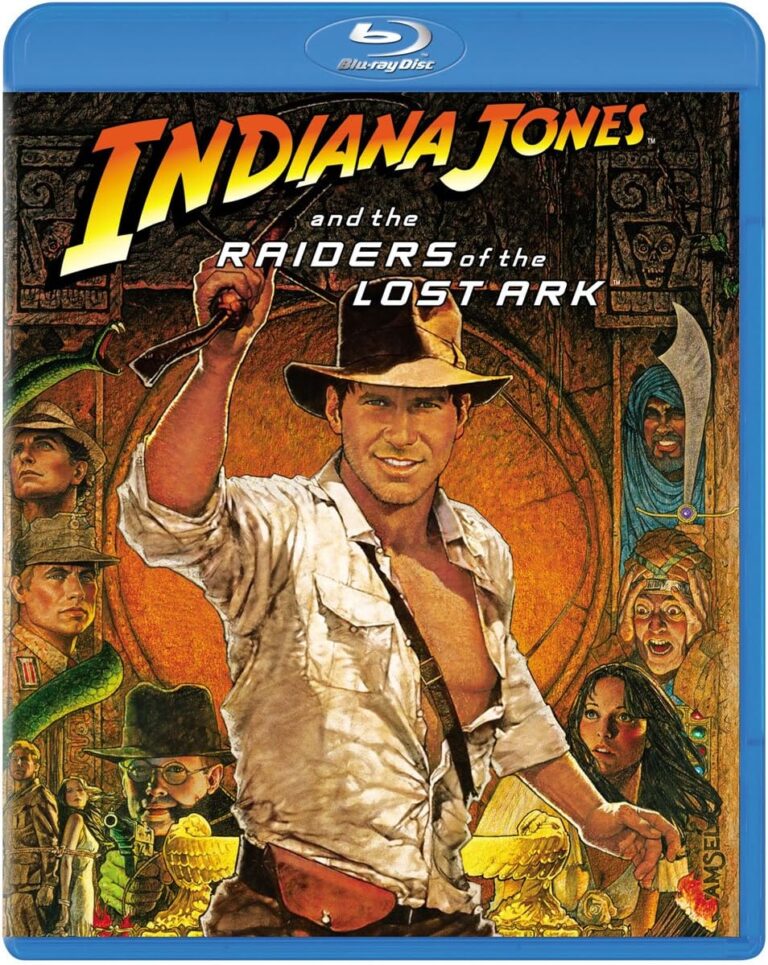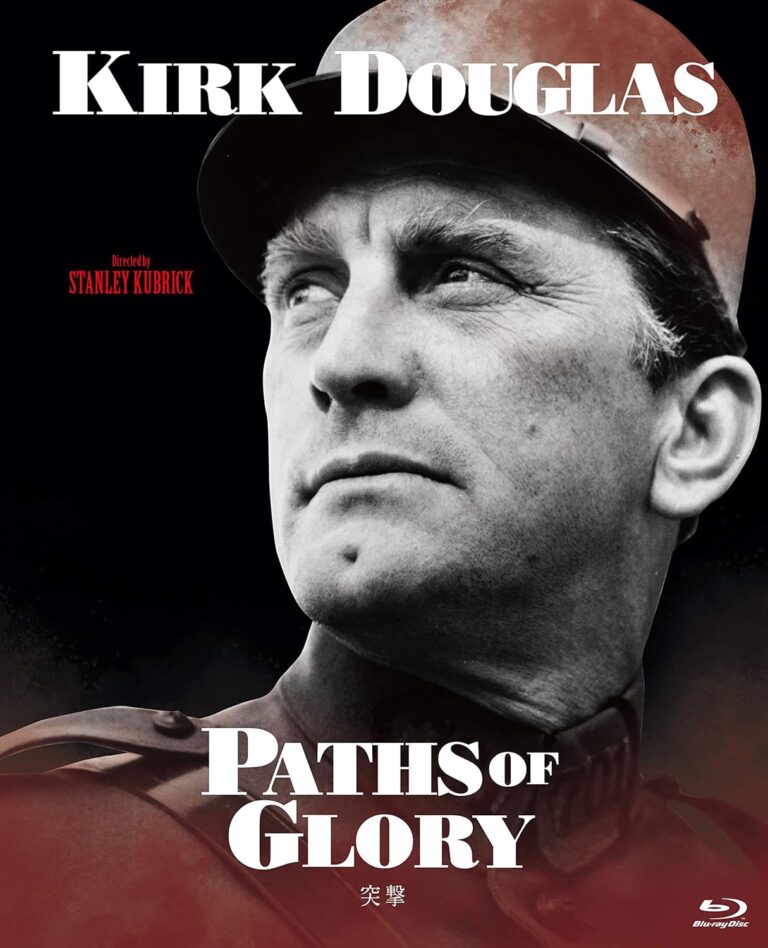『Dolls』──失われたキタノ・ブルー
『Dolls』(2002年)は、北野武が文楽をモチーフに三つの愛の悲劇を描いたファンタジー映画である。若い恋人が赤い紐で結ばれ四季を彷徨い、盲目の青年が失われた偶像を追い、老いた男女が約束の場所へ向かう。桜や雪が巡る中、登場人物たちは時を超えた宿命に導かれるようにすれ違い、やがてそれぞれの結末へとたどり着く。
キタノ・ブルーの美学とその逸脱
『Dolls』(2002)は、かぐわしいほどに美しいファンタジーである。いや、美しすぎる。
北野武はこれまで、徹底してエモーションを削ぎ落とし、その余白によって観客に生々しい感覚を与えてきた。だが『Dolls』は、それまでの彼の映画と決定的に異なる。色彩の洪水、過剰な装飾、音楽の濃密さ──そのすべてが「空虚」を排除し、観念を装飾で覆い尽くしてしまう。
撮影監督・柳島克己はこう語る。
『キッズ・リターン』は本当はモノクロで撮りたかったが実現できず、結局青ベースの色彩設計になった。余計なものを徹底的に取り除いた結果、それが“キタノ・ブルー”と呼ばれるようになったんです。
この証言が示すのは、キタノ・ブルーは“足し算の色”ではなく“引き算の結果として残った色”だという事実。暖色の情報(赤み、黄み)、過剰な飾り、説明的な道具立て――それらを削ぎ落とした先に、空・海・コンクリートに共通する冷たいスペクトラムが露出する。
言い換えれば、キタノ・ブルーとは「余白の色」であり、画面内の情報密度を意図的に下げることで、観客の感情と想像力が流れ込む余地=〈間〉をつくる仕掛けなのだ。
具体的には、低彩度・寒色寄りのグレーディング、ニュートラルグレーを基調にした美術、肌の赤みを抑える露出設計が組み合わさり、静止画面(スタティック)+長めのショットと相まって、画面は冷たく平たいまま、しかし奥行きを秘めて佇む。
『あの夏、いちばん静かな海。』(1991年)の防波堤、『ソナチネ』(1993年)の沖縄の海原、『HANA-BI』(1998年)の冬の空色――いずれも“色が語る”のではなく、“色が黙ること”で出来る沈黙の空間が、暴力や喪失の気配を受け止めてきた。久石譲のスコアですら、その沈黙を縫う“糸”として点在し、けっして面で塗り込めない。ここに北野映画の体温――冷たさゆえの熱――があった。
この原理から見ると、『Dolls』は決定的に異質だ。四季の移ろい(桜・新緑・紅葉・雪)が高彩度の面として前景化し、色彩自体が記号(=主張)に転じる。
さらに衣装(山本耀司)が舞台装置的な強度で画面を占拠し、久石譲の音楽は点ではなく面として感情を誘導する。結果として、従来の「削ぎ落とし→余白→観客が補完」という回路が、「付け加え→装飾→作り手が規定」に反転する。
つまり、『Dolls』は“色が黙る映画”から“色が語りすぎる映画”への転調であり、キタノ・ブルーの根幹――情報を捨てて生まれる静謐――を意図的に外している。
もちろん、文楽を枠組みにした寓話性を高めるために、様式化と色彩の強度を上げる戦略自体は理解できる。しかし、その様式は北野映画の編集律・間合い・省略(省筆の美学)とシンタックス(文法)レベルで嚙み合っていない。
かつては“青”が空間を空け、観客の時間を引き延ばし、暴力や死を必然として沈殿させた。『Dolls』では“色”が空間を埋め、時間を圧縮し、感情を先回りして断定してしまう。ここに、キタノ・ブルーの美学からの逸脱が最もくっきりと現れる。
キタノ・ブルー=余白/Dolls=装飾。前者は観客の想像力を信頼し、後者は作品の意図を可視化する。美しいこと自体が問題なのではない。その美が「沈黙」を奪い、必然を「演出」に置き換えたとき、北野映画の核は微妙に位置をずらすのだ。
衣装と音楽の「過剰」
山本耀司が手がけた衣装は、映画の一要素を超えてスクリーン全体を支配してしまう。文楽的な象徴性を狙ったのかもしれないが、現実との距離感を失わせ、観客を冷笑に誘う瞬間さえあった。山本自身が「ファッションショーにさせてもらう」と語ったというが、映画とショーの境界を取り違えた発言であり、結果的に物語の重心を狂わせたといえる。
布の重さやレイヤーの陰影はあまりに強度を持ち、俳優の表情や身体のリズムを後景へと押しやってしまう。本来、北野映画の核心にあるのは素っ気ないブロッキングと間によって「余白」に感情が立ち上がることだ。
しかし『Dolls』では、衣装がその余白を充填し、象徴性を先回りして観客に提示してしまう。二人を結ぶ赤い紐は、もともと「運命の糸」を暗示するはずの記号だったはずが、縄のような物体として画面に現前し、寓話的な意味を補助するどころか、物語を覆い尽くす主題へと化してしまった。北野映画の省略の美学はここで大きく損なわれ、観客の解釈の自由度は大幅に狭められている。
同様の問題は音楽にも見て取れる。初期から中期にかけての北野と久石譲の関係は、短い旋律が沈黙の間に点のように差し込まれるという形式に支えられていた。音が入る瞬間が合図となり、消えたあとに余韻が残り、観客はその沈黙に自らの感情を投影する余地を与えられていたのだ。
しかし『Dolls』における久石の音楽は、弦楽のレガートや持続音によって情緒を連続的に塗り込めていく。結果として沈黙はマスキングされ、観客が自分の手で感情を発見するプロセスは奪われてしまう。
音楽が結論を先に提示してしまうために、映像が語るはずの「無言の物語」は力を失い、北野映画のアイデンティティとも言える空虚や冷たい静謐が、温かい情緒に置き換わってしまったのである。
こうして衣装と音楽は、いずれも映画を彩るはずの要素でありながら、作品全体の呼吸と均衡を乱してしまった。強い造形と持続する情緒が重なり合うことで、『Dolls』は美しいがゆえに観客の想像力を窒息させてしまう。これこそが、この作品において感じられる「過剰」の正体なのである。
3つのエピソードとその明暗
『Dolls』の三つの挿話のうち、個人的にもっとも印象に残ったのは、深田恭子演じるアイドルと彼女を追いかける青年・温井の物語。事故で顔を損ない引退を余儀なくされた彼女に同調し、温井は自らの目を潰す。これは明らかに谷崎潤一郎『春琴抄』を踏まえた翻案であり、古典文学が持つ倒錯的な愛のモチーフを、現代のアイドル文化に移植した試みといえる。
もっとも、文楽人形を狂言回しに据えている以上、本作全体を通して古典的悲恋譚との響き合いを前提とした統一感が欲しかった。三つのエピソードの中でこの挿話だけが古典的参照の強度を持つため、むしろ他の二つが相対的に弱く見えてしまう。
結果として、深田と西島秀俊が見せる虚無感や、偶像と追随者という現代的な関係性が最も鮮やかに立ち上がり、他の挿話との差異を際立たせてしまう。
一方で、高年齢の男女を描く挿話は観ていて辛かった。若き日に交わした約束を何十年も守り続け、老境に至ってなお再会を果たすという筋立ては、古典的な恋愛譚の枠組みを思わせる。
しかし、そこに配された山本耀司の衣装は寓話的象徴を補強するどころか、現代的な鮮烈さゆえに物語の時間感覚と乖離を生んでしまった。古典的モチーフと現代的装飾の衝突が、観客にとっては荘厳さではなく時代錯誤的な滑稽さに映ってしまうのである。
松原智恵子は意識的に「痛々しい女」を演じているように見えるが、その演技は作品全体のトーンに吸収されず、観客の側に冷笑を誘う結果となった。ここには寓話性と現実感覚の接合がうまく機能せず、物語の重さが空転している印象を否めない。
三つの挿話を並べてみると、深田恭子編は古典の引用を介して現代に説得力をもたらし、高齢カップル編は逆に古典的図式が現代的表現と乖離して失速する。
つまり『Dolls』という作品は、三つのエピソードを通じて「古典と現代をどう接続するか」という問いを投げかけているように見える。だが、その試みは必ずしも均質には成功しておらず、挿話ごとのバランスの悪さが、作品全体の評価を揺らがせているのである。
「死」の必然性をめぐって
北野映画における死は、しばしば唐突に訪れる。しかしその唐突さは偶然の軽さではない。『ソナチネ』のラストで主人公が自死を選ぶ瞬間、『HANA-BI』で夫婦が静かに海へと去る場面、『その男、凶暴につき』で倫理の袋小路が破綻する終幕――いずれも死は物語の外から落ちてきた“事故”ではなく、暴力の構造や関係の劣化、あるいは主体の最終判断によって導かれた帰結である。
北野のカメラは、死を煽らない。むしろ余白と沈黙で包囲し、決定的な瞬間の前後にわずかな間を置く。そのわずかな間に、観客は死の必然を自らの中で完成させる。だからこそ唐突でも納得できる――北野の“唐突”は、周到に準備された“必然”の別名なのだ。
その文法で『Dolls』を見返すと、温井の死だけが異質に浮かぶ。盲目になった彼は、あまりにあっけなく命を落とす。そこに至るまでの“関係”の緊張や、主体の選択としての覚悟、あるいは社会的構造が押し出す駆動力が、十分に画面に沈殿していない。
北野武自身が「『冥途の飛脚』も死ぬと分かっているから泣ける」と言うとき、彼が引いているのは“結末の既知性”ではなく、“結末までの道筋の様式”だ。
文楽における死は、型と音曲と間によって避け難い必然として立ち上がる。ところが『Dolls』の温井は、様式の外、すなわち型の呼吸が整わないうちに、メロドラマ的な“涙のスイッチ”として消えてしまう。悲劇の条件は「結果」ではなく「過程」に宿る。過程が端折られたとき、死は悲劇ではなく装置に堕ちる。
他方で、赤い紐に結ばれ季節の中を彷徨する若い二人や、約束の時間へ回帰しようとする老いた男の挿話では、死はより“北野的”に配置されている。四季の変奏が時間の不可逆性を可視化し、身体が自然へ還元されることで、死は世界の輪郭に溶ける。
ここでは死が語られず、ただ置かれる。北野の得意とする、世界の静けさが死を包む運動がまだ機能しているのである。だが、衣装と音楽の過剰がその静けさを埋めてしまうと、死は風景に吸われる前に意味で固定され、観客の想像が動く余地を失う。若い二人の“凍える終幕”が美しいにもかかわらず、どこか説明的に感じられるのは、そのためだ。
過去作では死が関係の臨界として到来していた。暴力の回路から降りる最後の選択(『ソナチネ』)、尊厳の護持としての二人の退出(『HANA-BI』)、倫理の破綻の果てに訪れる沈黙(『その男、凶暴につき』)――そこには原因と結果の微細な糸が張られ、観客は沈黙の間にその糸を撫でながら“そうなるしかない”という納得へ至る。
対して『Dolls』の温井は、その糸が結ばれる前に断ち切られる。彼の死は、北野映画に固有だった余白→補完→必然という三段階の回路を経ない。だから唐突さが唐突さのまま残り、涙の誘導として視える。
もし彼の死が真に“文楽的”であろうとするなら、型の配置と間の呼吸――すなわち、彼と彼女の関係の“型”がもう一段、画面に編み込まれていなければならなかったのではないか。
『Dolls』はロマンチシズムの氾濫である。だが、その過剰な美は北野武の核にあった「空虚」や「沈黙」と噛み合わない。死は必然を失い、衣装や音楽は物語を凌駕し、寓話性は現実感の欠如へと転落した。
美しさが映画を救うのではない。むしろ美しすぎることによって、北野映画が持っていた「冷たさ」「虚無感」「残酷な静謐さ」が失われた。それが『Dolls』という作品を、彼のフィルモグラフィの中で最も異質で、最も議論を呼ぶ一本にしているのである。
- 製作年/2002年
- 製作国/日本
- 上映時間/113分
- 監督/北野武
- 脚本/北野武
- プロデューサー/森昌行、吉田多喜男
- アソシエイト・プロデューサー/川城和実、古川一博、石川博
- 撮影/柳島克己
- 音楽/久石譲
- 編集/北野武
- 衣装/山本耀司
- 美術/磯田典宏
- 菅野美穂
- 西島秀俊
- 三橋達也
- 深田恭子
- 武重勉
- 岸本加世子
- 津田寛治
- 大家由祐子
- 大杉漣