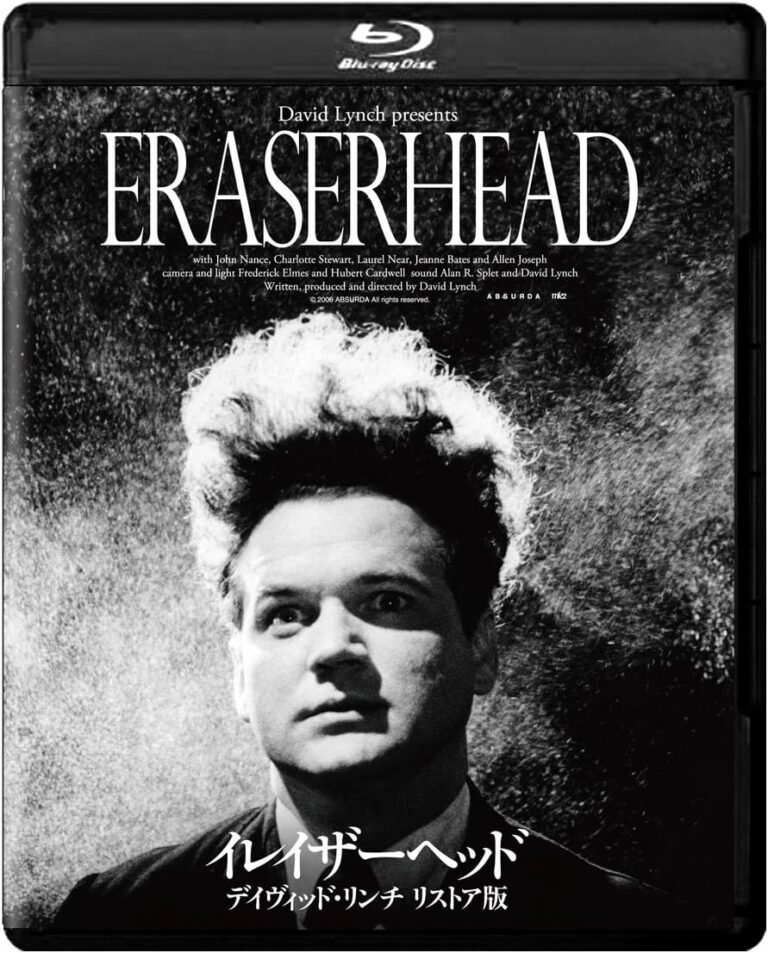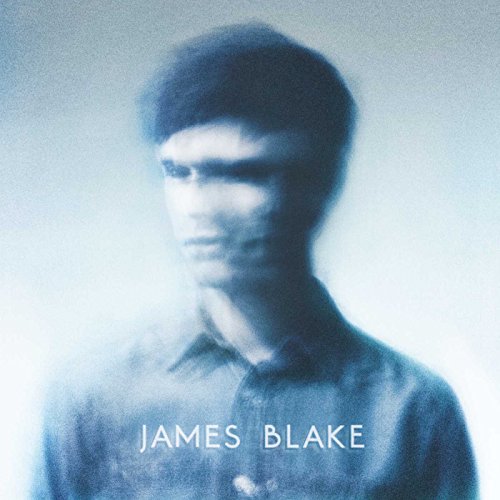『ウォーリー』(2008)
映画考察・解説・レビュー
『ウォーリー』(原題:WALL-E/2008年)は、ゴミの山と化した29世紀の地球を舞台に、孤独な清掃ロボットの淡い恋心と冒険を描いたアンドリュー・スタントン監督のSFファンタジーである。荒廃した世界でただひたすらに稼働し続ける彼の前に、探査ロボット・イヴが現れたことで、静寂に包まれていた運命が大きく動き出す。セリフを極力排したサイレント映画のような演出が、機械たちの無垢な感情と、消費社会への鋭い風刺を鮮烈に浮かび上がらせる。
宇宙的常識が生んだ、無音の30分
冬が終われば春が来るように、あるいは地球が24時間かけて自転するように、ピクサー・スタジオが常にハイレベルのアニメーションを供給し続けることは、もはや抗いようのない宇宙的常識である。
世界中からアニメIQの高い天才たちを選りすぐり、数年のスパンで確実にマスターピースを連発してくる、鉄板の安定感。観ているこっちのハードルが成層圏まで上がっていようとも、軽々と飛び越えてくる凄みすらある。
『ウォーリー』(2008年)もまた、その例に漏れない。いや、むしろ過去のピクサー・ワークスの中でも、その作家性と商業性のバランスにおいて、異常なまでの高水準を叩き出した怪物作と言っていいだろう。
舞台は29世紀の地球。緑は枯れ果て、かつての文明はただの「ゴミの山」として積み上げられた荒野と化している。『ブレードランナー』(1982年)を嚆矢に、『未来世紀ブラジル』(1985年)や『マッドマックス2』(1981年)で描かれたディストピアの系譜を、ファミリー映画の皮を被って堂々とやってのけているのだ。
主人公は、ゴミ処理ロボットのウォーリー。彼は700年間、たった一人(一台)でゴミを圧縮し続けている。見た目は完全に、映画『ショート・サーキット』(1986年)の「ナンバー・ファイブ」だ。
アンドリュー・スタントン監督は、冒頭の約30分間、ほとんど台詞のないサイレント映画として物語を構築することにこだわったという。
チャールズ・チャップリンやバスター・キートンの映画をスタッフ全員で研究し尽くし、「言葉」ではなく「動き」だけで感情を語るという、アニメーションの原点回帰を最先端のCGIでやってのけたのだ。
ウォーリーの唯一の楽しみが、ゴミの中から見つけたiPod(らしきもの)で、往年の傑作ミュージカル映画『ハロー・ドーリー!』(1969年)を鑑賞すること。
「日曜は晴れ着で(Put On Your Sunday Clothes)」の陽気なメロディが、死に絶えた地球に響き渡るあの哀切とユーモア。現在では絶滅危惧種となった「ミュージカル」と「サイレント」への深い敬意と愛が炸裂しており、映画ファンならこの冒頭だけで快哉を叫びたくなるはず。
スティーブ・ジョブズの遺伝子と音の魔術
ほのぼのとした日常を静的なトーンで描いた前半とは打って変わり、後半は人類が逃げ込んだ巨大宇宙船「アクシオム」艦内での、いかにもピクサーらしい縦横無尽なアクションが炸裂する。
この前半と後半の鮮やかなコントラストこそが、わずか97分という短い尺の中に、大河ドラマのような深みとジェットコースターのような快感をもたらしている仕掛けだ。
そして本作の最大の功績は、無機質で無感情なはずの金属の塊・ウォーリーを、人間以上に人間臭い、血肉の通ったキャラクターとして描き切った点にある。
双眼鏡のような目のレンズ、錆びついたボディ、キャタピラの足。表情筋など存在しないはずなのに、彼はレンズの角度とピントの合わせ方だけで、喜び、悲しみ、そして恋心を雄弁に語ってみせる。
しかも、ここには「音の魔術」が深く関わっている。ウォーリーの声を担当したのは、『スター・ウォーズ』(1977年)でライトセーバーの音やR2-D2のビープ音を創造した伝説のサウンド・デザイナー、ベン・バート。
彼は、あえてシンセサイザーによる電子音を使わず、モーターの回転音やバネの弾ける音といった「アナログな環境音」をサンプリングし、それを加工することでウォーリーの感情を表現した。R2-D2で培った「言葉を持たない機械に魂を吹き込む技術」が、ここで頂点に達しているのだ。
さらに見逃せないのが、ウォーリーが太陽光充電で再起動する際に鳴り響く音。うわ、Macintoshの起動音そのものじゃんか!当時、ピクサーの筆頭株主であったスティーブ・ジョブズへのリスペクト、あるいは遊び心が隠されているのは明白だろう。
さらに、ヒロインである最新鋭ロボット・イヴの、白くてツルツルした流線型のボディは、明らかに当時のApple製品(iPodやiMac)のデザインコードを反映している。
泥臭く錆びついたWindows(的な旧世代PC)としてのウォーリーと、洗練されたApple製品としてのイヴ。この「OSの違う二者」が恋に落ちるという構図こそが、テックギークたちの心をくすぐる究極のロマンスなのである。
「手をつなぐ」という神話、そして「完璧すぎて愛せない」という倒錯した本音
本作が最も大切に描こうとしているテーマ、それは「手と手をつなぐ」という、あまりにもシンプルで、だからこそ根源的な愛情表現だ。
言葉も通じず、出自も違う二つの存在が、最後に指を絡ませ合うショットの、なんと神々しいことか。細田守の傑作『サマーウォーズ』(2009年)でも「手をつなぐ」ことが物語の核心として描かれていたが、これはアニメ界におけるシンクロニシティー(共時性)なのか、あるいはデジタル化が進む世界に対するクリエイターたちの「身体性への渇望」なのか。
映画は、真正面からエコロジーを説教するのではなく、あくまで極上のエンターテインメントとしてストーリーテリングを全うしている。人類がテクノロジーに依存しすぎてブクブクに太った「肉塊」として描かれる強烈な皮肉や、善意に満ちた映画と見せかけてエンドクレジットに巨大企業「BNL(Buy n Large)」のロゴをインサートするブラックジョークの手つきも小面憎い。
だが、僕にはどうしても、ピクサー・アニメが「頭の良い連中が、たっぷりの時間と予算と計算機を使って作った、隙のない優等生の映画」に見えてしまう。「この映画のためなら、ウォーリーと一緒に宇宙の藻屑になってもいい!」というような狂信的な愛が芽生えないのだ。
見渡す限り計算し尽くされた完全性ゆえに、もしくはツッコミどころがなさすぎるがゆえに、偏愛の対象になり得ないのである。
僕が宮崎駿を偏愛してやまない理由は、作品のそこかしこに、彼自身でも封印しきれない狂ったビジョンが、歪みとして露呈しているから。ピクサーには「完璧な物語」はあるが、「作家の業(ごう)」のような汗臭い変態性が綺麗に消臭されている。
映画ってやつは、ある種の破綻や変態性がないと、本当の意味で心の柔らかい部分には突き刺さらないんじゃないだろうか。
- 監督/アンドリュー・スタントン
- 脚本/アンドリュー・スタントン、ジム・リアドン
- 製作/ジム・モリス
- 製作総指揮/ジョン・ラセター、ピート・ドクター
- 制作会社/ピクサー
- 原作/アンドリュー・スタントン、ピート・ドクター
- 撮影/ジェレミー・ラスキー、ダニエル・フェインバーグ
- 音楽/トーマス・ニューマン
- 編集/スティーヴン・シェイファー
- 美術監督/ラルフ・エグルストン
- 音響監督/ベン・バート
- ウォーリー(2008年/アメリカ)
![ウォーリー/アンドリュー・スタントン[DVD]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/71oeELBOsL._AC_SL1000_-e1759751076976.jpg)
![未来世紀ブラジル/テリー・ギリアム[DVD]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/81GEhNBB5L._AC_SL1259_-e1758988925287.jpg)
![サマーウォーズ/細田守[DVD]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/81Iv902lW8L._AC_SL1461_-e1759034786603.jpg)