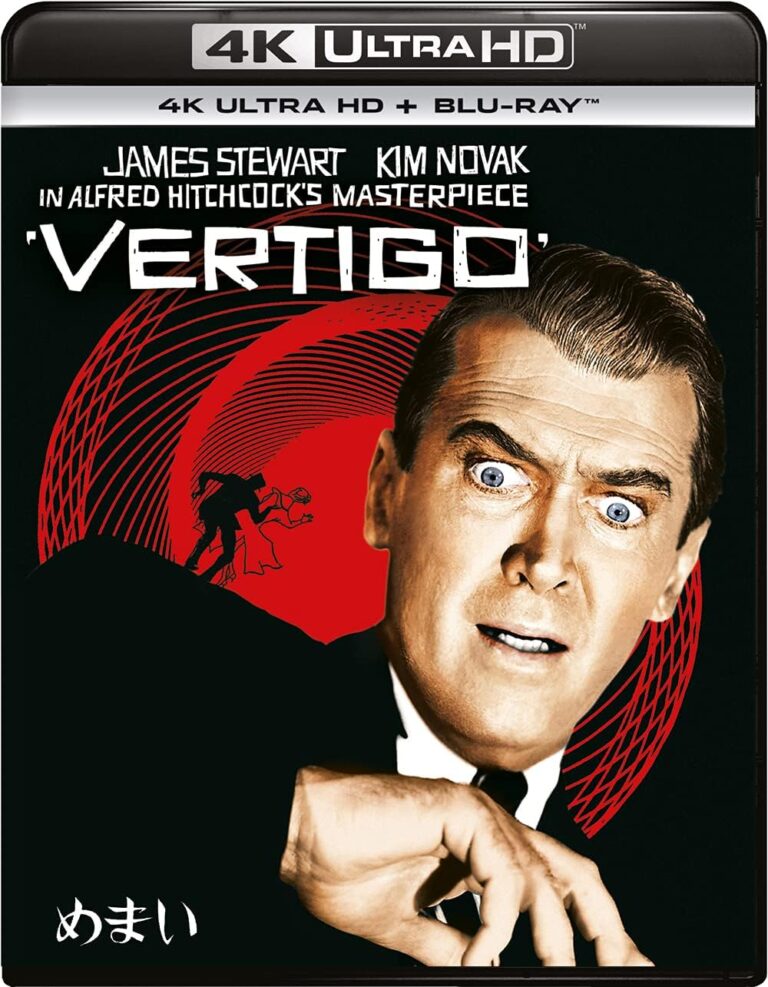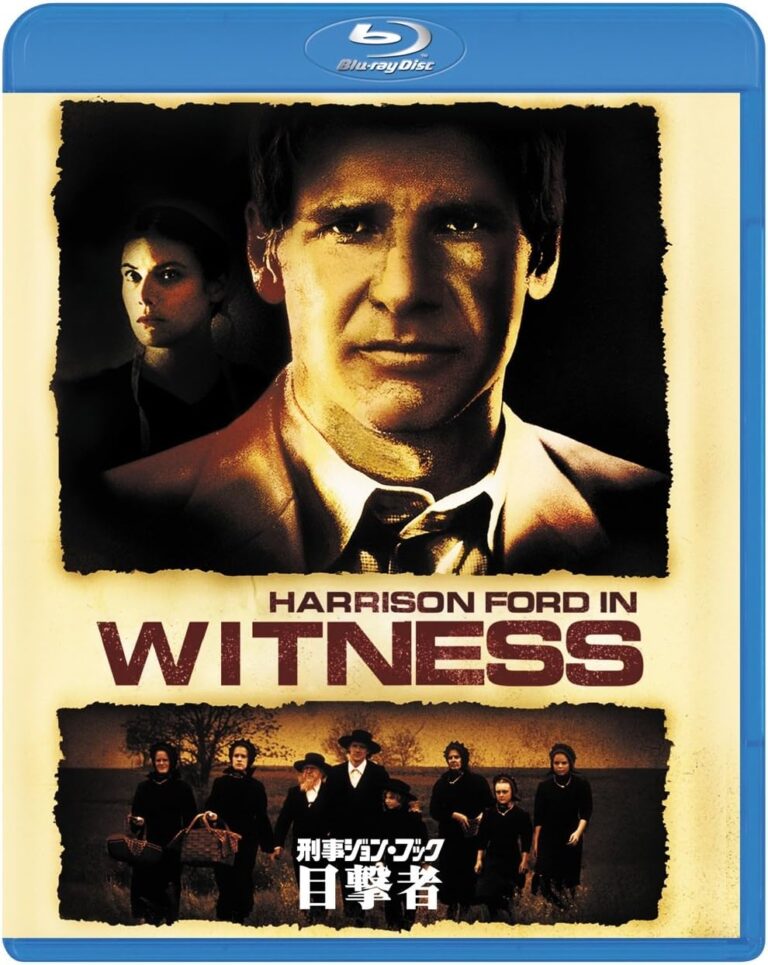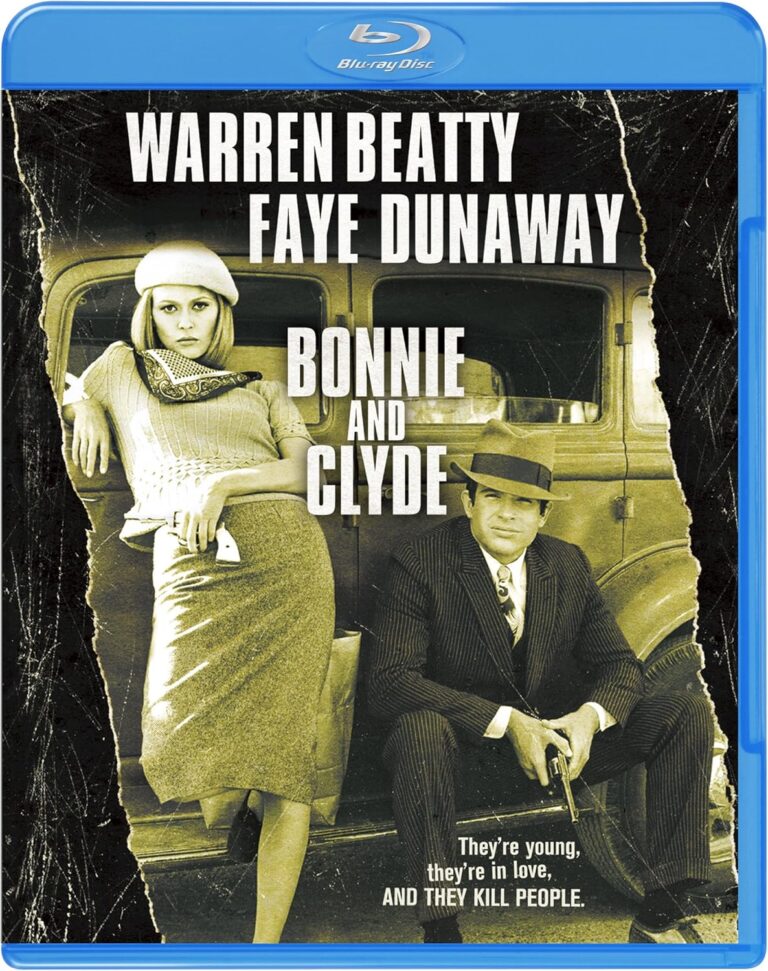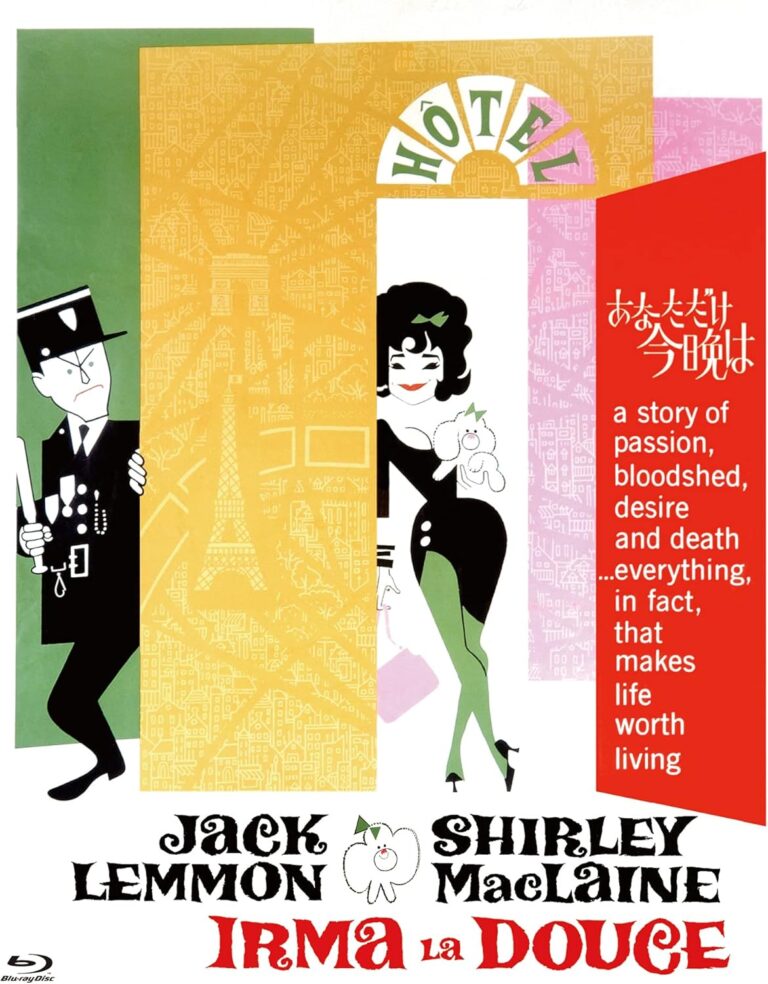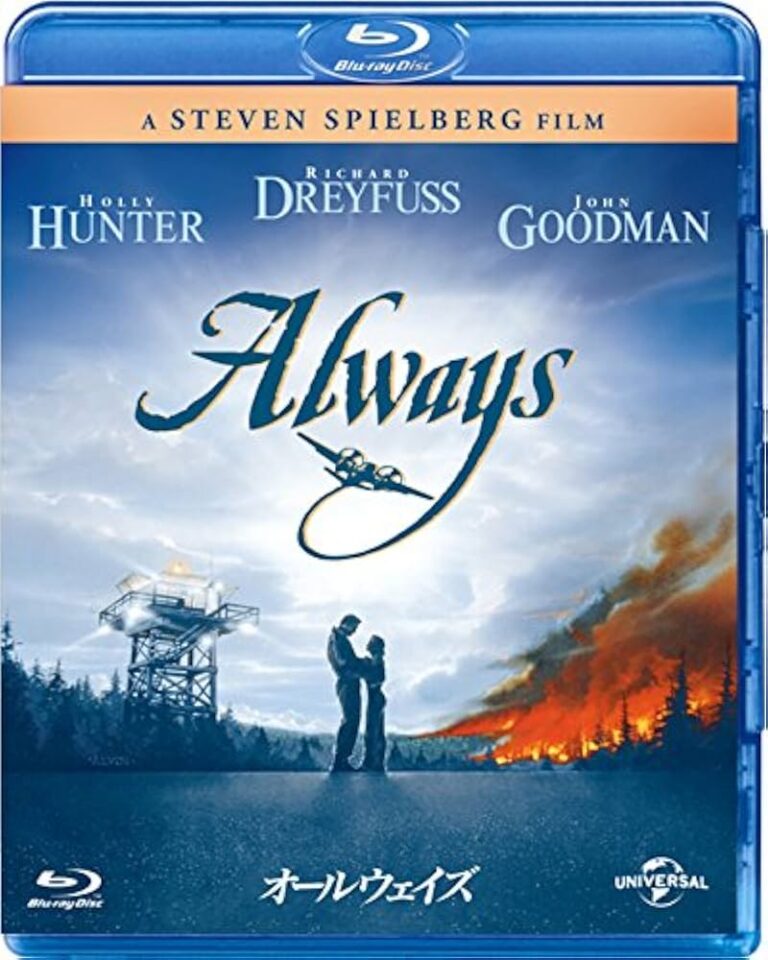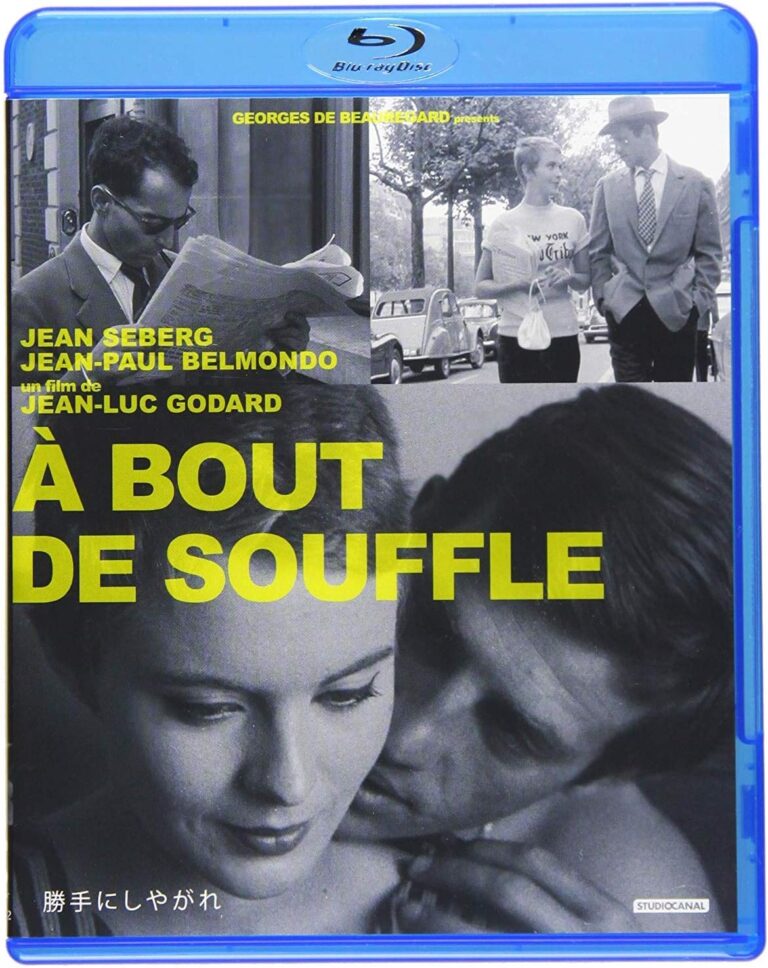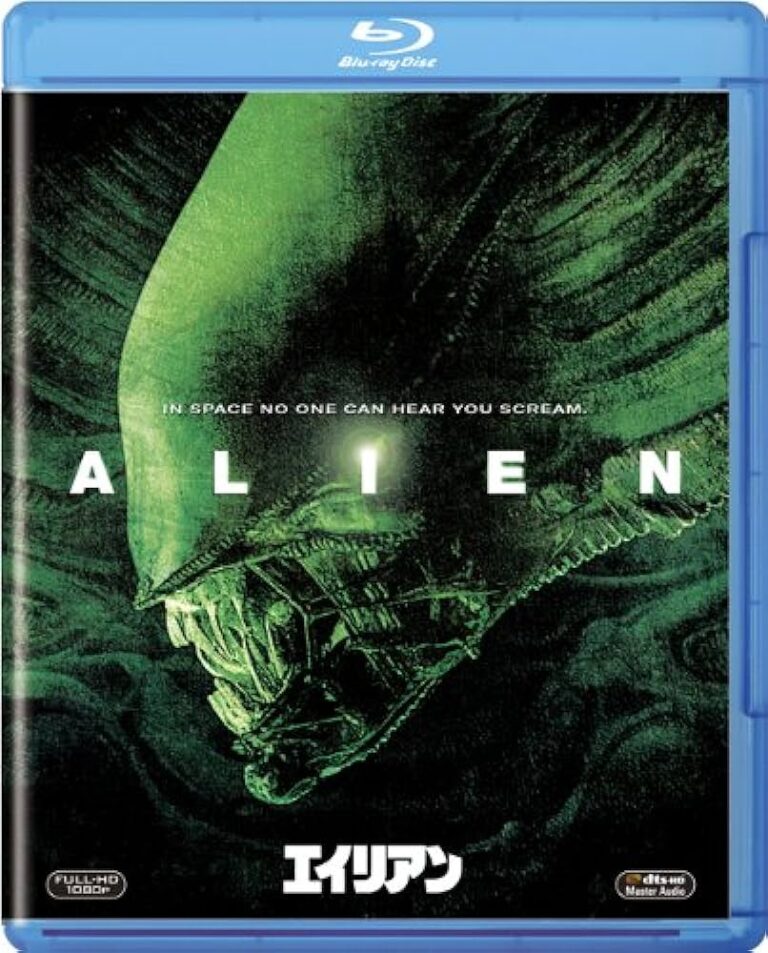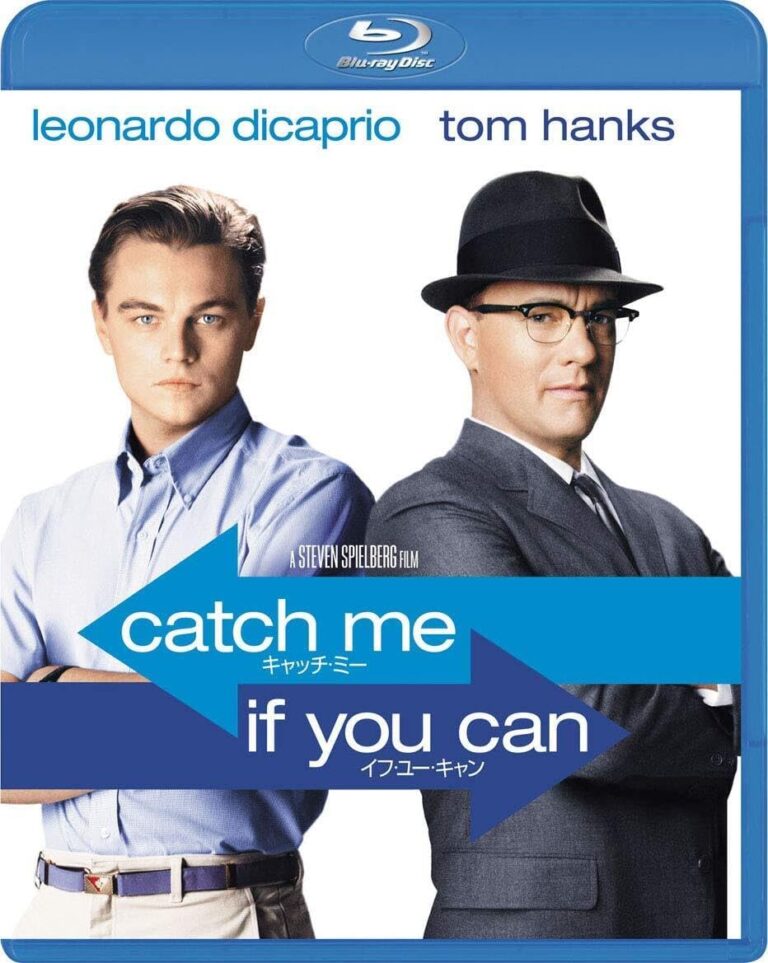『ウィンブルドン』(2004)
映画考察・解説・レビュー
映画『ウィンブルドン』(2004年)は、恋とテニスを通して再び“生きる身体”を取り戻す男の物語。落ち目のベテラン選手ピーター(ポール・ベタニー)が、若手スターのリジー(キルステン・ダンスト)と恋に落ち、失われた情熱を取り戻していく。ワーキング・タイトル印の知的ユーモアと英国的リアリズムが融合した、成熟のロマンティック・スポーツ映画。
恋という名のドーピング、CGIという名の魔球
テニスにおいてラブ(Love)とは0点のこと。つまり、テニスとは愛が無価値とされる残酷なスポーツである。
だが、映画『ウィンブルドン』(2004年)は、その定義に真っ向から喧嘩を売る。これは、31歳・世界ランキング119位、引退目前の崖っぷち英国男が、生意気なアメリカ娘とのセックスと恋をガソリンにして、物理法則を無視した快進撃を続ける「中年男のファンタジー」であり、同時に映画史上最も高度なテクノロジーが駆使された「SFテニス映画」なのだ。
実は、劇中のラリーシーンにおいて、ボールは一球たりとも打たれていない。 そう、あの高速サーブも、ネット際のボレーも、全てCGなのだ。俳優はプロではないから、どんなに練習しても、時速200キロのサーブを正確なコースに打ち込み、それをラリーとして続けることなど不可能。
そこで監督のリチャード・ロンクレインは、狂気じみた決断を下した。「ボールは後で足す。お前らはパントマイムで演じろ」。だが、動き自体は本物でなければならない。そこで招聘されたのが、1987年のウィンブルドン覇者、パット・キャッシュである。
彼はポール・ベタニーを徹底的にしごき抜いた。朝から晩までコートを走り回らせ、プロのフォーム、筋肉の動き、疲労した時の呼吸法までを叩き込んだ。ベタニーはボールのない空間に向かって、あたかもそこにボールがあるかのようにフルスイングを繰り返したのだ。
これは『スター・ウォーズ』でライトセーバーを振り回すジェダイの演技に近い。見えない敵(ボール)と戦うポール・ベタニー。その姿には、彼が『ダ・ヴィンチ・コード』のシラス役で見せたような、ある種の狂信的な集中力が宿っている。
VFXチームは、そのスイングに合わせて物理演算されたボールを合成。カメラがボールの軌道を追い、インパクトの瞬間にズームする…そんな、現実の中継では不可能なアングルが可能となった。これは、デジタル技術が肉体の躍動を補完した、最初のスポーツ映画の金字塔なのだ。
階級闘争としてのラブゲーム
本作を製作したのは、英国の至宝ワーキング・タイトル・フィルムズ。『ノッティングヒルの恋人』や『ラブ・アクチュアリー』で知られるロマコメ工場だ。彼らの十八番は「イケてない英国男」を描くことにある。
主人公ピーター(ポール・ベタニー)は、典型的なアッパーミドルクラスの出身だが、闘争心に欠ける。「勝てなくてもいいや」「怪我せず終わりたい」──このブリティッシュ・ペシミズムこそが彼の病理だ。
彼は、かつてのナブラチロワのような勝利への執念を持たない。テニスを紳士の嗜みとして捉え、泥臭い勝利よりも品行方正な敗北を選ぶ。
そこに現れるのが、キルステン・ダンスト演じるリジー・ブラッドベリーだ。 彼女はアメリカ人であり、勝利至上主義の塊。審判に文句を言い、父親(サム・ニール!)と喧嘩し、欲しいものは男でもタイトルでも強引に奪い取る。
この対比が最高に面白い。ピーターにとって彼女は、単なる恋人ではない。彼が失ってしまった(あるいは最初から持っていなかった)、野蛮な生命力の象徴。二人の恋愛は、静かな英国庭園にブルドーザーが突っ込むようなものなのである。
リジーとの情事の翌日、ピーターのサーブ速度が上がるシーンがある。これは愛の力なんて生易しいものではない。性的なエネルギーの解放が、そのまま競技能力の向上に直結しているのだ。
抑圧された英国紳士が、アメリカ的な欲望の肯定を受け入れることで、野生を取り戻す。つまりこれは、テニスウェアを着た『野生の呼び声』なのだ!
キルステン・ダンストのキャスティングも見事。彼女は決して守ってあげたいヒロインではない。ふてぶてしく、顎を上げ、相手を見下ろす。その可愛げのない可愛さこそが、ピーターのMっ気のある闘争心に火をつける。彼女はミューズ(女神)ではなく、トレーナーなのだ。
All England Clubが許した“本物”の空気
この映画のもう一人の主役。それがウィンブルドンだ。通常、この厳格なクラブは映画撮影に許可を出さない。だが、本作は奇跡的に、実際の大会期間中を含めた撮影許可を得た。観客席を埋め尽くすエキストラの一部は本物のテニスファンであり、通路ですれ違う選手たちも本物だ。
特にセンターコートの静寂は、セットでは再現不可能な重圧を漂わせている。芝生の匂い、曇天のロンドンの光、そしてポイントが決まった瞬間の、あの独特な拍手の音。
監督のリチャード・ロンクレインは、この聖地の空気をドキュメンタリーのように切り取った。CGのボールという嘘を成立させるために、背景となる場所は徹底して本物である必要があったからだ。
映画の後半、ピーターは満身創痍で決勝戦を戦う。相手は若く、強く、速い。ピーターにあるのは経験と、観客の判官贔屓(アンダードッグへの応援)だけだ。
しかしピーターは、リジーとの出会いを通じて、技術を超えた「魂の持続力」を体得する。老いとは肉体の衰えではない。「もう無理だ」と心が決めた瞬間に訪れるものだ。彼がライン際ぎりぎりにボールを落とすこととは、彼が自分の人生の境界線(ライン)を、自らの意志で書き換えた瞬間なのである。
この映画は教えてくれる。人生の第2セットは、いつからだって始められるし、サービス権さえ持っていれば、まだ逆転のチャンスはあるのだと。と言う訳で、僕のようなやる気のない中年男性のは必見作かと。
- 監督/リチャード・ロンクレイン
- 脚本/アダム・ブルックス、ジェニファー・フラケット、マーク・レヴィン
- 製作/ライザ・チェイシン、エリック・フェルナー、メアリー・リチャーズ
- 製作総指揮/ティム・ビーヴァン、デブラ・ヘイワード、デヴィッド・リヴィングストン
- 撮影/ダリウス・コンジ
- 音楽/エドワード・シェアマー
- 編集/ハンフリー・ディクソン
- 衣装/ルイーズ・スチャンスワード
- ウィンブルドン(2004年/イギリス)
![ウィンブルドン/リチャード・ロンクレイン[DVD]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/61TkuuFAIJL._AC_SL1024_-e1759134135248.jpg)