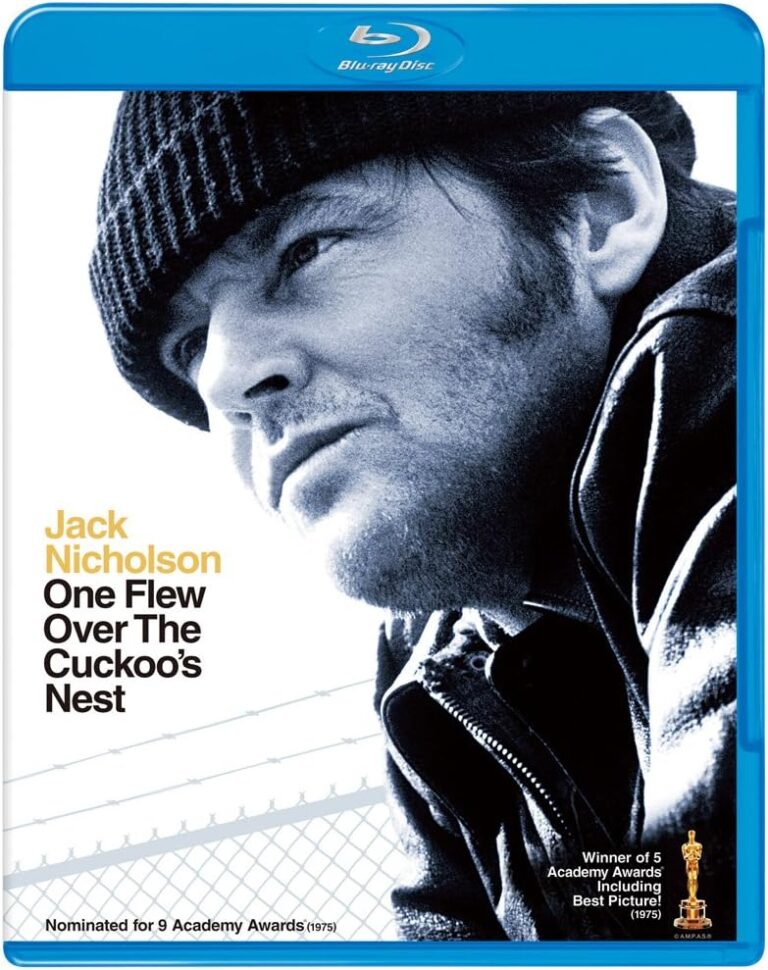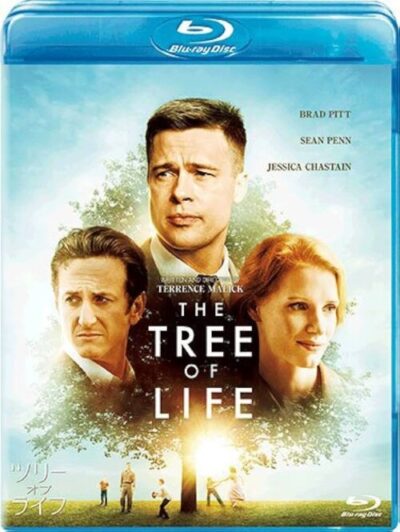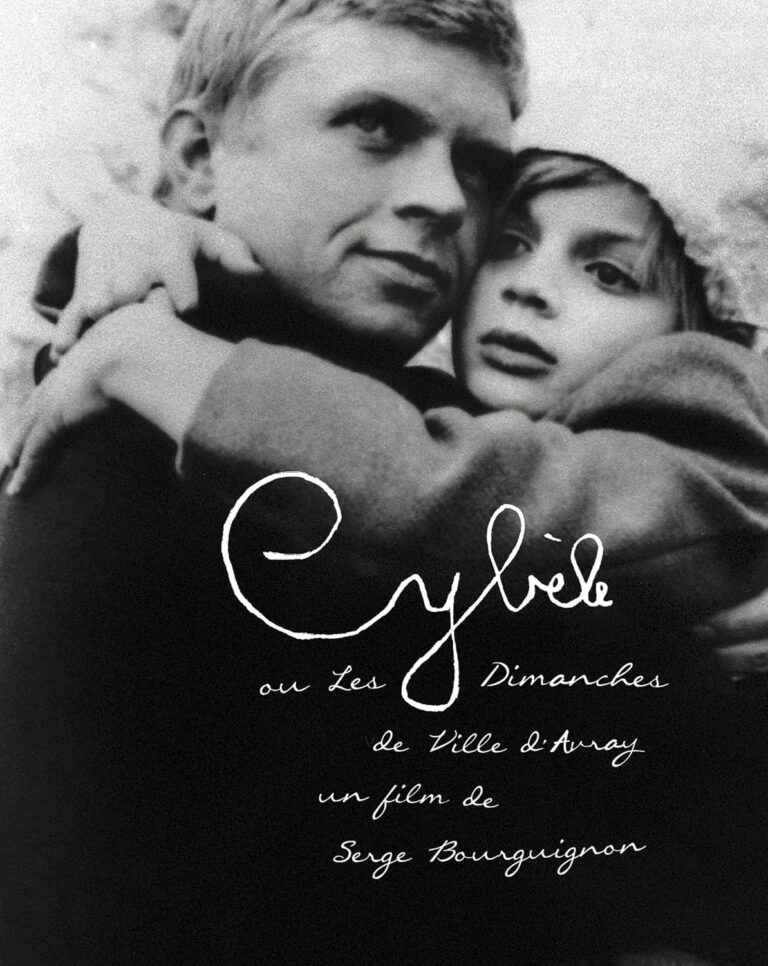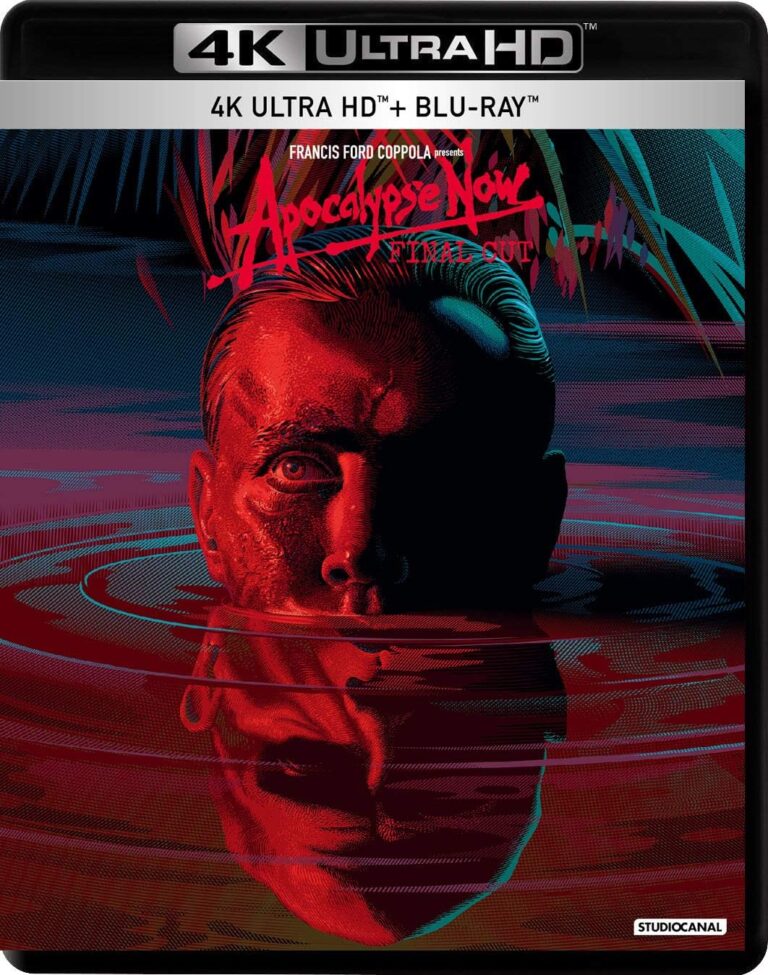『アマデウス』(1984)
映画考察・解説・レビュー
『アマデウス』(原題:Amadeus/1984年)は、神に選ばれなかった作曲家アントニオ・サリエリの視点から、モーツァルトの天才とその残酷さを描く物語である。老境に差し掛かったサリエリは、かつて宮廷で目撃した若きモーツァルトの奔放な才能と、その裏に潜む孤独や焦燥を回想していく。ウィーン宮廷の煌びやかな音楽文化の中で、才能によって運命を狂わされた二人の作曲家が、信仰・嫉妬・敬愛の狭間で揺れ動き、やがて取り返しのつかない衝突へと向かっていく。
理解できてしまうという無間地獄
『アマデウス』(1984年)は、決して天才モーツァルトの数奇な生涯を描いた感動の伝記映画じゃない。
ピーター・シェーファーの戯曲をミロス・フォアマンが映像化した本作は、才能という名の暴力によって一人の真面目な秀才が精神崩壊していく様を克明に記録した、映画史上最も残酷な「音楽的NTR(寝取られ)ホラー」である。
主人公は、ウィーン宮廷のトップに君臨していた秀才宮廷作曲家、アントニオ・サリエリ(F・マーリー・エイブラハム)。彼は敬虔なカトリックであり、「禁欲と努力をもって神に奉仕すれば、必ず報われる」という信仰のもと、血を吐くような努力でその地位を築き上げた。
しかし、神は残酷だ。サリエリの祈りに対する神のアンサーとしてウィーンに送り込まれたのは、下品なウンコ・チンチン・ジョークを大声でわめき散らし、女の尻を追いかけ回す、ピンク色のカツラを被った軽薄なクソガキ、ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト(トム・ハルス)だったのだ!
「なぜ、神はあんな下品な猿を選んだ? なぜ、禁欲的に祈り続けた俺ではなく、あいつの口を借りて『神の声』を響かせるのだ?」 この神学的なバグ、理不尽極まりない宇宙の不条理に直面したとき、サリエリの信仰は音を立てて崩落する。だが、この映画が真にエグいのはここからだ。
サリエリの最大の悲劇は、彼が凡人ではなく、モーツァルトの天才性を、世界で最も正確に理解できてしまう超一流の鑑賞眼(耳)を持っていたことにある。
複雑な対位法、劇的構造を自然に推進するアンサンブル、予想を裏切りながら完璧な調和を見せる転調。凡庸な貴族たちが「音符が多すぎる」と的外れな批判をする中、サリエリだけは、その音楽が書き直しの一切ない、神の完璧な口述筆記であることを一瞬で見抜いてしまう。
理解できる知性があるからこそ、己の絶対的な限界と敗北を骨の髄まで思い知らされる。才能がないことよりも、才能がないことを自覚できる鋭敏なセンサーを持ってしまったことこそが、サリエリを狂気へとドライブさせる地獄の釜の蓋なのだ。
楽譜というポルノグラフィ
本作が単なる嫉妬劇の枠を超え、普遍的な人間ドラマへと跳躍しているのは、俳優陣による身体表現の異常な強度に他ならない。特に、サリエリ役のF・マーリー・エイブラハム(本作でアカデミー主演男優賞を受賞)の演技は、もはや神憑りである。
妻コンスタンツェが持ち込んだモーツァルトの直筆スコアを、サリエリが立ち読みするシーン。インクの染み一つ、修正の跡一つないその楽譜から、頭の中に完璧なオーケストレーションが鳴り響く。
サリエリは、まるで極上のポルノグラフィを見せつけられたかのように恍惚の表情を浮かべ、直後にあまりの絶望から、その楽譜を床にポロリと落としてしまう。
嫉妬、驚愕、絶望、そして抗いがたい美への陶酔。 矛盾する感情が同時にスパークし、理性のヒューズが飛ぶ瞬間を、彼は「顔面の筋肉の微細な痙攣」だけで表現しきった。
対するモーツァルト役のトム・ハルスも凄い。あの神経を逆撫でする「ケラケラケラ!」という甲高い笑い声で観客をイラつかせながら、いざピアノの前に座ると重力が変わる。
撮影前に数百時間の猛特訓を積んだ彼の指先は、弾いているフリではなく、音楽が内側から爆発して漏れ出ているようにしか見えない。 この「日常の圧倒的軽薄さ」と「創造時の神聖さ」の落差が、サリエリの殺意(=神への復讐心)を決定的なものにしていくのだ。
2002年に公開された『ディレクターズ・カット版』には、「コンスタンツェへの肉体要求シーン」が追加されている。夫の就職斡旋を頼みに来たコンスタンツェに対し、サリエリは無言で「身体を差し出せ」と要求する。
彼女が屈辱に耐えながら服を脱ぎ、乳房を露わにした瞬間、サリエリは冷酷にベルを鳴らし、メイドを呼んで彼女を追い出す。一見、サリエリが優位に立った加虐的なシーンに見える。
だがこれは、サリエリの、人間としての尊厳の完全なる自己破壊だ。神の愛を受けたモーツァルトに対する無力感が、こんな卑劣な八つ当たりでしか自我を保てない所まで彼を堕落させたのだ。
音楽家として敗北し、信仰者として敗北し、最後は人間としても底辺へ落ちる。この底なしの残酷さこそが、ミロス・フォアマン監督の真骨頂である。
凡庸なる我らの守護聖人──ミロス・フォアマンの冷徹なる視線
なぜ、この虚構の物語がこれほどの圧倒的なリアリティと血肉を持っているのか? それは、監督ミロス・フォアマン自身の壮絶な人生がバックボーンにあるからだ。
彼はチェコ出身であり、両親をナチスの強制収容所で殺され、自身はソ連の共産党独裁体制下(プラハの春の弾圧)からアメリカへ亡命した人物である。
フォアマンの人生には、常に「個人の努力では絶対に覆せない、理不尽で巨大な力(=全体主義、あるいは神)」が存在した。サリエリが抱く「神に選ばれなかった理不尽な痛み」の背後には、フォアマン自身が味わった血の滲むような絶望が二重写しになっているのだ。
おまけに本作のロケ地は、当時まだ鉄のカーテンの向こう側だった共産圏のプラハである。秘密警察(KGB)の監視下で、18世紀のウィーンを自然光と蝋燭の光だけで完全再現した執念。そのヒリヒリとした現場の緊張感が、フィルムの全フレームに焼き付いている。
映画のラスト。精神病院の車椅子に乗せられた老サリエリは、廊下にひしめく狂人たちに向かって十字を切る。「私は凡庸なる者たちの神だ。世界中の凡庸なる者たちよ、私が罪を赦してやろう」。
そう、モーツァルトになれる人間など、この世界に一握りもいない。僕たちは皆、サリエリなのだから。
- 監督/ミロス・フォアマン
- 脚本/ピーター・シェーファー
- 製作/ソウル・ゼインツ、マイケル・ハウスマン、バーティル・オールソン
- 撮影/ミロスラフ・オンドリツェク
- 音楽/ネヴィル・マリナー
- 編集/ネーナ・デーンヴィック
- 美術/カレル・サーニー
![アマデウス/ミロシュ・フォアマン[DVD]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/91bJyDncnL._AC_SL1500_-e1759986061743.jpg)