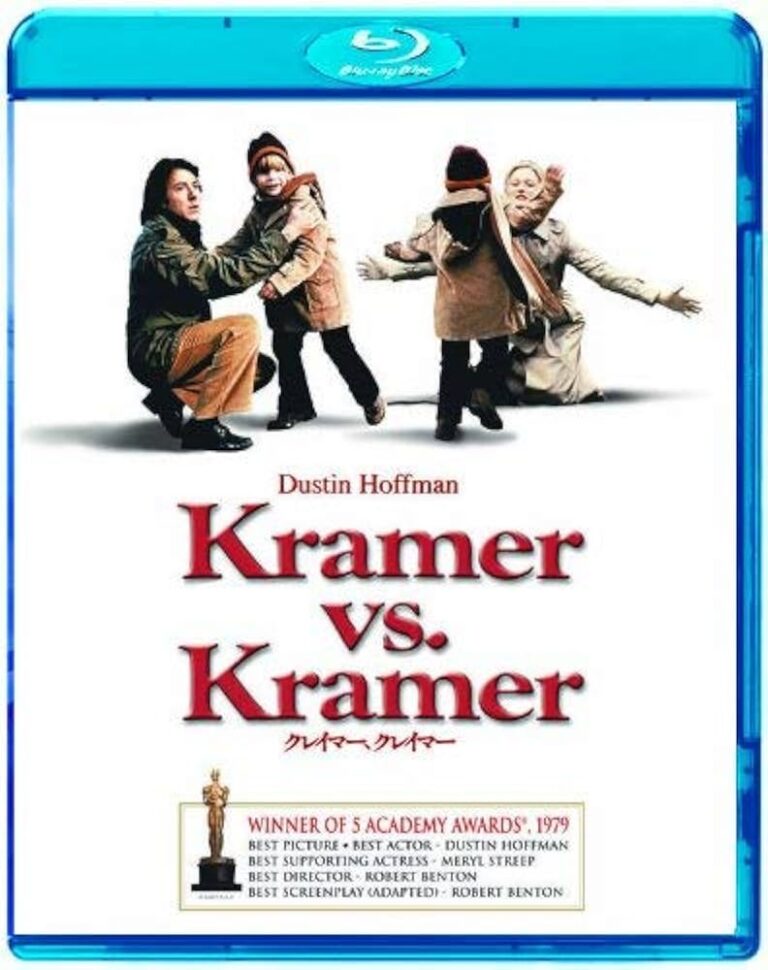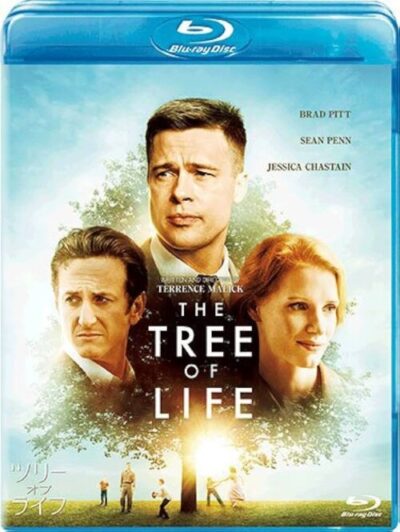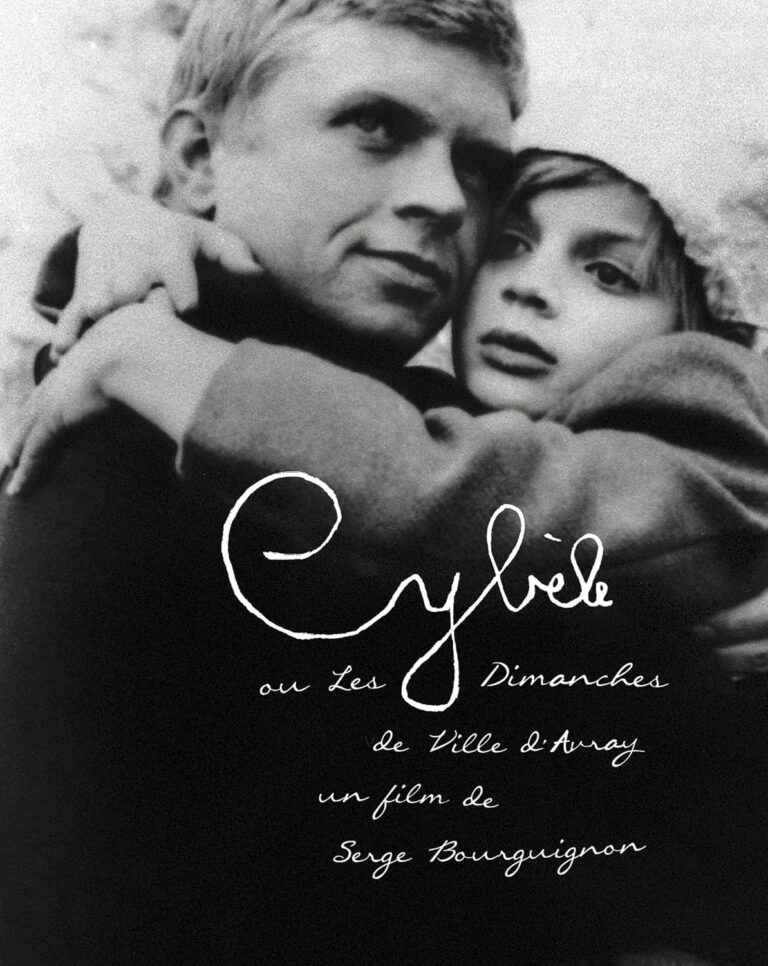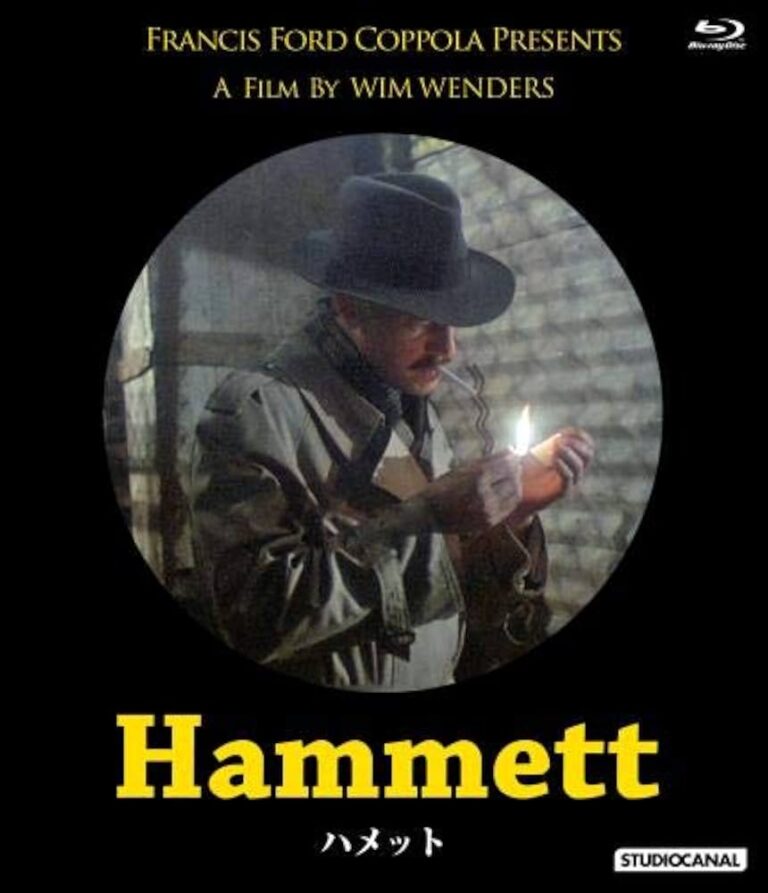【ネタバレ】『白いカラス』(2003)
映画考察・解説・レビュー
『白いカラス』(原題:The Human Stain/2003年)は、フィリップ・ロスの同名小説を原作に、ロバート・ベントン監督が映画化した人間ドラマ。1990年代のアメリカ東部を舞台に、名門大学の教授コールマン・シルク(アンソニー・ホプキンス)が、授業中の発言をめぐる差別問題で職を失う。孤立した彼は、清掃員の女性フォーニア(ニコール・キッドマン)と出会い、秘密を抱えたまま関係を深めていく。人種・階級・名誉をめぐるアメリカ社会の構造を背景に、人間の内面に潜む“隠された顔”を描く。
観客を迷子にする語りの不在
小説であれ映画であれ、物語に「私」という一人称の語り手が登場した瞬間、我々観客はその視点に導かれ、安心しきって物語の世界へと足を踏み入れる。物語を強固に統べるのは語り手の主観であり、そこに一貫性が保たれている限り、観客は迷うことなくその迷宮を歩くことができるのだ。
だが、途中でその一人称がフッと消滅し、何の断りもなく三人称へとすり替わったとしたらどうだろう?観客は完全に方向感覚を失い、語りの重心が消え去った瞬間、物語の中心そのものがガラガラと音を立てて瓦解してしまう。
もちろん、ウィリアム・フォークナーの文学のように、あえて語りをズラすことで多層的な真実を浮かび上がらせる、アクロバティックで意図的な成功例も存在する。
しかし、そこには緻密な計算と明確な演出意識が不可欠。1ミリでも軸がぶれれば、それは単なる作者の混乱としてスクリーンに垂れ流されることになる。『白いカラス』(2003年)は、まさにその最悪の罠に両足から突っ込んでしまった映画だ。
本作は、ピュリッツァー賞作家フィリップ・ロスの小説を、『クレイマー、クレイマー』(1979年)で人間ドラマの名手として名を馳せたロバート・ベントンが映画化した作品。
映画は、ゲイリー・シニーズ演じる作家ネイサンのモノローグで静かに幕を開ける。観客は当然、この物語は彼の語りによってナビゲートされるのだなと思い込む。
だが、次第に彼は物語の中心からフェードアウトし、視点はアンソニー・ホプキンス演じる元大学教授コールマン・シルクへとヌルリと移行する。
さらに中盤からは、ニコール・キッドマンやエド・ハリスらが担う三人称的エピソードが無秩序に挿入され、物語の焦点は四方八方に完全分散。すっかり忘れた終盤になって、ネイサンの視点が復帰してくるのだ。
いやもう、訳がわからん。文学的な多視点を映画的に翻訳したつもりかもしれないが、実際には視点の切り替えに明確な必然性がなく、少なくとも僕は混乱しっぱなしでした。
テーマの大渋滞と、過去と現在の致命的な断絶
さらにこの映画は、2時間に満たない短い尺の中に「黒人差別」「自己同一性の偽装」「幼児虐待」「ベトナム帰還兵のPTSD」という、一つ一つが単独で映画になるレベルの激重テーマを同時に抱え込もうとして自滅している。
アンソニー・ホプキンス演じる老齢のコールマンと、ウェントワース・ミラー演じる青年時代のコールマン。時制が複雑に絡み合い、現在と過去が交錯し、語り手が消え、視点が漂う。結果として、すべての主題が多重露光のように中途半端に重なり合い、どの層にもピントが合わないという大惨事を引き起こしているのだ。
特に致命的な問題は、物語の絶対的な核であるはずの「黒人差別」と「自己同一性の偽装」が、この無駄に複雑な構造の中に完全に埋没してしまっていること。
コールマンが白人社会に同化するために、自らの黒人としてのルーツと家族を捨てて生きてきたという、血を吐くような悲劇的真実。それが語りの不安定さのせいで、観客の感情を揺さぶるまでに至らない。
若き日のコールマンの苦悩を演じ切ったウェントワース・ミラーのパフォーマンスは、文句なしに素晴らしい。本来なら、そこにこそ映画の核心と熱量があったはず。
だが、現在パートとの接続がプツリと断たれ、彼の過去はただの孤立したフラッシュバックとして宙を漂っている。物語の太い本流がどこにあるのか判然とせず、観客は出口のない語りの迷宮に置き去りにされてしまうのである。
「語ること」を放棄した映画の末路
なぜこんなことになってしまったのか?その最大の要因は、ロバート・ベントン監督とニコラス・メイヤー脚本という、水と油の絶望的なミスマッチにある。
ベントンはもともと、限られた人物の心理を精緻に、そして親密に描くことに長けた監督で、複数の視点が交錯する複雑な群像劇には絶望的に不向きな作家だ。
彼の演出は常に人物の内面に優しく寄り添おうとするが、この映画ではメイヤーが構築した語りの構造そのものが、人物の内面を破壊してしまっているのだ。
脚本を担当したニコラス・メイヤーは、『スター・トレック』シリーズ(第2作、第6作など)の監督・脚本で知られる人物。彼のフィルモグラフィーを見れば明らかなように、彼は物語の倫理的・哲学的な深みよりも、構造的ギミックやプロットの仕掛けに関心を寄せるタイプの作家だ。
だが、この『白いカラス』という題材に必要だったのは、ギミックではなく、人間の業を抉り出す倫理の物語としての圧倒的な深度だったはず。
黒人であることを隠して白人として生きるという、存在の二重性。それを描くには、小手先の構造操作よりも魂の切実さが必要だった。しかしメイヤーの脚本は構造をこねくり回すことに夢中になり、登場人物たちをただのパズルのピースとして消費してしまう。結果、ロス文学の根底に流れる強烈なアイロニーや人間的な苦味が、すべて形式のノイズの中に吸い込まれて消滅してしまった。
『白いカラス(The Human Stain)』というタイトルには、社会の異端であることへの誇りと、拭い去れない人間の「染み(Stain)」の意味が込められている。
黒人でありながら白人として生きるコールマンの二重性は、アメリカ社会の差別構造そのものを強烈に照射する巨大な寓話になり得た。しかしこの映画は、その倫理的重みを語りの迷走によって、自ら手放してしまった。
作家ネイサンは、語り手として登場しておきながら、途中でその語る意志を無責任に放棄する。彼は観察者にも当事者にもなりきれず、物語の外縁をフワフワと漂う幽霊のような存在へと退化していく。その構図こそが、この映画が抱える根源的な欠陥の象徴なのだ。
多重視点を採用するならば、各視点の間に生まれる激しい倫理的摩擦こそがドラマの推進力になるべきだった。だがこの映画は、複数の語りをただ無機質に並列に配置しただけで、その交差点での衝突を描くことから逃げている。
かえすがえすも、残念な映画です。
- 監督/ロバート・ベントン
- 脚本/ニコラス・メイヤー
- 製作/トム・ローゼンバーグ、ゲイリー・ルチェッシ、スコット・スタインドーフ
- 製作総指揮/ロン・ボズマン、アンドレ・ラマル
- 制作会社/ミラマックス、レイクショア・エンターテインメント
- 原作/フィリップ・ロス
- 撮影/ジャン・イヴ・エスコフィエ
- 音楽/レイチェル・ポートマン
- 編集/クリストファー・テレフセン
- 美術/デヴィッド・グロップマン
- 衣装/リタ・ライアック
- クレイマー、クレイマー(1979年/アメリカ)
- 白いカラス(2003年/アメリカ)
![白いカラス/ロバート・ベントン[DVD]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/71M39SzjQWL._AC_UL640_FMwebp_QL65_-e1761012645896.webp)