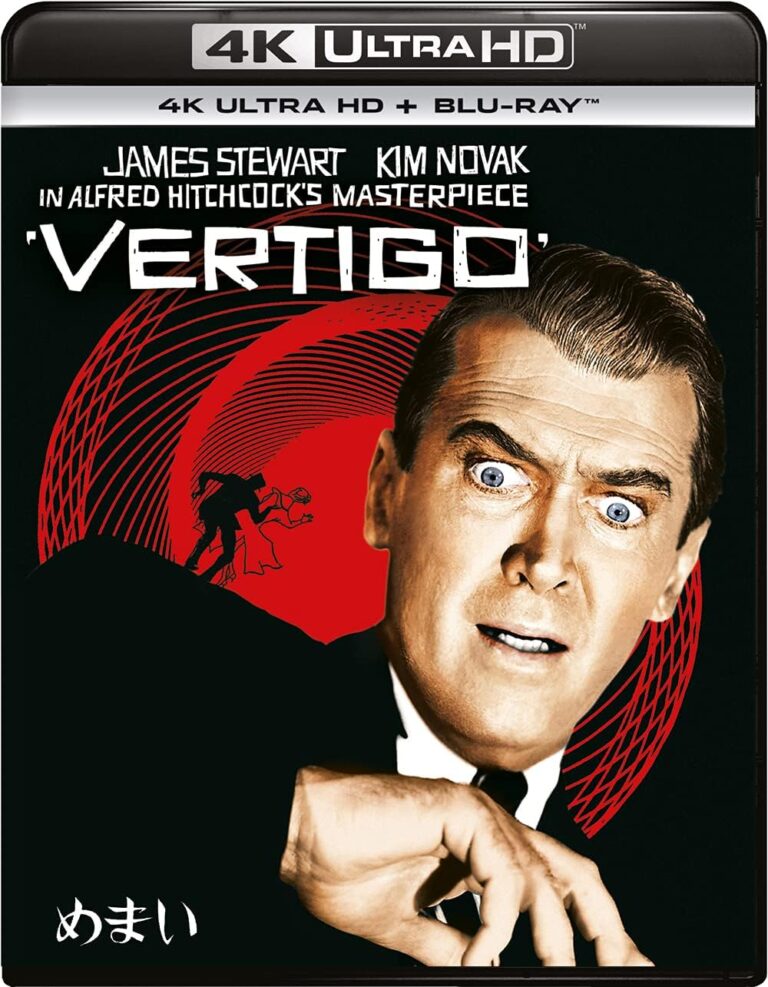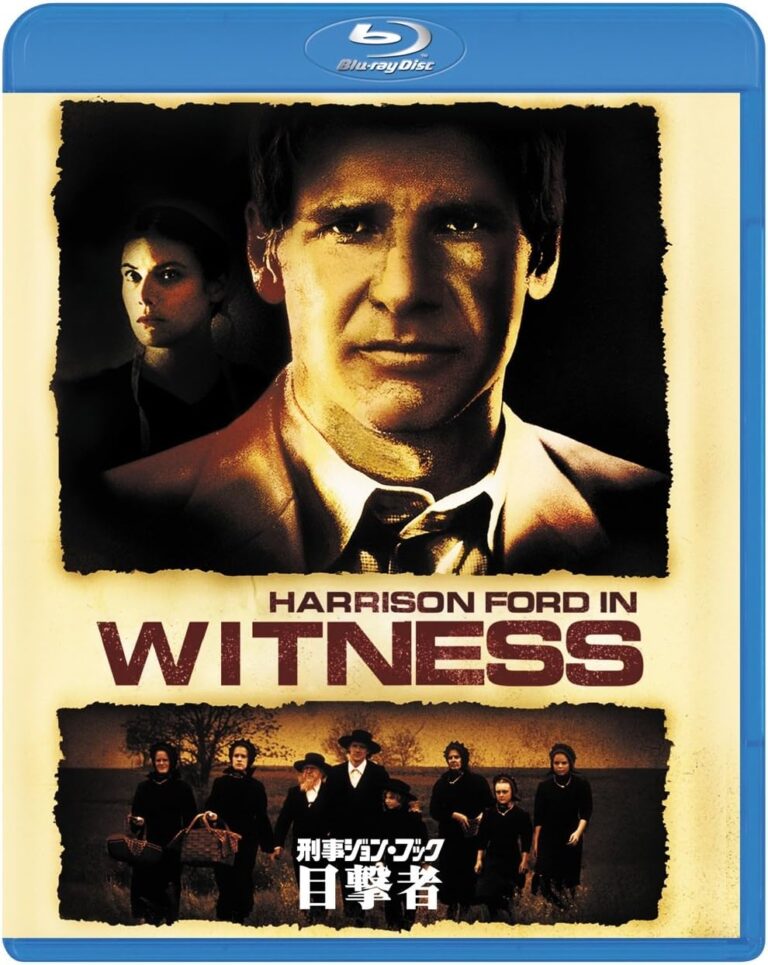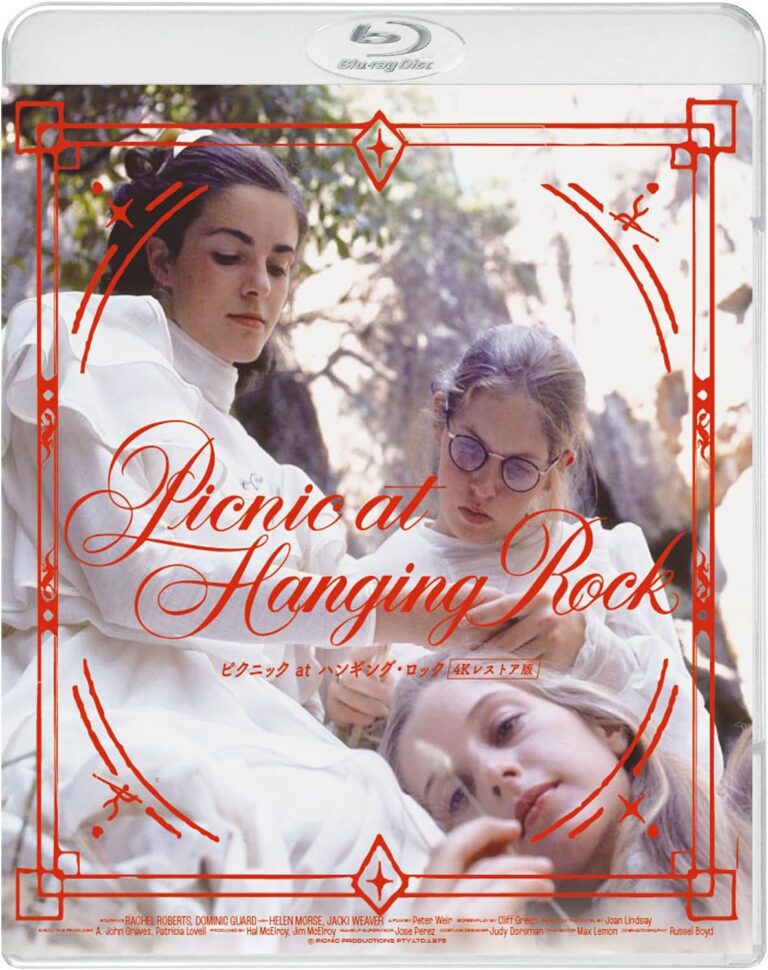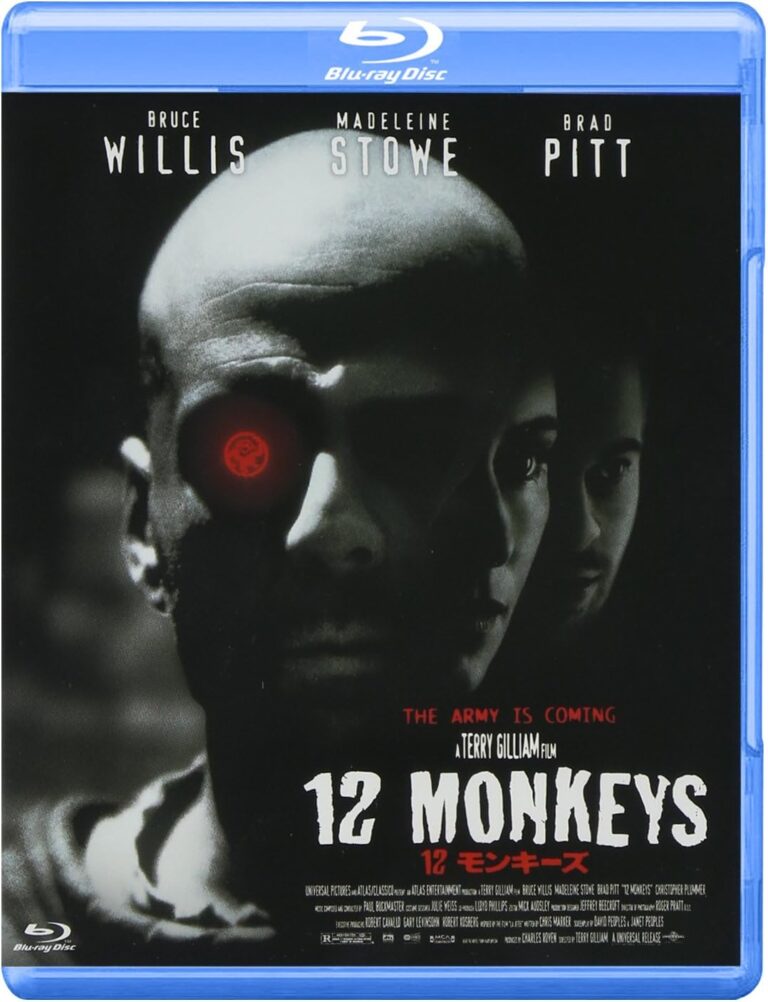『黒い画集 あるサラリーマンの証言』(1960)
映画考察・解説・レビュー
『黒い画集 あるサラリーマンの証言』(1960年)は、妻子ある中年社員・石野(小林桂樹)が、同僚の女性との密会を隠すために嘘の証言をしてしまう物語。無実の同僚を救うには不倫を告白するしかないという板挟みの中で、彼の小さな嘘が次第に取り返しのつかない悲劇を呼び込んでいく。
東宝モダニズムと清張の「湿り気」──清潔な地獄の誕生
1960年は、日本映画界において松本清張ブームが爆発した年。松竹が『張り込み』で成功を収め、東映などの他社もこぞって清張作品の映画化に乗り出すなか、東宝が満を持して放ったのが『黒い画集 あるサラリーマンの証言』(1960年)だ。
ここで注目すべきは、東宝というスタジオのカラーと、松本清張という作家が持つ土着的な湿り気の衝突である。東映や松竹が描く清張映画は、汗と泥と欲望にまみれた、湿度100%の情念劇になりがち。しかし東宝は山の手の映画会社で、サラリーマン喜劇や都会的なメロドラマを得意とする、モダンなスタジオだった。
監督の堀川弘通は黒澤明の愛弟子であり、徹底したリアリズムと理知的な演出が信条。彼が撮る清張映画は、驚くほど画面が洗練されている。オフィスは整然としており、小林桂樹演じる主人公・石野の家庭も、当時の団地・マイホーム文化を象徴するような、小奇麗で幸せそうな空間として描かれる。だが、この清潔さこそが、本作の恐怖を倍増させる装置なのだ。
主人公の石野は、真面目で、仕事熱心で、家庭を大事にする(ように見える)、どこにでもいる善良な市民。そんな彼が、部下の梅谷千恵子(原知佐子)と不倫をしている。その不倫ですら、ドロドロした情欲というよりも、日々のストレスを解消するための必要経費のような、妙に乾いた事務的な関係に見える。
彼が隣人の杉山(織田政雄)の無実を証明できる唯一の目撃者でありながら、沈黙を守る理由は、単純にして明快。課長への昇進を控えていて、家庭を壊したくないから。
ここにあるのは、殺人への加担意識ではなく、組織の中で生きるサラリーマンの自己保全本能だけ。東宝の明るい照明の下で繰り広げられるこの無作為の罪は、薄暗い路地裏の犯罪よりも遥かに現代的で、タチが悪い。
脚本の橋本忍は、原作の持つ文学的な独白を排除し、状況証拠と心理的圧迫だけで主人公を追い詰める詰将棋のような構成を作り上げた。石野が追い詰められていくプロセスは、まるで会社の稟議書が決裁されていくように、冷徹で、合理的で、そして逃げ場がない。
この「システムとしての悲劇」を描ききった点において、本作は日本映画史におけるサラリーマン・ノワールの金字塔となったのである。
小林桂樹という免罪符の剥奪
本作最大の勝因は、主人公・石野役に小林桂樹をキャスティングしたことに尽きる。当時の小林桂樹といえば、「社長シリーズ」の真面目な秘書役など、日本中の誰もが安心感を抱く良きサラリーマンであり、良き家庭人の象徴だった。
もし、この役を悪役顔の俳優が演じていたら、観客は最初からこいつは悪いやつだ!と距離を置いたはず。だが、演じているのはあの小林桂樹であるからして、観客は無意識のうちに「彼には何か事情があるはず」という期待を抱いてしまう。
映画は、その観客の信頼を残酷に裏切り続ける。石野はいつまで経っても自首しない。それどころか、アリバイ工作のためにさらに嘘を重ね、無実の人間が死刑になろうとしているのに、自分の出世のことばかり考えている。
あの温厚な丸顔から脂汗が滲み出し、目が泳ぎ、卑小なエゴイズムが露呈していく様を見せつけられる恐怖。それは、我々が信じている善意や常識なんてものは、保身の前では紙切れ同然という現実を突きつけられる体験だ。小林桂樹の起用は、日本のサラリーマン社会全体に対する、強烈なアイロニーとして機能している。
そして、もう一人の怪物が、愛人・梅谷千恵子を演じる原知佐子だ。彼女は、戦後の高度経済成長が生み出した、消費社会的で、倫理観が希薄な“新しい女性像”だ。
彼女は石野を愛しているわけでも、金を巻き上げようとしているわけでもない。ただ楽しいから一緒にいるだけ。隣人が死刑になるかもしれないという重大事態に対しても、他人事のようにしか思ってない。
この悪気のない悪こそが、石野を泥沼に引きずり込む。彼女の無邪気な笑顔は、石野の罪悪感を麻痺させ、共犯関係をただの秘密のデートへと矮小化させてしまう。
脇を固めるキャストも異常なほど豪華かつ鋭利だ。まだミスター・アタックチャンスになる前の、若き日の児玉清が、千恵子の新しい恋人役で登場。その軽薄でニヒルな大学生ぶりは、石野のような古いサラリーマンの苦悩を笑い飛ばす、次世代の冷たさを体現している。
そして、石野を強請るチンピラ役の小池朝雄。後に『刑事コロンボ』の吹き替えで知られる彼の、あの粘着質で、不快感を催す声の演技ったら!彼が登場するだけで、画面の湿度が上がり、東宝の清潔なセットに汚泥が流れ込んでくるようだ。
これらのキャラクター配置が、石野という平均的な日本人を包囲し、解体するための舞台装置として機能している。
橋本忍脚本による完全包囲とラストの虚無
映画の後半、石野は警察と検察によって、じわじわと追い詰められていく。ここで特筆すべきは、橋本忍の脚本術だ。彼は『羅生門』(1950年)や『生きる』(1952年)で培った構成力を駆使し、石野の嘘を一つ一つ論理的に粉砕していく。
警察は、石野が犯人だと思って捜査しているわけではなく、あくまで証言の矛盾を突いているだけ。だが石野にとっては、その質問の一つ一つが、喉元に突きつけられたナイフとなる。
日常の些細な行動が、嘘のアリバイと矛盾し、綻びが広がっていく。この尋問サスペンスの緊張感は、派手なアクションシーンをはるかに凌駕する。石野が手帳を見返し、記憶を捏造し、冷や汗を拭う。その生理的な息苦しさは、観ているこちらの胃まで痛くさせるほどだ。
原作では、石野は社会的に抹殺されるものの、ある種の「逃げ道」が残されている。だが、映画版のラストはもっと残酷で、徹底的だ。
検察官(中谷一郎)が仕掛けた罠により、石野はついに決定的な証拠を突きつけられる。それは、彼が保身のために行った偽装工作が、皮肉にも彼自身を犯人として指し示す証拠となってしまった瞬間だ。
真実(不倫)を隠すためについた嘘が、より重い嘘(殺人)として確定してしまう不条理。彼は社会的に死ぬだけでなく、人間としての尊厳も、真実を語る資格もすべて剥奪される。
ラストシーンの、護送車に乗せられる石野の虚ろな目。そこには罪を償うという安堵すらない。あるのは、計算高いサラリーマンが計算を間違えたことへの、底知れぬ後悔と虚無だけだ。
石野は特別な悪人ではない。私たちの中にもいる、小さな保身の塊だ。だからこそ、この映画は恐ろしいのである。
- 黒い画集 あるサラリーマンの証言(1960年/日本)
![黒い画集 あるサラリーマンの証言/堀川弘通[DVD]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/71BwICcULRL._AC_SL1080_-e1758994176990.jpg)
![張込み/野村芳太郎[DVD]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/91qjgrziYzL._AC_SL1500_-e1759038178751.jpg)
![羅生門/黒澤明[DVD]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/710g2zTMOvL._AC_SL1265_-e1758350034647.jpg)