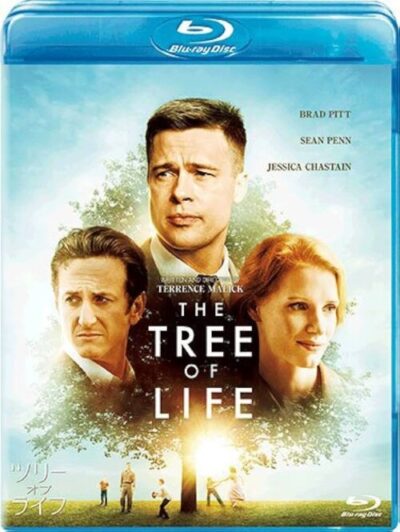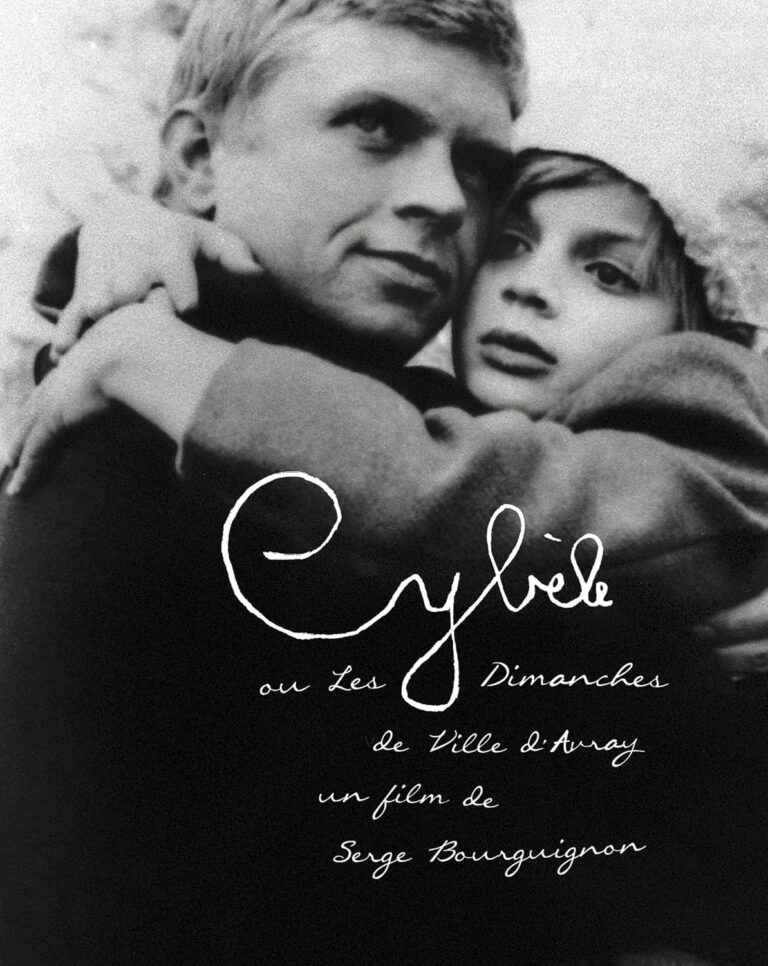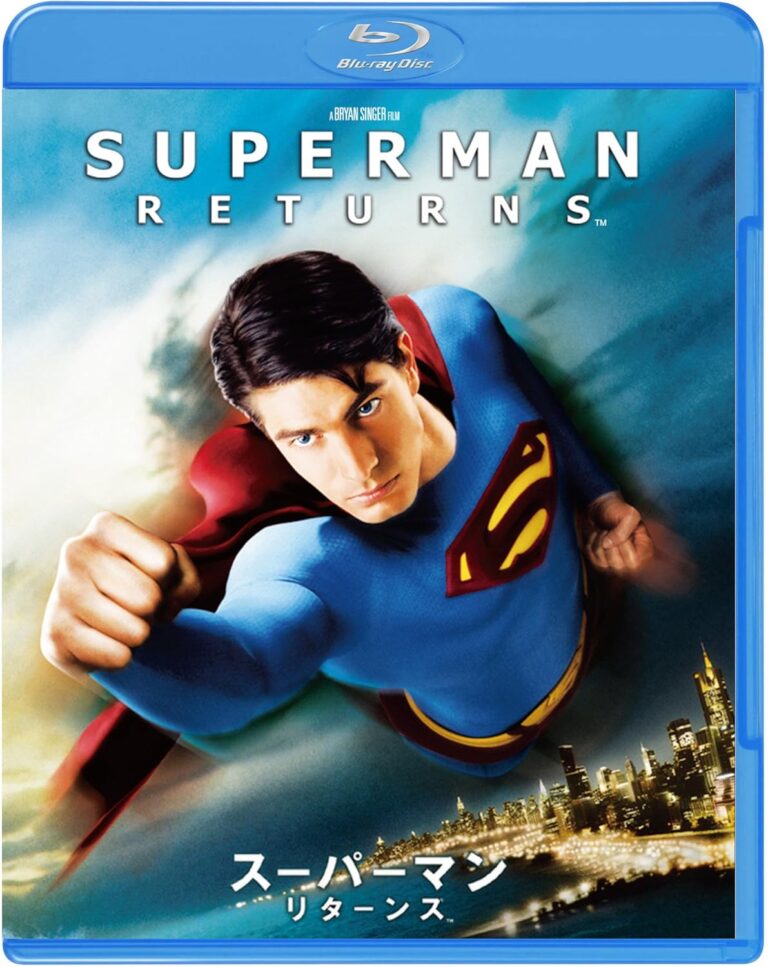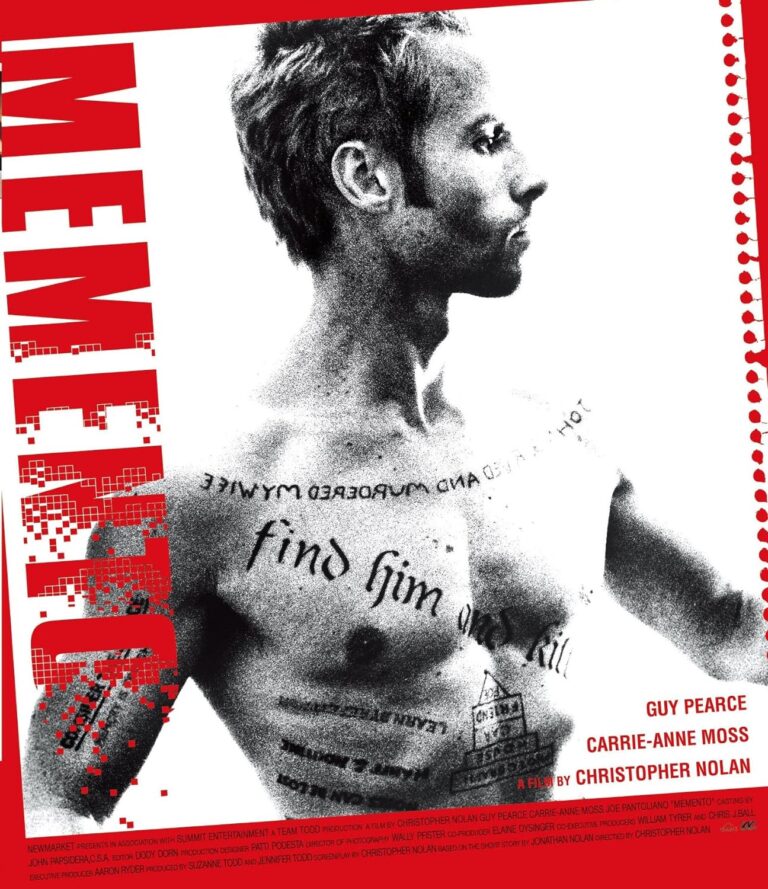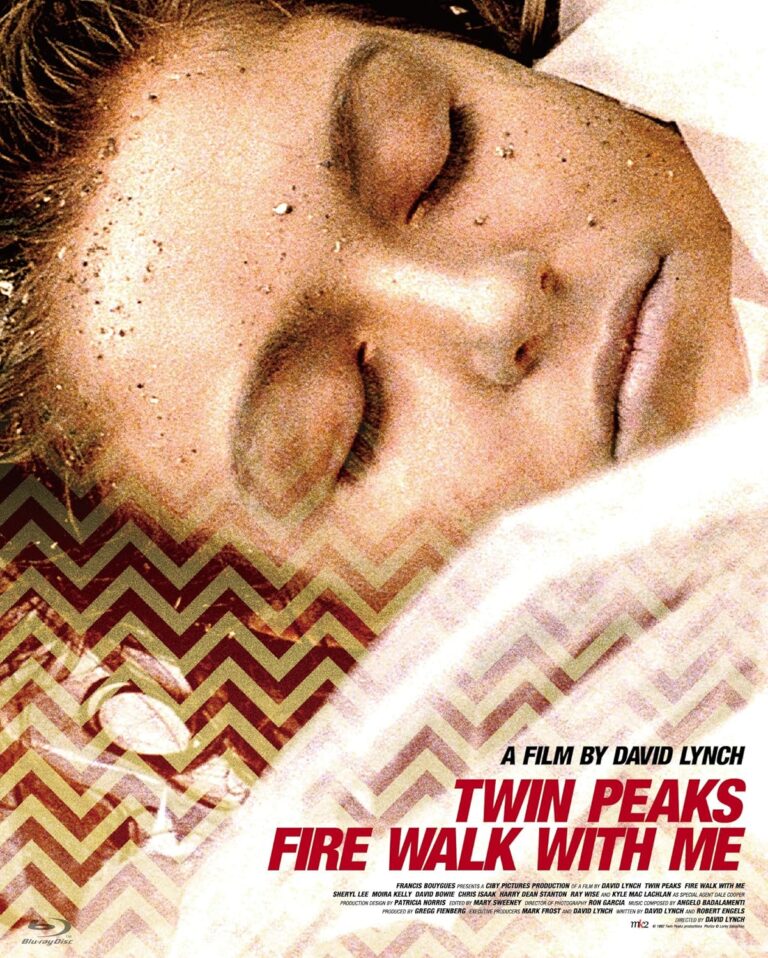『大人は判ってくれない』(1959)
映画考察・解説・レビュー
『大人は判ってくれない』(原題:Les Quatre Cents Coups/1959年)は、フランソワ・トリュフォーが自身の少年期を下敷きに、パリで暮らす12歳の少年アントワーヌ・ドワネル(ジャン・ピエール・レオ)の日常と挫折を描いた、初の長編映画。学校では規則に適応できず、家庭では実母と継父との関係がうまくいかず、責任を問われる出来事が続いたアントワーヌは、嘘をついたことをきっかけに教師や両親の不信を招く。やがて友人ルネと共に家出を試み、盗難や無断欠席によって警察に連行され、未成年拘留施設へ送られる。その後も制作されるアントワーヌ・ドワネルの冒険シリーズの第一作。
世界中のアウトサイダーに捧ぐ、ヌーヴェルヴァーグの咆哮
フランソワ・トリュフォーの長編デビュー作『大人は判ってくれない』(1959年)を観て、心が震えない人間なんているのだろうか?いや、そんな奴は最初から映画を観る資格がない(断言)!
ここで誕生した少年アントワーヌ・ドワネルは、単なるキャラクターではない。以後20年、5本の作品にわたってトリュフォーと共に歳を重ねていく、監督自身の生き写し──「もう一人のフランソワ」なのである。
この映画を調べれば調べるほど、この映画の「実録性」には戦慄を覚える。劇中、アントワーヌが警察に連行され、指紋を採取されるシーン。あれはトリュフォー自身が少年時代に体験し、生涯消えない「屈辱の記憶」として脳に刻まれた風景そのもの。
実母から「お前なんか産まなければよかった」という呪いの言葉を投げかけられ、孤児同然でパリを彷徨った少年の絶望。トリュフォーは、当時14歳だったジャン=ピエール・レオという「野生児」の中に、自分自身の傷跡を見出した。
撮影現場でのトリュフォーは、レオを子役としてではなく、一人の対等な親友として扱った。彼はレオに「大人が何を言っても気にするな。君が正しいと思うように動け」と囁き続けたという。
これこそが映画という名の「自伝」であり、最もパーソナルな痛みが世界の普遍的な宝物へと昇華された、奇跡の瞬間。アントワーヌが校内で嘘をつき、家庭で疎外され、社会の規範に押しつぶされていく姿は、トリュフォーという“映画を愛しすぎた少年”の血を吐くような自画像である。
この少年が大人たちへ向ける反抗の視線は、そのまま既成の映画界をぶち壊そうとした若き批評家グループ「カイエ・デュ・シネマ」の戦士たちの眼差しでもあったのだ。
手持ちカメラがぶち壊した古い映画の化石たち
撮影監督アンリ・ドカエのカメラが捉えたパリ。そこにはセットで作り込まれた偽物の街なんてどこにもない。
手持ちカメラによる流動的なショット、自然光が生み出す即興的な明暗、そして街の呼吸をそのまま録音したような瑞々しさ。これがヌーヴェルヴァーグの正体であり、旧態依然とした映画界への「民主化」宣言なのだ。
当時、トリュフォーは批評家として「フランス映画のパパたち」を痛烈に批判していたが、本作で自ら「こう撮るんだよ!」と実力行使に出たわけだ。
特筆すべきは、アントワーヌが精神科医(声のみ出演のトリュフォー!)の尋問に答える伝説のシーン。このシーンの撮影中、トリュフォーはレオに対して「君の好きなように喋っていい。僕の質問にどう答えてもいいんだ」とだけ告げ、即興を促した。
レオが時折見せるはにかんだような笑いや、言葉に詰まる仕草。あれは演技を超えた、レオという個体から漏れ出した「真実」そのものである。監督はレオを一人の人間として尊重し、台本という檻を壊して、少年の内側にある生々しい言葉を誘い出したのだ。
学校の厳格な規律や、冷え切った家庭の空気から逃れ、パリの路地裏を駆け抜け、回転するアトラクションの中で重力さえも振り切ろうとするアントワーヌの走り。それを執拗に追い続けるロングショットの圧倒的なグルーヴ感が素晴らしい。
それは映画の工業性からの解放であり、同時に権威や制度を拒絶した新しい現実の風景の発見だ。日常をそのまま映画にするという「自由」を手に取った瞬間、トリュフォーは世界中のクリエイターに「君も、君の周りにある世界を撮ればいいんだ!」という希望のバトンを渡したのである。
海の彼方へ、師バザンへ
本作を語る上で、トリュフォーの精神的父親であり、映画批評の神様アンドレ・バザンの存在を欠くことはできない。
本作は「父殺しと父探し」の物語でもある。実父を知らず、義父に疎まれたトリュフォーにとって、自分を刑務所から救い出し、映画の世界へ導いてくれたバザンこそが唯一の、そして真実の父だった。
だが、悲劇的なことに、バザンはこの映画のクランクインと同時に病に倒れ、その完成を見ることなくこの世を去った。トリュフォーにとって、この映画は師への挽歌であり、映画という信仰告白そのものなのだ。
バザンは「映画とは現実の痕跡である」と説いた。トリュフォーはその教えを骨の髄まで体現し、ラストシーンでアントワーヌをひたすら海へと走らせる。
それまでの閉鎖的なアパートや、息の詰まる少年鑑別所を飛び出し、世界の果てである「海」を目指して駆ける少年の姿。それは、現実のトリュフォーを暗闇から救い出したバザンへの「自由への飛翔」の報告であり、師の死という耐え難い現実に対する、映画的表現での復讐でもあった。
そして、全映画史の中で最も有名な、あの「フリーズ・フレーム」のラスト。海に辿り着き、カメラを真っ直ぐに見つめる少年の瞳。そこで時間は止まり、映画は終わる。
だが、物語は終わらない。あの静止画に象徴されているのは、現実を永遠化する映画の残酷なまでの美しさと、バザンが語った「生の断片を救い上げる力」そのもの。
理解されない孤独、行き場のない怒り、それらをすべて抱えたまま、少年は僕たちの視線を射抜く。それは大人にならない勇気の証明であり、映画史という永遠の海へと漕ぎ出したトリュフォーの、血を吐くような倫理の刻印なのだ。
『大人は判ってくれない』という絶望は、いつしか「それでも映画があるじゃないか」という最強の希望へと反転していく。我々はその瞳に見つめ返されることで、自分たちがかつて抱いていた「純粋な反逆心」の現在地を問われ続けるのである。
ドワネル・シリーズが暴く残酷な真理
『大人は判ってくれない』の疾走は、たった一作では終わらない。
トリュフォーはこの後、20年もの歳月をかけて『アントワーヌとコレット』、さらには大人になった彼を描く『夜霧の恋人たち』や『家庭』、そして完結編の『逃げ去る恋』へと物語を繋いでいった。この壮大な実験が暴き出したのは、愛の不可能性というあまりに鋭利な真理なのだ!
アントワーヌは、少年時代の家庭不和によって空いてしまった「心の穴」を埋めるために、生涯を通して女性の中に救いを求め続ける。だが、彼はいつだって「愛し方」が分からない。
シリーズ第2作『アントワーヌとコレット』で見せた、好きな女の子の向かいの部屋に強引に引っ越してしまうという、ストーカー紛いの純粋で歪な情熱。彼は常に全力で恋に落ち、そして全力で自滅する。
トリュフォー自身もまた、私生活でも女性を熱烈に愛し、同時にその愛が壊れることを極端に恐れていた。アントワーヌが次々と女性を乗り換えていくのは、一人の女性に深く愛されることで、少年時代の母への不信感が再燃することを恐れた回避行動でもあったのだろう。
彼は、愛を自分を救ってくれる魔法だと思い込んでいる。だが、魔法はいつか解ける。トリュフォーは、分身であるアントワーヌを通じて、人間が他者を真に理解することの難しさと、孤独からは決して逃げられないという宿命を、執拗に、かつ愛おしく描き続けた。
完結編『逃げ去る恋』に至るまで、アントワーヌは結局のところ、どの女性とも精神的な安息に辿り着くことはなかった。この「愛への渇望と、それゆえの絶望」という永久ループこそが、アントワーヌが走り続ける真の動機であり、観る者の胸を締め付ける「終わらない思春期」の正体なのである。
- 監督/フランソワ・トリュフォー
- 脚本/フランソワ・トリュフォー、マルセル・ムーシー
- 製作/フランソワ・トリュフォー
- 撮影/アンリ・ドカエ
- 音楽/ジャン・コンスタンタン
- 編集/マリー=ジョゼフ・ヨヨット
- 美術/ベルナール・エヴァン
- 大人は判ってくれない(1959年/フランス)
- ピアニストを撃て(1959年/フランス)
- 黒衣の花嫁(1968年/フランス、イタリア)
- 夜霧の恋人たち(1968年/フランス)
- 大人は判ってくれない(1959年/フランス)
![大人は判ってくれない/フランソワ・トリュフォー[DVD]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/71c0uNglUuL._AC_UL640_FMwebp_QL65_-e1761675146909.webp)
![映画とは何か/アンドレ・バザン[本]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/61-kDoQjGAL._SL1434_-e1772870414835.jpg)
![夜霧の恋人たち/フランソワ・トリュフォー[DVD]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/baisersvoles-e1759052744716.webp)