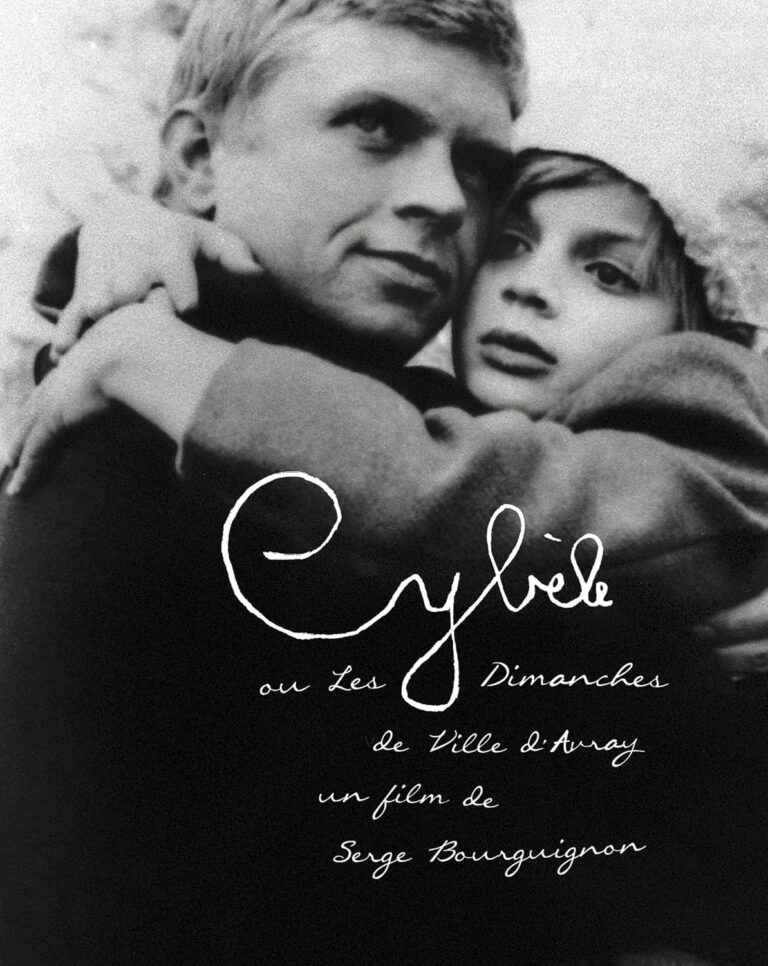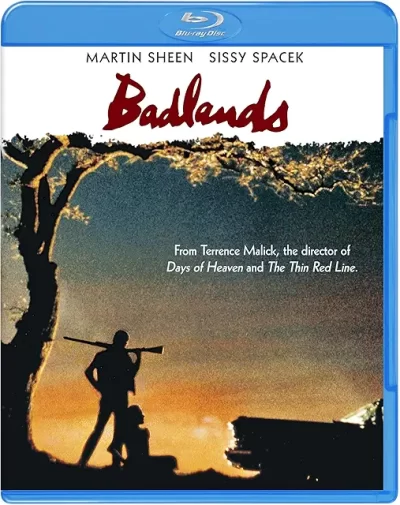【ネタバレ】『SUPER8/スーパーエイト』(2011)
映画考察・解説・レビュー
『SUPER8/スーパーエイト』(原題:Super 8/2011年)は、ヒットメーカーのJ・J・エイブラムス監督と、巨匠スティーヴン・スピルバーグが最強タッグを組み、映画制作を愛する少年たちの瑞々しい夏と、宇宙からの訪問者が引き起こす驚異の事件を描いたSFアドベンチャー。1979年のアメリカ。8mmカメラで自主製作映画を撮影していた少年たちが偶然目撃した、凄まじい貨物列車の脱線事故をきっかけに、壮大なアドベンチャーが展開される。
フェイク・ドキュメンタリーの誤解と、蘇る8mmの記憶──エイブラムスの真の出発点
J・J・エイブラムスという希代のクリエイターを語る上で、『SUPER8/スーパーエイト』(2011年)は極めて重要な転換点に位置している。
公開前、緻密なバイラル・マーケティングと謎に包まれた特報映像によって、本作は『クローバーフィールド/HAKAISHA』(2008年)のプリクエルではないか?という噂を引き起こした。
エイブラムスの代名詞であるミステリー・ボックスの手法が見事に機能した結果だが、実際の成り立ちは全く異なる。「エイブラムスが子供時代に自主映画を撮っていた青春物語」と、「エリア51から移送されるエイリアンを乗せた列車が脱線するSFパニック」という、本来交わるはずのなかった二つのアイデアが衝突し、強引に融合したことによって産み落とされた奇跡のプロットなのだ。
この野心的な脚本に、かつて8mm映画のコンテストで若き日のエイブラムスを見出したスティーヴン・スピルバーグ本人が製作として合流したことで、物語は劇的な化学反応を起こす。
『未知との遭遇』(1977年)や『E.T.』(1982年)といったアンブリン・エンターテインメント黄金期の輝きへの巨大なオマージュでありながら、エイブラムス自身の映画体験の原点・8mmフィルムの手触りをスクリーンに刻み込む、極めて私的でエモーショナルなセルフ・ポートレートへと変貌を遂げたのである。
デジタル全盛の現代において、あえてアナログのノイズと不完全さを前面に押し出した本作は、単なる懐古趣味を超え、「映画とは何か」を問い直すエンターテインメントとして我々の眼前に立ち上がったのだ。
スピルバーグの遺伝子と「空を見上げる少年」
「私の映画を象徴するショットは、『未知との遭遇』で少年が空を見上げる瞬間だ」。スピルバーグのこの言葉を体現する、いわゆるスピルバーグ・フェイス完全再現から『SUPER8/スーパーエイト』は幕を開ける。
1979年、オハイオ州の田舎町。夜空の圧倒的な光景を見つめる少年たちの表情には、未知への根源的な驚異と、世界を切り取ろうとする“撮る者の眼差し”が完璧に重なり合っている。
エイブラムスはここで、空を見上げる子供=映画を撮る監督という美しい等式を提示した。彼らにとってカメラは単なる玩具ではなく、残酷な現実から逃避しつつ世界と接続するための武器であり、フィルムは未知を物質化して永遠に保存する小さな魔法の箱なのだ。
さらに、スピルバーグ神話の絶対的ルールである「片親の不在」も色濃く継承されている。最愛の母を凄惨な事故で亡くした主人公ジョーと、悲しみから息子に感情を閉ざす父。
この『E.T.』にも通じる巨大な喪失と心の穴こそが、彼らが想像力(=エイリアンとの交流や映画制作)で必死に物語を紡ぐ最大の原動力となっている。
少年たちが憧れのジョージ・A・ロメロを真似て撮るホラー映画の擬似的現実感は、現実の恐怖(列車事故とエイリアン襲来)と並走し、やがて交錯する。
『ジョーズ』を彷彿とさせる、見せない怪物の演出で観客をコントロールしつつ、フィルムの駆動音と現代最高峰のVFXが融合する瞬間、映画は過去の記憶と未来のテクノロジーを美しく接続してみせるのだ。
エル・ファニングという奇跡と、ノスタルジーへの訣別
本作が単なるスピルバーグの秀逸なパロディに終わっていない最大の理由は、憧れの再現と同時に、憧れの終焉(=卒業)を描き切っている点にある。
クライマックス、強大な磁力で鉄屑を吸い上げ宇宙へ帰還する母船を見上げるジョーの姿に、観客は二重の視点を重ねる。未知への純粋な畏敬と、絶対的に守られていた子供時代(=映画という幻影)への別れだ。
70年代の少年たちが奇跡を無条件に信じて宇宙船を見送ったのに対し、21世紀のジョーは自らの意思で母親の形見のペンダントを手放し、磁力へと吸い込ませる。
それは過去のトラウマへの固執からの解放であり、70年代のノスタルジーそのものを自らの手で葬送する、極めて成熟した別れの儀式。本作はスピルバーグへの熱烈なラブレターであると同時に、エイブラムスからの偉大なる父への訣別の物語でもある。
そして、この映画を語る上で絶対に外せないのが、アリス役を演じた当時12歳のエル・ファニングだ!
深夜の無人駅で、カチンコが鳴った瞬間に少しグレた少女が悲劇の妻へと豹変し、本物の涙をこぼす。少年たちが言葉を失い、ジョーが一瞬で恋に落ちるあのシーンで彼女が放つ光は、まさに映画の精霊そのもの。
VFXで作られたエイリアンよりも遥かに恐ろしく、美しく、神秘的な未知なるもの。それこそが、レンズを通してひとりの少女を見た瞬間の「恋」という名の奇跡なのである。
『SUPER8/スーパーエイト』は、70年代の熱狂を21世紀に再体験させ、そして優しく幕を下ろすための、時空のタイムカプセルだ。
エンドロールの横で流れる、少年たちが完成させた自主製作映画『The Case』のチープで愛おしい映像を見たとき、我々は思い知らされる。映画を作ること、信じること。その最高に純粋でバカバカしい行為の尊さを、J・J・エイブラムスは狂おしいほどの熱量で我々に突きつけているのだ。
- 監督/J・J・エイブラムス
- 脚本/J・J・エイブラムス
- 製作/スティーヴン・スピルバーグ、J・J・エイブラムス、ブライアン・バーク
- 製作総指揮/ガイ・リーデル
- 制作会社/パラマウント・ピクチャーズ、バッド・ロボット、アンブリン・エンターテインメント
- 撮影/ラリー・フォン
- 音楽/マイケル・ジアッチーノ
- 編集/メリアン・ブランドン、メアリー・ジョー・マーキー
- 美術/マーティン・ホイスト
- 衣装/ハー・ヌウィン
- SUPER8/スーパーエイト(2011年/アメリカ)
![SUPER8/スーパーエイト/J・J・エイブラムス[DVD]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/71p0D2Dy-KS._AC_SL1250_-e1759043275403.jpg)
![クローバーフィールド/HAKAISHA/マット・リーヴス[DVD]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/71u80hmKqkL._AC_SL1250_-e1759134334604.jpg)
![未知との遭遇/スティーヴン・スピルバーグ[DVD]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/813MEbIWnvL._AC_SL1500_-e1756663860162.jpg)