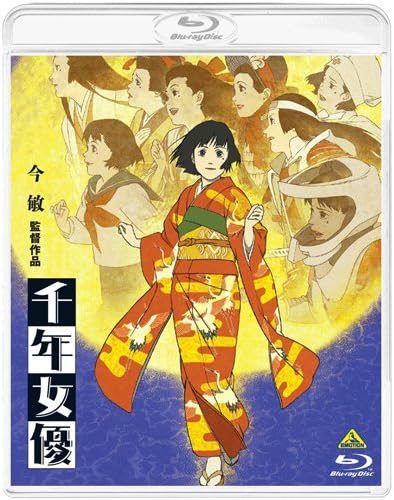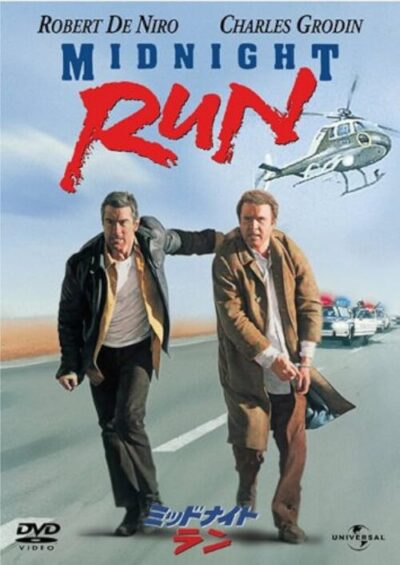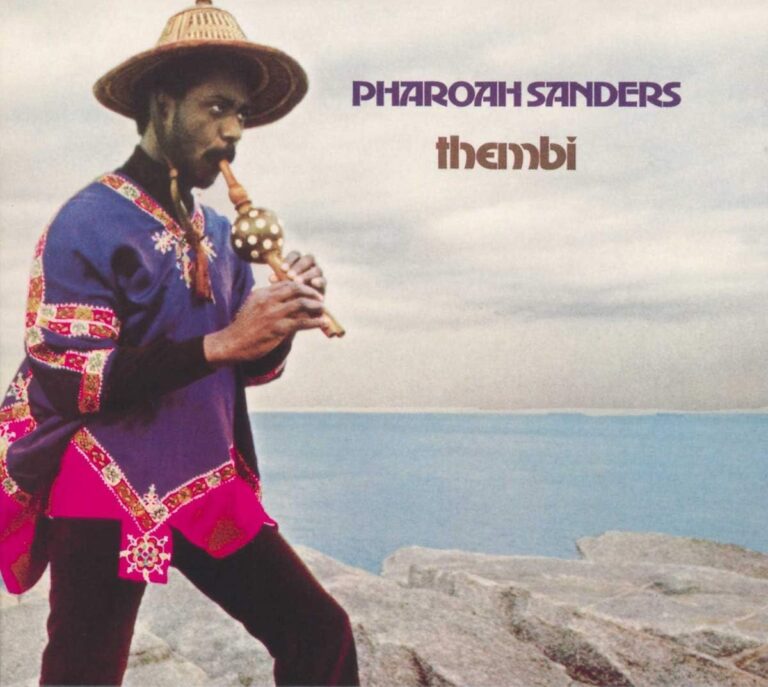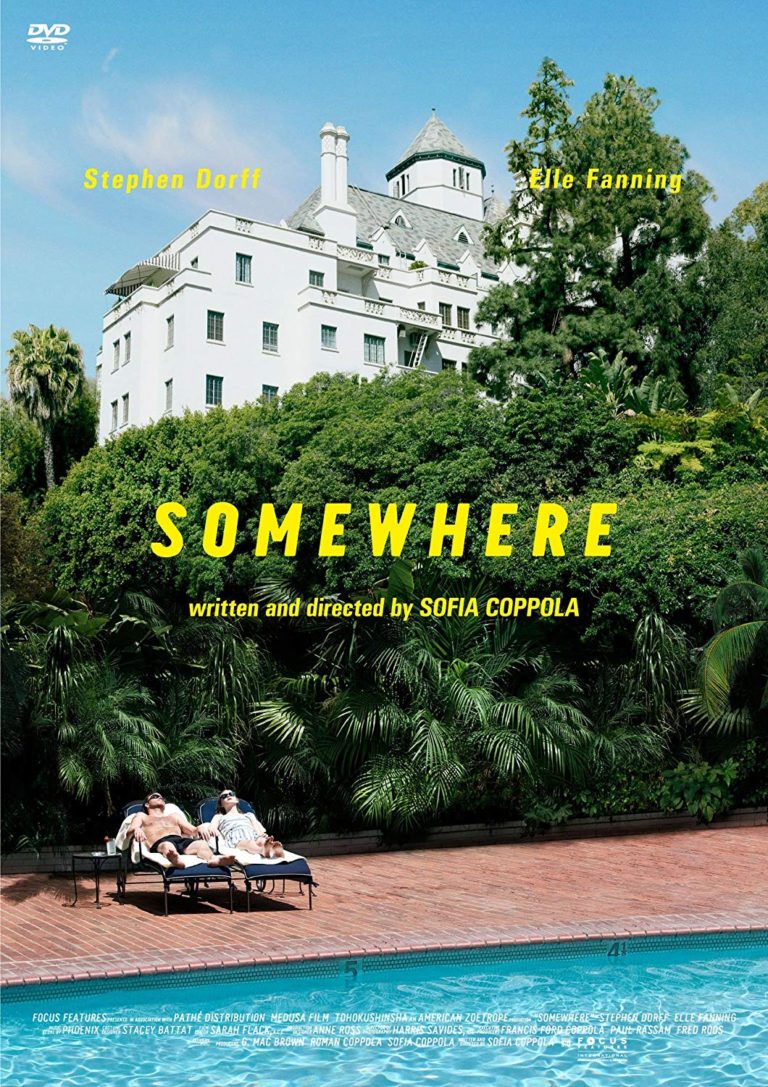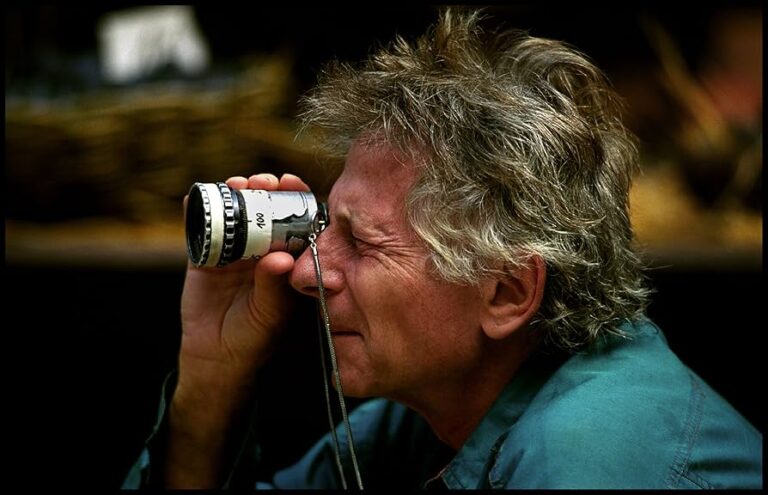『TOMORROW 明日』──「永遠に来ない明日」を生きる人々の24時間
『TOMORROW 明日』(1988年)は、黒木和雄監督による長崎を舞台とした群像劇であり、戦争レクイエム三部作の第一作にあたる。1945年8月8日、翌日の原爆投下をまだ知らぬ人々が、それぞれの生活や夢を抱えて一日を過ごす。結婚式の準備に追われる家族、出産を控えた女性、職場で働く市民たちが交錯し、街はいつもと変わらぬ日常を取り戻そうとしていた。だが夜が更けるにつれ、誰も知らぬ“明日”が静かに近づいてくる。
南果歩という光──個人的崇拝から始まる映画体験
とにかく南果歩が好きで好きで好きで好きだった。少し鼻にかかった声、少年のような顔立ち、細身ながら均整の取れた身体。そのすべてが僕にとってひとつの信仰だった。
同級生が宮沢りえだ西田ひかるだと騒いでいた高校時代、僕はただひとり南果歩を追いかけていた。テレビで、雑誌で、写真集で――。彼女の存在はスクリーン上の“憧れ”というより、ほとんど“観念”に近いものだったのかもしれない。
だから黒木和雄の『TOMORROW 明日』(1988年)を観たのも、きっかけは南果歩だった。だが、映画はそんな軽い動機を一瞬で打ち砕く。
タイトルの“明日”が、「永遠に来ない明日」であることに気づいた瞬間、僕はスクリーンの前で身動きが取れなくなったのである。
「8月8日 長崎」──知らされてしまった悲劇の時間
『TOMORROW 明日』は、黒木和雄の戦争レクイエム三部作の第一作にあたる。
舞台は長崎。戦時の混乱の中でも、ささやかな幸福を紡ごうとする市井の人々の24時間を描く。冒頭に映し出されるテロップ――「8月8日 長崎」――それだけで観客は、明日、この街が消えることを“知ってしまう”。
ヒッチコックは「観客に情報を与えることでサスペンスが生まれる」と語ったが、この映画の緊張は、まさにその“知ってしまった”瞬間から始まる。
だからこそ、一分一秒が愛おしい。食卓を囲む笑顔、結婚式の喧騒、子どもたちの笑い声――そのすべてが、明日の“消滅”を前提として輝く。
ラスト近く、劇伴に「カチカチ」と時限爆弾のような音が重なる演出は確信犯的だ。音楽が静かに時間を刻み、観客はその音を聞くたびに、“終わり”が近づいてくることを知る。美しさと恐怖が同時に流れ込むその感覚は、黒木和雄が生涯追い続けた「戦争のリアル」そのものだ。
群像劇としての構成は野心的。元帝国ホテルの料理長を演じる田中邦衛、敵国のアメリカ兵を救おうとする黒田アーサー、妊娠中の水島かおり。だが、それぞれのエピソードが過剰に感傷的で、一本の軸に収束しきれない印象もある。
映画はあらゆる手管を尽くして観客を“戦争のリアリティ”に引き込もうとする。だがその努力が、時に作為として浮き上がる瞬間がある。長崎弁の生々しさも、僕には聞き取りづらく、群像の輪郭がぼやけてしまった。
結婚式のシークエンスから始まる群像劇構成――それは黒澤明の『悪い奴ほどよく眠る』(1960)や、コッポラの『ゴッドファーザー』(1972)に通じる“開始の儀式”である。
だが、黒木の演出はそれを写実の枠にとどめず、死へ向かう時間の詩として描き出す。観客は物語を追うのではなく、時間そのものを見つめさせられる。
南果歩が刻んだ「生」の証
それでも僕にとって、この映画の核心は南果歩。初夜を迎える彼女が、手ぬぐいで身体を拭く場面。あの一瞬のバック・ヌードは、官能ではなく“祈り”だった。彼女の白い背中は、明日消えるはずの生命の証として、あまりにも神々しく、あまりにも静かだった。
黒木和雄のカメラは、その身体を欲望の対象ではなく、“生の痕跡”としての肉体として捉えている。死の前夜における、もっとも純粋な“生”の瞬間。それは、南果歩という俳優が持つ特有の清冽さを極限まで引き出していた。彼女の声、立ち姿、眼差し――すべてが明日を信じている。それがわかっているからこそ、観る側は痛みを覚える。
『TOMORROW 明日』は、戦争映画である以前に、「生きる」ということの記録映画なのだ。原爆の惨禍を描くことではなく、消えゆく日常を刻むこと。その時間の尊さを伝えるために、黒木和雄はあえて“明日”を描かなかったのである。
- 製作年/1988年
- 製作国/日本
- 上映時間/105分
- 監督/黒木和雄
- 製作/鍋島壽夫
- 原作/井上光晴
- 脚本/黒木和雄、井上正子、竹内銃一郎
- 撮影/鈴木達夫
- 音楽/松村禎三
- 美術/内藤昭
- 編集/飯塚勝
- 録音/井家眞紀夫
- 桃井かおり
- 南果歩
- 仙道敦子
- 黒田アーサー
- 佐野史郎
- 長門裕之
- 絵沢萠子
- 水島かおり
- なべおさみ
- 馬渕晴子
- 原田芳雄
- 田中邦衛