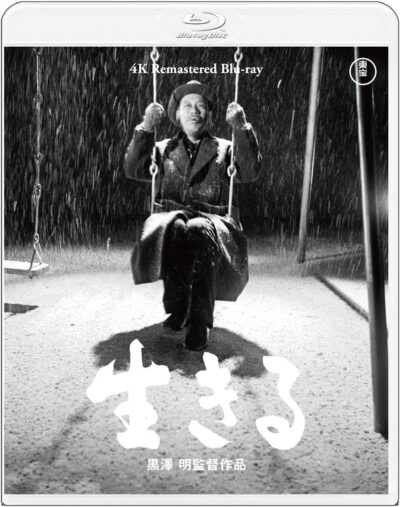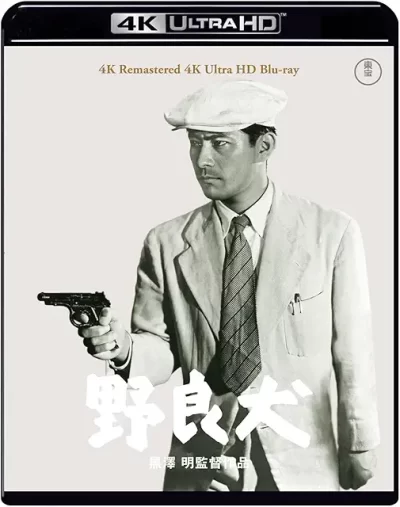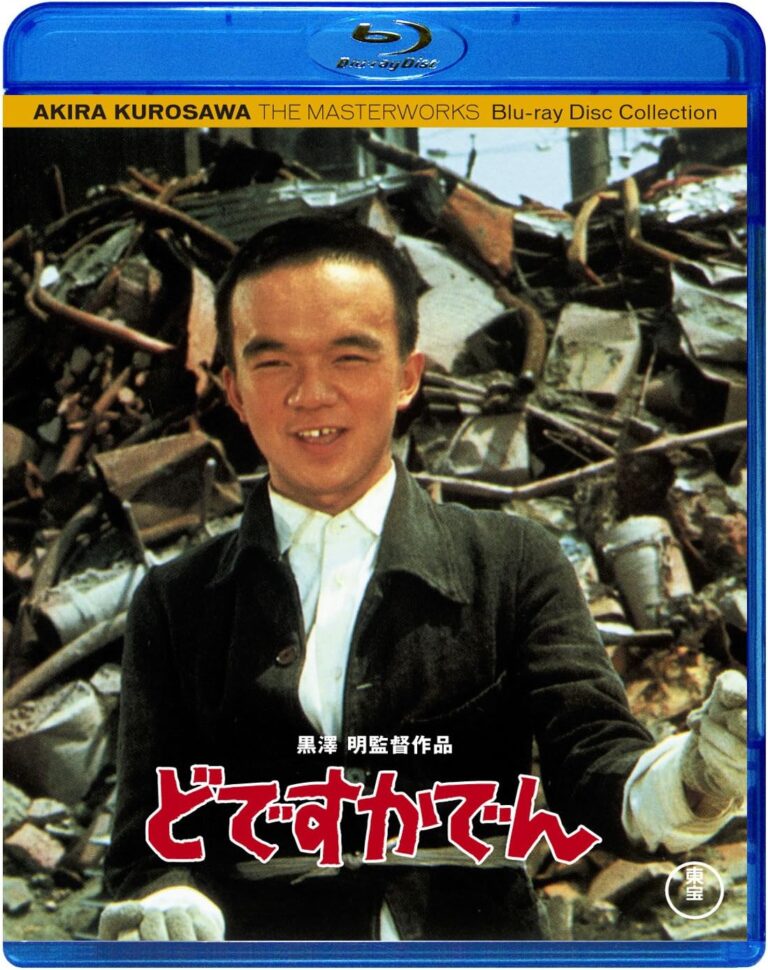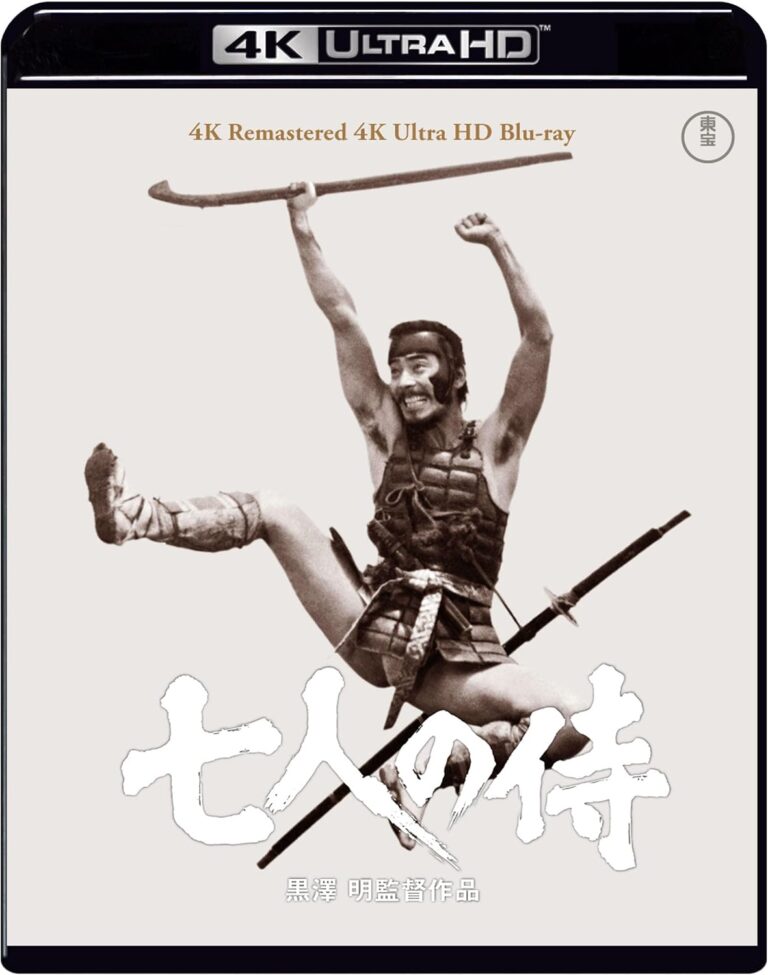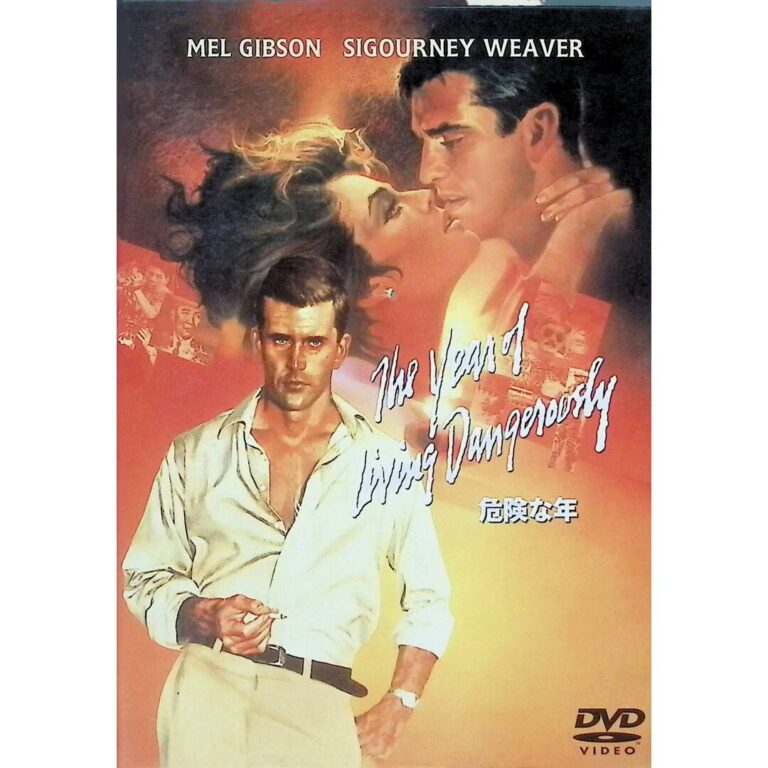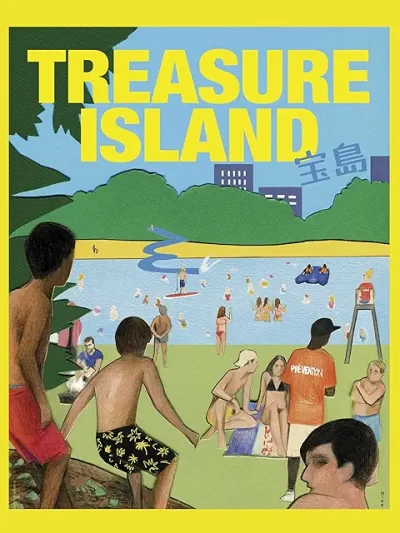『悪い奴ほどよく眠る』(1960)
映画考察・解説・レビュー
『悪い奴ほどよく眠る』(1960年)は、黒澤明監督が高度経済成長期の日本社会に鋭く切り込んだ社会派サスペンスであり、三船敏郎、仲代達矢、森雅之、山崎努といった名優陣が硬質なドラマを支える。官僚機構と企業の癒着によって父を死に追いやられた主人公・西(三船敏郎)は、復讐のために汚職事件の中心人物の娘(香川京子)と結婚し、巨大な権力構造の内部へ自ら潜り込んでいく。しかし、真相に近づくほどに、官僚組織は冷酷に、企業は巧妙に正義を押し潰し、個人の意志が巨大な利権の前でいかに脆いかが露わになっていく。第34回キネマ旬報ベスト・テン日本映画では、第3位に選出。
完璧主義と独立プロダクションの誕生
黒澤明は生来の完璧主義がたたって、撮影期間の遅延や予算超過をたびたび繰り返していた。その結果、撮影期間は長期化し、制作費は膨張する。
『生きる』(1952年)では、下水工事シーンでの群衆演出に黒澤が徹底的にこだわり、主人公・渡辺勘一(志村喬)の感情の変化を正確に映そうと芝居のタイミングを何度も調整したため、予定よりも撮影期間が1〜2か月延長。
『七人の侍』(1954年)の撮影期間は当初3か月だったものの、黒澤は群衆シーンや戦闘シーンの細部までこだわり、カット割りやカメラの動き、雨や土埃の演出などを徹底的に練り込んだため、最終的には倍となる6か月の撮影期間に。
『蜘蛛巣城』(1957年)でも、大広間の戦闘シーンや屋外の城攻めシーンで、カメラワークや俳優の立ち位置を1シーンごとに何度もやり直したため、撮影期間が大幅に超過する。映画会社にとっては頭の痛い存在だが、その徹底ぶりこそが数々傑作を生み出す源泉でもあった。
とはいえ、制作サイドも無限に予算を投じるわけにはいかない。度重なる予算超過に業を煮やした東宝は、リスクヘッジ策として「独立プロダクション方式」を黒澤に提案する。
これは「予算も権限も与えるが、リスクは自ら負え!」というもの。黒澤はこれを受け入れ、第一弾作品として、当時の世間を騒がせていた公団汚職をテーマにした『悪い奴ほどよく眠る』(1960年)を製作する。
映画の冒頭、実に25分間にも及ぶ結婚披露宴のシーンは、おそらく映画史における導入部の最高傑作の一つだろう。舞台は公団副総裁・岩淵(森雅之)の娘・佳子(香川京子)と、秘書の西(三船敏郎)の結婚式。
祝いの席に、場違いな警察が踏み込み、汚職疑惑のある幹部を連行していく。さらに、ハイエナのような新聞記者たちが取り囲み、皮肉な解説を加え続ける。
黒澤はここで、十数人もの主要キャラクターを一堂に会させ、ワルツの調べに乗せて、彼らの役職、性格、そして腐敗の構造を一気に見せる離れ業をやってのけた。画面構成は完璧に計算され、誰が誰を見ているか、誰が誰に怯えているかが、幾何学的な配置だけで説明される。
そして、会場に運び込まれる巨大なウェディングケーキ。それは、5年前に公団の課長が飛び降り自殺をした公団ビルの形をしていた。しかも、飛び降りた窓枠の一箇所には、赤いバラが一輪、無造作に突き刺さっている。
会場は凍りつき、幹部たちは蒼白に。このケーキこそが、西(三船)による復讐の狼煙。フランシス・フォード・コッポラが『ゴッドファーザー』の冒頭で参考にしたとも言われるこの濃密なシークエンスは、観客の心臓を冒頭から鷲掴みにし、これから始まる地獄巡りへと引きずり込む。
三船敏郎が封印した肉体と口笛
この映画の三船敏郎は、いつもの暴れん坊じゃない。『羅生門』の山賊や、『七人の侍』の菊千代で見せた、あの躍動する肉体は完全に封印されている。
彼は黒縁眼鏡をかけ、感情を押し殺し、インテリジェントな事務屋として振る舞う。だがその正体は、汚職のスケープゴートにされ自殺を強いられた男の息子、板倉だ。彼は顔を変え、戸籍を変え、仇敵・岩淵の懐に入り込んだ現代のハムレットである。
三船が見せる演技の凄みは、その抑制にある。彼は能面のような無表情を貫くが、一人になった瞬間、あるいは極度の緊張状態に置かれた瞬間、微かに口笛を吹く。
その乾いた音色は、彼の内側で渦巻く狂気と殺意が、高圧蒸気のように漏れ出している証拠だ。眼鏡の奥で光る冷徹な眼差しは、抜身の刀よりも鋭く、観る者の心臓を抉る。
そして、この映画を真の悲劇にしているのは、西が復讐のためにオフィーリアである佳子(香川京子)を利用しようとし、あろうことか本気で愛してしまったことにある。
足の不自由な佳子は、純粋無垢な存在だ。西は彼女と結婚し、岩淵の家族となることで復讐の足場を固めるが、指一本触れようとしない。それは紳士だからではない。彼女を抱くことは、復讐の純度を濁らせるからだ。
復讐者は、愛を知ってはならない。この矛盾が、西を内側から引き裂いていく。廃墟となった軍需工場跡のアジトで、西が相棒の板倉(加藤武)に心情を吐露するシーンの、「俺は憎しみが足りないんだ!」という痛切な叫び。愛してしまったがゆえに、鬼になりきれない男の苦悩。
三船敏郎は、アクションを封じられたことで、逆にその魂の震えをスクリーンに焼き付けることに成功したのだ。
悪は眠り、正義は死ぬ──1960年の絶望と希望
対する悪役、副総裁の岩淵を演じる森雅之の“悪の凡庸さ”も見事と言うほかない。彼は家庭では良き父であり、エプロン姿でステーキを焼きながら娘に微笑みかける。しかし一歩書斎に入れば、部下に「死んでくれ」と電話で無表情に命じる冷酷な官僚となる。
黒澤は彼を決して怪物としては描かない。組織の論理に従い、保身のために淡々と業務を遂行する、システムの一部として描く。ハンナ・アーレントがアイヒマン裁判で指摘した“悪の凡庸さ”を、黒澤は先取りしていたのだ。
だからこそ、岩淵というキャラクターは圧倒的なまでに恐ろしい。彼は特別な悪人ではなく、日本の組織社会ならどこにでもいる、優秀なサラリーマンの成れの果てなのだから。
物語の終盤、西は岩淵を追い詰め、汚職の決定的な証拠を掴む寸前までいく。しかし、黒澤明が用意した結末は、あまりにも冷酷で、絶望的だ。 西は殺される。しかも、画面の外で、あっさりと。
彼の死体は映されない。ただ「交通事故で死んだ」という報告と、揉み消された記事だけが残る。岩淵は記者会見で「遺憾です」と頭を下げ、その後、電話の向こうのさらに巨大な権力者に対して、「はい、すべて処理しました。ご安心ください」と受話器を置き、安堵の眠りにつく。 タイトル『悪い奴ほどよく眠る』は、比喩ではない。文字通りの、ヘドが出るような現実なのだ。
1960年代の日本映画界全体を見渡すと、松本清張原作映画群や、今井正の『真昼の暗黒』(1956年)、大島渚の『日本の夜と霧』(1960年)など、社会の歪みを告発する作品が相次いでいた。
その流れの中でも『悪い奴ほどよく眠る』は、正義の敗北を描くことで、逆説的に観客の正義感に火をつける、最も危険で、最も誠実なプロパガンダ・フィルムなのである。
![悪い奴ほどよく眠る/黒澤明[DVD]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/81lNm5v1SWL._AC_SL1383_-e1758349560105.jpg)