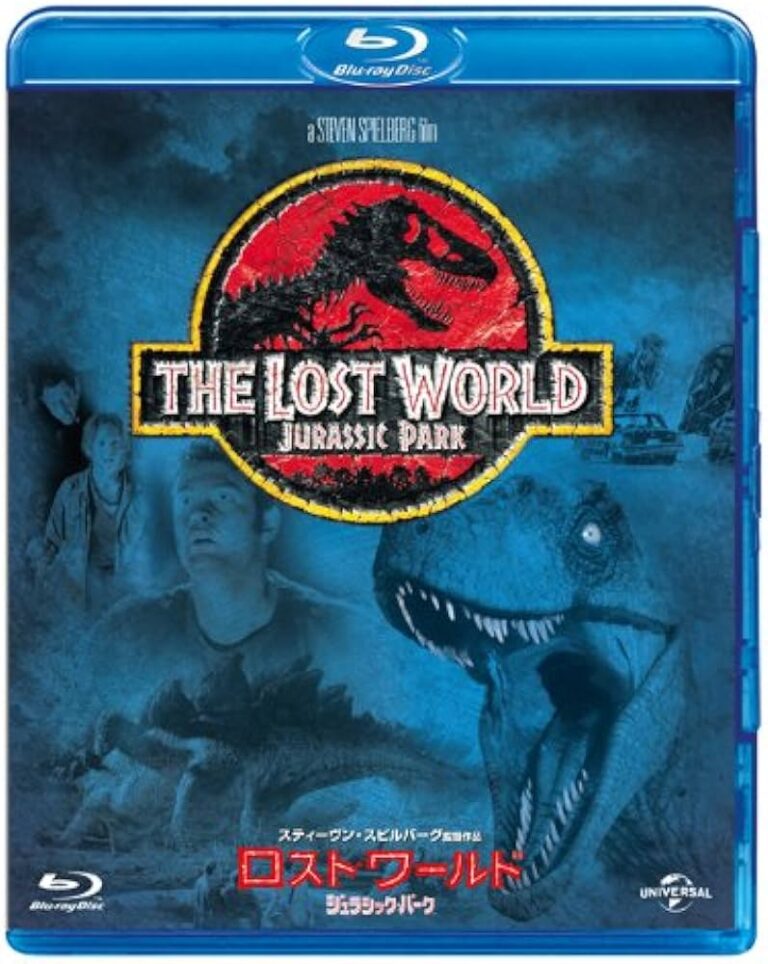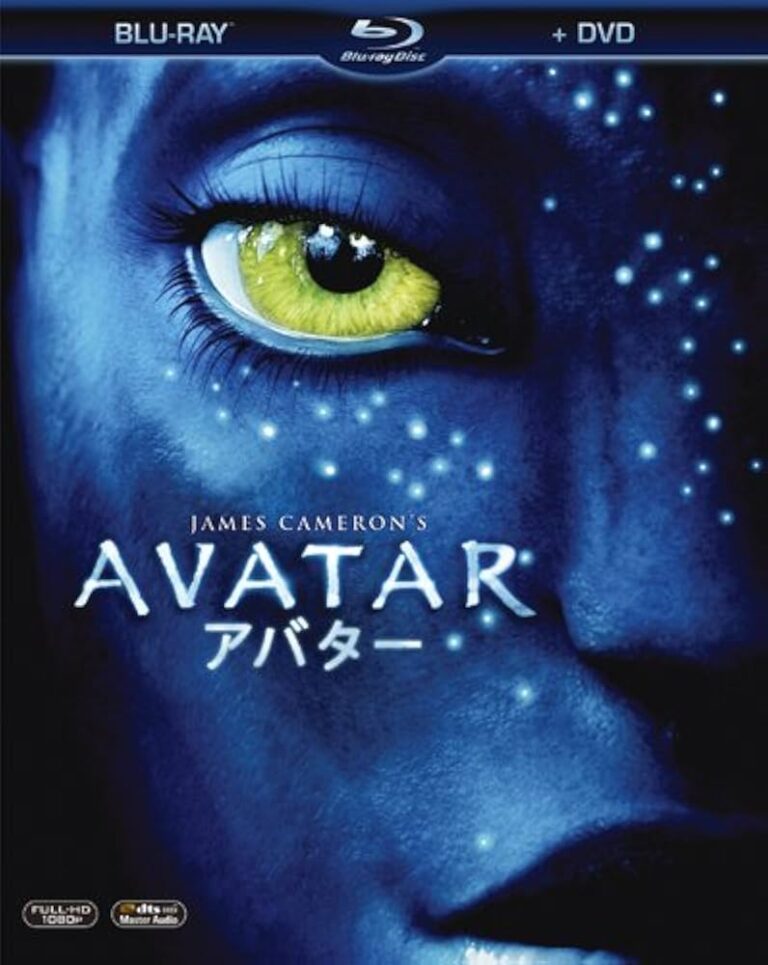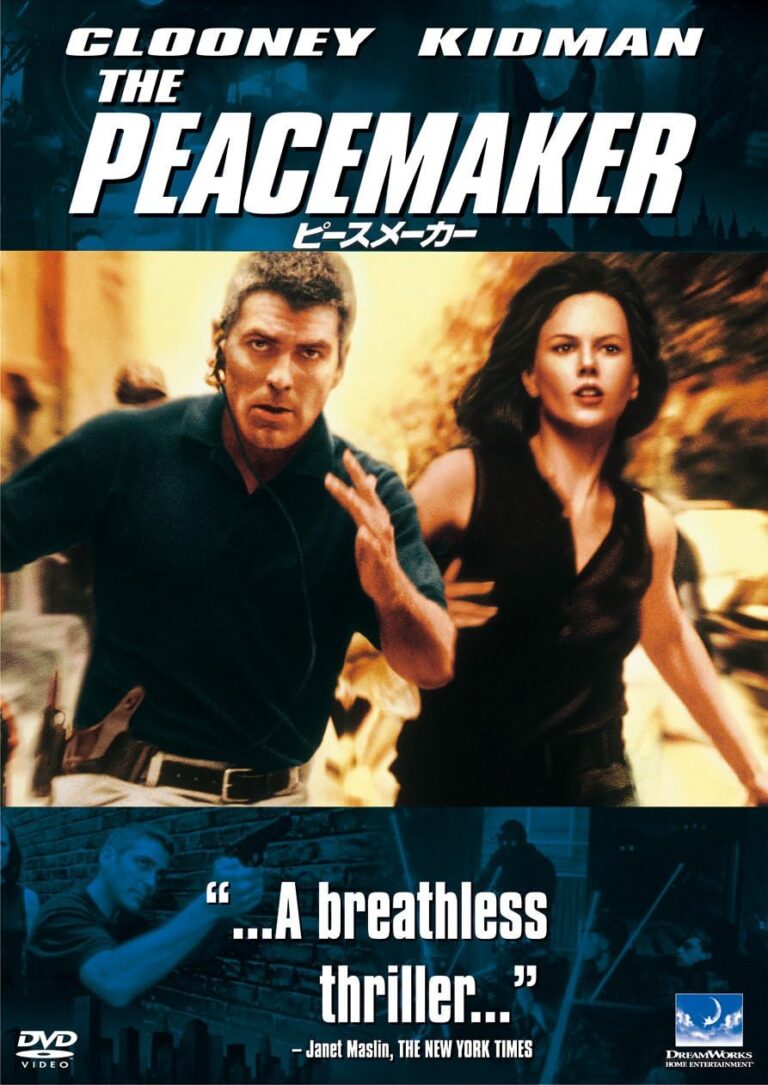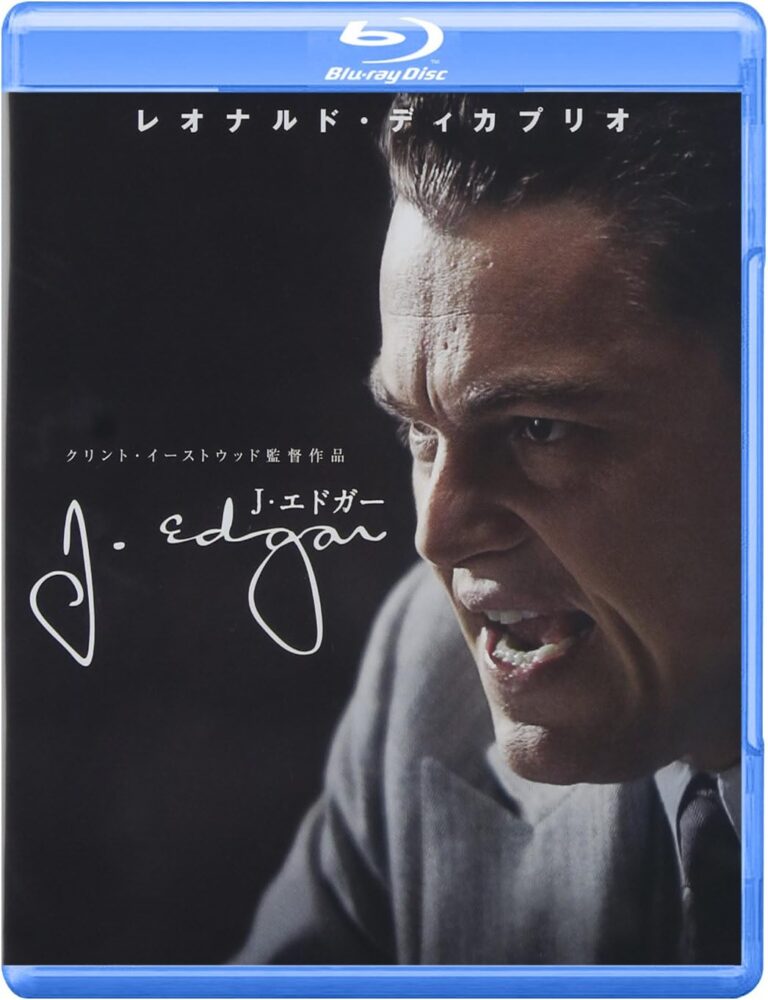『エイリアン』(1979)
映画考察・解説・レビュー
『エイリアン』(原題:Alien/1979年)は、宇宙貨物船ノストロモ号の乗組員が、未知の生命体に襲われる恐怖を描いたSFホラーである。探索チームが不時着した惑星で異形の卵を発見し、寄生生物が船内へ侵入。乗組員たちは逃げ場のない密室で、ひとりまたひとりと犠牲になっていく。
錆と油にまみれた、汚れた未来の衝撃
錆とオイルの臭いが漂う巨大な工業機械、薄暗い閉鎖空間、そして低賃金に不満を垂れ流す労働者たち。リドリー・スコット監督の『エイリアン』(1979年)は、それまでのSF映画が積み上げてきた“夢見る未来”を、強酸性の血液でドロドロに溶かし尽くし、冷徹なリアリズムで描き出した。
この映画の主役である宇宙貨物船ノストロモ号には、『2001年宇宙の旅』(1968年)のような白く輝く哲学的な回廊はない。狭く、汚く、天井からは絶えず冷却水が滴り落ち、パイプが内臓のように絡み合っている。
美術監督ロジャー・クリスチャンとロン・コッブが作り上げたこのセットデザインは、ジャンボジェットの廃材や古い爆撃機の部品を流用して作られたというが、その質感が圧倒的な生活感を生み出している。これは宇宙船というよりも、深海を漂う原子力潜水艦か、あるいは古びた石油掘削リグに近い。
そこで働く7人の乗組員たちもまた、エリートパイロットでも科学者でもない、いわゆる宇宙のトラック野郎たちだ。機関長のパーカーと機関士のブレットが交わす会話も、「ボーナスの査定はどうなる?」とか、「契約書にはこう書いてある」とか、労働条件への不満ばかり。
彼らは薄汚れた作業着を着て、タバコを吹かし、不味そうなコーヒーをすする。組織の歯車として働く労働者たちに焦点を当てた、「生活感のある未来(Used Future)」という概念こそが、本作のリアリティを支える骨格だ。
だからこそ、その日常が“異物”によって浸食されたとき、我々観客は我がことのように戦慄してしまう。彼らが直面するのは、名誉ある戦死でも英雄的な犠牲でもなく、業務中に発生した、理不尽で無慈悲な労働災害なのだから。
リドリー・スコットは、徹底した光と影のコントロールで、この閉鎖空間を“逃げ場のない檻”へと変貌させた。カメラは手持ちで揺れ動き、蒸気や点滅するライトが視界を遮る。何かがいる気配はあるが、姿は見えない。
このじっとりとした演出は、SFというよりもゴシック・ホラーの文法に近い。当時、CMディレクター出身の新鋭リドリーは、その映像感覚を既に完成させていた。
生体機械(バイオメカニカル)の性的悪夢
本作を不朽の金字塔たらしめている最大の要因、それはやはりビッグチャップ(エイリアン)というクリーチャーの造形と、それに付随する生理的な恐怖演出だろう。
スイスの変態芸術家H・R・ギーガーを、デザイナーに抜擢したリドリー・スコットと脚本家ダン・オバノンの慧眼には、今さらながら脱帽するしかない。
それまでの映画に出てくる宇宙人といえば、巨大なタコか、銀色のスーツを着た人間、あるいはゴムの着ぐるみが相場と決まっていた。しかし、ギーガーが生み出したのはバイオメカニカル(生体機械)という、有機物と無機物が融合した悪夢そのもの。
画集『ネクロノミコン』に描かれた「Necronom IV」をベースにしたその怪物は、骨格が剥き出しになったような外見、金属光沢を放つ皮膚、背中から伸びる奇妙なパイプ状の突起、そして何より目がないという異様な特徴を持っていた。
目が見えない=意思疎通が不可能という不安を観客に植え付けるこのデザインは、恐怖の象徴としてあまりにも完璧。スーツアクターには身長208cmのナイジェリア人学生、ボラジ・バデジョが起用され、その非人間的なプロポーションと動きが、着ぐるみ感を完全に消し去った。
特筆すべきは、そのライフサイクルとデザインに込められた、強烈かつ冒涜的な性的メタファーである。ここにはフロイト的な精神分析の材料が山のように転がっているのだ。
卵から飛び出し、人間の顔面に張り付くフェイスハガー。その強引な寄生のプロセスは、単なる捕食を超えた、肉体への強制的な侵入という、生理的な嫌悪感を我々に突きつける。
そして、寄生された男性乗組員ケインの体内ですくすくと育ち、食事中に腹を食い破って誕生するチェストバスターは、妊娠・出産という、生物としての根源的な不安を具現化したものと言えるだろう。
血飛沫を上げながら突き破られる胸郭、苦悶するケイン。このシーンの撮影では、出演者たちのリアクションを最大限に引き出すために、リドリー・スコットは詳細を伏せ、本物の動物の内臓を現場で使用したという。その甲斐あって、あの戦慄の表情は本物となった(サイテーな演出だけど)。
さらに成体となったエイリアンの長く伸びた頭部も、男性的なシンボルを強く連想させるフォルムをしている。ギーガーは当初、エイリアンの頭部に本物の人間の頭骨を埋め込み、さらに不気味さを増そうとしていたというが、完成した造形だけでも十分に我々の精神を侵食する。
これらは、観客の理性ではなく、無意識下に眠る原始的な本能や、生理的な恐怖のスイッチを直接押してくる。単に強い怪物が追いかけてくるのではなく、異物に内側から侵食され、個としての尊厳を脅かされる、という恐怖。
リドリー・スコットは、スクリーンという膜を通して、我々の深層心理に潜む悪夢をまさぐり回したのだ。
システムに抗う個人の孤独な戦争
エイリアンは確かに恐ろしい。凶暴で、強酸性の血液を持ち、あらゆる環境に適応する。だが、劇中の科学主任兼アンドロイド、アッシュが首だけになりながら恍惚とした表情で語るように、エイリアンは「良心や悔恨、道徳に左右されない、純粋な生物」に過ぎない。
生きるために食らい、種を残すために殺す。それは台風や地震といった自然災害と同じく、善悪を超越した存在だ。では、この映画の真のヴィランとは何者か?
それは、現場の乗組員の命よりもエイリアンの捕獲を優先させた、巨大企業ウェイランド・ユタニ社そのものである。
「乗組員は消耗品」。マザー・コンピュータが弾き出したこの冷酷な指令こそが、本作を単なるホラー映画の枠を超えた、現代社会にも通じる普遍的な寓話にしている。
我々は日常的に、企業の論理やシステムの中で生きている。利益のために安全が軽視されたり、現場の声が握りつぶされたりするニュースを見るたびに、我々はこのスペシャル・オーダー937を思い出さずにはいられない。
主人公のリプリー(シガニー・ウィーバー)は、エイリアンという生物学的脅威と戦うと同時に、人間性を排除した企業のシステムとも戦わねばならなかった。
彼女が最後にたった一人生き残ることができたのは、検疫規則を遵守しようとし、情に流されず、システムの矛盾に抗う理性を持っていたから。
当初の脚本案では、リプリーもまたエイリアンに殺され、エイリアンがリプリーの声を模倣して地球に通信を送るという、絶望的なバッドエンドも検討されていたという。しかし、リドリー・スコットらが選択した結末は、より意味深いものとなった。
リプリーが脱出シャトルでエイリアンを宇宙の彼方へ葬り去り、猫のジョーンズと共にハイパースリープに入るラストシーン。あれは、管理社会の冷酷さと不条理な暴力の双方に対する、個人の孤独な、しかし力強い勝利宣言だ。
パート2以降、アクション映画へと変貌を遂げていく本シリーズだが、第一作が持つこの“孤立無援の絶望”と“個の抵抗”というテーマの純度は、決して薄まることはない。
それは、我々が生きる現代社会の闇を、宇宙の彼方から鏡のように照らし返しているからだ。
- 原題/Alien
- 製作年/1979年
- 製作国/アメリカ
- 上映時間/SF,ホラー分
- 監督/リドリー・スコット
- 脚本/ダン・オバノン
- 製作/ゴードン・キャロル、ウォルター・ヒル、デヴィッド・ガイラー
- 製作総指揮/ロナルド・シャセット
- 撮影/デレク・ヴァンリント
- 音楽/ジェリー・ゴールドスミス
- 編集/テリー・ローリングス
- 美術/レスリー・ディリー、ロジャー・クリスチャン
- 衣装/ジョン・モロ
- SFX/ブライアン・ジョンソン
- キャラクターデザイン/H・R・ギーガー
- エイリアン(1979年/アメリカ)
- プロメテウス(2012年/アメリカ)
- エイリアン ロムルス(2024年/アメリカ)
![エイリアン/リドリー・スコット[DVD]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/51RZATQjZXL._AC_UF10001000_QL80_-e1755700564349.jpg)
![2001年宇宙の旅/スタンリー・キューブリック[DVD]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/81Qj6NhjVLL._AC_SL1500_-e1710387063181.jpg)
![ネクロノミコン 1/H.R. ギーガー[本]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/91fJ4SRPeXL._SL1500_-e1769833637907.jpg)