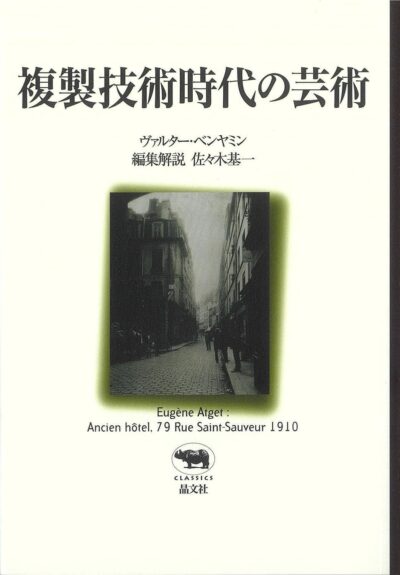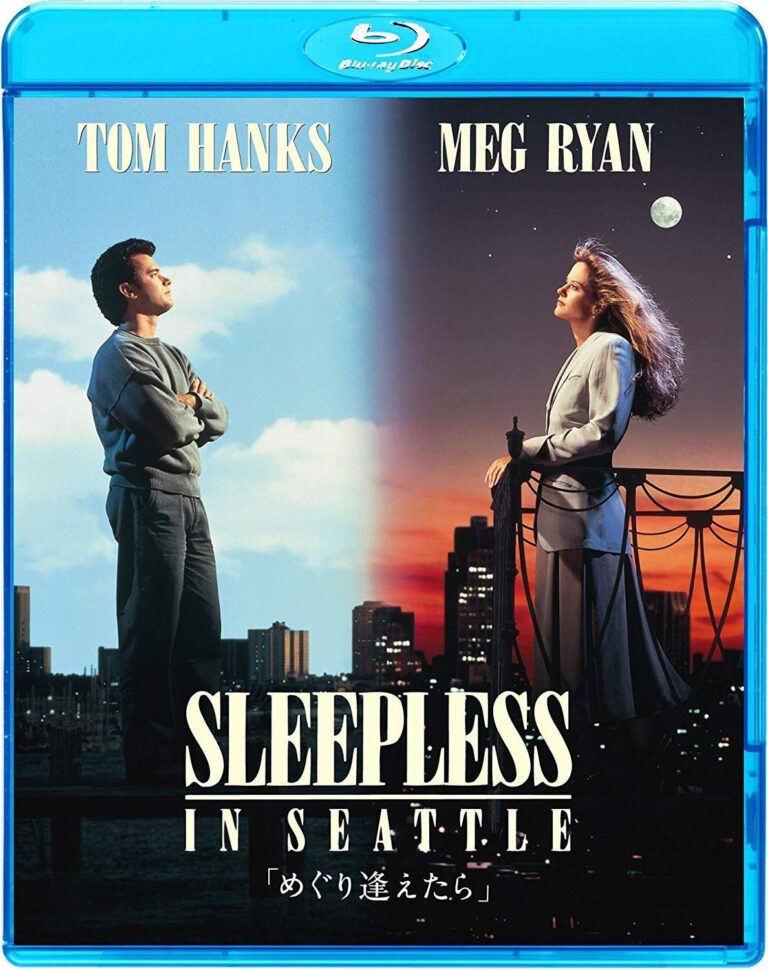『ルパン三世 カリオストロの城』(1979)
映画考察・解説・レビュー
『ルパン三世 カリオストロの城』(1979年)は、宮崎駿監督の長編デビュー作にして、日本アニメ史を変えた不朽の名作。カリオストロ公国に潜入したルパンは、秘密裏に継承される古文書の陰謀に巻き込まれながら、城に幽閉された少女クラリスと出会う。彼女を支配しようとする伯爵の野望が明らかになる中、ルパンは過去と因縁を抱えたまま、仲間たちとともに決死の作戦へ踏み出していく。
公開当時の評価と興行成績
今でこそ『ルパン三世 カリオストロの城』(1979年)は、アニメーション映画史における金字塔とされているが、公開当時の評価は必ずしも高くなかった。興行成績も前作『ルパン三世 ルパンVS複製人間』(1978年)を下回り、東宝の期待を裏切る結果に。
背景には1977年の『スター・ウォーズ』を起点とするSF映画ブームがある。日本映画界は観客動員の面でハリウッド大作に圧倒され、国内のアニメ映画も「子ども向け娯楽」か「スペクタクルSF」に二分されつつあった。
そうした市場において、浪漫的冒険譚である『カリオストロの城』はあまりにも場違い。公開当時の観客に、強いインパクトを残すことができなかった。しかし、この異質さこそが後年の再評価の契機となる。
宮崎駿のデビュー作としての意義
今さら述べるのも気が引けるが、本作は宮崎駿の長編劇場映画デビュー作である。彼は東映動画においてアニメーターとして出発し、高畑勲監督の『太陽の王子 ホルスの大冒険』(1968年)で大きく注目された。
その後、『未来少年コナン』(1978年)で確立された“宮崎アニメ”の文法――力動感に満ちたアクション、子どもと大人の狭間に立つヒーロー、理想化された少女像――は、その翌年の『カリオストロの城』において劇場映画として初めて花開く。
本作は「ルパン三世」という既存キャラクターを借りつつも、宮崎駿自身の世界観を表明する堂々たるデビュー作であり、日本アニメにおける「監督作家主義」の萌芽を象徴する作品でもある。
ルパン像の改変と「男の倫理」
最大の特徴は、ルパン像の大胆な改変だ。原作のルパンは冷酷かつハードボイルドな怪盗であったが、宮崎が描くルパンは「少女クラリスを守護する中年の理想像」として再構築されている。モンキー・パンチが「これは本当のルパンではない」と述べたのも当然だろう。
クラリスの純粋な想いを受け止めながらも決して応えないルパンの態度は、宮崎作品に繰り返し現れる「男の倫理」の原点である。『風の谷のナウシカ』(1984年)のアスベル、『天空の城ラピュタ』(1986年)のパズーなど、少女を守るヒーロー像は、この作品ですでに形を成していた。ここには自己抑制と献身を重んじる宮崎独自の男性像が投影されている。
物語構造の脆弱さと演出の力
しかし!冷静に物語構造を分析すれば、『カリオストロの城』は決して堅牢な脚本を持っているとは言えない。ルパンがカリオストロ公国を訪れる動機は冒頭では曖昧だし、クラリスに命を救われた過去が明かされるのも終盤直前。国営カジノ襲撃から結婚式阻止に至る展開も論理的必然性を欠く。
NHK『BSアニメ夜話』という番組で、評論家の唐沢俊一が「ルパンが国営カジノから盗んだ紙幣をニセ札だと一発で見破ったのに、わざわざカリオストロ公国に行く理由が分からない」と指摘したのは、まさにその通りなのである。
しかしーーここが最も重要なのだがーー観客はそれを意識しない。宮崎の演出が「作画の力」で論理を超越するからだ。押井守が指摘したように、宮崎の作劇術は「アニメーションの運動感覚によって観客を説得させてしまう」のである。
崖を駆け上がるフィアット、塔から塔へと跳ぶルパン。その非現実的な動きが観客に強烈な快感をもたらし、物語の綻びを意識させない。ここには論理ではなく「アニメーション的リアリズム」が支配している。
作画と美術の貢献
作画監督・大塚康生の存在も重要。大塚は東映動画以来、リアリズムとユーモアを融合させたアニメーションを追求し続け、宮崎の構想を確かな描線で支えた。二人の協働は『未来少年コナン』に始まり、『カリオストロの城』で頂点を迎える。
背景美術も超重要。小林七郎らの手による石造りの城や水路は、現実感と幻想性を併せ持ち、観客に「この世界に住みたい」と思わせる力を持っていた。緻密な背景と大胆なキャラクター作画が結びつくことで、物語世界の厚みが形成されている。
「作者の死」と作家主義
かつて哲学者のロラン・バルトは、1968年に発表した有名なエッセイ「作者の死(La mort de l’auteur)」において、作品の意味を支配するのは「作者」ではなく「読者」であると説いた。
従来、文学作品の解釈は「作者が何を意図したか」「作者の生涯や思想からどう読み解くか」に大きく依拠していた。たとえば「シェイクスピアは生涯こういう経験をしたから、この作品にはこういう意味がある」といった具合に。
しかしバルトはこの「作者中心主義」を批判する。彼によれば、テクストの意味は作者の意図に固定されるのではなく、むしろ言語そのものの運動、そして読者の解釈の多様性に開かれているべきだというのだ。つまり、テクストが読者の手に渡った瞬間、作者の権威は死ぬ。作品の意味を支配するのは「作者」ではなく「読者」である。これが「作者の死」という挑発的な比喩の核心である。
作品を作者の意図に還元する批評を否定したこの理論は、近代文学研究を大きく変えた。しかしアニメーション映画においては、監督の作家性が強く刻印される場合がある。『カリオストロの城』はその典型であり、商業的キャラクターであるルパンを媒介にしながら、宮崎自身の倫理観やロマン観が強烈に前面化している。
本作は、バルト的な意味での「作者の死」を拒否するほどに強烈な監督作家主義が刻印されており、日本アニメにおける「監督ブランド化」の先駆けとなったのである。
ベンヤミンの複製技術論
ここでもうひとり、偉大な哲学者を召喚してみよう。ヴァルター・ベンヤミンが1936年に発表した「複製技術時代の芸術作品」は、写真や映画といった複製技術による芸術の在り方を論じた重要なテキストだ。
ベンヤミンによれば、伝統的な芸術作品はその場その時にしか存在しない「唯一性」と「権威」、すなわち「アウラ(後光・聖性)」をまとっているという。しかし複製技術の発展によって芸術作品は大量生産され、誰もが享受可能な形で拡散される。その過程で「アウラ」は喪失するが、逆に芸術は政治的・社会的に開かれたものとなる。
この枠組みをアニメーション映画に適用すると、特に『カリオストロの城』は興味深い事例となる。なぜなら、アニメーションそのものが最初から「複製性」を前提としたメディアだからだ。フィルムはコピーされ、テレビ放送やビデオ、DVD、配信へと無限に再生される。その意味ではアニメーション映画は、最初から「アウラを欠いた芸術」として生まれているともいえる。
ところが『カリオストロの城』を鑑賞した観客は、強烈な「唯一無二の経験」を感じ取ってしまう。たとえば崖を駆け上がる小さなフィアット500の疾走感や、塔から塔へと跳躍するルパンの運動感覚。これは現実の物理法則を逸脱しているにもかかわらず、「この動きしかありえない」と観客を納得させる説得力を持っている。
この感覚は、ベンヤミン的な意味での「アウラ」と非常に近い。つまり『カリオストロの城』は、大量複製される商業アニメーションでありながら、同時に観客に一回性の体験=アウラ的経験を与えるという逆説を体現しているのだ。
アニメ的リアリズム
ここで重要になるのが「アニメ的リアリズム」という概念。実写映画が現実世界の因果律や重力といった物理法則に制約されるのに対し、アニメーションは「作画の動き」そのものに現実性を依拠している。
線の伸縮や誇張されたジャンプは、本来の物理空間では不可能だが、アニメーションの運動として提示されると説得的なリアリティを獲得する。観客はそれを不自然とは感じず、むしろ必然的な自然として受け入れる。
『カリオストロの城』におけるルパンの跳躍やカーチェイスは、現実の物理を逸脱した誇張だが、それが作画のリズムと演出の緊張感によって成立する時、観客はそこに新しい種類のリアルを見出す。つまり物理的リアリズムではなくアニメ的リアリズムである。
ベンヤミンの議論に引き寄せるなら、ここで再び「アウラ」が立ち上がっている。複製技術によって生まれたはずのアニメ映画が、逆説的に唯一無二の体験を観客に与えてしまう。この矛盾こそが『カリオストロの城』の核心的魅力なのである。
さらに言えば、この「アニメ的リアリズム」は単なる映像効果にとどまらない。物語の粗雑さや論理的飛躍をも覆い隠し、観客を納得させる装置として機能している。筋の整合性に欠ける脚本であっても、観客はそれを問題視しない。なぜなら「動き」が物語を説得してしまうからだ。
宮崎駿の演出が示すのは、物語の論理を超えた作画の論理であり、それがベンヤミン的にいう「新しいアウラ」を生み出しているといえる。
日本アニメ史における転換点
1970年代末の日本アニメーション映画は、東映動画の「子ども向け大作」と虫プロの実験的作品に二分されていた。そのなかで『カリオストロの城』は、娯楽性を備えつつ大人も鑑賞に耐える作品として、新しい地平を切り開いた。以後のジブリ作品が「家族全員が楽しめるアニメ映画」として世界的評価を獲得するのは、この作品の延長線上にある。
また、本作は「監督作家主義」の萌芽を示した点でも特筆される。テレビシリーズを基盤としながら、監督の個性を全面に押し出した劇場映画は当時まだ稀であった。宮崎駿という作家の登場は、日本アニメ文化を大きく変える契機となった。
『ルパン三世 カリオストロの城』には、「少女を守る男の倫理」があり、「飛翔」「冒険」「老獪な敵役」というジブリ的モチーフの萌芽がある。さらに「作者の死」を拒む監督作家主義の胎動があり、ベンヤミン的な複製技術時代における「アニメ的リアリズム」の可能性が提示されている。考えれば考えるほど、偉大な作品だ。
- ルパン三世 カリオストロの城(1979年/日本)
- 魔女の宅急便(1989年/日本)
- もののけ姫(1997年/日本)
- 千と千尋の神隠し(2001年/日本)
- 風立ちぬ(2013年/日本)
- ルパン三世 ルパンVS複製人間(1978年/日本)
- ルパン三世 カリオストロの城(1979年/日本)
![ルパン三世 カリオストロの城/宮崎駿[DVD]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/61Ev3ao86AL._AC_SL1000_-e1757626659843.jpg)