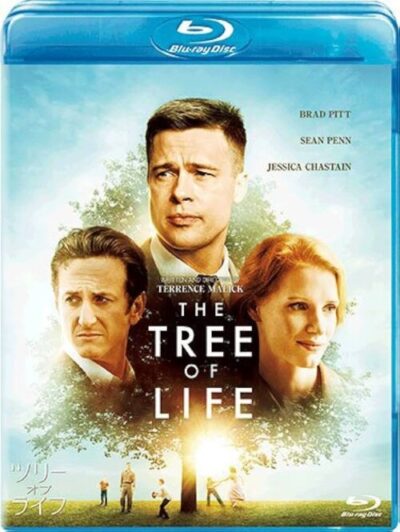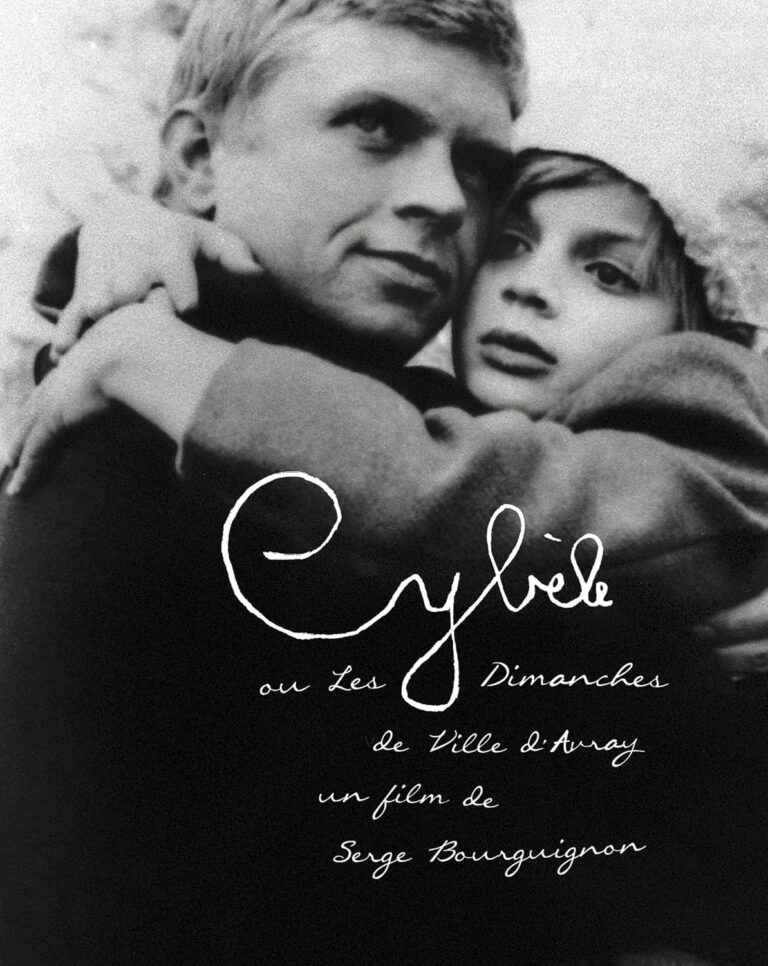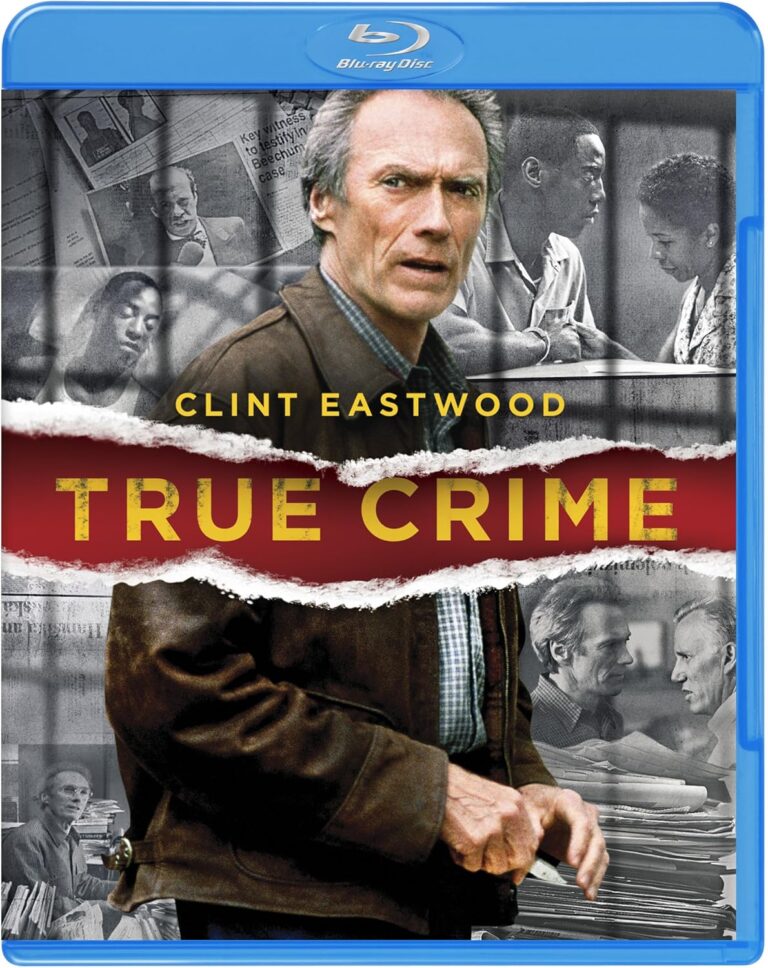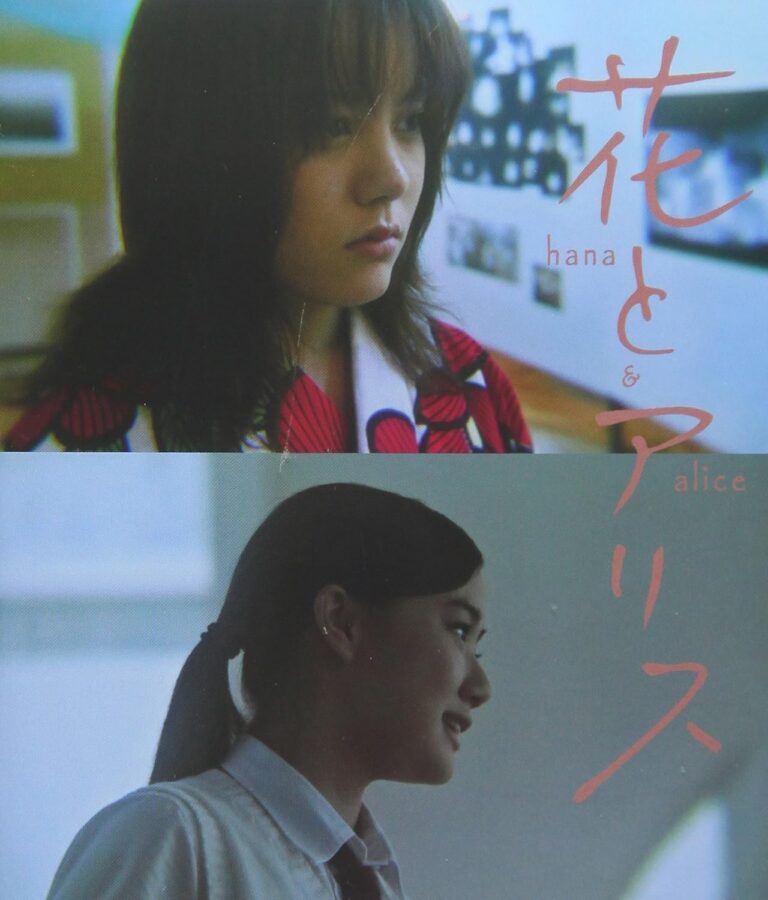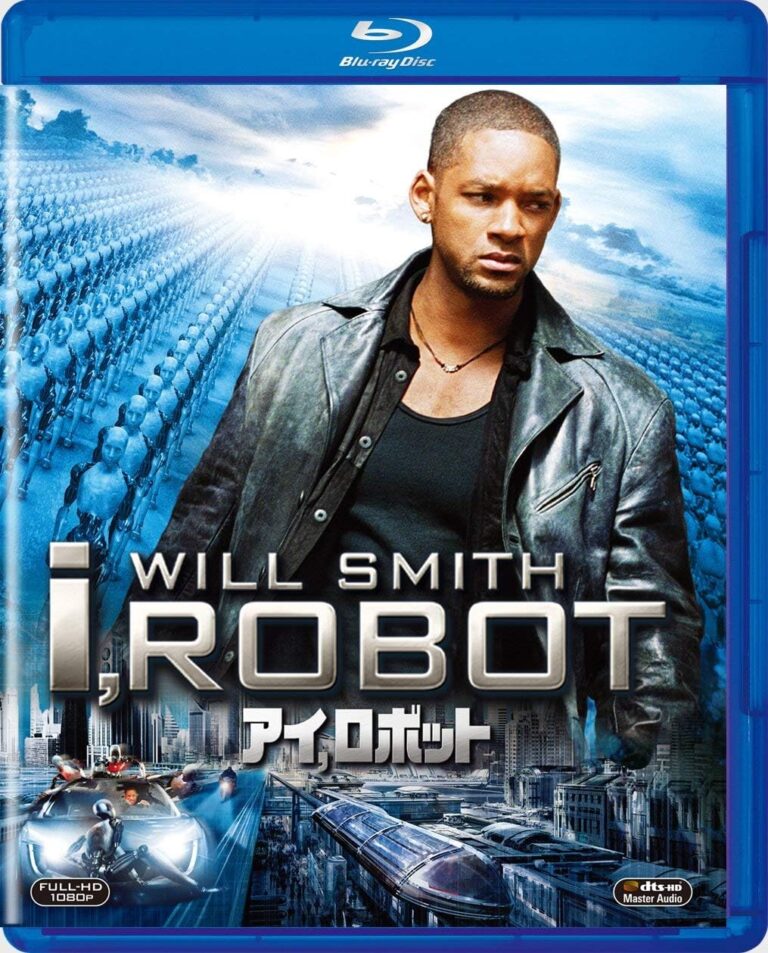『鏡の女たち』(2002)
映画考察・解説・レビュー
『鏡の女たち』(2002年)は、吉田喜重監督が14年ぶりにメガホンを取った心理ドラマ。記憶を失った女(田中好子)と、彼女を実の娘と信じる女(岡田茉莉子)、そして若い世代の娘(⼀⾊紗英)の三人が、過去と現在のあわいを彷徨う。彼女たちは“波打ち際の病院”という断片的記憶を手掛かりに広島へ向かうが、時間は進まず、記憶は反復する。母娘の断絶と「被爆の記憶」という戦後的トラウマが交錯し、映像は静止と沈黙のなかで時間そのものを失っていく。無時間性の映像が、観る者に“記憶の迷宮”を体感させる。
幽霊たちは真昼に踊り、鏡の中で時間は死ぬ
松竹ヌーヴェルヴァーグの異端児にして、映画というメディアを極限まで抽象化し続けた孤高の作家、吉田喜重。彼が『嵐が丘』以来、14年という沈黙を破ってメガホンを取ったのが、『鏡の女たち』(2002年)だ。
長い長い空白を経て、吉田喜重が我々に叩きつけたのは、皮肉にも、時間が存在しない世界。光と影、そして記憶が乱反射する、極めて美しく、そして残酷な視覚的実験室。
まず冒頭からして異様だ。死の気配が濃厚に漂う住宅街。そこにあるのは、おどろおどろしい闇ではない。暴力的なまでに降り注ぐ陽光だ。しかし、風も吹かず、音もせず、ただただ白い光が世界を包み込んでいる。
その中を、あの大女優・岡田茉莉子が日傘を差して歩いてくる。はっきりいって、生きている人間には見えない。まるで、あの世とこの世の境界線をふわふわと漂う、優雅なゴーストのようだ。
吉田喜重の映像設計は、徹底して「映画的な快楽」を拒絶する。ハリウッド映画ならここでカーチェイスの一つでも始まるところだが、本作では車が登場しても、フロントガラスには木々の緑が映り込むばかりで、運転手の顔すら映さない。
誰が運転しているかなんて、どうでもいい。移動しているという事実すら、ここでは怪しい。吉田喜重にとって、カメラとはアクションを記録する道具ではなく、“記憶”という名の亡霊を、無理やり現実に引きずり出すための降霊術の装置なのだ。
だからこそ、画面は常に静止画(タブロー)のように凝固している。この動かない絵の連続が、観客の脳内にじわじわと、真綿で首を絞めるような緊張感を生み出す。
時間は停滞し、空間は歪む。これこそが吉田マジック。映画が進んでいるようで、実は一歩も前に進んでいないという、この奇妙な浮遊感。むしろこの停滞こそが、本作のグルーヴなのだ。
「無時間性」とか「脱構築」なんて言葉を使ってしまうと、アレルギー反応を起こすかもしれないけれど、要するに、「飲み会で上司が何度も同じ昔話をするループ地獄」の高尚なバージョンだと思えばいい。
時間は直線的に進まず、過去と現在がごちゃ混ぜになり、終わったはずの話が何度も蒸し返される。吉田喜重は、映画という「時間を操る機械」を使って、この終わらない悪夢を芸術的に再現しているだけなのだ。
通常の映画が「A地点からB地点へ行く冒険」だとしたら、吉田映画は「A地点の周りをグルグル回りながら、地面に穴を掘り続ける行為」に近い。
深く、深く、どこまでも深く。その穴の底に何があるのか、それを見届けるのが、我々観客の使命なのである。
噛み合わない三人の女たちと、暴力的な歴史の継承
物語の構造もまた、とてつもなく歪んでいる。記憶を失った女・田中好子と、彼女を「生き別れの娘だ」と信じ込む岡田茉莉子。そして、田中好子の娘である一色紗英。この三世代の女優陣の組み合わせだけで、もう何かが起こりそうな予感がビンビンする。
特に岡田茉莉子の圧がすごい。彼女は、娘を失った悲しみによって時間が止まってしまった女性だ。その空っぽになった心の穴を埋めるために、記憶喪失の田中好子という“器”に、自分の都合のいい過去を注ぎ込もうとする。
これはもはや愛ではない。記憶の強制であり、精神的な侵略行為だ。「あなたは私の娘なのよ」と囁くその姿は、ホラー映画のモンスターよりも恐ろしい。過去を共有することで歴史を再生しようとするその執念は、他者の現在を踏みにじる暴力そのものだ。
田中好子演じる女は、かすかな記憶の断片――波打ち際の病院というイメージ――だけを頼りに、岡田茉莉子、一色紗英とともに広島へと向かう。
ロードムービーの形を取ってはいるが、これもまた通常の旅ではない。彼女たちが向かっているのは地理的な場所ではなく、過去という到達不可能な幻影なのだ。
田中好子が必死の形相で「DNA検査をしてください!」と懇願するシーンがあるが、ここには現代人の悲痛な叫びが込められている。「私が誰なのか、科学的に証明してくれ!」と。
彼女が求めているのは、岡田茉莉子の物語の一部になることではない。「現在における自分の居場所」を確保することだ。しかし、吉田喜重はそんな安易な解決を許さない。DNAという客観的な事実よりも、「信じたい記憶」という主観的な虚構の方が、この世界では遥かに重い質量を持っているからだ。
ここで広島という舞台装置が、物語に重層的な意味を与え始める。この地は、我々日本人にとって被爆という巨大なトラウマの象徴だ。
岡田茉莉子が語る被爆の過去。だがその話は、あくまで他人の物語であり、共有不可能な痛みでしかない。ここで吉田喜重が突きつけるのは、「戦争を知らない世代に、戦争の記憶は継承できるのか?」という、戦後日本が抱え続ける巨大な問いかけだ。
教科書で読んだ歴史は、個人の皮膚感覚としての記憶にはなり得ない。吉田喜重は、この残酷な断絶を、感動ドラマにするのではなく、冷徹な外科医のような手つきで解剖してみせる。
記憶とは、リレーのバトンのように綺麗に手渡せるものではない。語るたびに形を変え、受け取る側の解釈で歪められていく、伝言ゲームのようなものなのだ。
『鏡の女たち』に出てくる「鏡」とは、過去を歪曲し、見る者の願望を投影してしまう“魔鏡”。三人の女たちは、互いに異なる方向を見つめながら、決して交わらない視線を投げかけ合う。この不協和音こそが、映画全体を支配するスリリングな緊張感の正体なのだ。
終わらない終わりに取り残される快感
物語は終盤、解決に向かうどころか、迷宮の最深部へと迷い込んでいく。三人の旅は、まさかの出口のない循環へと着地する。
時間は進まず、記憶はメリーゴーランドのように回転し、登場人物たちは同じ場所を何度も何度も歩き続ける。戸惑う観客を置き去りにして、映画は静かに、しかし断固として結末を拒絶する。
これぞ、吉田イズムの真骨頂。彼の映画では、終わりすらも一つの通過点に過ぎない。すべては永遠に繰り返される、ニーチェ的永劫回帰の地獄絵図、あるいは天国なのだ。
吉田喜重にとって、映画とは時間を疑うためのメディウム(媒介)なのだろう。我々が普段当たり前のように信じている「昨日、今日、明日」という直線の時間は、実は幻想であることを、知り尽くしている。
『鏡の女たち』は、その問いを極限まで純化させた結晶だ。無時間性の真っ白な光の中で、人は誰かを愛そうとし、誰かを失い、そしてまた同じ記憶の回廊を歩き出す。岡田茉莉子が鏡の前で立ち尽くすとき、我々観客もまた、スクリーンの前で立ち尽くすことになる。
なぜなら、その鏡に映っているのは、過去に囚われた彼女の姿であると同時に、映画という虚構を見つめる「私たち自身の亡霊のような姿」でもあるからだ。
この映画は、出口のないゴールに向かって全力疾走し続けるようなものだ。時間の牢獄に囚われた人間の姿を描く寓話でありながら、その映像の美しさは、逆説的に我々を解放する。
物語の整合性や論理的な解決を求める左脳的な思考を停止させ、ただただ「映像と音の奔流」に身を任せる快感。理解することなんて、この圧倒的な映像体験の前では些細なことだ。我々はただ、吉田喜重が仕掛けた鏡の迷宮の中で、心地よいめまいに身を委ねればいいのだから。