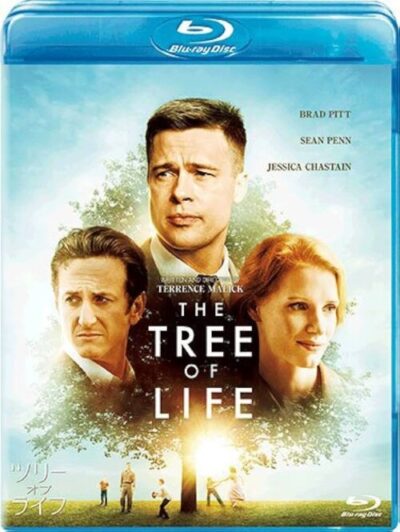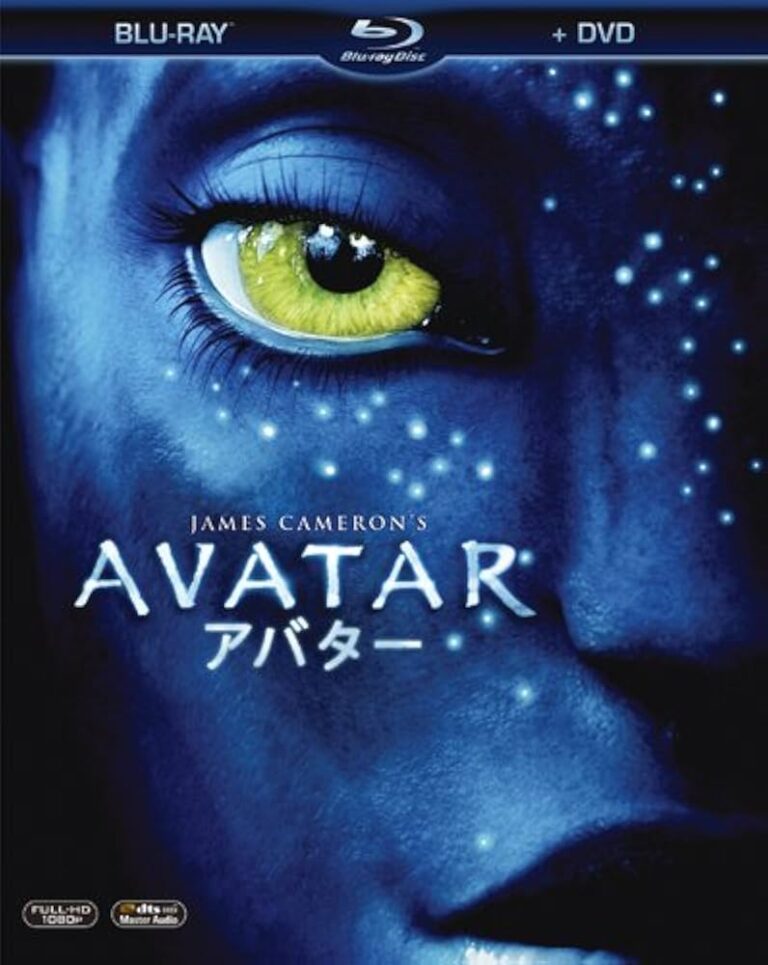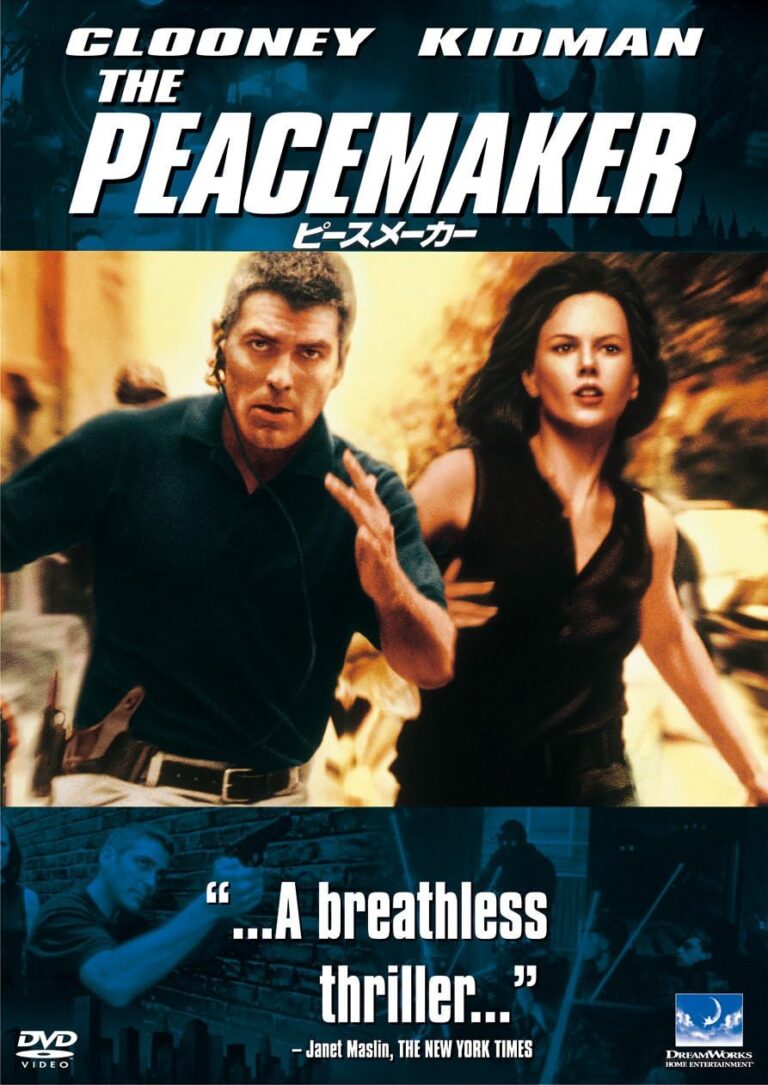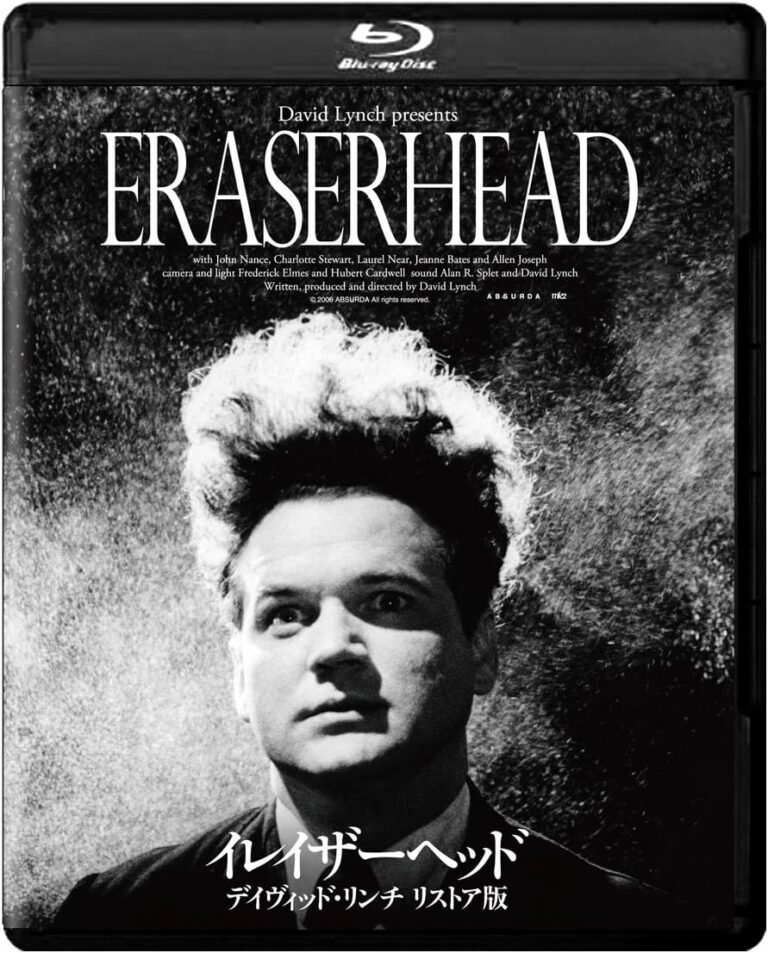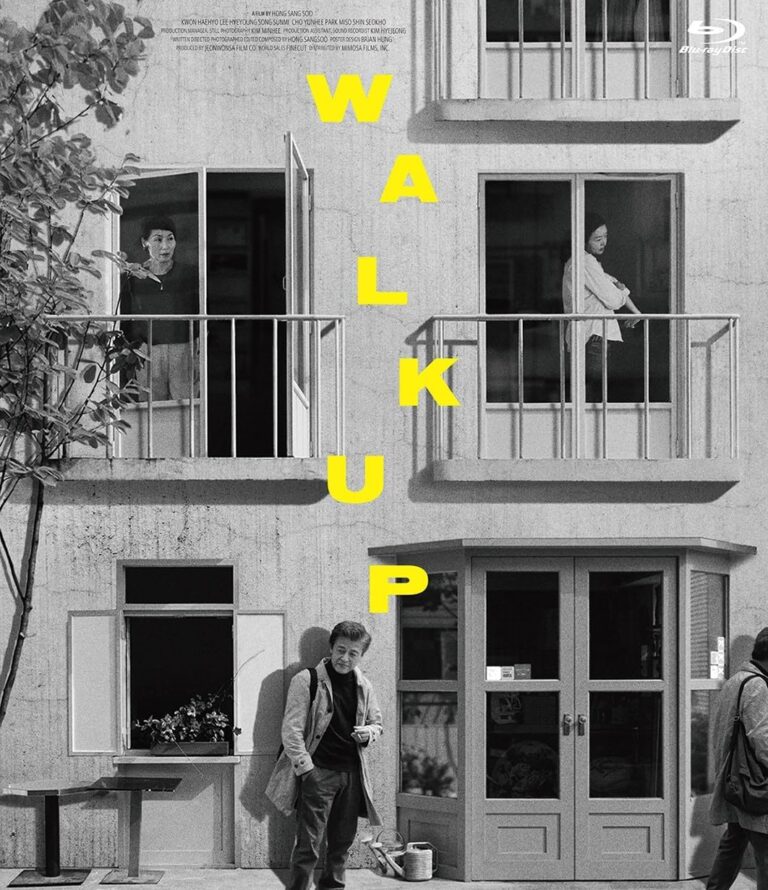『おとうと』(1960)
映画考察・解説・レビュー
『おとうと』(1960年)は、市川崑監督が脚本・水木洋子、撮影・宮川一夫と組み、幸田文の原作を映画化した傑作。銀残しによる淡い光の中で、姉弟の愛と断絶を冷ややかに描く。岸恵子、川口浩、田中絹代の演技が、感情の表出を抑えた“祈りのような演出”の中で静かに響く。家族という閉鎖系を通して、市川崑が到達した“禁欲と倫理”のモダニズムを体現する作品である。
「銀残し」という禁じ手が暴いた、大正の闇と姉弟の血
市川崑という男は、単なる映像の魔術師ではない。彼は、観客の網膜に「時代の記憶」を直接叩き込むテロリストである。
『おとうと』(1960年)を語る上で絶対に外せないのが、日本映画の光学史を根底から覆した技法「銀残し」だ。市川は撮影監督の宮川一夫に「カラーなのにモノクロに見える、そんなデタラメな映像が欲しい」と要求したという。
宮川は当初、現像所のスタッフと共に「そんな無茶な」と頭を抱えたが、現像工程で本来除去すべき銀粒子をあえて残すという、当時の常識では考えられない「タブー」を犯すことで、あの淡い灰銀のトーンを生み出した。
この技法がもたらしたのは、単なる渋い色調ではない。画面に残された銀の粒子は、光を乱反射させ、影の領域に「泥のような重み」を与える。これによって、大正時代の重苦しい空気感、そして閉鎖的な家庭内に漂う「死の予感」が、物理的な質感として立ち上がった。
原作者の幸田文は試写の暗闇で、「父(露伴)の書斎の匂いがする」と漏らしたという。鼻腔を突くような古い紙とインク、そして病室の薬品の匂い。視覚が嗅覚を刺激するほどの圧倒的な情報密度。
この色彩の抹殺は、デヴィッド・フィンチャーの『セブン』が都会の腐敗を描くためにこの技法を「再発見」する35年も前に、市川と宮川によって完成されていたのだ。
この映像美は、記憶の底に沈んでいた姉弟の愛憎を、銀の粒子という名の「時間の残骸」に変えてスクリーンにぶちまける、残酷なまでの芸術的暴力なのである。
姉弟のリボンが結ぶ、残酷すぎる依存の迷宮
物語は、しっかり者の姉・げん(岸恵子)と、不良少年として疎まれる弟・碧郎(川口浩)の愛を描く。だが、市川崑が撮ったのは、巷に溢れる安っぽい「家族愛」などではない。そこにあるのは、互いの存在なしでは呼吸さえままならない、非対称で暴力的なまでの「依存の構造」だ。
岸恵子はこの役を演じる際、市川から「女であることを捨てろ、だが女の情念で弟を包め」という、俳優の精神を破壊しかねない矛盾したディレクションを受けたという。
その極致が、病床の弟と自分の手首をリボンで結び合うあの伝説的なシーン。直接的な肉体の接触をあえて避け、一本の布切れに全ての情念を託す演出。それは一見、献身的な純愛に見えるが、その実体は「愛という名の監禁」。
姉のげんにとって、碧郎を守ることは自らのアイデンティティを維持する唯一の手段であり、彼女は無意識のうちに弟を「未熟な存在」という檻に閉じ込め続けている。
川口浩演じる碧郎が、姉の愛に救われながらも、時折見せる「やりきれない」という表情。それは、独立した個体として認められないことへの、魂の悲鳴なのだ。
市川崑は、家族という閉鎖系の中に潜む「愛情の毒性」を、冷徹な設計図で描き出した。彼らが結び合ったリボンは、絆であると同時に、互いの首を絞め合う絞首刑のロープでもあったのである。
『黒い十人の女』へと至る、美しき人間不信の美学
ここで、市川崑のもう一つの顔、冷徹な人間観察者としての真髄に触れないわけにはいかない。
『おとうと』で見せた映像の禁欲主義は、翌年の傑作『黒い十人の女』において、さらに研ぎ澄まされた「虚無的な笑い」へと進化を遂げる。市川は人間を「愛すべき存在」としてではなく、完璧な構図の中に配置されるべき「滑稽なパーツ」のように捉えていたのではないか。
『おとうと』の姉弟がリボンで結び合っていたように、市川の描く人間関係は常に「糸」で繋がっている。だがその糸を操っているのは、愛ではなく、抗い難い「構造」だ。
『黒い十人の女』では、一人の男を巡る十人の女たちが、殺意という名の糸で繋がれ、市川の完璧な演出によって美しく、かつ無残に踊らされる。
市川にとって、家族も不倫も、すべては銀残しの暗闇の中に浮かび上がる「絶望的なパワーゲーム」に過ぎない。彼は宮川一夫という最強のパートナーを得ることで、人間のドロドロとした感情を「幾何学的な様式」へと昇華させることに成功した。
この冷笑的な視点、そして人間を突き放す冷たさこそが、市川モダニズムの真骨頂であり、観る者がその「美しき地獄」から目を離せない理由なのである。
田中絹代が体現した、涙を許さない冷徹なモダニズムの倫理
本作で最も異様な、そして最も恐ろしい存在。それは田中絹代が演じる母親だ。片足を引きずり、信仰の世界へ逃避し、祈りの中で現実の家族を拒絶する。
日本映画界の至宝・田中絹代は、この「無機質な母」を演じるために、自身の代名詞であった「情愛」を完全に剥ぎ取られた。市川は制作にあたり「お客には一滴の涙も流させるまじ」と宣言し、現場で少しでも情緒に流されようとする俳優を、それこそ銀残しのトーンのように冷たく制止し続けたという。
母が神に祈る姿は、慈愛の象徴ではなく、もはや狂信に近い「他者への拒絶」として機能している。この冷徹な演出こそが、本作を安っぽいお涙頂戴のメロドラマから救い出し、不朽の芸術へと押し上げた。
感情を直接提示することは、観客の想像力を奪う暴力である──この市川のモダニズム倫理は、物語よりも光、言葉よりも構図を優先させる。
碧郎が吐き出す「うっすらと哀しい」という台詞さえ、完璧に制御された映像文法の中では、唯一の「詩的な破綻」として生身の人間の体温を感じさせるための、計算された歪みとして機能する。
1950年代の古臭い感傷主義を葬り去り、60年代の理性と形式の時代を切り開いた市川崑。そのラストに残るのは、もはや涙ではなく、銀の光が滲むフィルムのざらついた感触だ。
そのざらつきこそ、僕たちが忘れてはならない「時代の記憶」であり、愛という名の呪縛の中で生きる人間の、最後の抵抗の跡なのである。
![おとうと/市川崑[DVD]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/6c1c1e26-a030-4f05-aac9-abca0e4a42b8-e1760058864675.jpg)