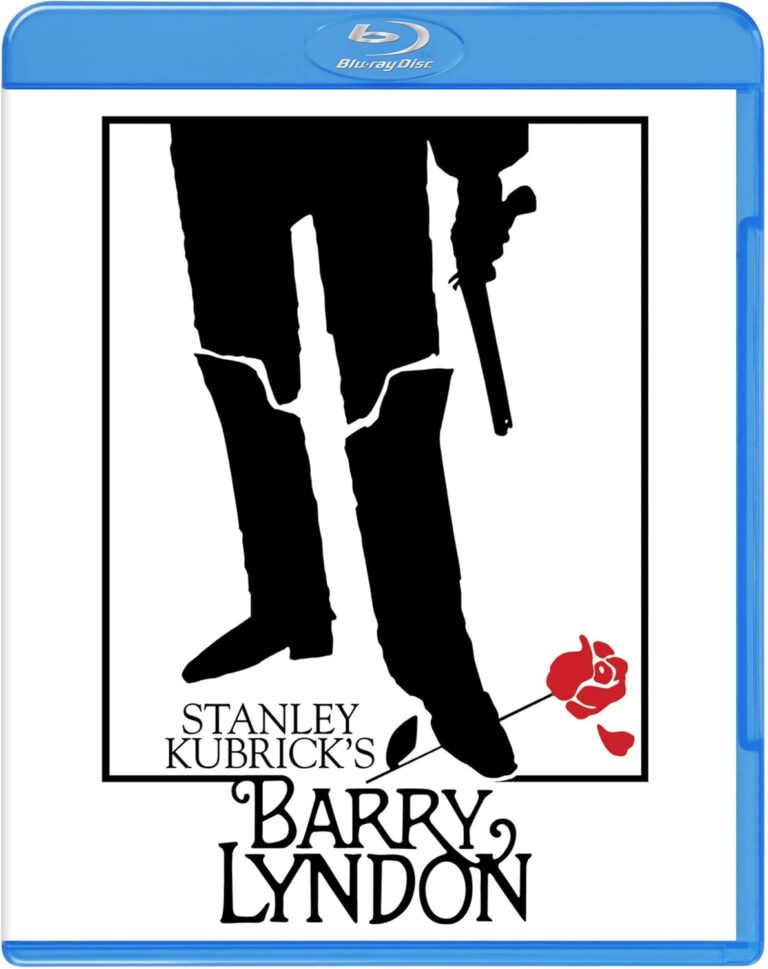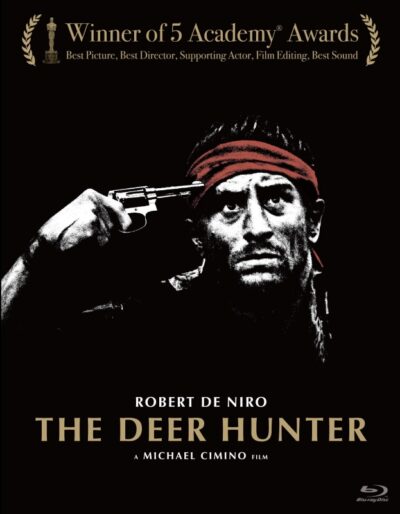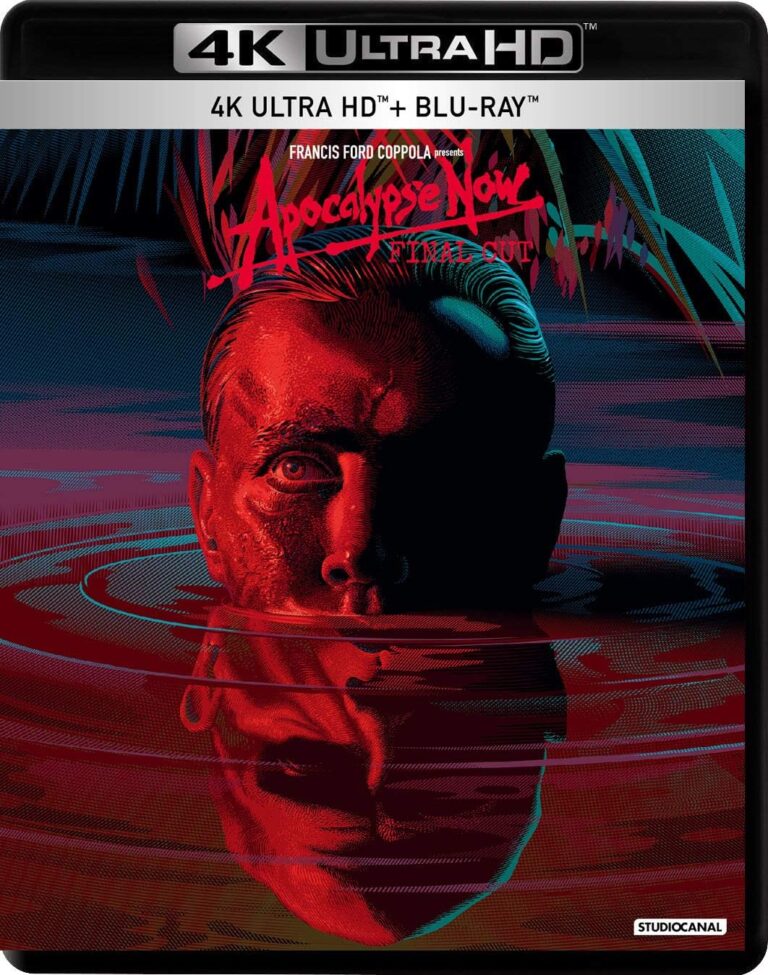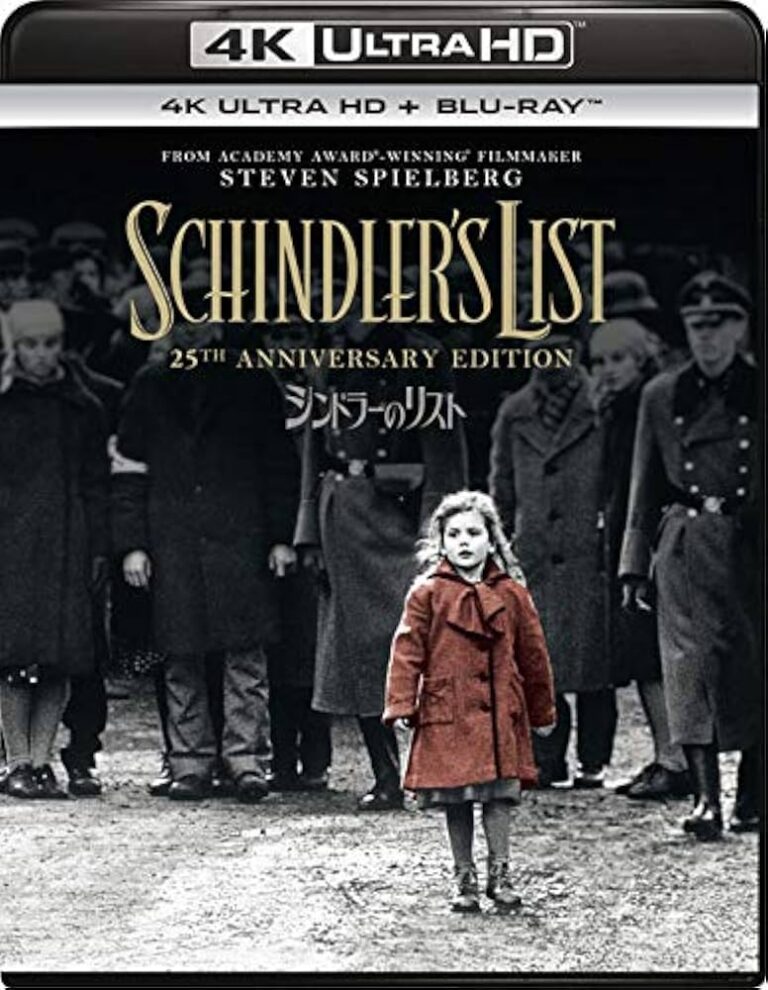『突撃』──若きキューブリックはなぜ正義を信じたのか?
『突撃』(原題:Paths of Glory/1957年)は、フランス軍上層部の命令により、無謀な突撃を強いられる兵士たちを描くキューブリック初期の反戦映画。軍の論理と個人の倫理の対立を軸に、カーク・ダグラスが理想と現実のはざまで苦悩する姿を描く。横移動カメラによる戦場描写と冷徹な構図が、彼の後年の作風を予感させる。
『栄光の小径』をもとにした反戦映画
『現金に体を張れ』(1956年)でスタンリー・キューブリックと共同でシナリオを手がけたジム・トンプソンは、完成したクレジットに「脚本/スタンリー・キューブリック、追加台詞/ジム・トンプソン」と記載されているのを見て愕然としたという。自らの功績が軽んじられた扱いにショックを受けたのだ。
シナリオの功績を一人占めしてしまうあたり、キューブリックの陰険さと高慢さが垣間見える。カーク・ダグラスから「才能あるクソッタレ野郎」と呼ばれた男らしいエピソードだ。
完全に裏切られたトンプソンだったが、それでも次回作『突撃』(1957年)に再び参加したのは、極貧ゆえ金のため。生前の彼は酒と困窮にまみれ、後に暗黒小説の巨人として再評価されるとは夢にも思っていなかった。キューブリックはその境遇を計算高く利用したのだろう。
『突撃』の原作は、ハンフリー・コッブの反戦小説『栄光の小径』。第一次世界大戦時、3人の兵士が無理な作戦の責任を押しつけられ銃殺刑となった実話をベースにしている。当初はツヴァイク『燃える秘密』の映画化が進んでいたが、MGMの経営不振で頓挫。そこで、14歳のときにこの小説を読んで衝撃を受けたキューブリックが映画化を決断した。
異質でストレートなキューブリック作品
こうして完成した『突撃』は、彼のフィルモグラフィーの中でも異質だ。皮肉や冷笑ではなく、真っ直ぐな理想主義で描かれた反戦映画。国家のメンツのために兵士が犠牲になるという不条理を正面から問いかけるディスカッション・ドラマとして成立している。初見時、「本当にキューブリックが撮ったのか?」と驚く観客も多いだろう。
とはいえ、丹念に観れば確かに「キューブリック印」が刻まれている。ドイツ軍の要塞「アリ塚」を横移動カメラで捉えた突撃シーンのダイナミズム。銃殺を控えた兵士が牧師に「性欲がなくなった」と嗚咽するブラックなユーモア。
さらには死刑囚の最後の晩餐で、何度もテイクを重ねすぎて俳優がマジ切れしたという逸話まで残っている。完全主義的演出もすでに芽を見せていた。
キューブリックイズムの萌芽
美学的・冷徹・嘲笑的と評される後年の作風からは想像しがたいが、この作品にはその萌芽が確かにある。理想主義と反戦メッセージの背後に、徹底した構図設計、冷酷な演出術、そしてユーモア感覚が潜んでいるのだ。我々キューブリック・ファンにとって、『突撃』はその始まりを目撃する作品でもある。
最後に余談をひとつ。酒場で歌を披露するドイツ人歌手を演じたスザンヌ・クリスチャンは、のちにキューブリックの妻となった。作品づくりにおいても私生活においても、彼の完璧主義は一切の隙を見せない。映画制作のただ中で、人生の伴侶をも見つけてしまうあたり、さすがはスタンリー・キューブリックである。
- 監督/スタンリー・キューブリック
- 脚本/スタンリー・キューブリック、カルダー・ウィリンガム、ジム・トンプソン
- 製作/ジェームズ・B・ハリス
- 原作/ハンフリー・コッブ
- 撮影/ゲオルグ・クラウゼ
- 音楽/ジェラルド・フリード
- 編集/エヴァ・クロール
- 美術/ルートヴィヒ・ライバー
- 現金に体を張れ(1956年/アメリカ)
- 突撃(1957年/アメリカ)
- スパルタカス(1960年/アメリカ)
- 時計じかけのオレンジ(1971年/イギリス)
- バリー・リンドン(1975年/イギリス、アメリカ)
![突撃/スタンリー・キューブリック[DVD]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/81auf-tK4pL._AC_SL1500_-e1757476822383.jpg)