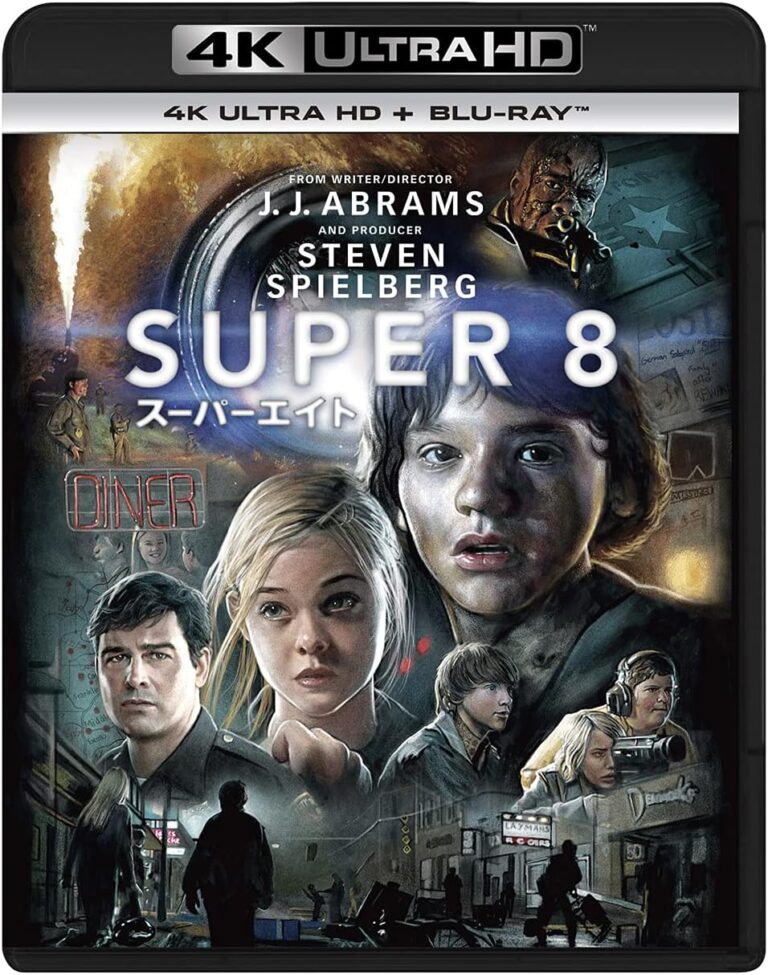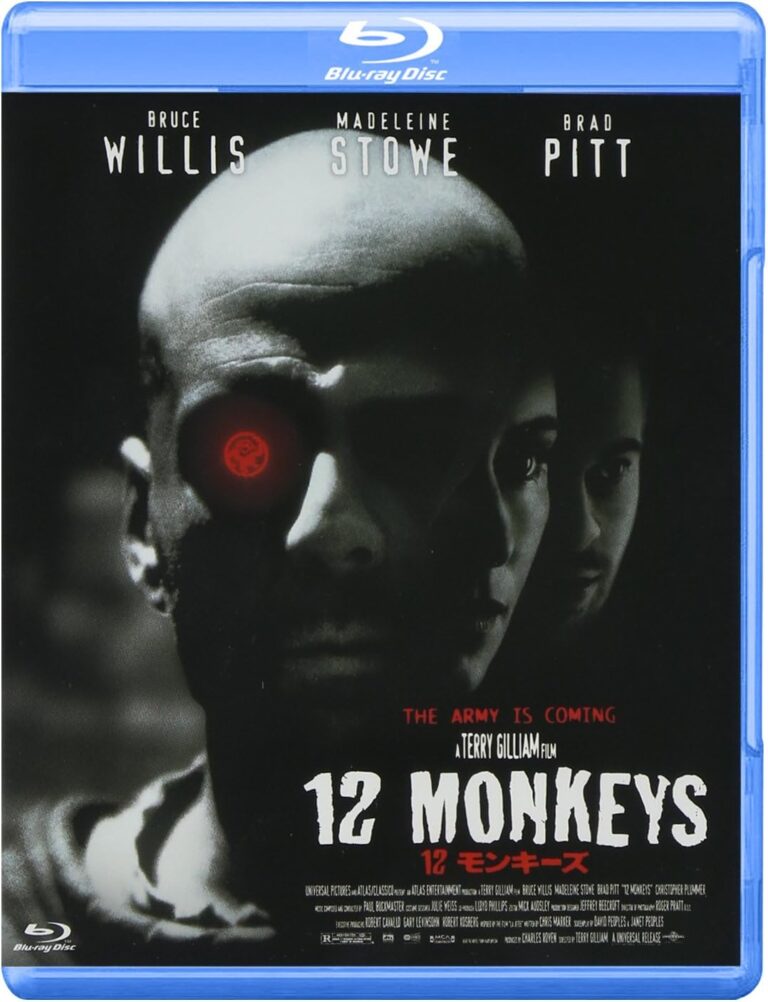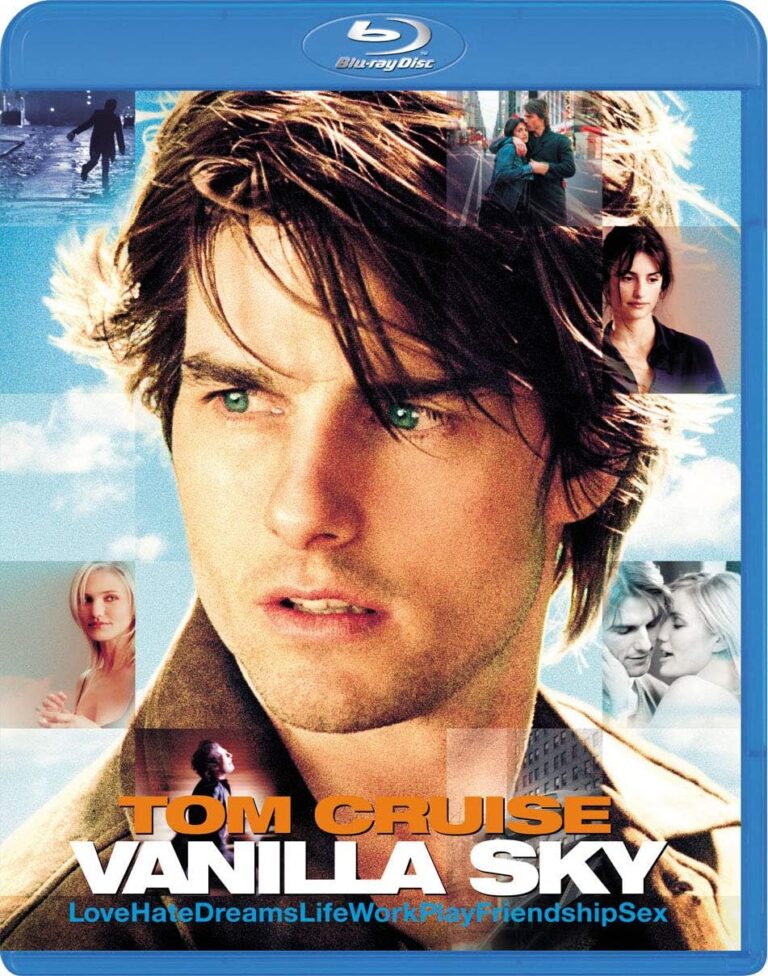『リアル・スティール』(2011)
映画考察・解説・レビュー
『リアル・スティール』(原題:Real Steel/2011年)は、リチャード・マシスン原作の短編を映画化したSFドラマ。衰退した人間ボクシングの代わりにロボット同士が殴り合う近未来を舞台に、かつてのプロボクサーであるチャーリーと、疎遠だった息子マックスの父子が、一体の旧型ロボット〈アトム〉を通じて絆を結び直していく物語だ。過酷な競技世界での挑戦と家族再生のドラマが重なり、80年代父性映画の感触を現代的にアップデート。古典的モチーフと最新VFXが共鳴し、アトムの成長物語が父子の変化を映し返す異色の感動作となっている。
オールドスクールな手触りを纏った近未来SF
想像に反して『リアル・スティール』(2011年)は、古き良きアメリカ映画の匂いを放つ、オールドスクールな作品であった。リチャード・マシスンによる原作『四角い墓場』が1956年に発表されたことを踏まえれば、その源流が半世紀以上前にさかのぼるのも納得である。
時代設定こそ2020年という近未来だが、フルCGで描かれるロボット・ボクシングのスペクタクルの背後には、クラシカルなアメリカ映画のお約束が幾重にも張り巡らされている。そのため観客は新鮮さよりも懐かしさ、既視感を抱きながら物語に引き込まれていく。
この作品をひとことで表すなら「未来を舞台にした過去の映画の総合カタログ」。ハリウッドが積み重ねてきた父子ドラマやボクシング映画の文脈を巧みに再利用しつつ、最新VFXによってアップデートした映画なのである。
リチャード・マシスンと1950年代アメリカの影
原作小説『四角い墓場』を書いたリチャード・マシスンは、ホラーやSFの分野で独自の地位を築いた作家だ。冷戦期のアメリカにおいて、科学技術の発展に伴う恐怖や、人間と機械の関係性を先鋭的に描いた。その作品群は、テレビシリーズ『トワイライト・ゾーン』やスティーヴン・キングら後進の作家に強い影響を与えている。
1950年代という時代は、テレビの普及やロックンロールの誕生に象徴されるように、大衆文化が爆発的に花開いた時代だった。『四角い墓場』の「人間に代わってロボットが戦うボクシング」という設定には、労働力の機械化や冷戦下の軍拡競争といった社会的背景が色濃く反映されている。そうした古層を持つ物語を2010年代にリメイクした時点で、作品がオールドスクールな肌触りを帯びるのは必然ともいえる。
父と子の再生劇としての『リアル・スティール』
物語の中心は、ダメ親父チャーリー・ケントン(ヒュー・ジャックマン)と息子マックス(ダコタ・ゴヨ)の交流。二人のぎこちない関係が、旧式ロボットATOMを通じて修復されていくプロセスは、80年代以降の「父性の再生」をテーマにしたアメリカ映画の系譜に連なる。
たとえば『クレイマー、クレイマー』(1979年)は、離婚を契機に父が子育てに向き合う姿を描いた名作だったし、『フィールド・オブ・ドリームス』(1989年)は野球を介して父と息子が再会する物語だった。
『リアル・スティール』は、ボクシングという肉体的でシンボリックな舞台を選ぶことで、「父親が失った夢を子どもと共に取り戻す」という普遍的なテーマを鮮烈に可視化している。
ATOMは単なる格闘マシンではない。父の愛を知らずに育ったマックスにとってATOMは代理父であり、栄光を失ったチャーリーにとってはかつての自分を投影できる存在でもある。つまりATOMは、父と子を媒介する「もうひとりの家族」なのだ。
このあたりは、ショーン・レヴィの作家性ともリンクしている。『ナイト ミュージアム』(2006年)やNetflixの『ストレンジャー・シングス』で知られるように、彼は「家族的な温もり」と「ファンタジー性」を掛け合わせるのが得意。単なるロボット格闘アクションにせず、親子和解のドラマとして着地させたのはレヴィならではの演出といえる。
もし本作をマックGが監督していたら、無意味にセクシーなカットが連発されただろう。だがレヴィはむしろ「感情移入できる家族の物語」として整えてみせた。その選択が結果的に作品の普遍性を担保している。
ロッキーからあしたのジョーへ──ボクシング映画の記憶
無名ロボットのATOMが王者ゼウスに挑戦する図式は、どうしたって『ロッキー』(1976年)を想起させる。倒れても倒れても立ち上がるATOMの姿は、ロッキー・バルボアと重ね合わされるし、試合後にチャーリーが恋人ベイリー(エヴァンジェリン・リリー)と抱き合う場面には「エイドリアーン!!」という叫びが脳内再生される。
さらに日本的視点で見れば、貧乏親子が金持ちに挑む構図は『あしたのジョー』に近い。マネージャー的立場のチャーリーは丹下段平、息子のマックスは矢吹丈、そしてライバル役のファラ(オルガ・フォンダ)は白木葉子に対応する。アメリカ映画でありながら、日本のボクシング漫画を彷彿とさせるのも面白い。
アメリカン・ロボット像とジャパニーズ・ロボット像がはっきり異なるのも興味深し。日本では『鉄腕アトム』以来、ロボットは「人間を超える理想」や「未来文明の象徴」として描かれてきた。一方アメリカでは『リアル・スティール』に代表されるように、ロボットは「無骨な戦士」「人間の代替」としてのイメージが強い。
日本製ロボットのノイジーボーイが「超悪男子」と刻印されているのは、多くの観客に失笑を誘った。しかしその存在は、アメリカ映画に「アキバ系電子立国としての日本」を異物として混入させる仕掛けでもある。つまり「アメリカ的なるもの=ボクシング」と「日本的なるもの=ハイテク文化」との衝突が作品の奥に組み込まれているのだ。
ATOMの比喩性と神話的イメージ
ATOMの強さは合理的には説明されない。シャドー機能が優れているからでもなく、スパークリング用だから打たれ強いわけでもない。ただ「なぜか強い」のだ。この不条理さこそが比喩性を高めている。
試合前にATOMが鏡越しに自らを見つめるシーンは象徴的である。アイデンティティを持たないはずのロボットが、自意識に目覚めたかのように見える。ここにはユダヤ神話のゴーレムや、メアリー・シェリーの『フランケンシュタイン』に連なる神話的モチーフを読み取ることもできる。ATOMは単なる機械ではなく、父子の祈りを受けて「魂」を宿した存在として提示されているのだ。
未来に蘇る古き良きアメリカ映画
『リアル・スティール』は、最新のVFXを用いながらも、その本質は「古き良きアメリカ映画の記憶の集積」である。ロードムービー風の展開は『ブロンコ・ビリー』を、父子の交流は『センチメンタル・アドベンチャー』を、そしてボクシングの熱狂は『ロッキー』を思い出させる。
同時に日本のロボット文化を取り込み、ATOMに多義的な役割を背負わせることで、物語に開かれた解釈を残している。SFとしての新味は少ないかもしれないが、安心感と普遍性を両立させたこの映画は、まさに「近未来に蘇った古典映画」と呼ぶにふさわしい。
- 監督/ショーン・レヴィ
- 脚本/ジョン・ゲイティンズ
- 製作/ドン・マーフィ、スーザン・モントフォード
- 製作総指揮/ジャック・ラプケ、ロバート・ゼメキス、スティーヴ・スターキー、スティーヴン・スピルバーグ、ジョシュ・マクラグレン、メアリー・マクラグレン
- 原作/リチャード・マシスン
- 撮影/マウロ・フィオーレ
- 音楽/ダニー・エルフマン
- リアル・スティール(2011年/アメリカ)
![リアル・スティール/ショーン・レヴィ[DVD]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/51JHBroOVnL._UF10001000_QL80_-e1759623279188.jpg)

![ナイト ミュージアム [AmazonDVDコレクション] [Blu-ray]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/61Mo%2B5R%2BNGL.jpg)
![ブロンコ・ビリー [DVD]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/61o4-OYgglL.jpg)