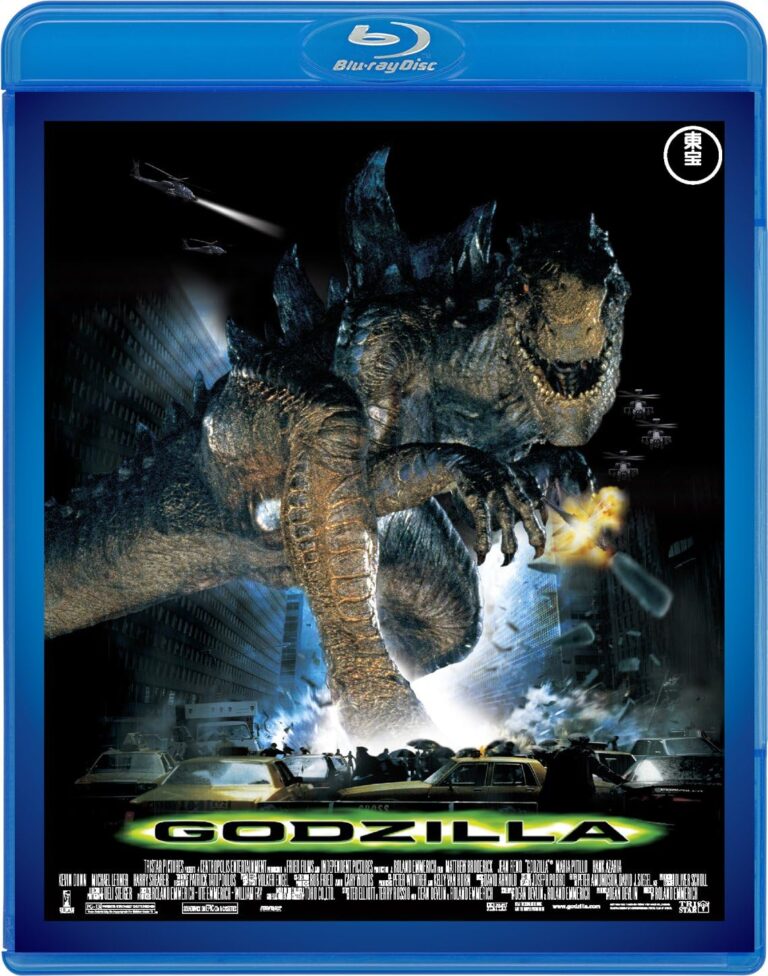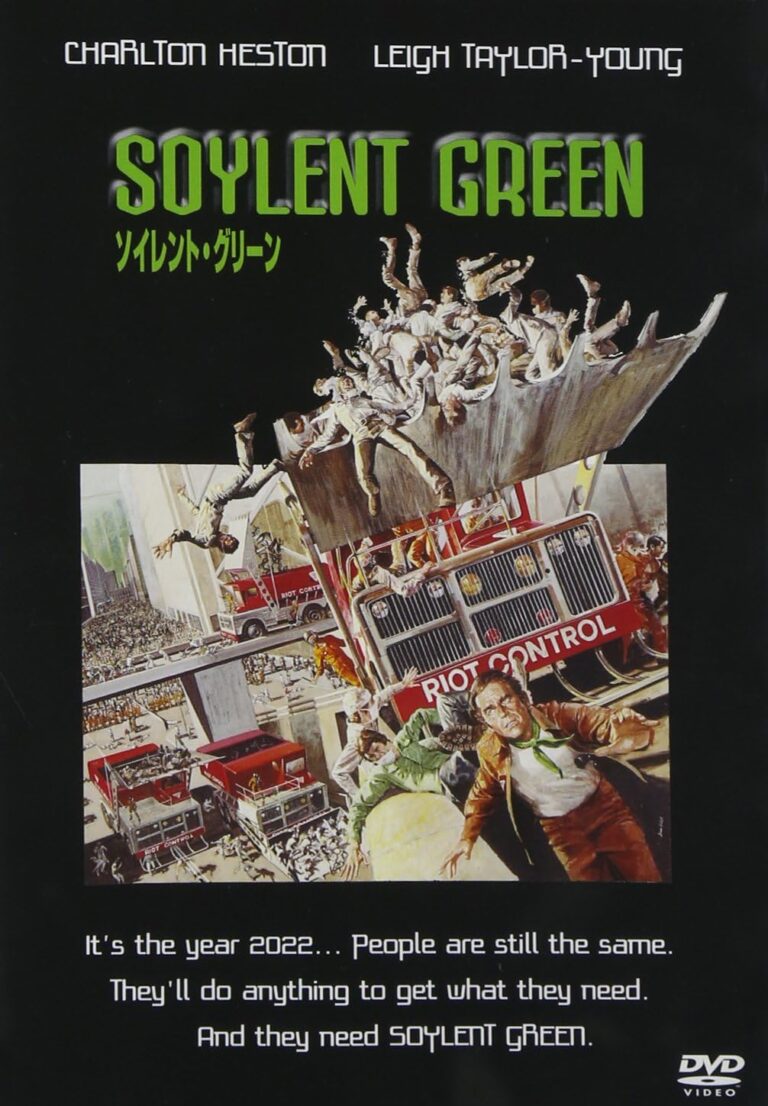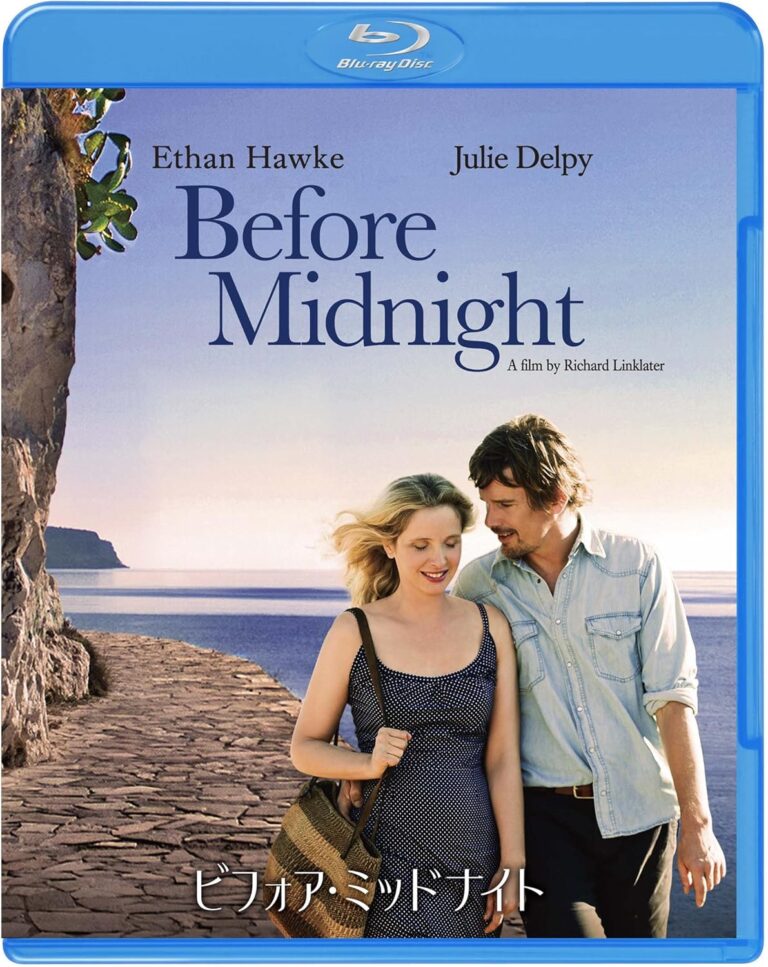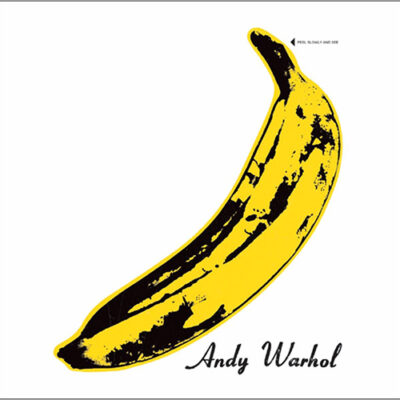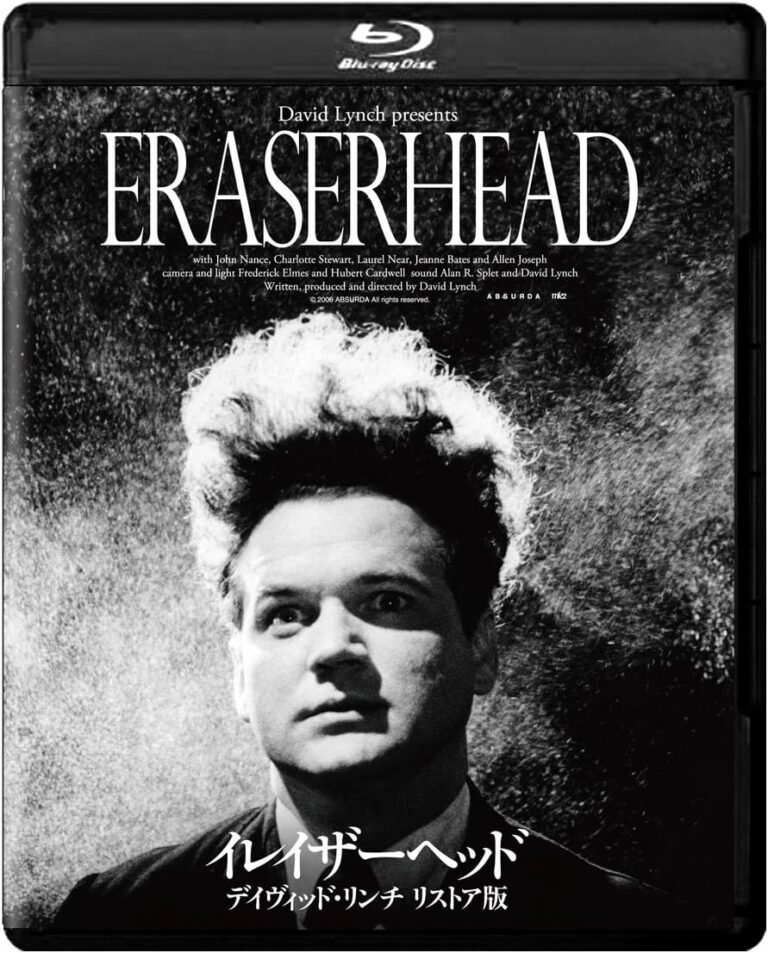『デイ・アフター・トゥモロー』(2004)
映画考察・解説・レビュー
『デイ・アフター・トゥモロー』(原題:The Day After Tomorrow/2004年)は、ローランド・エメリッヒ監督が手掛けたディザスター映画。気象学者ジャック(デニス・クエイド)が警告した破局が現実となり、人類が築き上げた文明はいとも容易く崩れてしまう。国境も経済も無力化された極限地平において、人間が明日を繋ぐために必要なのは、他者への献身と科学への誠実さであることを再発見する、サバイバルの記録。
破壊王エメリッヒのニューヨーク・フェティシズム
ローランド・エメリッヒほど、ニューヨークという都市を愛し、そして憎んでいる映画作家はいない。
『インデペンデンス・デイ』(1996年)では巨大円盤のレーザーでエンパイア・ステート・ビルを一瞬で灰にし、『GODZILLA』(1998年)ではイグアナのような怪獣にマンハッタンを踏み荒らさせた。
そして本作『デイ・アフター・トゥモロー』(2004年)では、巨大津波で水没させた挙句、マイナス100度のスーパー・フリーズでカチコチに冷凍保存してみせる。
なぜ彼はこれほどまでに執拗に、ビッグアップルを破壊することに固執するのか? それはニューヨークこそが、世界金融の中心であり、多民族のサラダボウルであり、アメリカという現代のローマ帝国の心臓部だからだ。
エメリッヒはハリウッドのど真ん中で映画を撮りながらも、出自はドイツ・シュトゥットガルト生まれの異邦人監督。彼の破壊衝動の底には、かつて自国のイデオロギー暴走によって崩壊した祖国の記憶と、アメリカという超大国に対する、外部者としての冷徹な観察眼が潜んでいる。彼にとってニューヨークの摩天楼は、バベルの塔と同じく、人間の傲慢さの象徴なのだ。
本作が公開された2004年は、同時多発テロからわずか3年後。当時、リアルなビル崩壊映像はタブー視され、『スパイダーマン』(2002年)の予告編からツインタワーが消されるほどの自粛ムードが漂っていた。
そんな空気の中で、エメリッヒはあえて再びニューヨークを徹底的に破壊してします。だが、そこにかつてのような「GO!アメリカ!」的無邪気な高揚感はない。
あるのは、自然という抗いようのない神の鉄槌によって、文明がいとも簡単に跪く姿だ。自由の女神が氷に閉ざされるビジュアルは、アメリカが掲げる自由や民主主義といった理念そのものが、環境破壊という自業自得によって死滅することのメタファーとして機能している。
さらに興味深いのは、エメリッヒがこの災害を怪獣映画の文法で描いている点だ。彼は台風の目を生き物のように描写し、冷気が獲物を追いかけるように廊下を疾走する演出を加えた。
これは、自然災害を擬人化された敵として描くことで、観客に恐怖を植え付けると同時に、対テロ戦争の構図を対自然戦争へとスライドさせようとする試みでもあるはず。
だが、銃もミサイルも通用しないこの敵に対し、アメリカはただ逃げ惑うことしかできない。この無力感こそが、エメリッヒが突きつけた最大の批評なのだ。
プロパガンダの大反転と政治的挑発
本作が画期的だったのは、ディザスター映画というジャンルを使って、強烈な反・愛国プロパガンダ展開した点にある。
公開当時のアメリカはジョージ・W・ブッシュ政権下であり、京都議定書からの離脱を表明するなど、環境問題に対して極めて後ろ向きだった。エメリッヒはこの映画を、単なる娯楽作ではなく、再選を目指すブッシュ政権への痛烈なカウンターパンチとして設計したのだ。
劇中に登場する副大統領ベッカー(ケネス・ウェルシュ)を見れば、その意図は明白。彼は外見から立ち振る舞いに至るまで、当時のディック・チェイニー副大統領をモデルにしており、「経済より環境を優先することはできない」と断言する傲慢なタカ派として描かれている。
主人公の気象学者ジャック(デニス・クエイド)の警告を嘲笑い、対策を怠った彼が、ラストシーンでは「I was wrong(私は間違っていた)」と弁明する。これは、ハリウッド映画が時の政権に対して突きつけた、フィクションの力を借りた公開処刑だ。
さらに強烈なのが、南北問題の逆転というアイロニー。寒冷化によって北半球が居住不能になり、アメリカ国民は生き残るために南へ、つまりメキシコ国境へと殺到する。
現実世界では、メキシコからの不法移民を締め出すために壁を作ろうとしているアメリカが、映画の中では難民としてメキシコに慈悲を乞い、国境のフェンスを力ずくで乗り越えていくのだ。
メキシコ政府が国境閉鎖を宣言し、アメリカ大統領が負債の免除を条件に受け入れを交渉するという皮肉!ここでエメリッヒは、アメリカ人が無自覚に信じている特権意識を粉々に粉砕してみせる。
助ける側ではなく助けられる側になるという、視点のパラダイムシフトこそが、本作を単なるパニック映画から、高度な社会風刺へと押し上げている。これはアメリカ中心主義的な世界観に対する強烈なアンチテーゼであり、エメリッヒ流のグローバリズムへの皮肉な回答なのだ。
公開当時、NASAの科学者たちは「数日で氷河期が来るなんてあり得ない」と苦言を呈したという。だがエメリッヒにとって、科学的正確さなど二の次だったのだろう。
重要なのは、アメリカ人に「自分たちが難民になる姿」を想像させること。その一点において、この映画はドキュメンタリー以上にリアルな恐怖を植え付けたのである。
贖罪としてのスペクタクル
エメリッヒの映画は常に「アメリカ万歳」と「アメリカ批判」の間で揺れ動いてきた。
『インデペンデンス・デイ』では大統領自らが戦闘機に乗って戦うという究極のマッチョイズムを描いた彼が、本作ではそのマッチョイズムが自然の前では無力であることを露呈させる。
これは、彼自身のフィルモグラフィーにおける贖罪だ。過去作で散々煽ってきたナショナリズムや軍事力への信仰を、自らの手で冷凍粉砕し、本当に守るべきものは何かを問い直す。
象徴的なのが、ニューヨークの公立図書館に避難した生存者たちが、暖を取るために本を燃やすシーンだ。彼らは何を燃やすか議論する。ニーチェか?法律書か?
結局、彼らが最初に燃やしたのは税法の棚だった。資本主義のルールブックは、極限状態ではただの燃料にしかならない。一方で、グーテンベルク聖書だけは、人類の理性の証として、無神論者の男が抱きしめて守ろうとする。
ここに、エメリッヒの文明に対するアンビバレントな想いが込められている。システムや金は燃やしてもいいが、知性や魂までは燃やしてはいけないのだと。
そして物語の主軸となる、ジャックとサム(ジェイク・ギレンホール)の父子のドラマ。仕事にかまけて家庭を顧みなかった父が、凍てつく嵐の中を、息子を救うためだけに歩いていく。
これは環境破壊をしてしまった大人世代が、未来を生きる子供世代に対して果たすべき責任のメタファーだ。ジャックは世界を救うことはできなかった。彼にできるのは、ただ一人の息子を迎えに行き、約束を守ることだけ。
このミニマムな救済こそが、エメリッヒがたどり着いた結論である。国家や地球規模の危機に対して、個人の力は無力だ。だが、愛する者を守るという一点においてのみ、人間は尊厳を保つことができる。
『デイ・アフター・トゥモロー』は、スペクタクル映画のふりをした、エメリッヒ流の文明批評であり、アメリカという巨人が膝を屈する瞬間を、最も美しく、最も残酷に描いた寓話なのである。
- 監督/ローランド・エメリッヒ
- 脚本/ローランド・エメリッヒ、ジェフリー・ナックマノフ
- 製作/ローランド・エメリッヒ、マーク・ゴードン
- 製作総指揮/ウテ・エメリッヒ、ステファニー・ジャーメイン
- 制作会社/ライオンズゲート、20世紀フォックス
- 原作/アート・ベル、ホイットリー・ストリーバー
- 撮影/ウエリ・スタイガー
- 音楽/ハラルド・クローサー
- 編集/デヴィッド・ブレナー
- 美術/バリー・チュシド
- 衣装/レネー・エイプリル
- インデペンデンス・デイ(1996年/アメリカ)
- GODZILLA(1998年/アメリカ)
- デイ・アフター・トゥモロー(2004年/アメリカ)
![デイ・アフター・トゥモロー/ローランド・エメリッヒ[DVD]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/51qHDxDem-L._AC_-e1758331926488.jpg)
![GODZILLA/ローランド・エメリッヒ[DVD]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/81OxBsKfZQL._AC_SL1447_-e1758333653435.jpg)
![インデペンデンス・デイ/ローランド・エメリッヒ[DVD]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/61fxzlxK40L._AC_-e1758334178902.jpg)