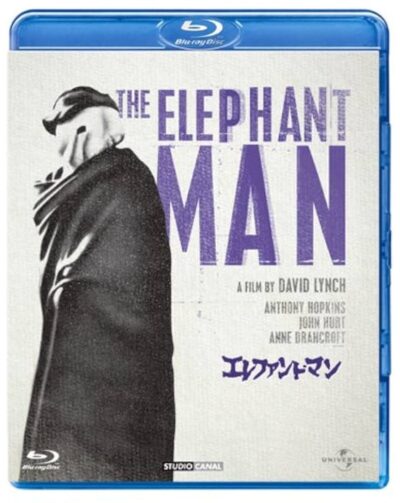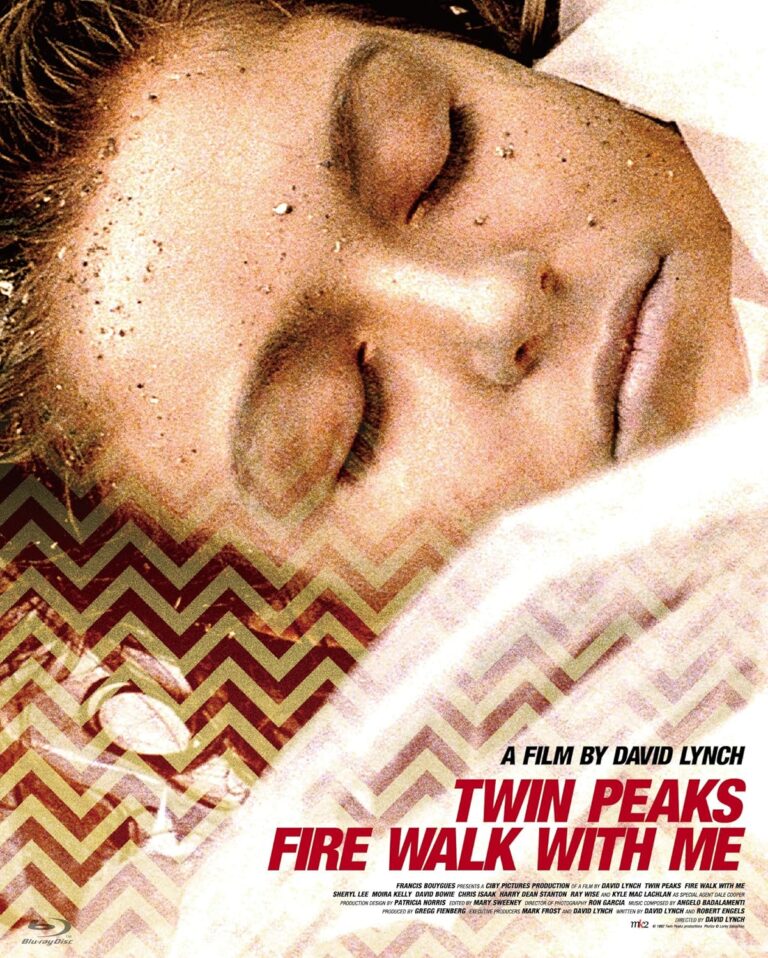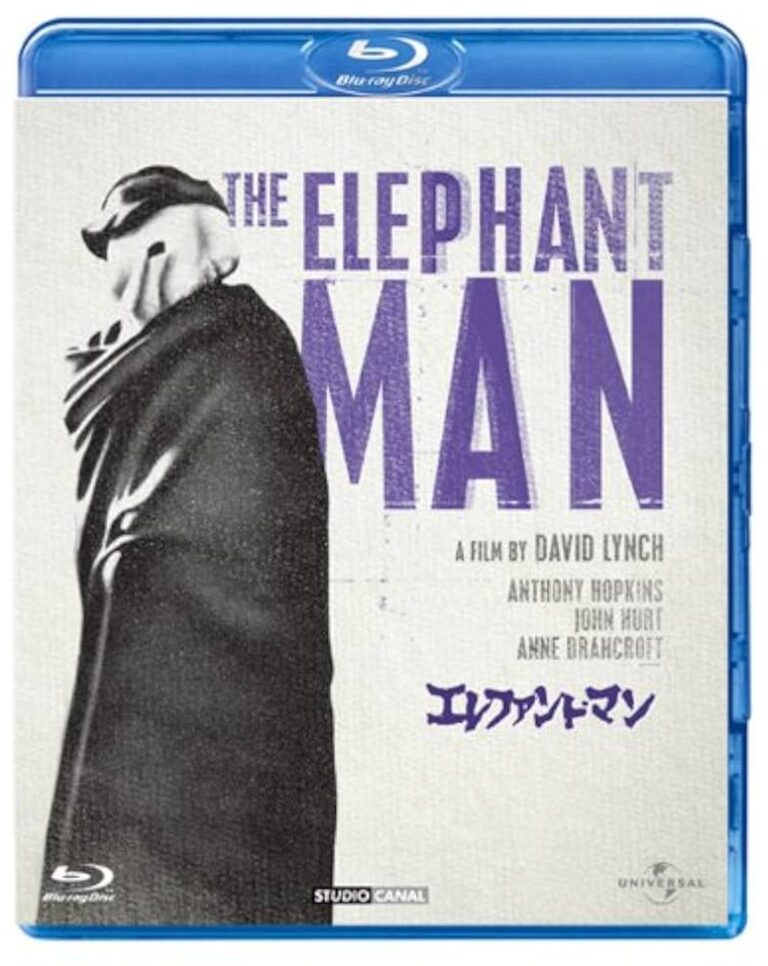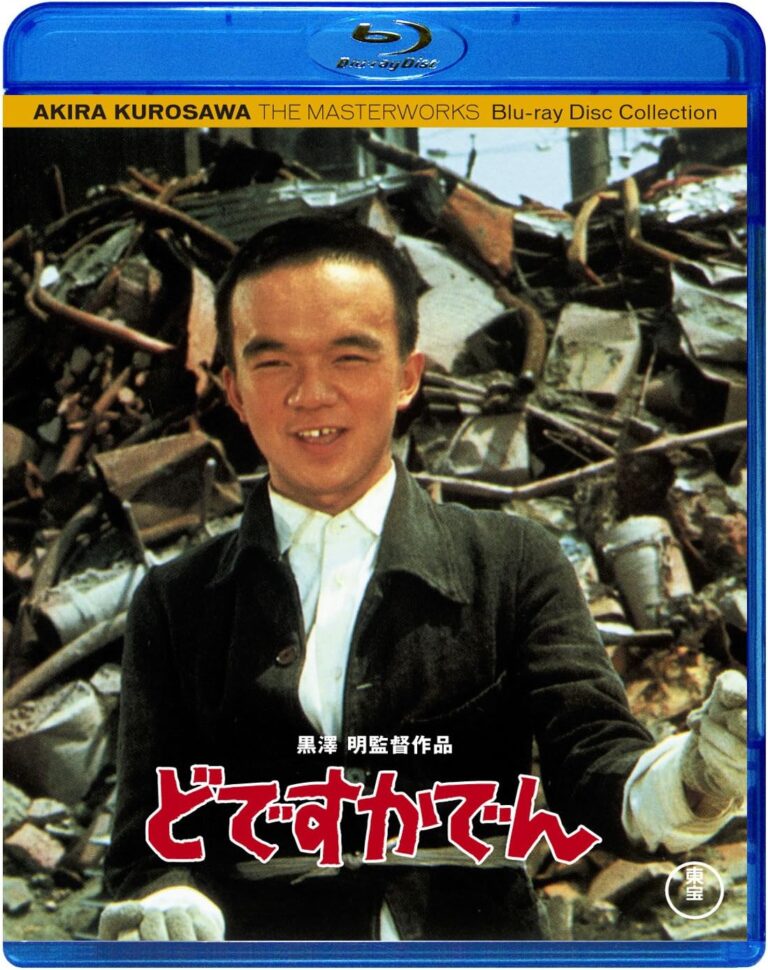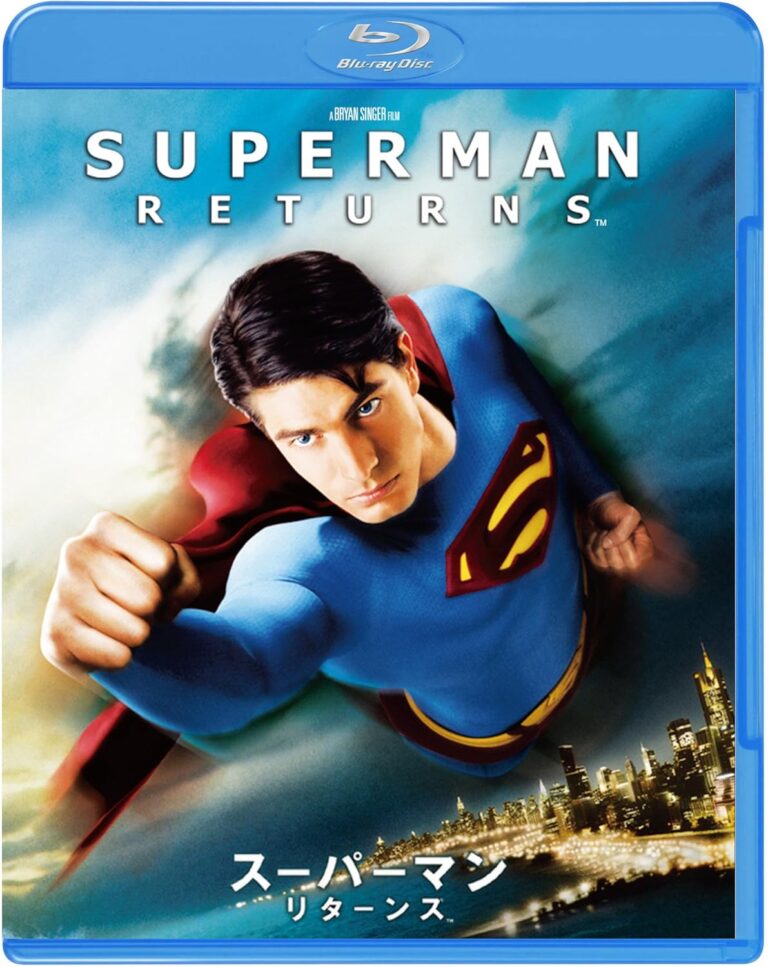『イレイザーヘッド』(1977)
映画考察・解説・レビュー
『イレイザーヘッド』(原題:Eraser Head/1976年)は、デヴィッド・リンチ監督の長編デビュー作。工場地帯のような都市に暮らす男ヘンリー(ジャック・ナンス)は、恋人との間に生まれた奇形児を前に、次第に正気を失っていく。暗闇に包まれたアパート、響き続ける機械音、現実と幻想が入り混じる悪夢の世界。そこに登場する“オタフク顔の少女”や“泣き叫ぶ赤ん坊”は、観客の無意識を揺さぶり、現実そのものの不確かさを露わにしていく。
1970年代アメリカ映画の中での位置づけ
天国では何もかも叶うわ。 あなたも私も思い通りのものが手にいれられるの
異形のオタフク少女が、暗がりのステージで奇妙な歌を歌いながら、天井から降り注ぐ精子を踏みつける。この倒錯したイメージの連なりこそ、デヴィッド・リンチの長編デビュー作『イレイザーヘッド』(1976年)を象徴する瞬間。観客は“現実”から切り離され、どこまでも深く、悪夢の迷宮へと引き込まれていく。
1970年代、ハリウッドが『ジョーズ』(1975年)や『スター・ウォーズ』(1977年)といったブロックバスターの狂乱に沸き、映画を効率的な「消費財」へと変貌させていく中、暗闇の片隅で産声を上げたのが『イレイザーヘッド』だった。
この映画は、大資本によるマーケティング戦略を嘲笑うかのように、「ミッドナイト・ムービー」という特殊な生態系の中でカルトの神へと登り詰める。
ニューヨークのエルジン劇場を中心に定着したこの上映形態は、単なる深夜営業ではなく、観客を「悪夢を共有する秘密結社」へと変貌させた。
ジョン・ウォーターズ監督の『ピンク・フラミンゴ』(1972年)が悪趣味の限界を突破して観客の胃袋を揺さぶり、『ロッキー・ホラー・ショー』(1975年)が仮装と叫び声による参加型の狂騒を生み出す中、『イレイザーヘッド』が提示したのは、静寂の中で精神を削り取る「沈黙と凝視の儀式」だったのだ。
深夜の劇場の椅子に沈み込んだ観客たちは、論理的なストーリーテリングを放棄し、リンチが提示する「純粋な不快感」と「不可解な美」に自らを供物として捧げた。
本作は、映画を「消費する娯楽」から、観る者の脳内に消えない傷跡を残す「不可逆的な精神体験」へと転換させた、アメリカ映画史における異端の金字塔なのである。
フィラデルフィアの地獄
本作の舞台となる、常に機械音が鳴り響く荒涼とした都市空間。それはリンチが青年期にアトリエを構えた、当時のフィラデルフィアという「現実の地獄」の投影だ。
リンチは当時、犯罪と銃声が絶えない危険地帯で、アパートの剥き出しの壁と対峙しながら、この悪夢を5年もの歳月をかけて練り上げた。リンチは資金難で撮影が中断するたびに新聞配達をして日銭を稼ぎ、スタジオの物置小屋で主演のジャック・ナンスとともに隠者のような生活を送っていたという。
特筆すべきはジャック・ナンスの執念。彼は、あの独特の逆立った垂直の髪型を維持するために、なんと5年間も公の場で帽子を脱がずに過ごした。撮影が再開されるその瞬間のために、彼は自らの外見さえも「悪夢の小道具」として捧げ続けたのだ。
さらに驚くべきは、リンチが資金繰りのために描き続けた幻の漫画『アングリエスト・ドッグ・イン・ザ・ワールド(世界一腹を立てている犬)』の存在。同じコマを使い回し、一切動かない犬が繋がれたまま怒りに震えるというそのシュールな哲学は、本作の閉塞感と完全に見事に共鳴している。
特に、耳を劈くようなインダストリアル・ノイズが絶え間なく流れる音響設計は、今なお並ぶものがない。リンチは音響担当のアラン・スプレットと共に、工場地帯の重苦しい響きや、古びた空調の不気味な唸りを何年もかけてサンプリングし、人間の無意識に直接トラウマを植え付ける「聴覚的暴力」を完成させた。
映画全編を覆う低周波のバズ音や、湿った粘着音。これらは、リンチが実際に吸い込んだ都会の排気ガスと、腐敗した死の気配が「音」として結晶化したものなのだ。
観客の三半規管を狂わせ、逃げ場のない不安の底へと引きずり込むこの「音の檻」こそが、本作を単なる映像作品から、逃れられない物理的な監獄へと昇華させている。
「父性の恐怖」と奇形児の神話
公開当時から世界を震撼させたのが、あの「赤ん坊」の正体だ。牛の胎児説、あるいはリンチが拾い集めた動物の死体を繋ぎ合わせた禁断のパペット説……。
あの完璧主義者スタンリー・キューブリック監督までもが「どうやって撮ったのか?」と執拗にリサーチし、自身の『シャイニング』(1980年)の製作中、スタッフ全員に「世界で最も好きな映画だ」と称して本作を上映したという逸話は、あまりにも有名。
だが、リンチは半世紀近く一貫してその制作手法に沈黙を貫いている。この「秘密」の維持こそが、作品を神話的な領域へと押し上げているのだ。
ここで重要な批評軸となるのが、本作に潜む、家庭という閉鎖系への根源的な恐怖。リンチは長女ジェニファーが誕生した時期に制作を開始したが、当時の彼は結婚生活と育児という、逃げ場のない社会的責任に猛烈な不安を感じていた。
赤ん坊を「祝福」ではなく、親の平穏を食い潰し、不気味な粘液を撒き散らす「異形の他者」として描くその視線。フランシス・ベーコンの絵画のように肉体が物質へと変容していく描写は、人間が「生の象徴」であると同時に、いつかは腐りゆく「死の肉塊」でもあるという残酷な真理を突きつける。
観客がこの映画を観て覚える本能的な戦慄は、特殊効果の精巧さゆえではない。その奥に、我々が心の奥底に封印している「親になることへの拒絶反応」や「血の繋がりの不気味さ」を暴き出されるからなのだ。
『エレファント・マン』へ続くリンチ美学の原風景
リンチは異形を単なるホラーの道具としては扱わない。彼は、社会から疎外された「フリークス」の奥にある尊厳と悲しみを、誰よりも深く愛している。
本作の赤ん坊が不気味でありながら、どこか哀愁を漂わせ、その泣き声ひとつで主人公ヘンリーの情動を揺さぶるのはそのためだ。この視線は、後の『エレファント・マン』において、ヴィクトリア朝のガス灯が揺れる光と影の中で、見世物小屋の怪物の内なる知性と崇高な魂を描き出すことで決定的となる。
本作で見せたモノクロームの極致、そして工業地帯の冷徹な質感は、次作において「様式美としての歴史劇」へと見事に継承・昇華されている。
リンチのカメラは、常に「人間存在を最も深く映し出す鏡」として異形を見つめてきた。それは『ツイン・ピークス/ローラ・パーマー最期の7日間』(1992年)の巨人や、『マルホランド・ドライブ』(2001年)の劇場のステージで崩れ落ちる歌手にも通底している。
彼らは世界の裂け目から現れる「預言者」であり、平穏な現実の裏側に潜む「真実」を告げる存在。リンチにとって、異形とは排除すべき異物ではなく、我々が日常生活を維持するために直視を避けている「人間そのものの真実」にほかならない。
『イレイザーヘッド』から始まったこの美学は、以降の作品すべてに流れる通奏低音となり、我々を夢と現実の境界へと永遠に誘い続けるのである。
- 監督/デヴィッド・リンチ
- 脚本/デヴィッド・リンチ
- 製作/デヴィッド・リンチ
- 撮影/ハーバード・カードウェル、フレデリック・エルムズ
- 音楽/ピーター・アイヴス
- 編集/デヴィッド・リンチ
- 美術/ジャック・フィスク
- イレイザーヘッド(1977年/アメリカ)
- エレファント・マン(1980年/イギリス、アメリカ)
- デューン 砂の惑星(1984年/アメリカ)
- ブルーベルベット(1986年/アメリカ)
- ツイン・ピークス ローラ・パーマー最期の7日間(1992年/アメリカ、フランス)
- ロスト・ハイウェイ(1997年/アメリカ)
- ストレイト・ストーリー(1999年/アメリカ)
- マルホランド・ドライブ(2001年/アメリカ)
- インランド・エンパイア(2006年/アメリカ)
![イレイザーヘッド/デヴィッド・リンチ[DVD]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/71jNdfXRG7L._AC_SL1144_-e1707308920901.jpg)
![ロッキー・ホラー・ショー/ジム・シャーマン[DVD]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/512BaMRYvnL._AC_-e1758558777465.jpg)