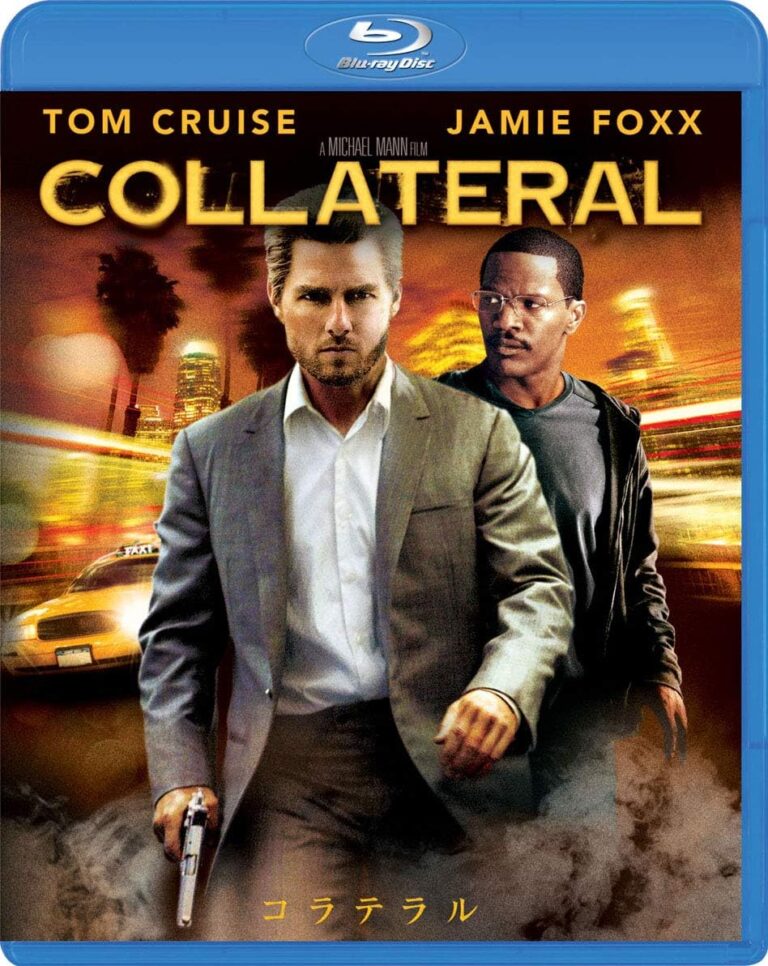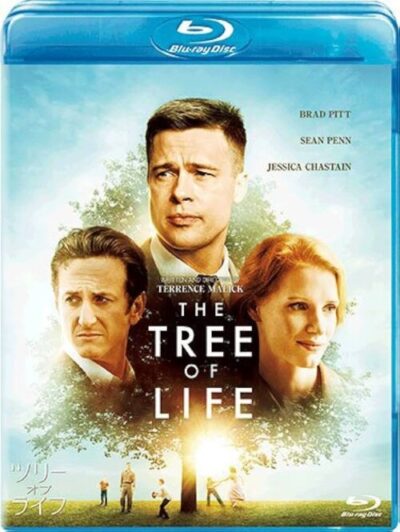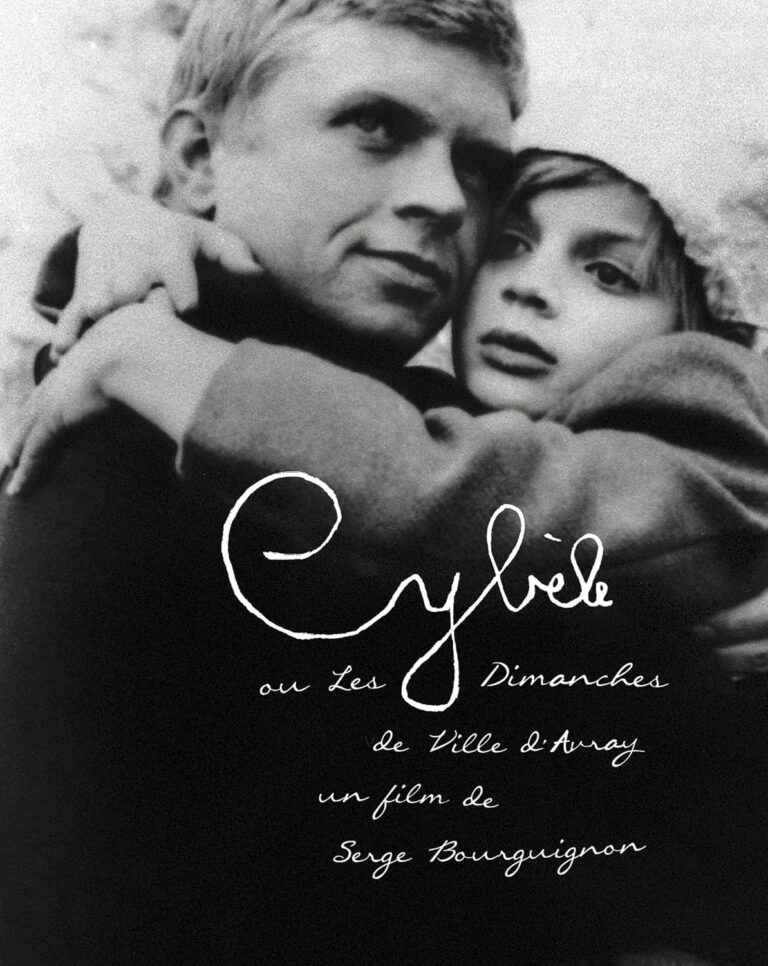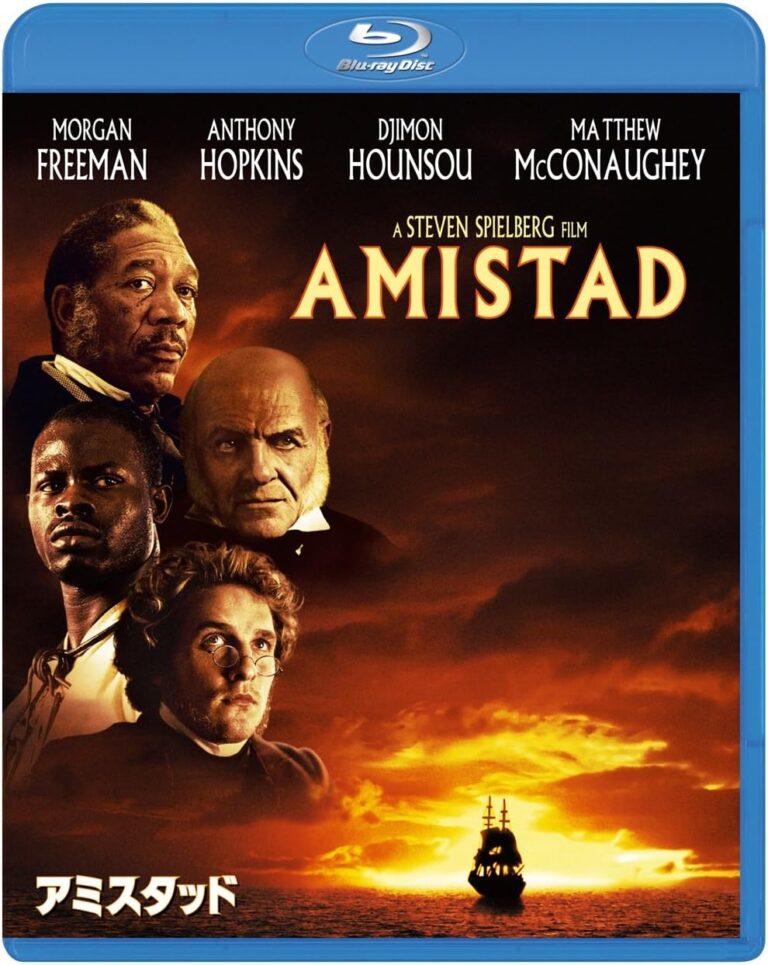『フェラーリ』(2023)
映画考察・解説・レビュー
『フェラーリ』(原題:Ferrari/2023年)は、1957年のイタリアを舞台に、自動車メーカーの創設者エンツォ・フェラーリの苦悩と葛藤を描いた人間ドラマ。レース界での栄光の裏側で、妻ラウラとの確執や家庭の危機に直面するエンツォ(アダム・ドライバー)の姿が浮き彫りとなる。ペネロペ・クルス演じるラウラとの激しい対立、若き恋人リナとの関係、そして伝説的な公道レース「ミッレミリア」での悲劇が、家族と事業の行方を大きく揺るがしていく。
サーキットではなく「食卓」が戦場になる衝撃
もしあなたがジェームズ・マンゴールドの『フォードvsフェラーリ』(2019年)で味わったような、エンジン音とガソリンの匂いが充満する爽快なレース映画を期待して劇場へ足を運んだなら、開始30分で「詐欺だ!」と叫びたくなるに違いない。
それほどまでに、マイケル・マンの最新作『フェラーリ』(2023年)は、我々の予想を裏切り、斜め上を行く怪作に仕上がっている。
本作が描いているのは、華々しいレースの栄光でも、チェッカーフラッグを受ける歓喜の瞬間でもない。描かれるのは、エンツォ・フェラーリ(アダム・ドライバー)とその妻ラウラ(ペネロペ・クルス)による、血で血を洗うような「夫婦喧嘩」だ。 そう、本作はマシンの加速競争ではなく、互いの精神を摩耗させ合う心理的攻防戦なのである。
この企画、実は2000年代初頭から動いていた。当初はあのシドニー・ポラックが監督する構想もあったらしいが、巡り巡ってアダム・ドライバーが主演に選ばれたのは、もはや映画の神様の悪戯としか思えない。なぜなら、アダム・ドライバーといえば、あの夫婦崩壊の地獄巡りを描いた傑作『マリッジ・ストーリー』(2019年)の主演俳優なのだから。
本作での彼の演技を見ていると、まるで『マリッジ・ストーリー』で負った古傷がまだ癒えていないかのような、ヒリヒリとした緊張感が漂っている。
息子ディーノを失った悲しみを共有しながらも、修復不可能な亀裂が入ってしまった夫婦関係。朝のコーヒーを啜る音さえもが、銃弾のように重く響く。これはもう、実質的に『マリッジ・ストーリー:イタリア・モデナ編』と言っても過言ではない。
ベルイマン的密室劇
これまで我々映画ファンが、親指を立てて「マイケル・マン最高!」と叫んできた理由は何か? それは圧倒的な“戦い”の美学にあったはず。
『ヒート』(1995年)の銀行強盗、『コラテラル』(2004年)の殺し屋、あるいは『マイアミ・バイス』(2006年)の潜入捜査官たち。彼らがロサンゼルスやマイアミの、あの独特なブルーに染まった「夜の都市」を疾走する姿に、我々は痺れてきたのだ。
しかし、『フェラーリ』には煌びやかな摩天楼も、濡れたアスファルトに反射するネオンもない。あるのは、イタリアの重厚な石造りの屋敷と、息詰まるようなリビングルームだけ。
若きレーサーたちはあくまで脇役、真の闘争者(グラディエーター)は、リビングで睨み合うエンツォとラウラ。これは、老境に達したマイケル・マンの視座が、「路上」から「家庭」へと、そして「物理的な暴力」から「精神的な暴力」へと移行したことを意味している。
僕が愛聴しているポッドキャスト番組「the sign podcast」で、批評家の木津毅氏が鋭く指摘していた通り、これはマイケル・マンが意図的に自らの作家性(シグネチャー)を封印した確信犯的な試みだろう。
この映画が接続しようとしているのは、ハリウッドのアクション映画史ではない。イングマール・ベルイマンの『ある結婚の風景』(1973年)や『秋のソナタ』(1978年)、あるいはジョン・カサヴェテスの『こわれゆく女』(1974年)といった、人間の深淵を覗き込むような「夫婦劇の系譜」なのだ。
さらに言えば、ルキノ・ヴィスコンティの『家族の肖像』(1974年)に見られるような名家の没落や、フェデリコ・フェリーニ的な家庭と個人の断絶といった、イタリア映画のDNAまで濃厚に感じさせる。
マイケル・マンはここで、ハリウッド的なエンターテインメントを拒絶し、イタリア映画的な「業(カルマ)」を再演してみせたのである。
「ファミリービジネス」の真の恐怖
そして本作を語る上で外せないのが、「企業映画」としての奇妙な二重性だ。
通常、アメリカ映画で「企業」を描く場合、フォードやGMのような巨大資本は、労働問題や技術革新、あるいは国家規模の産業力の象徴として扱われる。『フォードvsフェラーリ』で描かれたフォード社なんて、まさに巨大な官僚機構そのものだったではないか。
だが、『フェラーリ』における「企業」は違う。それは国家産業というより、血縁と愛憎で結びついた、中世の「王国」のようなものとして描かれるのだ。
会社の存亡は、株価ではなく、愛人の存在や隠し子の認知といった「家庭の事情」に直結している。ここに、ドライなアメリカ的企業映画と、ウェットなイタリア的家族劇の決定的な差異が浮かび上がる。
つまり本作は、企業映画の顔をした家族映画であり、アメリカ映画の皮を被ったイタリア映画という、極めて歪で魅力的な二重構造を持っているのだ。
マイケル・マンは本作で、自身のトレードマークである「都市の夜の官能」を脱ぎ捨て、企業と家族、外敵との競争と内面の葛藤という新たな闘技場を切り開こうとした。その挑戦心には敬意を表したい。
だがその一方で、「マン先生、俺たちが見たかったのはこれじゃないんです!」という思いもある。この映画には、あの濡れたような情感、男たちが夜の闇に溶けていくような、あのどうしようもない寂寥感が欠けている。
これを刷新と呼ぶべきか、喪失と呼ぶべきか。僕にとっては、悲しいかな後者である。都市の夜の匂いがしないマイケル・マン映画なんて、炭酸の抜けたコーラのようなものなのだから。
- 監督/マイケル・マン
- 脚本/マイケル・マン、トロイ・ケネディ・マーティン
- 製作/マイケル・マン、P・J・ファン・サンドバイク、マリー・サバレ、ジョン・レッシャー、トーマス・ヘイスリップ、ジョン・フリードバーグ、アンドレア・イェルボリーノ、モニカ・バカルディ、ギャレス・ウェスト、ラース・シルベスト、トーステン・シューマッハー、ローラ・リスター
- 製作総指揮/ミキ・エメリッヒ、ロバン・ル・シャニュ、ロバート・シモンズ、ジャム・ナジャフィ、ノア・フォーゲルソン、アダム・フォーゲルソン、サミュエル・J・ブラウン、トーマス・マクレオド、アダム・ドライバー、パメラ・イェーツ、バハン・イェプレマイアン、アルトゥール・ガルスティアン
- 原作/ブロック・イエーツ
- 撮影/エリック・メッサーシュミット
- 音楽/ダニエル・ペンバートン
- 編集/ピエトロ・スカリア
- 美術/マリア・ジャーコビク