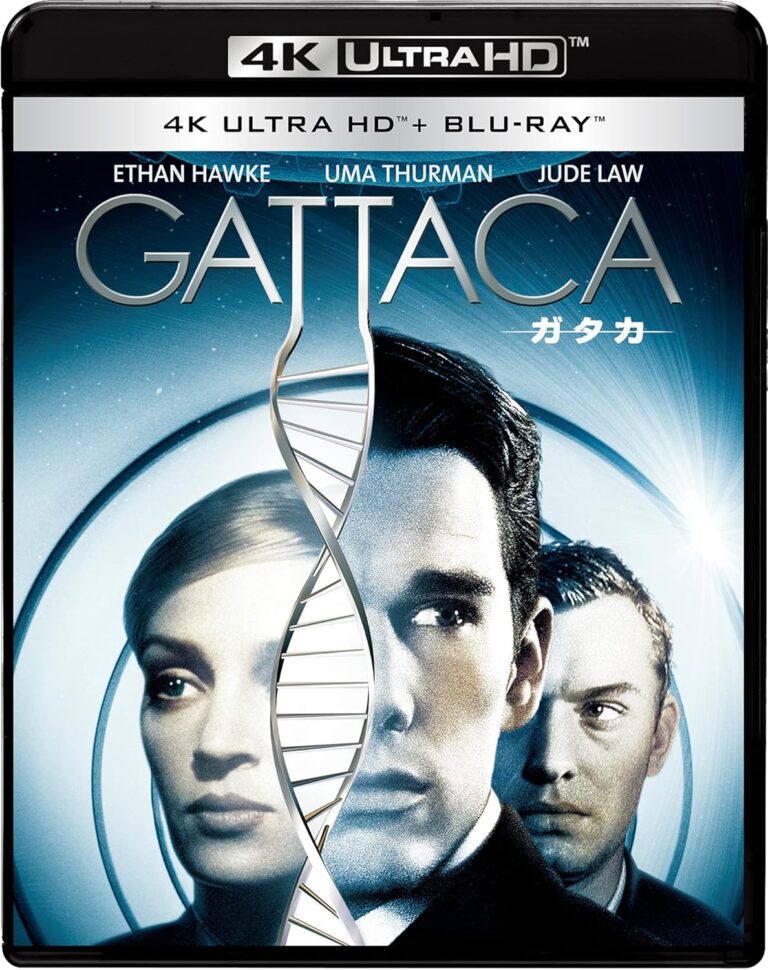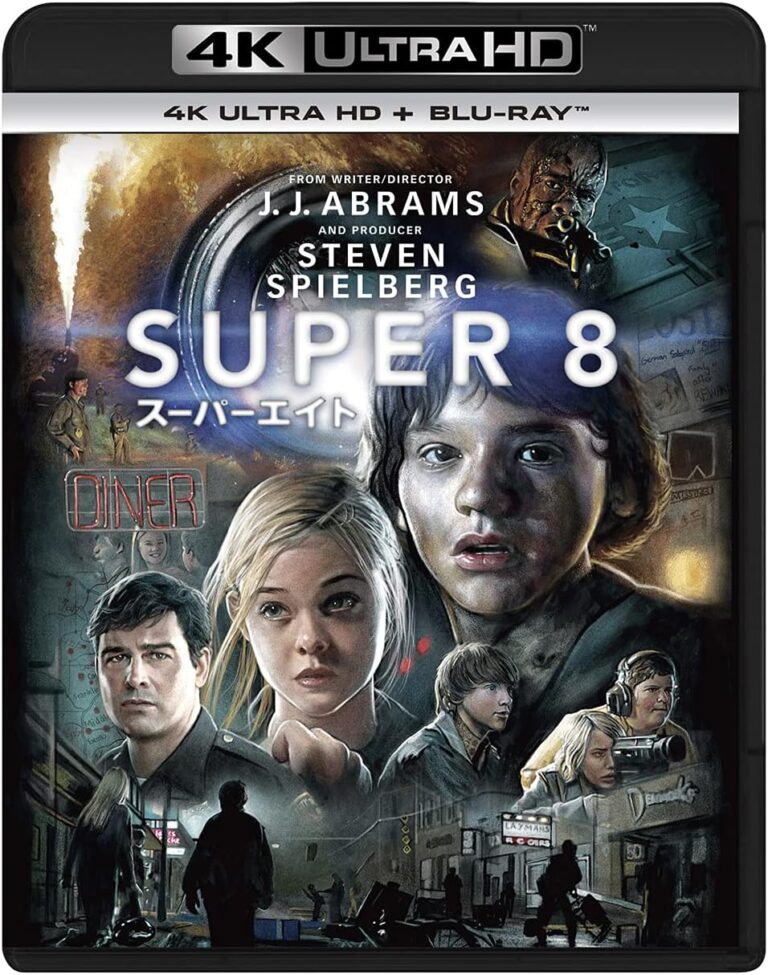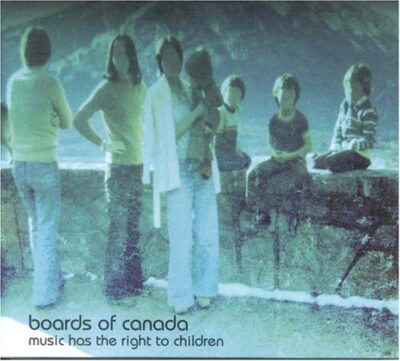【ネタバレ】『シモーヌ』(2002)
映画考察・解説・レビュー
『シモーヌ』(原題:S1m0ne/2002年)は、映画監督ヴィクター・タランスキー(アル・パチーノ)が理想の女優をCGで創造し、やがてその虚像に支配されていく物語である。アンドリュー・ニコル監督が『トゥルーマン・ショー』(脚本)と対をなす形で描くのは、虚構が現実を侵食する21世紀的神話。創造と被創造の境界が崩れる瞬間が、静かなユーモアとともに映し出される。
『トゥルーマン・ショー』の裏面をいく、神の悪あがき
現在、我々の世界はAIによる画像生成やディープフェイク技術が爆発的に進化し、VTuberがドーム球場を超満員にする時代に突入している。
だが、そんな虚像が現実を凌駕する世界を、今から20年以上も前の2002年に完璧な解像度で予言し、極上のブラックコメディとして叩きつけていた映画が存在する。アンドリュー・ニコル監督による『シモーヌ』(2002年)だ。
この映画は、ニコル自身が脚本を担当した『トゥルーマン・ショー』(1998年)と、見事なまでの鏡像関係を結んでいる。あちらがジム・キャリー演じる「世界という名の巨大セットの中に閉じ込められた人間」の寓話であるなら、本作はアル・パチーノ演じる「世界を外側からCGで操作して騙す人間」の寓話。いわば、スクリーンの外側に立つ“神の視座”の物語である。
『トゥルーマン・ショー』の主人公は、無数の視聴者に監視される商品化された現実に気づき、スタジオの壁を突き破って現実世界へと脱出を果たした。それは虚構からの脱出であり主体の覚醒だ。
対して『シモーヌ』では、創造主の側にスポットライトが当たる。落ち目の映画監督ヴィクター・タランスキー(アル・パチーノ)は、ワガママな生身の女優に愛想を尽かし、天才プログラマーが遺したソフトを使って、自分の理想をすべて詰め込んだ“完璧なCG女優”をでっち上げる。
彼女の名はシモーヌ。人間でも女優でもなく、純粋なピクセルとデータの集合体だ。だが、この都合の良い操り人形は、やがて創造主の手を離れて現実社会を猛烈に侵食していく。
ニコルがここで描いているのは、虚構が現実を喰い殺す瞬間であり、神(監督)と被造物(データ)の立場が完全に逆転してしまうという、現代的な恐怖なのだ。
“外から内へ”の侵略劇と、アル・パチーノの悲しき顔芸
アンドリュー・ニコルの作品群には、一貫して境界を越える者が登場する。
監督デビュー作『ガタカ』(1997年)では、遺伝的欠陥を持つ男が宇宙という絶対的な外界へと脱出しようとし、脚本を手がけた『ターミナル』(2004年)では、JFK空港という密室空間から自由を求めてアメリカの地を踏もうとする男が描かれた。これらはいずれも「内から外へ」の越境の物語だ。
しかし『シモーヌ』では、そのベクトルの方向が完全に反転する。カメラはスクリーンの外側に固定されたまま、現実世界の内側に向けて、シモーヌという虚構のウイルスがドバドバと侵入していく。
タランスキー監督は、自らがキーボードを叩いて作り出した完璧な虚像に世界中が熱狂する様に酔いしれるが、誰も自分の演出手腕を褒めてくれないし、全部シモーヌの手柄になっている!というレンマに陥っていく。
スクリーンの外側にいて世界をコントロールしていたはずの神が、自身の創造物の巨大すぎる影に吸い込まれ、嫉妬で発狂していく。この「創造と所有のジレンマ」を演じるアル・パチーノの空回りっぷりと悲しき顔芸が、とにかく最高に滑稽で笑えるのだ。
映画というメディアは、つねに「虚構を現実化する力」と「現実を虚構化する力」の二面性を持つ。タランスキーはその麻薬のような力に取り憑かれ、観客を騙しているうちに、彼自身も自分の創作物が「本当に存在している」と錯覚し始めてしまう。
ニコルは映画監督という職業の神になりたがるエゴイズムを、容赦ないアイロニーでメッタ刺しにしているのだ。
誰もが自分を編集する時代の予言
映像美学の面でも、『シモーヌ』はアンドリュー・ニコルらしい偏執狂的なこだわりに満ちている。
強いフィルターを通した色彩設計、グラフィカルで幾何学的なポートレート構図、そしてフェデリコ・フェリーニを思わせるチネチッタ風の撮影所セット。これらはすべて、映画全体が人工的な現実であることを意図的に強調している。フィルムの生々しい粒子感は意図的に排除され、すべてがプラスチックのように滑らかに磨かれた光沢を帯びている。
いわばその画面は、人間の不在を可視化する美である。シモーヌの肌はピクセル単位で完璧に整い、毛穴もなければ不自然な陰影も存在しない。カメラが彼女を捉えるとき、そこに映っているのは実体ではなく、大衆の欲望の投影でしかない。
マスコミがこぞってシモーヌの正体を暴こうと狂奔し、ホログラムのライブ・コンサートで熱狂する後半の展開は、虚構と現実の区別が誰にもつかなくなり、社会全体が喜んで騙される観客と化していくプロセスを描き出している。
ここでニコルが批判の矛先を向けているのは、SNSのフィルター加工で誰もが画像を編集し、見栄えの良い完璧な自己を演出して承認欲求を満たす、21世紀のメディア環境そのもの。
人間が自らをアバター化していく現代の病理を、2002年の時点ですでにここまで冷徹に批評していたニコルの先見性には、ただただ背筋が凍る思いがする。
監督本人がCG女優を娶る神話の完成
アンドリュー・ニコル監督はこの映画の撮影を通じて、シモーヌを演じたカナダ人モデルのレイチェル・ロバーツと恋に落ち、実生活で結婚してしまった。
「お前が娶るんかい!」という、世界中の映画ファンからの強烈なツッコミが聞こえてきそうだが、これほどまでに映画のテーマを地で行くメタ展開があるだろうか?
虚構の存在(シモーヌ)をでっち上げた映画の創造主(ニコル監督)が、その虚構のベースとなった生身の女(被造物)を現実世界で自らの妻にしてしまう。まるでギリシャ神話のピグマリオンの狂気的な再演だ。この現実の逸話こそが、『シモーヌ』が内包していた「スクリーンと現実の境界線の完全なる崩壊」を象徴している。
ニコルは現実世界でもシモーヌを自らの隣に置くことで、自らが描いた映画のテーマを文字通り生きてしまった。『シモーヌ』は、その意味でニコル作品の最大の転回点に位置する。
『ガタカ』や『トゥルーマン・ショー』が監視社会からの人間の解放を描いたのに対し、『シモーヌ』は虚構による現実の侵食を描いた。ここでは、自由はもはや祝福ではない。
虚構が現実を模倣し、現実が虚構を模倣する無限ループの世界。それこそが、我々が今生きている21世紀のバベルの塔なのだ。
- 監督/アンドリュー・ニコル
- 脚本/アンドリュー・ニコル
- 製作/アンドリュー・ニコル
- 製作総指揮/ブラッドリー・クランプ、マイケル・デ・ルーカ、リン・ハリス
- 撮影/エドワード・ラックマン、デレク・グローヴァー
- 音楽/カーター・バーウェル、サミュエル・バーバー
- 美術/ヤン・ロールフス
- 衣装/エリザベッタ・ベラルド
![シモーヌ/アンドリュー・ニコル[DVD]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/71dweuUIpsL._AC_SL1436_-e1759245042144.jpg)