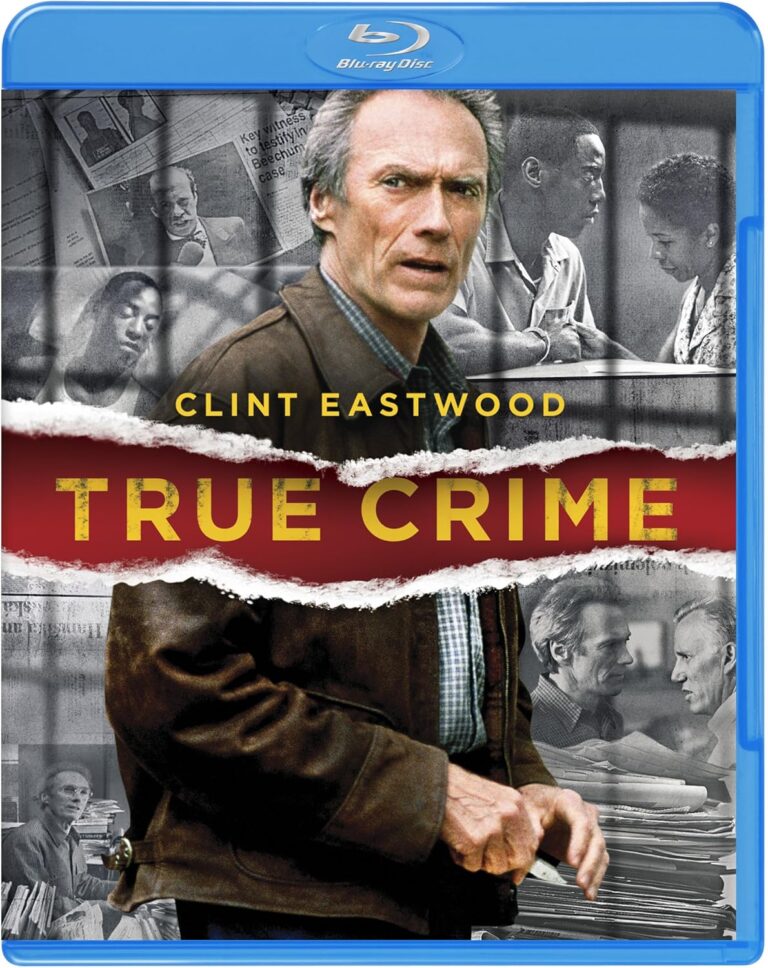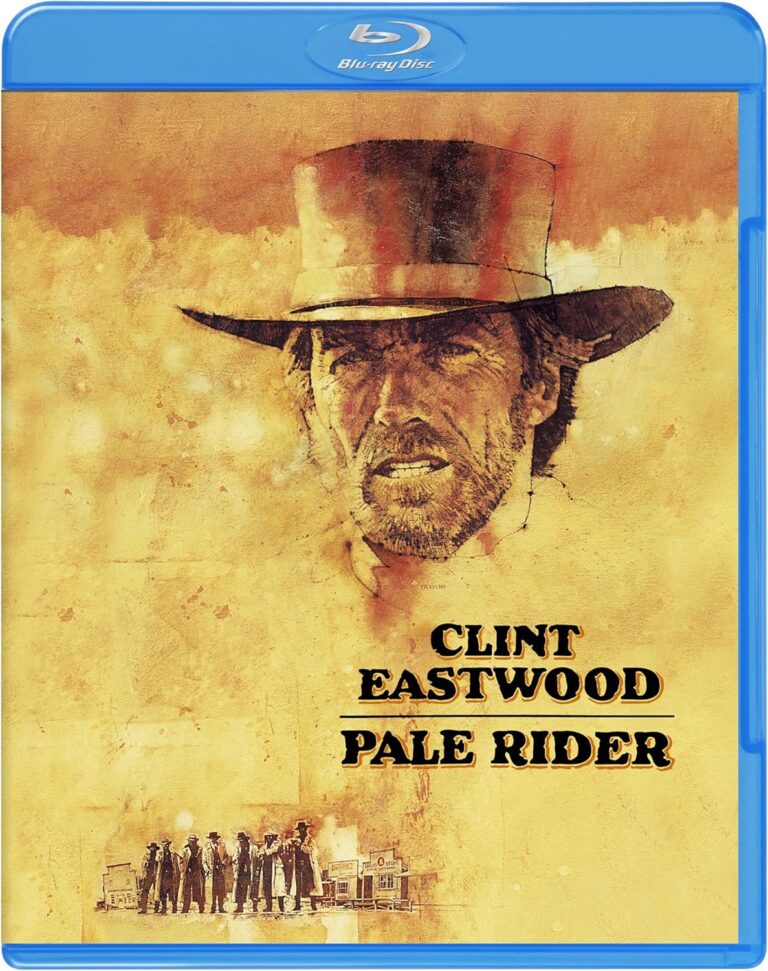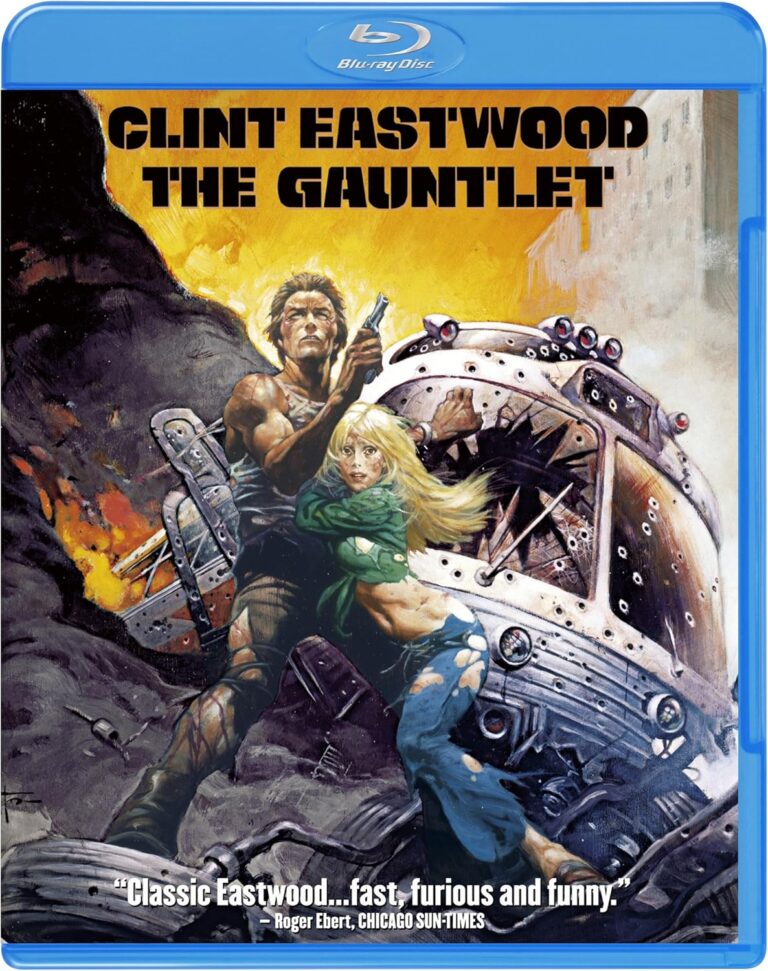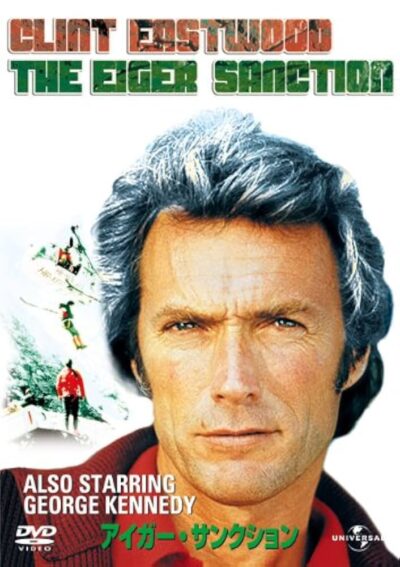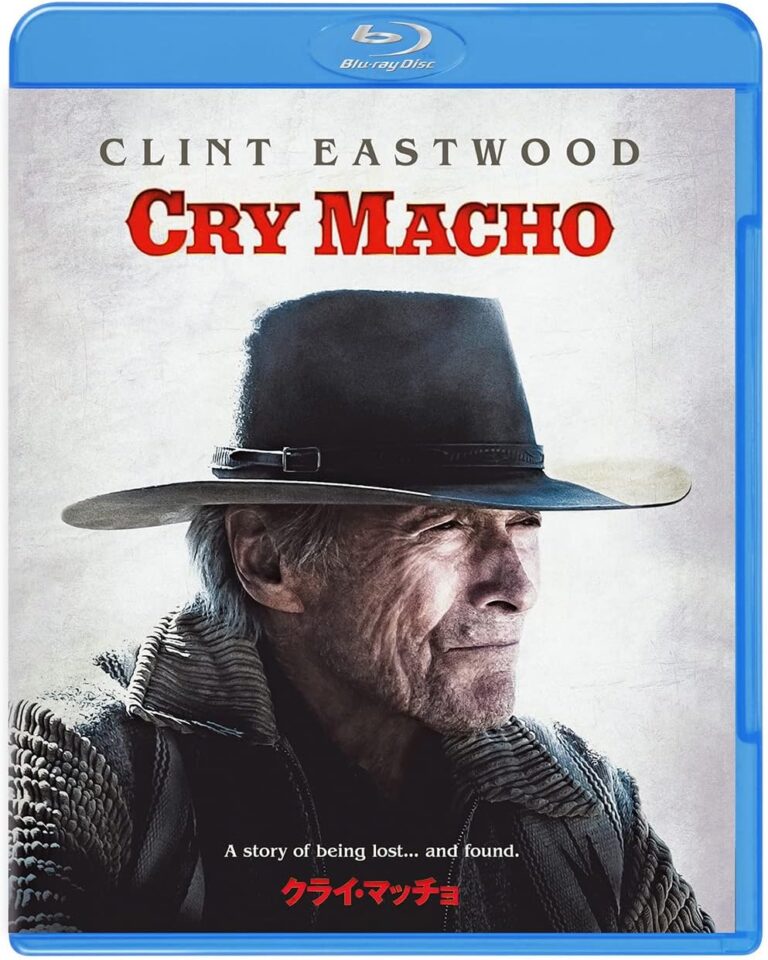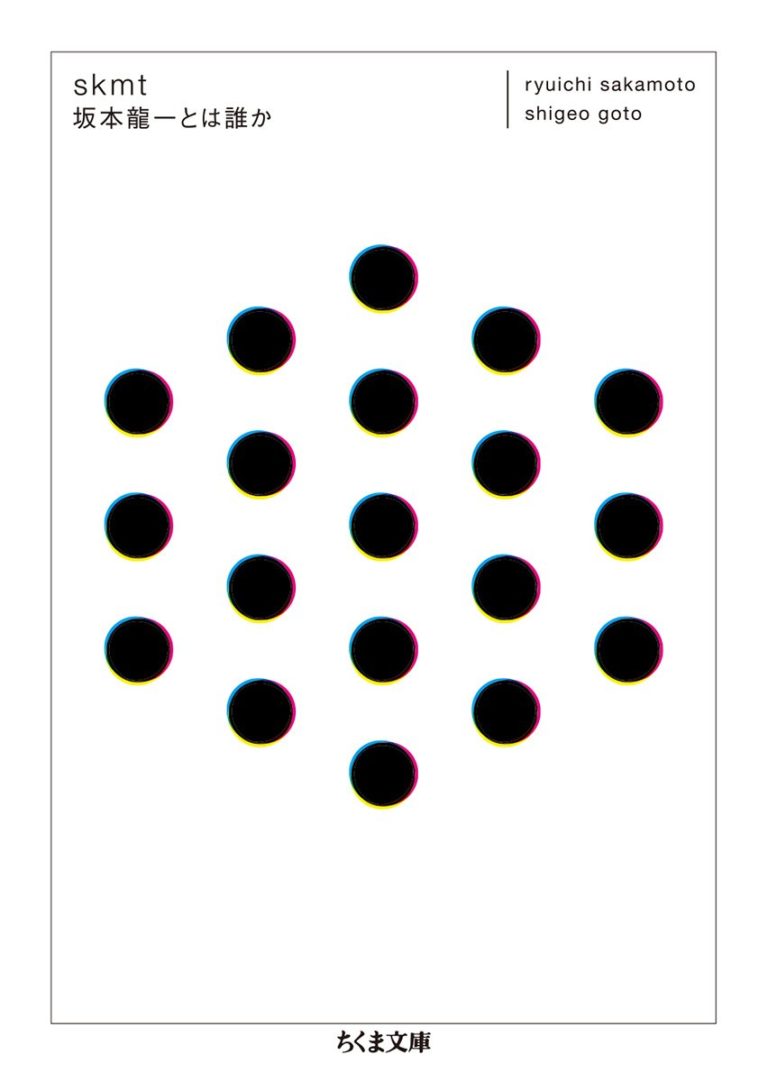『ハドソン川の奇跡』(2016)
映画考察・解説・レビュー
『ハドソン川の奇跡』(2016年)は、クリント・イーストウッド監督が、航空機事故という極限状況下で下された「決断」の是非を、一人の男の孤独な内面と社会のシステムとの対立から描き出した実録映画。主演のトム・ハンクスは、英雄として祭り上げられることに困惑し、自身の判断を疑い、夜のマンハッタンを疾走する機長の揺らぎを、最小限の表情の変化で雄弁に物語る。効率化とデータが支配する現代において、不確かな「経験」という名の重みを信じ抜いた者たちへ捧げられた、静かなる勝利の賛歌。
トム・ハンクスの「毛穴」というスペクタクル
クリント・イーストウッドという男は、映画の常識を完全に無視して、誰も到達できない境地で遊ぶ、確信犯的変態である。
『ハドソン川の奇跡』(2016年)における最大の技術的トピックは、ほぼ全編がARRI ALEXA 65という最新鋭のデジタルIMAXカメラで撮影されたことだ。
通常、このバケモノ級の解像度を持つカメラは、『アベンジャーズ』(2012年)や『レヴェナント: 蘇えりし者』(2015年)のような、画面の端から端まで情報が詰まったスペクタクル超大作のためにある。
だが、イーストウッドはこの6.5Kという超高解像度を、ニューヨークの摩天楼でもなければ、爆発炎上するアクションでもなく、トム・ハンクスの眉間の皺と脂汗、そして白髪交じりの髭の震えを撮るために使ったのだ!
これは映画史上、最も贅沢で、かつ最も倒錯的なIMAXの誤用ではないか。しかし、この選択こそが、本作の批評的核心。イーストウッドは、機長サリー(チェスリー・サレンバーガー)が抱える精神的閉塞感を、逆説的に「画面の広さ」と「被写界深度の浅さ」で表現した。
巨大なスクリーンに、老いたパイロットの顔が大写しになる。逃げ場がない。観客は、サリーの毛穴の一つ一つ、瞳の奥の微細な揺らぎ、英雄として祭り上げられながら犯罪者として追及される男の魂の摩耗までを、強制的に目撃させられる。
これはもはやパニック映画ではない。超高解像度で撮影された、息詰まるような心理的密室劇なのだ。
さらに、イーストウッド組の常連撮影監督トム・スターンによる、徹底的に彩度を落としたルックにも注目すべきだろう。画面を支配するのは、凍てつくようなグレーとブルー。
それは事故当日の極寒のニューヨークの空気感であると同時に、サリーが置かれた“英雄と容疑者の境界線”という冷徹な状況を視覚化している。
イーストウッドは、観客から感情を剥奪し、ただ事象を見つめる観察者としての冷めた視点を強要する。この突き放した演出こそが、逆にラストの感情的カタルシスを論理的に爆発させるための伏線となっているのだから、このジジイは恐ろしいとしか言いようがない。
PTSDシミュレーターとしての反復と脱構築
本作の脚本構成(トッド・コマーニキ)と編集(ブル・マーリー)は、時系列を解体する脱構築の手法が凄すぎて、もはや現代アートの領域に達している。
通常のパニック映画なら、「離陸→トラブル→着水→救助→裁判」という直線的な時間軸を採用し、エモーショナルな家族ドラマを挟みこんでいくだろう。
だが、イーストウッドはそれを拒絶する。映画は、サリーが見る「市街地に墜落する悪夢」から幕を開け、その後も実際の着水シーンが断片的に、視点を変えて何度も何度も反復される。これは、確実にPTSD(心的外傷後ストレス障害)の映画的再現に他ならない。
観客はサリーと同様に、あの日、あの瞬間、あの寒さを、何度もフラッシュバックさせられる拷問に近い体験を強いられる。 コックピット視点、客室乗務員視点、管制官視点、そして救助に向かうフェリーの船長視点。カメラアングルが変わるたびに事実の解像度が上がり、パズルのピースが埋まっていく構成の妙。
特筆すべきは、音響設計だ。バードストライクの瞬間、エンジン音が消失し、劇場は完全な静寂に包まれる。聞こえるのは風切り音と、サリーの呼吸音だけ。この音の不在こそが、リアリズムの極北であり、観客の心拍数を最大化させる演出なのだ。
そしてクライマックスの公聴会シーン。ここで映画は、時間そのものを批評の対象とする。 NTSB(国家運輸安全委員会)のシミュレーションは、「空港へ引き返せたはずだ」と主張する。だがサリーは「人的要因が考慮されていない」反論。
バードストライクから状況を認識し、手順を確認し、決断を下すまでの時間。NTSBはその35秒のラグを無駄な時間とみなすが、イーストウッドはこれを「人間性の証明」として定義し直す。
機械的な即時反応ではなく、人間だからこそ生じる迷いと決断のタイムラグ。この35秒を計算に入れた途端、シミュレーション上の機体は空港に届かず墜落する。
人間が、システムに対して論理的に勝利する瞬間。イーストウッドは、映画というメディアが操作可能な時間という概念を使って、データ至上主義に対する痛快な右ストレートを叩き込んだのである。
ポスト9.11の除霊と86歳の職人が遺したマニフェスト
本作は強烈なポスト9.11映画であり、ある種の除霊(エクソシズム)の儀式でもある。
冒頭、低空でマンハッタンのビル群をかすめる旅客機のビジュアル。これが、2001年9月11日の悪夢を喚起しないはずがない。イーストウッドは意図的に、観客のトラウマスイッチを押す。
だが、決定的に違うのはその結末だ。機体はビルには突っ込まず、ハドソン川へ不時着し、155人全員が生還する。これは、アメリカ人が集団的無意識の中で15年間待ち望んでいた、9.11の書き換えだ。あの日、誰も助けられなかった絶望を、この映画は全員生存という奇跡で上書き保存してみせたのだ。
特に、着水後の救助シーンにおける演出には、イーストウッドの作家性が色濃く出ている。 NY市警のダイバーがヘリから躊躇なく飛び降り、通勤フェリーの船長たちが現場へ急行する。その手際の良さ、プロフェッショナルたちの連携。
ここには、彼が『アメリカン・スナイパー』(2014年)などで描いてきた個の英雄とは対照的な、名もなきプロフェッショナルたちの集合体への信頼がある。
誰かが演説するわけでもなく、ただ淡々と自分の仕事を全うする大人たち。おそらくこれこそが、イーストウッドが信じる“アメリカの良心”なのだ。
一方で、NTSBを徹底的に官僚的な悪役として描いたことには批判もある(事実はもっと協力的だったらしい)。だが、これは「個人の尊厳 vs システムの論理」という、イーストウッド映画に一貫する対立構造を作るための必然的な改変だ。
彼は、サリーという一人の叩き上げの職人を、現代社会を覆うアルゴリズムやマニュアル主義に対する最後の砦として配置した。86歳の監督が、最新のデジタル技術を用いて、「人間の経験知(勘)はデータに勝る」という超アナログなテーマを描く。この皮肉、この矛盾こそが映画だ。
余計な感傷や抱擁を一切排し、96分というタイトな尺に情報を圧縮した本作は、映画作りそのものが職人芸であるという、イーストウッドからの遺言のようなマニフェストだ。
これを枯淡の境地などと、生ぬるい言葉で片付けてはいけない。これは、映画という武器を使った、管理社会システムへの宣戦布告なのだから。
- 監督/クリント・イーストウッド
- 脚本/トッド・コマーニキ
- 製作/クリント・イーストウッド、フランク・マーシャル、アリン・スチュワート、ティム・ムーア
- 製作総指揮/キップ・ネルソン、ブルース・バーマン
- 制作会社/マルパソ・プロダクションズ、ザ・ケネディ/マーシャル・カンパニー
- 原作/チェズレイ・サレンバーガー、ジェフリー・ザスロー
- 撮影/トム・スターン
- 音楽/クリスチャン・ジェイコブ、ザ・ティアニー・サットン・バンド
- 編集/ブル・マーレイ
- 美術/ジェームズ・J・ムラカミ
- 衣装/デボラ・ホッパー
- 恐怖のメロディ(1971年/アメリカ)
- アイガー・サンクション(1975年/アメリカ)
- ガントレット(1977年/アメリカ)
- ファイヤーフォックス(1982年/アメリカ)
- ペイルライダー(1985年/アメリカ)
- ホワイトハンター ブラックハート(1990年/アメリカ)
- 許されざる者(1992年/アメリカ)
- パーフェクト・ワールド(1993年/アメリカ)
- マディソン郡の橋(1995年/アメリカ)
- トゥルー・クライム(1999年/アメリカ)
- スペース カウボーイ(2000年/アメリカ)
- ブラッド・ワーク(2002年/アメリカ)
- ミスティック・リバー(2003年/アメリカ)
- チェンジリング(2008年/アメリカ)
- グラン・トリノ(2008年/アメリカ)
- インビクタス/負けざる者たち(2009年/アメリカ)
- ヒア アフター(2010年/アメリカ)
- J・エドガー(2011年/アメリカ)
- アメリカン・スナイパー(2014年/アメリカ)
- ハドソン川の奇跡(2016年/アメリカ)
- クライ・マッチョ(2021年/アメリカ)
- 陪審員2番(2024年/アメリカ)
![ハドソン川の奇跡/クリント・イーストウッド[DVD]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/91NGxGgJqyL._AC_UL640_FMwebp_QL65_-e1769752645354.webp)
![レヴェナント: 蘇えりし者/アレハンドロ・ゴンサレス・イニャリトゥ[DVD]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/81DixGETsKL._AC_UL640_FMwebp_QL65_-e1767690186360.webp)
![アメリカン・スナイパー/クリント・イーストウッド[DVD]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/81y3nEzSnmL._AC_SL1500_-e1707310983750.jpg)