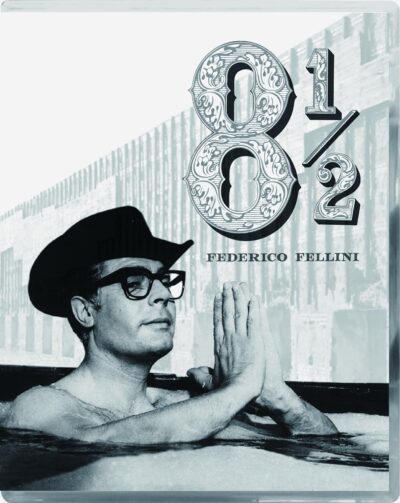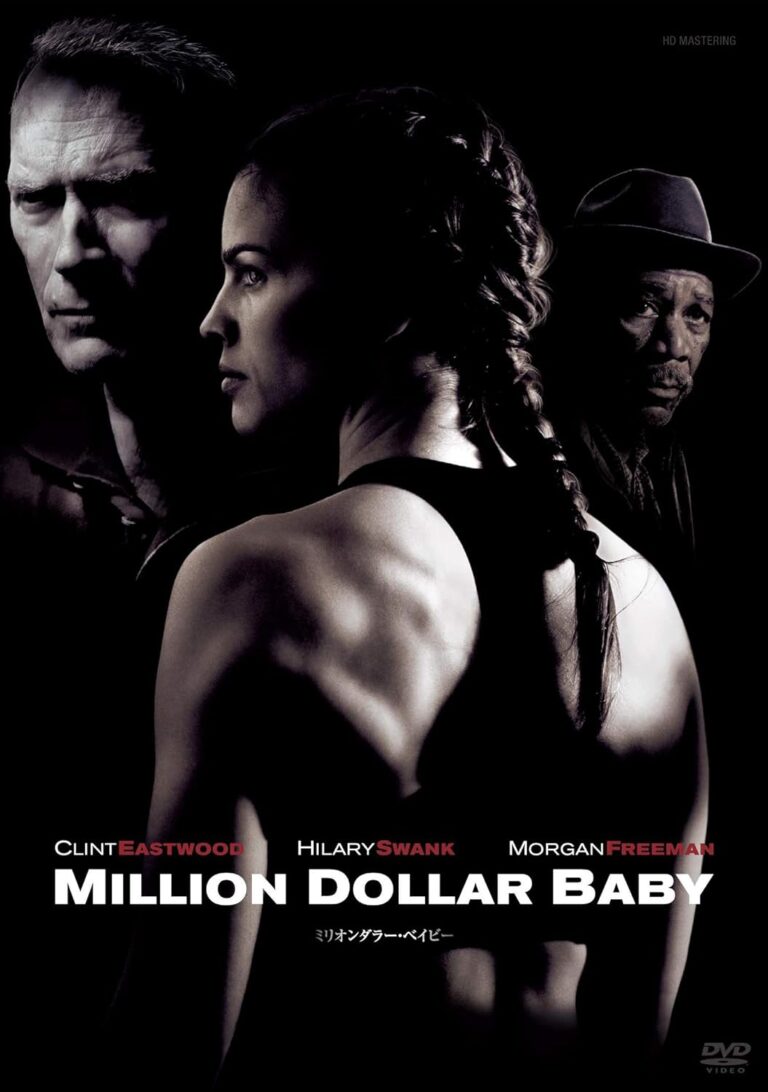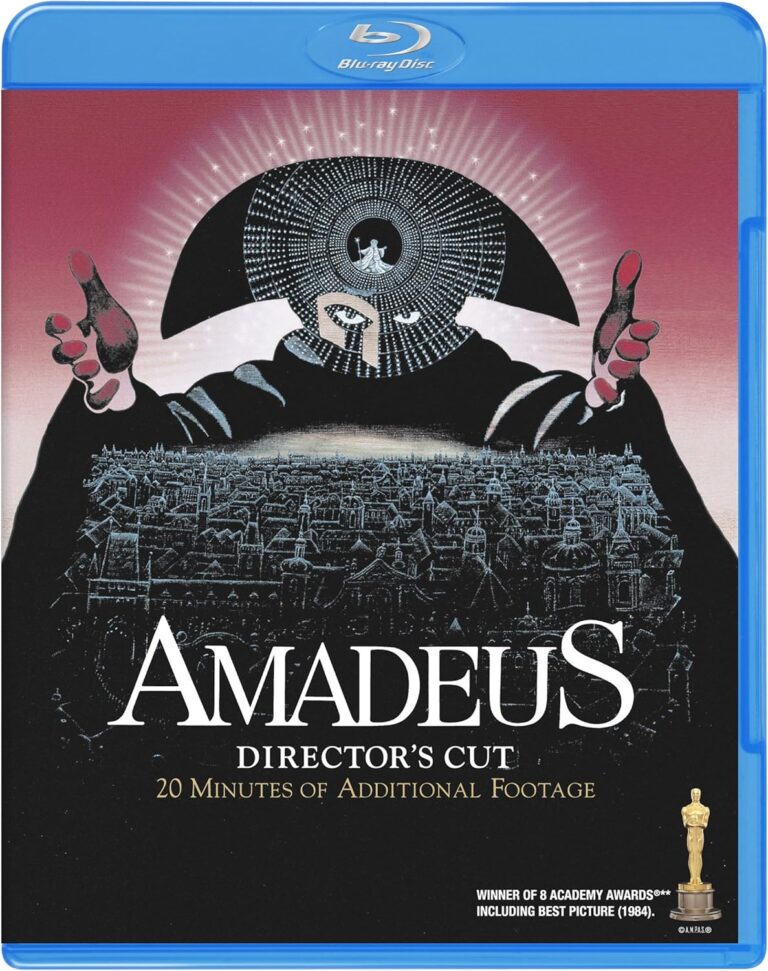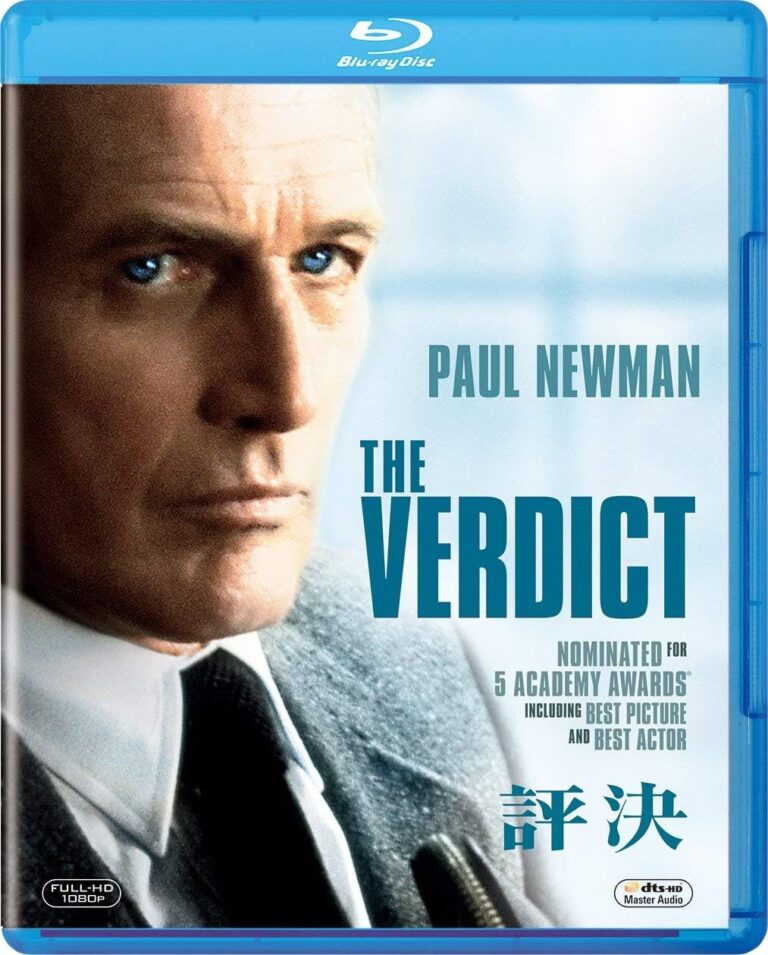『TAKESHI’S』──“ビートたけし”が“北野武”を殺すとき
『TAKESHI’S』(2005年)は、ビートたけし監督が自らをモチーフに、“ビートたけし”と“北野武”という二重の人格を描いた異色作。売れっ子俳優として成功する男と、コンビニ店員として日々を過ごすもう一人の自分。夢と現実、映画と日常が交錯する中で、銃を手にした瞬間、虚構のバランスは崩れ、暴力と幻覚が入り混じる迷宮へと変貌していく。
『ドッグヴィル』と通底する力の行使
『TAKESHI’S』(2005年)を観終わったあと、僕の脳裏にまず浮かんだのはラース・フォン・トリアーの怪作『ドッグヴィル』(2003年)だった。
終盤、マフィアの首領を演じるジェームズ・カーンがニコール・キッドマンに言い放つ「力は行使されるべきものだ」という台詞。それは、圧倒的パワーを持つ者がそれを行使しないことは欺瞞であり、傲慢ですらあるという文脈で語られる。だが、この言葉はそのまま北野武という一個人が抱えてきた内面的問題に直結している。
それは、単なる物語の転換点を示す言葉ではない。そこには、圧倒的な力を保持しながらそれを用いないことは欺瞞であり、むしろ傲慢ですらあるという苛烈な倫理的要請が含まれている。その言葉を『TAKESHI’S』に接続したとき、浮かび上がるのは北野武が抱え続けてきた「力」との格闘だ。
監督としての資本や演出の決定権、カメラを通じて何を見せ何を切り捨てるかという可視化の権力、そして物語の中で銃を持ち暴力を振るうキャラクターの力。これらすべてが彼の身体の中で短絡し、逃げ場なく自分自身へと跳ね返ってくる。
だからこそ『TAKESHI’S』は、力を行使しないことで免責される道を初めから閉ざしている。持ってしまった以上、使わざるを得ず、使った以上は責任を引き受けるしかないのだ。
“ビートたけし”と“北野武”という二重構造は、責任を押し付け合う分身トリックのようにも見えるが、むしろ逆である。力の総体としてのビートたけしと、疎外される北野武という対立は、行使の愉悦とその嫌悪を一人の人間の中で増幅させる仕掛けだ。
銃を手にした瞬間、北野武は「力を行使する者」となり、やがてビートたけしを刺殺する。そこにあるのは、スターであることから逃れられない自分自身への自覚的な苛立ちであり、自己破壊的なカタルシスである。
「妄想の可視化」としての映画
映画は「見たいものだけを見せる/見せたくないものを消す」という選択の装置であり、その選択を実行するための時間・資金・人の身体を束ねる権利=資本が裏打ちしている。だから“妄想の可視化”は、脚本の着想や演出の妙といった創作の純度に還元できない。
キャスティングで誰を呼ぶか、画面のどこに立たせるか、どのテイクを残してどう繋ぐか、そしてどれだけのスクリーンに流通させるか――すべてが「誰の妄想が世界の標準になるのか」を決める政治である。
北野の場合、監督=設計者と俳優=担い手が同一の身体に収斂している。妄想の発注者と実演者が一致することで、行使と責任の回路は閉じ、免責の逃げ道はなくなる。
だから『TAKESHI’S』では、可視化の権力を「使わない」ことで清潔を装うのではなく、「使ってしまった後に何を引き受けるか」が正面から問われる。行使の瞬間に快楽と嫌悪が同時に立ち上がる、その揺れこそが映画の主題なのだ。
北野武は自分が“ビートたけし”であるからこそ、清純派女優の京野ことみをヌードにさせたり、ラーメン屋の主人をゾマホンにしちゃったり、ラーメン屋でナポリタンを注文することが可能となる。
まさしく、自分自身が作品内に持ち込むことができる力学の露出。画面の外側では、出演交渉や現場の段取り、プロダクションの判断が実際に動き、他者の時間と身体が北野の妄想に編入されている。その現実の編成こそが「特権」の正体であり、メタ構造はそれを免罪しない。
さらに言えば、可視化はそれ自体が軽い暴力を含む。カメラは誰かの内面を切り取り、編集は出来事の因果を作り替える。『TAKESHI’S』で繰り返される突発的な切断、唐突な配置替え、笑いに転化される違和感は、「見せる権利」を握る側の恣意をあえて露出させる演出だ。
ジェンダーや人種、階層の記号を遊戯的に扱うたび、画面は“遊び”の快楽と“非対称性”の居心地の悪さを同時に観客へ返す。
では倫理はどこに宿るのか。北野が選ぶのは“自粛”ではなく“露出”である。行使そのものをやめるのではなく、行使のプロセスと効果を作品内で可視化し、引き受けるべき影を隠さない。
観客もまた、その可視化を消費することで共犯化される。笑う/たじろぐ/目を伏せる――その反応は、私たち自身の妄想と特権のあり方を鏡にかける行為だ。『TAKESHI’S』が示すのは、妄想の可視化が「表現」だけでなく「現実の再配置」だという事実であり、そこにこそ映画というメディアの甘さと苦さが凝縮している。
二重の人格 ――「力を行使する者」と「される者」
映画スターとしての“ビートたけし”と、しがないコンビニ店員の“北野武”。二人は「力を行使する者」と「力を行使される者」という鮮やかな対照関係を成す。
銃を手に入れた北野武は、「力を行使される者」から「力を行使する者」へと変貌し、やがてビートたけしを刺殺する。このシークエンスは単なる作家的メタ演出ではなく、生涯「ビートたけし」として生を全うせざるを得ない本人の煩悶を直截に刻み込んでいる。
ここで想起されるのは、フェデリコ・フェリーニ監督の『8 1/2』(1963年)や、ジャン=リュック・ゴダール監督の『軽蔑』(1963年)の系譜だ。作家が自身の内的苦悩を投影した自己言及的フィルムの流れに、『TAKESHI’S』は確実に連なる。
『8 1/2』は、演出家グイドの内的分裂を〈夢・回想・妄想〉の流動体として循環させ、最後はサーカスの輪にすべての登場人物を呼び入れる“合唱”へと昇華していた。
ここでの力は、監督=指揮者が場を仕切る権能であると同時に、制御不能な欲望や記憶に身体を明け渡す受動性でもある。たとえばハーレム幻想の場面で、グイドは女性たちを規律するふりをしながら、結局は彼女たちに追い詰められる。行使と被行使が一つの円環で回り続ける――それがフェリーニの解答だ。
『軽蔑』は対照的に、映画産業の権力関係(プロデューサー/監督/脚本家)を夫婦の感情破綻に転写して、〈資本の命令〉と〈芸術の自尊〉のあいだに走る断層を冷徹に固定する。
プロデューサーの赤いスポーツカー、カプリ島の幾何学的な空間、ブリジット・バルドーの身体――それらは視線と所有の政治を可視化する装置であり、最終的にカップルは修復不可能な「断絶」に到る。
ここでの力は、交渉と譲渡の結果としての支配であって、個人の内奥に循環するものではない。だからゴダールは、合流ではなく分離の不可逆性をこそ映画の表面に刻む。
『TAKESHI’S』は、この二つのモードを踏まえつつ、さらに別の第三の解答を提示する。つまり、フェリーニ的な“円環”でも、ゴダール的な“断絶”でもなく、同一身体内での「処断」である。
スター“ビートたけし”と無名の“北野武”という二重身を、夢や象徴のレベルで融解させもせず、また外部の産業力学へと純化もしない。代わりに“北野武”は銃という行為能力を獲得し、“ビートたけし”を物理的に刺殺する。
ここではフェリーニ的な合唱=共存の祝祭は起きず、ゴダール的な制度批判の遠近法にも退かない。円環と断絶を飲み込んだ末に、作者は自らのスター・テクストを自分の手で処刑する。この決行の暴力性こそが、『TAKESHI’S』を自己言及映画の系譜に連ねながらも、そこから逸脱させるユニークな推進力になっている。
言い換えれば、フェリーニは分裂を“踊り”で和解させ、ゴダールは分裂を“距離”で確定させたのに対し、北野は分裂を“行為”で終わらせる。円環(合唱)/断絶(距離)/処断(行為)という三つのモードの中で、『TAKESHI’S』はもっとも苛烈に、作者が持つ力の行使とその責任を一身に引き受ける道を選ぶ。
だから観客が受け取る後味は、説明による了解でも、批評による安堵でもない。行使のあとにしか残らない引き受けの重さだけが、刺殺の残響として手の中に残るのだ。
岸本加世子という「バランサー」
作中、岸本加世子が演じる謎の女は、常に北野武の行動に茶々を入れ、妨害する。彼女は“力を行使する者=ビートたけし”と“力を行使される者=北野武”の共存を助けるバランサー的存在だ。この役割分担にこそ、北野武が抱く「力」への懐疑と矛盾が映し出されている。
また、この“横槍”には、北野が長く身を置いた漫才の回路――ボケ/ツッコミ――も埋め込まれている。逸脱=ボケ(恣意・越境)としてのビートたけしに対し、岸本は規範=ツッコミ(抑制・秩序)として反応する。
しかし彼女のツッコミは相手を屈服させるためではなく、過剰な力が破局へ直進する軌道をわずかに曲げ、両人格が共存できる振幅に調律するためのものだ。つまり彼女は笑いのためのブレーキではなく、破局回避のメトロノームとして機能している。
『ソナチネ』(1993年)や『HANA-BI』(1997年)における暴力は、しばしば“決断のショートカット”として示されていた。引き金を引けば世界は一気に収束する。『TAKESHI’S』で岸本が果たす役目は、そのショートカットをあえて遠回りに変えることにある。
映画を撮る=撃つ、という等式が作動しはじめるとき、彼女は無言のうちに回路へ抵抗を挿入し、即時性を遅延させ、行使の前後に横たわる責任や後味を見えるようにする。
だから彼女の妨害は単なる“物語の邪魔”ではない。行使を可視化するための条件づくりであり、可視化の倫理を作品内に埋め込むプロセスそのものだ。
さらに、岸本は観客の代理でもある。彼女が眉をひそめ、茶々を入れる瞬間、私たちの胸中の“ちょっと待て”がスクリーン上で言語化される。この同調が生まれることで、観客は消費者の無邪気さから一歩引き剥がされ、享受の共犯性を自覚する。
北野が「行使後に何を引き受けるか」を自問するのと同時に、観客も「見届けた自分は何を引き受けるのか」と問われる――その問いを運んでくるのが、彼女の反復的な介入である。
総じて、岸本加世子は“行使/抑制”のスイッチを切り替える手ではなく、スイッチそのものに抵抗を与えるバランサーだ。力の直進を鈍らせ、時間を稼ぎ、責任の層を浮かび上がらせる。
もし彼女が不在なら、『TAKESHI’S』は願望充足の一直線か、自己破壊の一撃で終わっていただろう。彼女の存在が、欲望の速度を倫理の速度へと変換し、映画を“撃つ快楽の記録”から“行使と引き受けの記録”へと転調させている。
「キタノの穴」としてのフィルム
『マルコヴィッチの穴』(1999年)ならぬ「キタノの穴」と呼ぶべき『TAKESHI’S』は、北野武の内的葛藤をそのまま追体験できる希有なフィルムである。ここに難解さは存在しない。あるのは「力を行使する者」の愉悦と苦悩がワンパッケージされた、極めて誠実な映像体験だ。
そして観客は、スクリーンを通じて“北野の穴”を覗き込んでしまった。もしかすると私たちは皆、彼自身と同じく「虚構と現実の狭間」に巻き込まれてしまったのかもしれない。
- 製作年/2005年
- 製作国/日本
- 上映時間/107分
- 監督/北野武
- 脚本/北野武
- プロデューサー/森昌行、吉田多喜男
- 撮影/柳島克己
- 音楽/NAGI
- 音楽プロデューサー/野田美佐子
- 美術/磯田典宏
- 編集/北野武、太田義則
- 衣装/山本耀司
- 録音/山堀内戦治
- ビートたけし
- 京野ことみ
- 岸本加世子
- 大杉漣
- 寺島進
- 渡辺哲
- 美輪明宏
- 六平直政
- ビートきよし
- 津田寛治