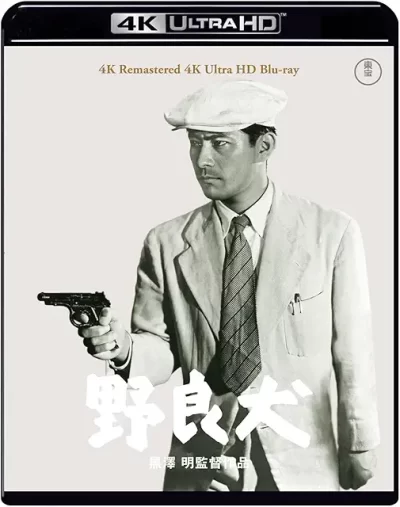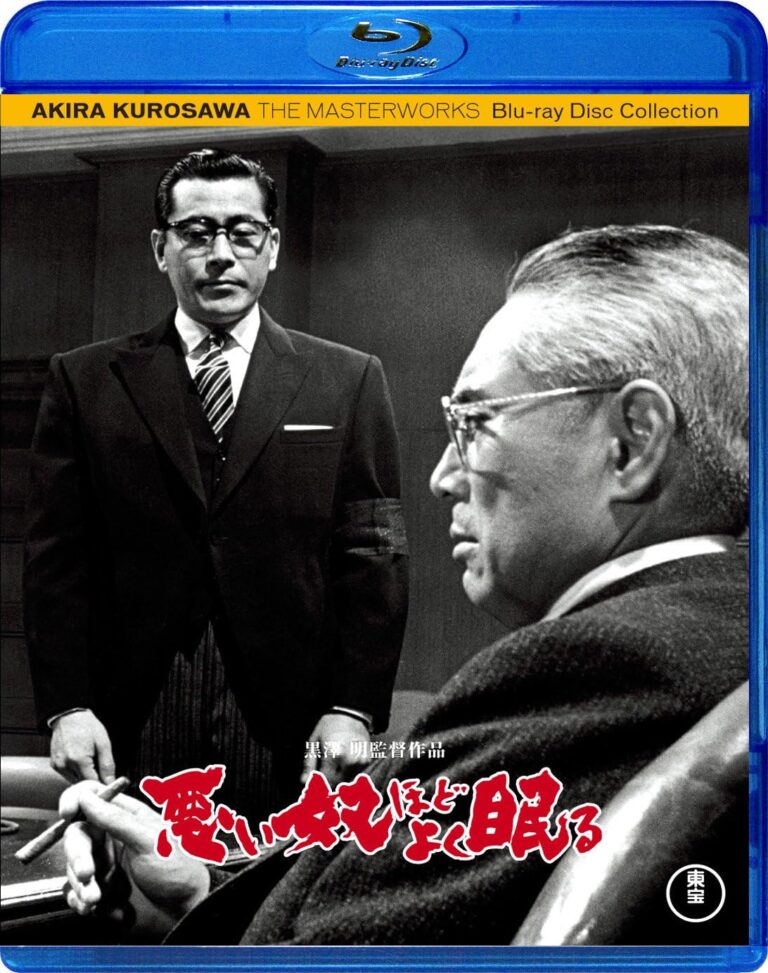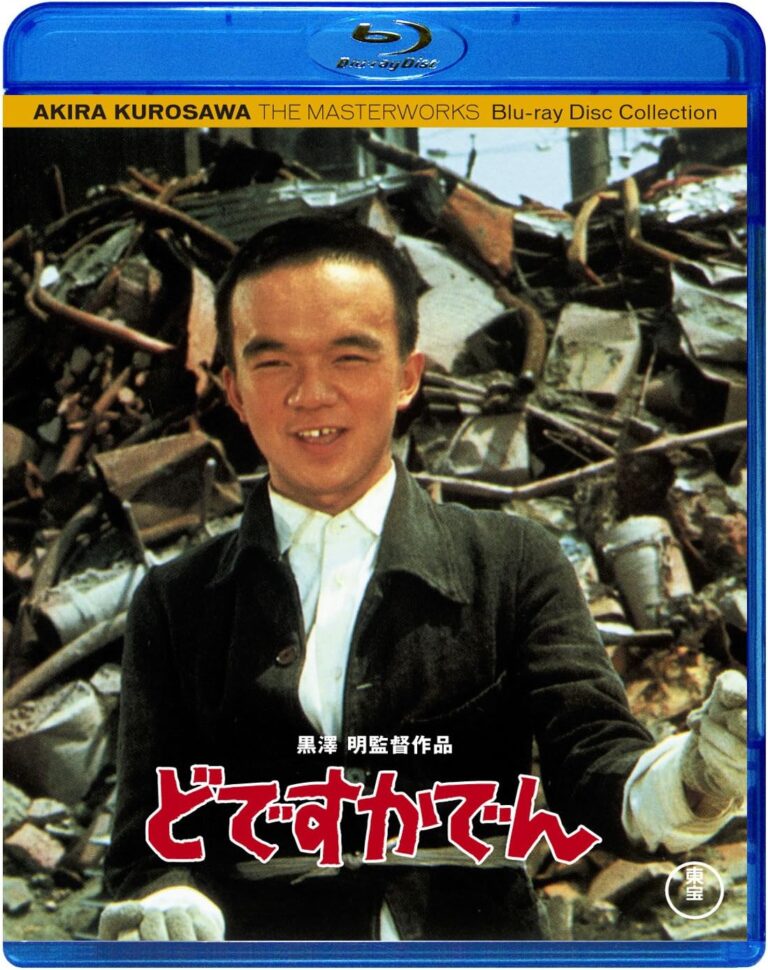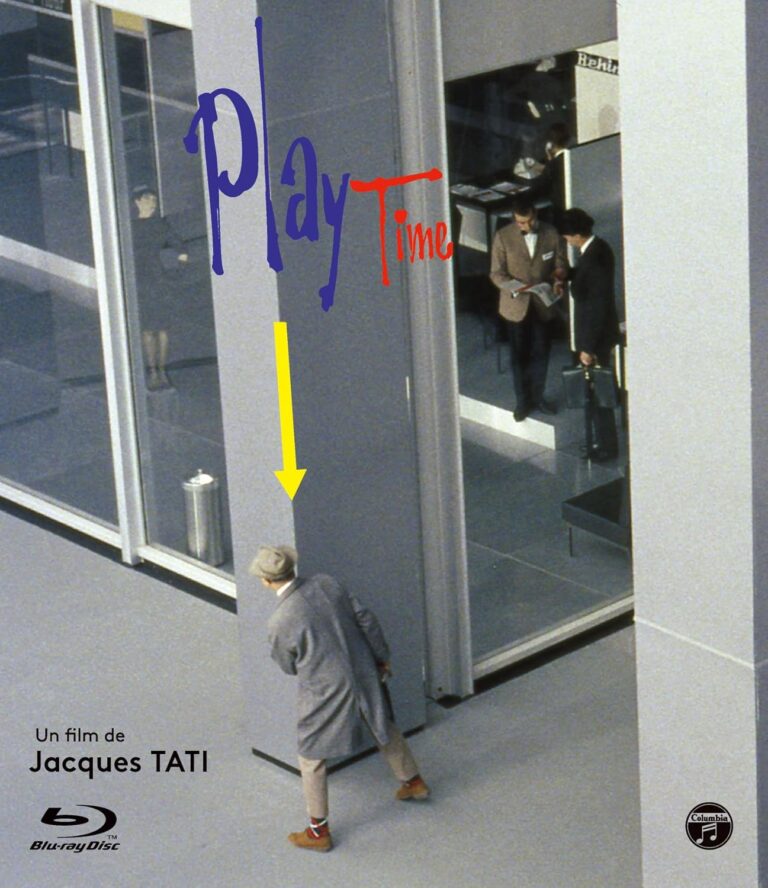『七人の侍』(1954)
映画考察・解説・レビュー
『七人の侍』(1954年)は、黒澤明が監督・共同脚本を務めた東宝製作の時代劇。戦国の農村が野武士の襲撃に怯える中、老侍・勘兵衛を中心とする七人の浪人が村を守るために雇われる。侍たちは農民と共に防衛策を練り、砦を築き、田畑を守るために奮闘する。豪雨の中での最終決戦、失われていく命、そして残された者たち。戦と平和の狭間で交錯する人間の絆と断絶を描いた、黒澤映画の代表作である。
「お茶漬け映画」への反逆──巨人・黒澤明の胃袋とスケール感
お茶漬けのようなこじんまりとした日本映画ではなく、御馳走がたくさん入った作品を作ろうと思った
『七人の侍』(1954年)に関するこの黒澤明の言葉は、単なる比喩ではない。戦後日本映画の小市民的傾向に対する、明確な戦宣布告だった。
当時の東宝は、サラリーマン喜劇や文芸メロドラマで安定した収益を上げていた。だが、身長180センチの巨躯を揺らし、肉を喰らい、映画のことしか考えないこの天皇は、そんな箱庭のような平和を許さない。
彼は、誰も見たことのない本物の戦国時代を再現するために、会社の金庫を空にする勢いで金を使いまくった。製作費2億1000万円(現在の貨幣価値で数十億円規模)、撮影期間は約1年。通常の映画の5倍以上のリソースを投入し、東宝の上層部は幾度となく撮影中止を画策した。
だが黒澤は、撮影済みのラッシュフィルムを重役たちに見せることで黙らせたという。その映像が放つ圧倒的な熱量は、経営判断という理性を蒸発させるほどの威力を持っていたのだ。
黒澤が本作で導入したマルチカム方式は、映画に偶然性とドキュメンタリー性を召喚するための魔術である。クライマックスの雨中の決戦、泥に足を取られ、馬が暴れ、人間が転げ回るカオスは、一度きりのテイクでしか生まれない。その必死さを逃さないために、黒澤は複数のカメラを配置し、あらゆる角度からその瞬間を切り取った。
さらに、望遠レンズの多用が画面に革命をもたらす。望遠レンズは遠近感を圧縮し、人間と馬と槍が団子状になって押し寄せるような密度の壁を作り出す。これにより、観客は安全な客席ではなく、戦場の真っ只中に放り込まれることになる。
黒澤の胃袋は、時間、空間、音響、群像という映画のポテンシャルをすべて飲み込み、消化し、巨大なエネルギーとしてスクリーンに吐き出した。そのあまりのカロリーの高さゆえに、我々は70年経った今もなお、胸焼けするほどの興奮を覚え続けている。
侍と農民を繋ぐ三船敏郎
『七人の侍』が、後の『荒野の七人』(1960年)から『アベンジャーズ』(2012年)に至るまで、あらゆるチーム結成もの(リクルート映画)の教科書とされる理由は、その緻密な構造にある。農民たちが侍を探し、一人また一人と仲間が増えていくプロセスが見事すぎるのだ。
リーダーの勘兵衛(志村喬)は、僧侶に変装して強盗を斬ることで、知恵と人格を示す。寡黙な剣豪・久蔵(宮口精二)は、竹藪での決闘を通じて技の極致を見せる。そして参謀の五郎兵衛、ムードメーカーの平八、古女房の七郎次、未熟な勝四郎。
黒澤は、それぞれのキャラクターの機能と魅力を、セリフではなくアクションによって紹介していく。観客は、教科書を読むようにではなく、彼らの生き様を目撃することで、自然と7人を愛してしまうのだ。
そして、この精密なパズルの中に放り込まれた爆弾こそが、三船敏郎演じる菊千代だ。彼は侍の家系図を盗んだ偽物であり、百姓の出だ。本来なら、侍と農民という二つの階級は決して交わらない。侍は農民を軽蔑し、農民は侍を恐れる。この冷たい断絶こそが、戦国時代のリアリズムだ。
だが、菊千代という獣だけが、その境界線を土足で踏み越える。彼が「農民を米粒一つないようにしたのは誰だ! お前ら侍じゃねえか!」と叫ぶシーン、あれは単なる罵倒ではない。この映画が抱える社会的な矛盾、搾取する者とされる者の歴史的な怨念を、すべて引き受けた魂の叫びだ。
黒澤は、三船敏郎という俳優の過剰な身体性をフル活用し、映画に土の匂いと生の躍動を与えた。菊千代がいなければ、この映画は高潔な騎士道物語で終わっていたかもしれない。彼がいることでこの映画は、階級闘争と人間愛が火花を散らす、普遍的なドラマへと昇華されたのだ。
豪雨の黙示録と「敗北」の哲学
豪雨のなか行われる、『七人の侍』のクライマックス・シーン。黒澤明は、雨を単なる気象現象として描かなかい。彼は雨を、画面を埋め尽くす“縦の線”として、そして人間たちの体温を奪い、視界を遮る物理的な暴力として描いた。墨汁を混ぜたとも言われるその黒い雨は、スクリーンを抽象画のように変貌させる。
ぬかるみの中で、侍も野武士も農民も、泥人形のように区別がつかなくなる。そこにあるのは、英雄的な剣戟ではなく、足を滑らせ、這いつくばり、悲鳴を上げながら殺し合う、惨めな殺し合いだ。
黒澤はここで、アクション映画のカタルシスを提供しつつ、同時に暴力の痛みと死のあっけなさを冷徹に突きつける。あれほど強かった久蔵が、火縄銃の一発であっさりと死ぬ衝撃。菊千代が相打ちになって倒れる時の、あの獣の断末魔。黒澤のカメラは、死にゆく英雄を美化しない。ただ、雨の中に転がる死体として記録する。
そして、戦いが終わり、晴れ渡った空の下で行われる田植えのシーン。生き残った勘兵衛は、新しい塚を見上げながら、あまりにも有名なセリフを吐く。「今度もまた、負け戦だったな。勝ったのはあの百姓たちだ。わし達ではない」。
侍たちは、命を賭けて村を守った。だが、平和が戻れば、彼らは用済みの暴力装置でしかない。農民たちは大地に根を下ろし、生命を循環させていくが、侍たちは風のように去るのみ。
黒澤はここで、西部劇のような去りゆくヒーローの美学ではなく、土着の生命力の前では、武士の理想がいかに儚く脆いものであるかという、残酷な歴史の真実を提示する。
『七人の侍』は、アクション映画の頂点でありながら、最終的にはアクションの虚しさを説くという、巨大な矛盾を孕んでいる。だが、その矛盾こそが、この映画を単なる娯楽作から名作へと押し上げた。
世間の圧倒的な評価ほど、僕はこの映画を愛していないかもしれないけど、未曾有の大作であることは揺るがない。ホント、何度見返しても眩暈がするくらいに面白いです。

![荒野の七人/ジョン・スタージェス[DVD]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/71LdKLT9wiL._AC_SL1254_-e1707299746944.jpg)