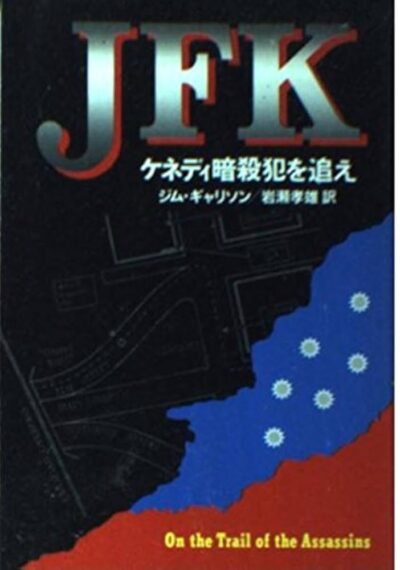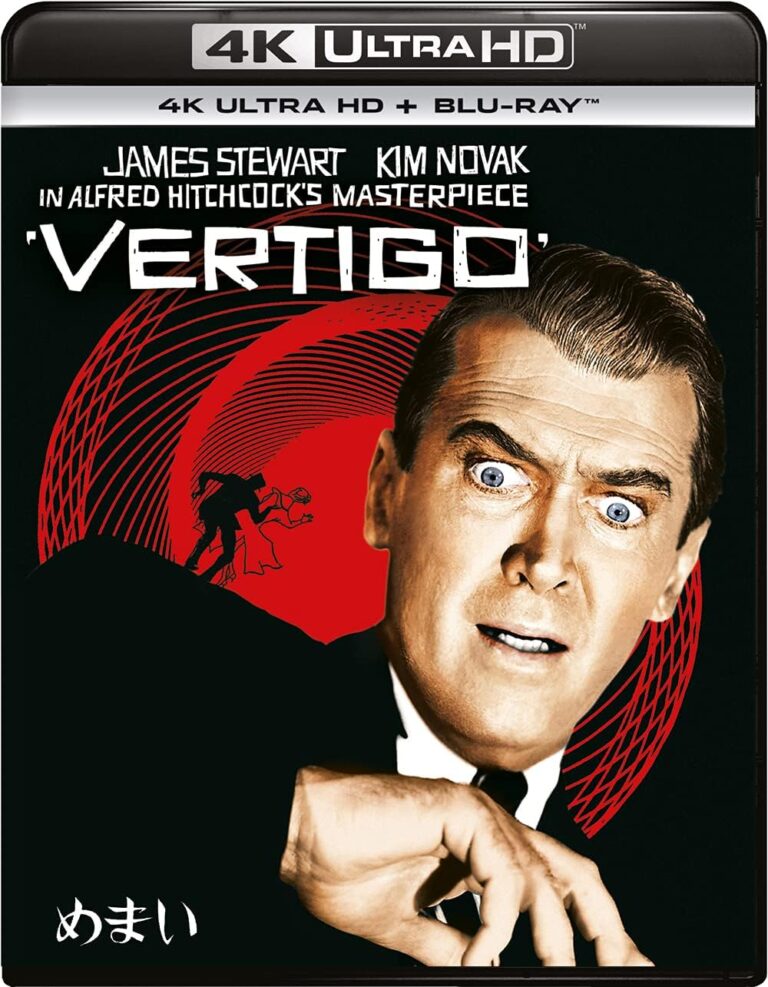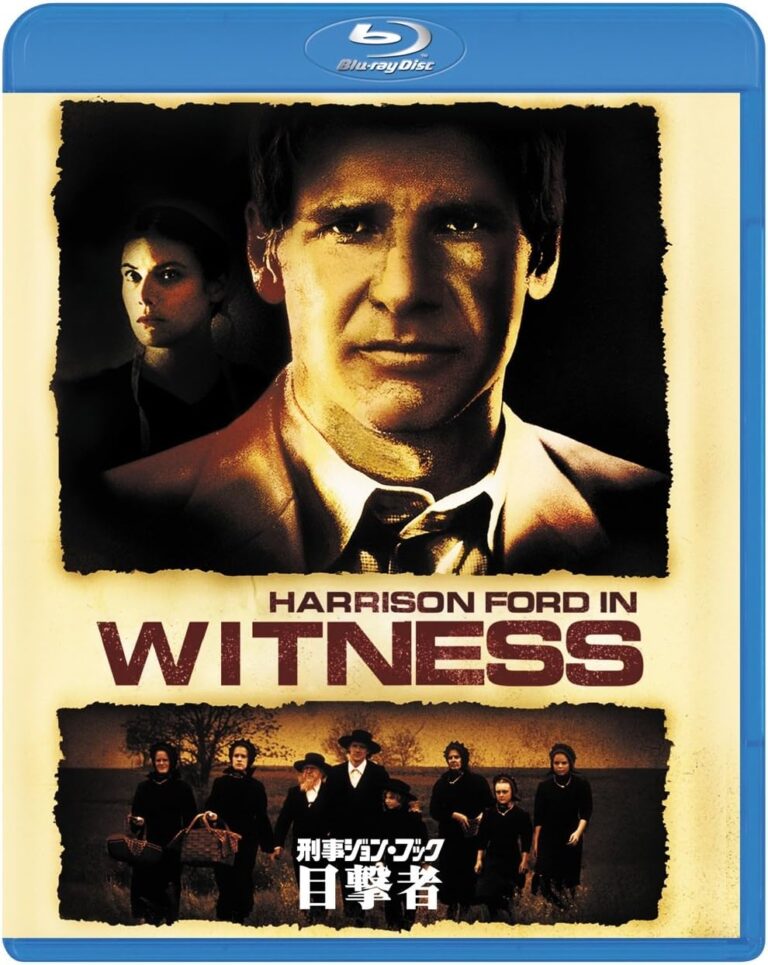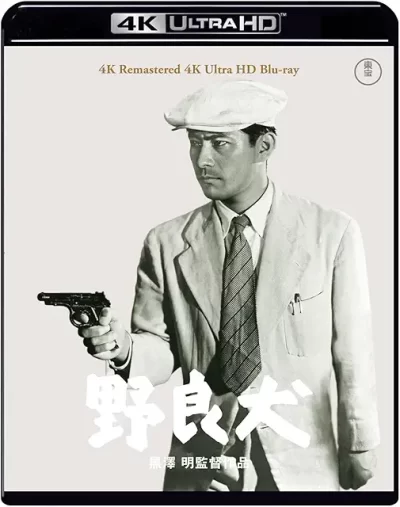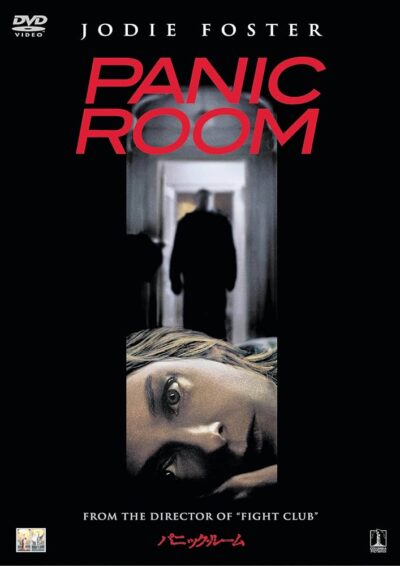『JFK』(1991)
映画考察・解説・レビュー
『JFK』(1991年)は、アメリカの歴史に刻まれたケネディ暗殺事件を再検証する法廷サスペンス。地方検事ジム・ギャリソン(ケビン・コスナー)が、オズワルド単独犯行説の矛盾に挑み、国家的陰謀の真相を探る。オリバー・ストーン監督は、断片的映像と証言を組み合わせることで、政治と正義の狭間にある“信じること”の意味を問い直す。
冷遇される巨匠オリバー・ストーン
オリバー・ストーンほど冷遇されている映画監督もいないだろう。
『プラトーン』(1986年)、『7月4日に生まれて』(1989年)で二度にわたりアカデミー監督賞を受賞した巨匠でありながら、彼の名が映画ファンや批評家の議論に上ることは驚くほど少ない。
本屋の映画コーナーを覗けば、ゴダールやヒッチコック関連の書籍は溢れているのに、ストーンに関する著作を見かけることはほとんどない。
その理由は自明だ。ストーンのフィルモグラフィーは、常にジャーナリスティックな視座と苛烈な政治性に貫かれている。『プラトーン』や『7月4日に生まれて』はベトナム戦争という国民的トラウマを露骨に可視化し、『ウォール街』(1987年)は資本主義の強欲を告発した。
これらの作品はすべてアメリカ社会の核心的矛盾を暴き出すものであり、作品を論じるには戦争史や経済構造、政治権力といった広大なコンテクストに触れざるを得ない。
言い換えれば、ストーンの映画は「純粋な映画美学」に閉じた批評領域に回収されにくいのだ。観客や批評家の政治的立場によって評価が大きく揺れ動き、時には「プロパガンダ」として切り捨てられることすらある。
そのため、彼は巨匠でありながら、ゴダールやヒッチコックのように「映画そのもの」の文脈で体系的に論じられる機会を逸してきた。
日本においても状況は相似形を描く。日本の映画批評文化は伝統的に、作家性や映像美学、ジャンル的革新といった「表現の形式」に焦点を当てる傾向が強い。その枠組みにおいて、ストーンのように政治的メッセージを前景化する作家は扱いづらく、結果として議論の俎上に載ることが少ない。
ゆえに、二度のアカデミー監督賞受賞という事実にもかかわらず、日本の書店でストーン関連書籍を見かけることは稀であり、彼の存在は批評的射程から外れ続けているのである。
『JFK』という衝撃的体験
そうした冷遇のなかで1991年に公開された『JFK』は、僕にとって映画体験の原点とも呼ぶべき衝撃を与えた作品だった。ケネディ暗殺事件の真相に迫る本作は、実写映像を織り込みながら怒涛のテンポで展開するドキュメンタリータッチのドラマ。
真犯人はオズワルドではなく国家権力の陰謀だった──というストーンの大胆な結論は独善的に映る部分もある。しかし「歴史的惨劇を再び問い直すべきだ」というストーンのメッセージは、当時まだ政治に無関心だった若者の僕にすら強烈に突き刺さった。
この映画の基盤となっているのは、ニューオーリンズ地方検事ジム・ギャリソンの著作『JFK: ケネディ暗殺犯を追え』。彼は実際にケネディ暗殺事件の再捜査を行い、CIAや軍産複合体の関与を疑った人物だ。
ストーンはその視点を映画化し、ギャリソンを「国家の暗部に挑む孤高の告発者」として描き出した。つまり『JFK』は、単なるフィクションではなく、現実の司法と政治の闇に立ち向かった一人の男の闘争を映像化したものでもあった。
実際の暗殺事件は1963年11月22日、テキサス州ダラスで起きた。世界が注視するなか、ジョン・F・ケネディ大統領はパレード中に銃弾に倒れた。
公式調査ではオズワルドの単独犯行とされたが、不可解な点や証言の矛盾が数多く残り、アメリカ社会には長らく陰謀論が渦巻いてきた。ストーンはその「歴史の空白」に大胆に切り込み、観客に「本当に真実はこれでよいのか」と問いかけるのである。
その中心に立つのが、ケビン・コスナー演じる検事ギャリソンだ。彼は誠実で実直な人物として描かれ、政治権力に翻弄されながらも真実を追い続ける姿は、観客にとっての「代弁者」となる。コスナーの静かな熱量と道徳的信念は、ストーンの過剰な演出を中和し、むしろ映画を普遍的なドラマへと押し上げている。
初見の衝撃が忘れられず、どうしても再確認したくなって再び劇場へ足を運んだ。同じ映画を二度映画館で観たのは、この作品が初めてである。
『JFK』には、ストーン作品特有のアクの強さや説教臭さをも凌駕するほどのエネルギーが横溢していた。むしろそのアクの強さこそが推進力として作用していたのである。
ダイナミックな編集のリズム
とりわけ圧巻なのは、編集のリズム。実際のニュース映像や暗殺現場の記録を巧みに差し込み、超高速のカット割りで観客を圧倒する。証言と証拠が畳み掛けるように提示されることで、観客はあたかも陪審員席に座らされ、否応なしに「事件の再検証」という劇場的空間に引きずり込まれていく。
この編集術は、単なるスピード感の演出ではない。ストーンにとって編集とは、断片化された歴史のパズルを再構築する政治的行為そのものなのである。
『JFK』のモンタージュは、エイゼンシュテイン的な知的モンタージュを想起させる。複数の映像断片を衝突させ、観客に新たな意味を読み取らせる手法だ。ストーンはそれを90年代のアメリカに蘇らせ、映像の氾濫するメディア社会に対して「歴史の真実」を構築しようと試みた。
この方法論は、ストーンの他の作品にも一貫して流れている。たとえば『ウォール街』では、株価ボードの点滅や新聞の見出し、電話をかけ続けるブローカーたちの断片を高速に切り替えることで、資本主義の狂騒を映像的に体感させた。
また『ナチュラル・ボーン・キラーズ』(1994年)では、35mmフィルムとビデオを混在させ、フィルターや色彩を極端に操作することで、メディア暴力が人々の知覚をいかに撹乱するかを可視化した。ここでも編集は単なる「テンポ」ではなく、「現実の分裂した姿」を表象する機能を担っている。
つまりストーンにおける編集とは、出来事の「再現」ではなく「再構築」である。『JFK』の法廷シーンで次々と提示される映像断片は、観客に「真実らしさ」を植え付けると同時に、「何が真実か」という不安を逆説的に呼び起こす。編集そのものが、歴史の信憑性に挑戦する批評的装置になっているのだ。
この観点から見ると、『JFK』の編集は決して中立的な証拠提示ではなく、ストーンによる「歴史の再脚本化」であり、政治的アクションそのものだったといえる。観客はその編集の渦に呑み込まれることで、ストーンの視座を追体験し、同時に歴史の真実をめぐる「審判」を強制される。
ジョン・ウィリアムズの音楽
その圧倒的リズムは、ジョン・ウィリアムズの音楽によってさらに増幅されている。ウィリアムズといえば『スター・ウォーズ』や『インディ・ジョーンズ』に代表されるスペクタクル映画の雄大なスコアが有名だが、『JFK』で彼が奏でる音楽は、それらの娯楽的昂揚とは異なる重厚な響きを帯びている。
ストリングスによる緊張感あふれる旋律、ブラスの鋭いアクセント、そして時に沈痛なチェロのフレーズが、ストーンのモンタージュと呼応するように配置される。
映像が超高速で断片を繋ぎ合わせるとき、音楽はその流れを秩序づけ、観客の感情をひとつの方向へ導いていく。逆に静かな場面では、余韻のある旋律が編集の隙間を満たし、観客に「考える時間」を与える。
この「映像断片の衝突」と「音楽の持続」がせめぎ合う構造は、単なるBGMの役割を超えて、映画全体をひとつの交響曲のように機能させている。
たとえば法廷シーンにおける証拠提示の場面では、編集の細かい切り返しとともに、音楽のリズムが緊張を高め、観客を追い詰めるように響く。その結果、観客は事実の積み重ねを「体感」させられると同時に、歴史の重圧を「聴覚的に」も受け止めることになる。
このように『JFK』における編集と音楽の相互作用は、映画を単なる物語以上のもの──すなわち「歴史と虚構の交響詩」へと高めている。
ケビン・コスナーの存在感
そして忘れてはならないのが、主演ケビン・コスナーの存在。
『アンタッチャブル』(1987年)や『フィールド・オブ・ドリームス』(1989年)で確立したように、彼はジェームズ・スチュワートの系譜に連なる「アメリカの良心」を体現する俳優だ。本作で彼が演じる検事ジム・ギャリソンは、真実を追い求めて孤独に戦う“市民の代弁者”として描かれている。
コスナーの実直で誠実な存在感は、アクの強いストーン映画を中和し、観客に「この人物の言葉は信じられる」という確かな説得力をもたらしていた。
特にラスト近く、彼が陪審員に向かって「信頼できるアメリカを取り戻そう」と訴える場面は、単なる演説を超えて映画の精神そのものを象徴している。スクリーン越しの視線は観客自身に突き刺さり、民主主義を信じ直すための試練を個々人に突き付けるのだ。
この瞬間、『JFK』は単なる陰謀論映画を超え、“民主主義への信頼を取り戻す寓話”へと昇華する。ストーンが必要としたのは、まさにコスナーのように「スポークスマンとして信頼に足る実直なイメージ」であった。
比較から見えるストーンの本質
同じ「スピーチ」でも、『インデペンデンス・デイ』(1996年)で大統領が叫ぶ戦意高揚的な演説は、観客を一時的に高揚させるエンターテインメントの装置にすぎなかった。それは迫り来る脅威に立ち向かうためのカタルシスであり、昂揚感は一過的なもの。
対して『JFK』のラストにおけるコスナーの言葉は、歴史の証言であり、同時に未来に託された祈りである。観客はスクリーンの前で戦闘態勢に駆り立てられるのではなく、「真実を見極める責任」を静かに問われる。
ここにこそストーン映画の本質がある。派手なアクションもスペクタクルもなくとも、言葉と映像の力だけで観客を揺さぶり、政治や社会の根源に直面させる。
その強度こそが、彼を冷遇させる一因であると同時に、オリバー・ストーンを唯一無二の作家たらしめている。
- 監督/オリバー・ストーン
- 脚本/オリバー・ストーン、ザカリー・スクラー
- 製作/A・キットマン・ホー
- 製作総指揮/アーノン・ミルチャン
- 制作会社/ワーナー・ブラザース・ピクチャーズ、リージェンシー・エンタープライズ、キャナル・プラス
- 原作/ジム・ギャリソン
- 撮影/ロバート・リチャードソン
- 音楽/ジョン・ウィリアムズ
- 編集/ジョー・ハットシング、ピエトロ・スカリア
- 美術/ヴィクター・ケンプスター
- 衣装/マーリーン・スチュワート
- ウォール街(アメリカ)
- JFK(1991年/アメリカ)
- ウォール・ストリート(2010年/アメリカ)
![JFK/オリバー・ストーン[DVD]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/51LNGbYOOL._AC_-e1759059811129.jpg)