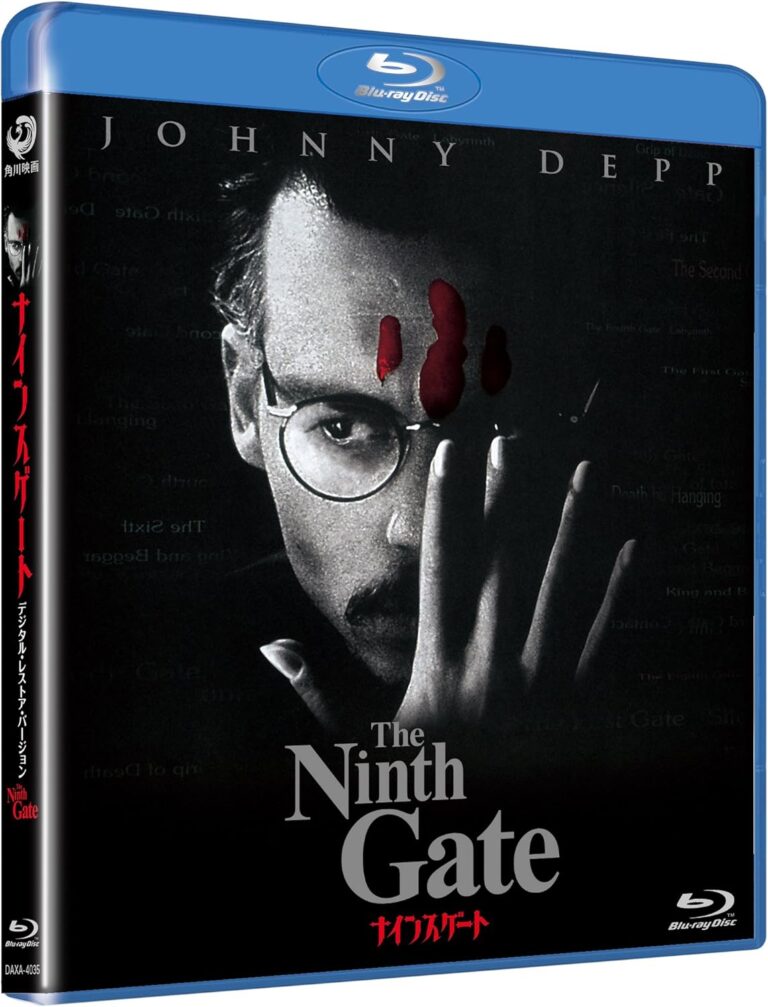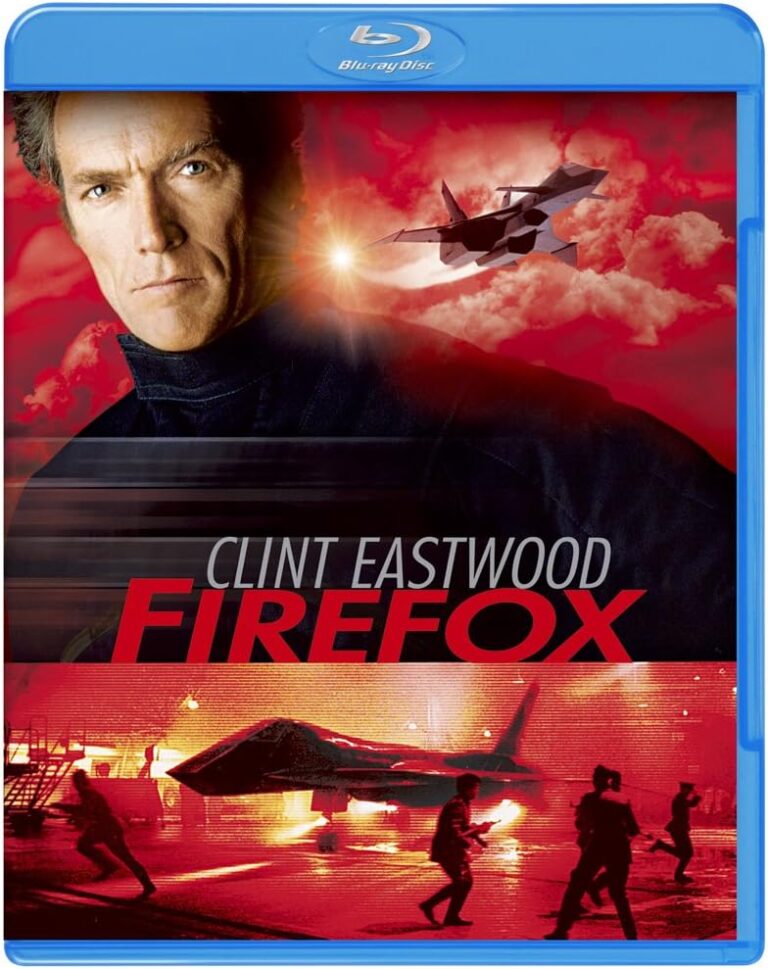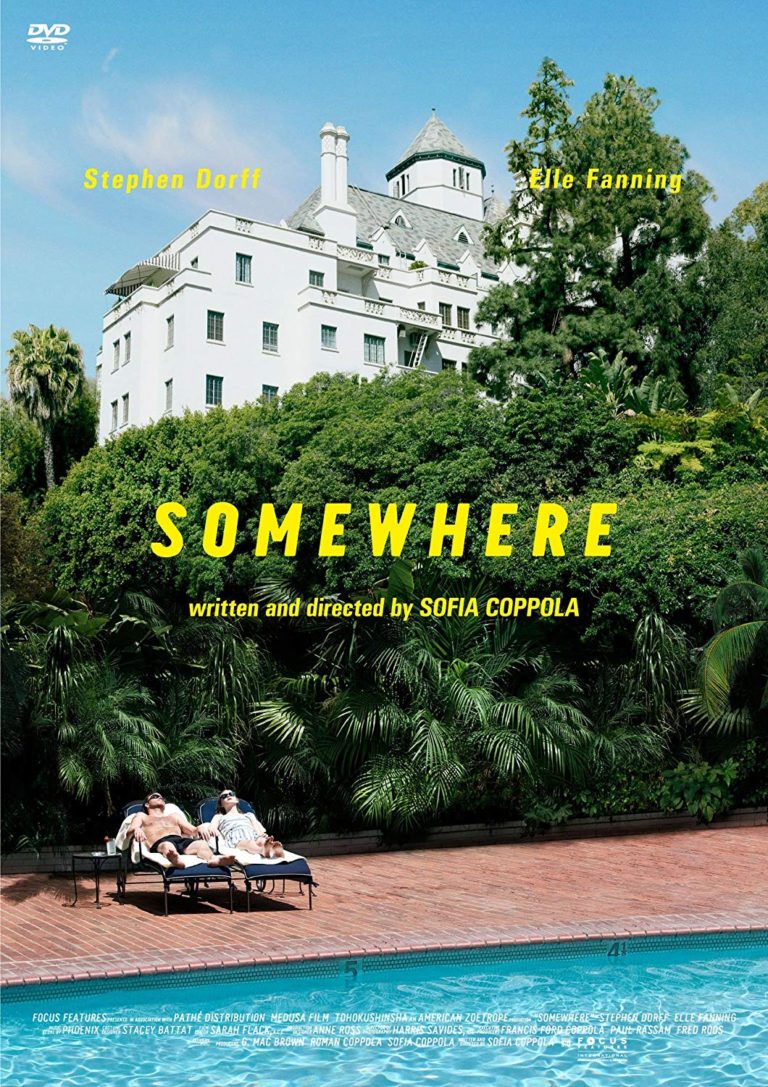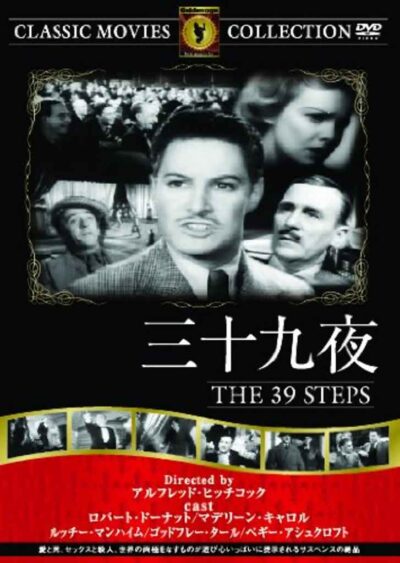『ダンサー・イン・ザ・ダーク』──夢が崩れ落ちる瞬間、ミュージカルは終わる
『ダンサー・イン・ザ・ダーク』(2000年)は、チェコスロバキアから渡米した移民女性セルマが、視力を失いながらも息子の未来のために働き続ける物語。工場の騒音をリズムに変え、現実を凌駕するように歌い踊る彼女の幻想は、やがて冷酷な現実と死刑という結末へと崩れ落ちていく。
崖から突き落とされたかのような衝撃
ラース・フォン・トリアー監督の前作『奇跡の海』(1996年)について、僕は「まるで生爪をはがされたかのよう」と書いたことがある。
だが『ダンサー・イン・ザ・ダーク』(2000年)は、さらに苛烈な体験を観客に強いる。まるで突然、崖から突き落とされたかのような衝撃。
「気持ちがブルーになる」というありきたりな言葉では、この作品を捕捉できない。むしろ「気持ちが宙ぶらりんになる」と言った方が正確だろう。地に足がつかず、支えを失い、どこにも逃げ場がないまま放り出されるような感覚。まるで、スクリーンの光が消えた暗闇の中で、自分の居場所を見失ってしまうような。
ひとつ確実に言えるのは、決してデートムービーにはならないということ。もし「ビョーク主演のミュージカル映画」と思って劇場に足を運べば、とんでもない悲劇を目撃することになるだろう。鑑賞後のディナーは、言葉を失った重苦しい沈黙に包まれるはずだ(実話)。
夢としてのミュージカルと、現実としてのアメリカ
『ダンサー・イン・ザ・ダーク』の主人公セルマは、チェコスロバキアからやって来た移民女性である。彼女の人生を突き動かしているのは、息子の未来を守りたいという願いであり、そこに「アメリカン・ドリーム」への憧れが複雑に絡み合っている。
ラース・フォン・トリアー自身もまた、少年時代からアメリカに矛盾した感情を抱き続けてきた。急進的左翼主義者の家庭に育った彼にとって、アメリカは資本主義の象徴であり、超大国としての圧倒的な力を誇る存在だった。しかし同時に、郊外に広がる住宅地、自動車、テレビ、洗濯機といった「豊かな暮らし」は眩しいほどに魅力的であり、羨望の対象でもあった。
この矛盾した感情は、映画の中でミュージカルという形式に結実する。セルマが工場での単調な作業をリズムに変え、現実を凌駕するように歌い踊る場面は、アメリカ的なモダニティの象徴。観客はそこで一瞬、古典的なミュージカル映画が提供してきたような夢と幸福を疑似体験する。
しかし、それは決して長くは続かない。幻想の幕が下りると、現実のアメリカは資本主義の矛盾と冷酷な国家権力の顔を露わにする。トリアーは「夢としてのミュージカル」と「現実としてのアメリカ」を衝突させ、観客に理想と現実の落差を突きつけるのだ。
キャスティングの反転とその意味
『ダンサー・イン・ザ・ダーク』を読み解くうえで忘れてはならないのがキャスティング。『ファーゴ』(1996年)で冷酷な悪人を演じ、観客に強烈な印象を残したピーター・ストーメアは、本作ではセルマを支える優しい隣人ジェフを演じている。一方、『グリーンマイル』(1999年)や『コンタクト』(1997年)で善良で誠実な人間像を体現してきたデヴィッド・モースは、ここでは金に目がくらんだ悪徳警官ビルを演じている。
この「役割の反転」は偶然ではない。観客が持つ先入観を意識的に裏切ることで、物語の構造そのものに不安定さを植え込んでいる。善人に見える者が悪を行い、悪人として知られる者が善を体現する。アメリカという国家が持つ二重性を、このキャスティングは鋭く示しているのだ。
観客は「誰を信じればよいのか」という根源的な不安を突きつけられ、セルマと共に孤立を深めていく。これは単なる役者の配置ではなく、トリアーが仕掛けた批評的装置なのである。
もちろん、本作を語るうえで主演のビョークの存在は欠かせない。演技経験のほとんどない彼女が、セルマという役柄に全身全霊を捧げたことは、奇跡的な成果を生んだ。
その歌声は観客を魅了し、彼女の身体表現はセルマの苦悩をリアルに伝える。しかしその代償は大きく、ラース・フォン・トリアーとの撮影現場での確執は公然の秘密となり、彼女はこの作品を最後に映画出演から退いてしまった。
死刑制度と現実の冷酷さ
物語はやがてセルマの絞首刑という苛烈な結末に到達する。観客はそこで、幻想の終焉ではなく現実の冷酷さと向き合うことになる。ヨーロッパでは死刑制度の廃止が人権の前提として定着しており、EUに新規加盟する国には死刑制度の撤廃が義務づけられている。対して、アメリカはいまだに先進国の中で死刑を維持し続けている数少ない国家である。
トリアーはこのギャップを、セルマの死という物語に凝縮させる。観客は「これは映画の中の悲劇」ではなく、「いま現実に存在する制度」であることを思い知らされる。
涙は単なる感動ではなく、現実を直視したときに溢れる絶望の涙へと変わる。ラース・フォン・トリアーは娯楽や慰めではなく、観客の心に痛みを刻み込むことを選んだのだ。しかも、ミュージカルという手法を使って。
これまでミュージカル映画は、『雨に唄えば』(1952年)や『サウンド・オブ・ミュージック』(1965年)に代表されるように、歌と踊りを通じて夢や幸福を表現してきた。観客は劇場で一時的に現実を忘れ、希望の物語に酔いしれることができた。
しかし『ダンサー・イン・ザ・ダーク』は、その約束を徹底的に裏切る。セルマが歌い踊る場面は確かに美しいが、それは現実逃避の一瞬にすぎず、最後に待ち受けるのは彼女の死という絶望だ。
ラース・フォン・トリアーはミュージカルを「幸福の装置」ではなく「残酷な対比装置」として用いることで、映画史における“反ミュージカル”を創り出した。だからこそこの映画は、単なるジャンル映画を超え、ミュージカルの伝統そのものを問い直す存在となっている。
行ったことのないアメリカを描く
『ダンサー・イン・ザ・ダーク』は、観客にとって耐えがたい映画体験を提供する。涙は単なる感動の証ではなく、心を引き裂かれるような苦痛そのものだ。エンターテインメントとしての映画を期待した観客に、トリアーは容赦なく絶望を突きつける。
この手法は「映画は観客に幸福を与えるべきか、それとも真実を突きつけるべきか」という根源的な問いを呼び起こす。観客にここまで苦痛を与えることは、映画倫理的に許されるのか? その議論自体が本作の批評性を証明していると言えるだろう。
皮肉なことに、ラース・フォン・トリアーは極度の飛行機恐怖症のため、一度もアメリカの地を踏んだことがない。『ダンサー・イン・ザ・ダーク』の撮影はスウェーデンで行われたが、彼は想像力と批評精神を武器に「アメリカ」という国の虚像と現実を描き出した。
彼にとってアメリカは「愛すべき夢」と「憎むべき現実」が矛盾したまま共存する存在だった。その矛盾がセルマの物語に凝縮され、観客はアメリカ社会の光と影の両方を同時に突きつけられる。
『ダンサー・イン・ザ・ダーク』は、ビョーク主演の異色ミュージカルであると同時に、監督のアメリカ観そのものを刻み込んだ批評映画なのだ。
- 原題/Dancer In The Dark
- 製作年/2000年
- 製作国/デンマーク
- 上映時間/140分
- 監督/ラース・フォン・トリアー
- 脚本/ラース・フォン・トリアー
- 製作/ヴィベケ・ブルデレフ
- 撮影/ロビー・ミュラー
- 音楽/ビョーク
- 美術/カール・ユーリウスソン
- 編集/モリー・マレーネ・ステンスガード
- ビョーク
- カトリーヌ・ドヌーヴ
- デヴィッド・モース
- ピーター・ストーメア
- ジョエル・グレイ
- ヴィンセント・ペイターソン
- カーラ・シーモア
- ジャン・マルク・バール
- ヴラディカ・コスティク
![ダンサー・イン・ザ・ダーク/ラース・フォン・トリアー[DVD]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/81Ulu69E1lL._AC_SL1500_-e1707106579966.jpg)