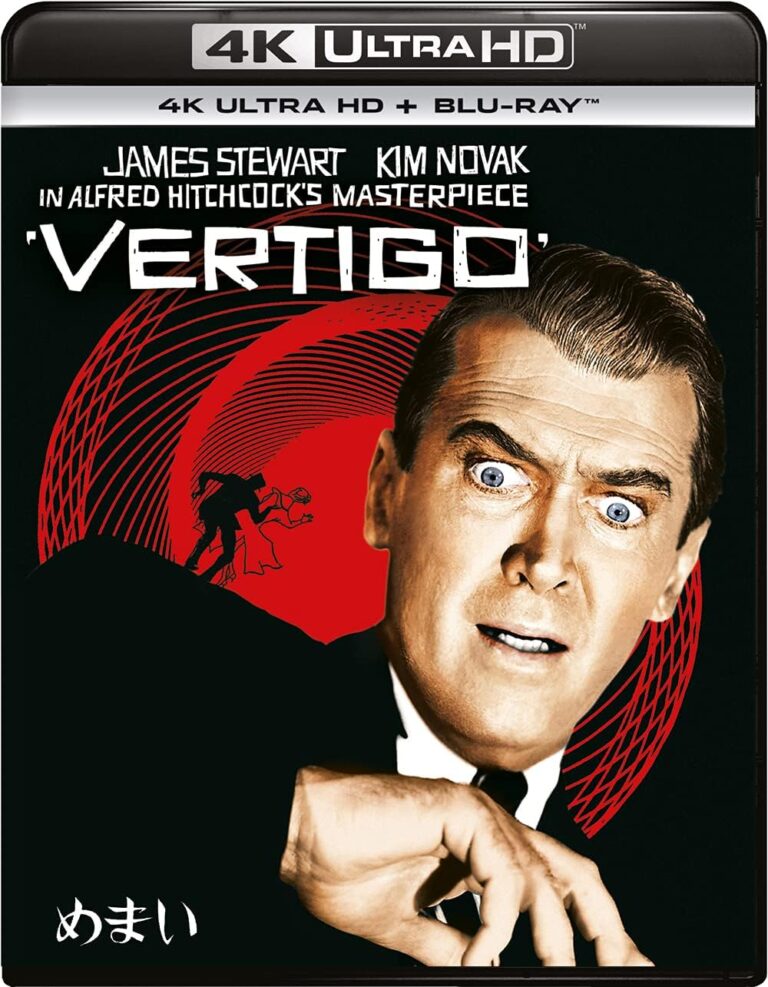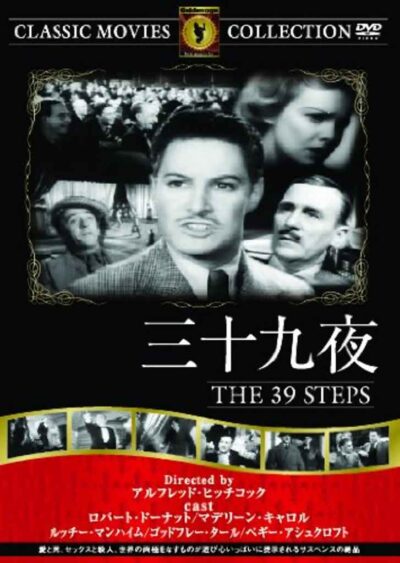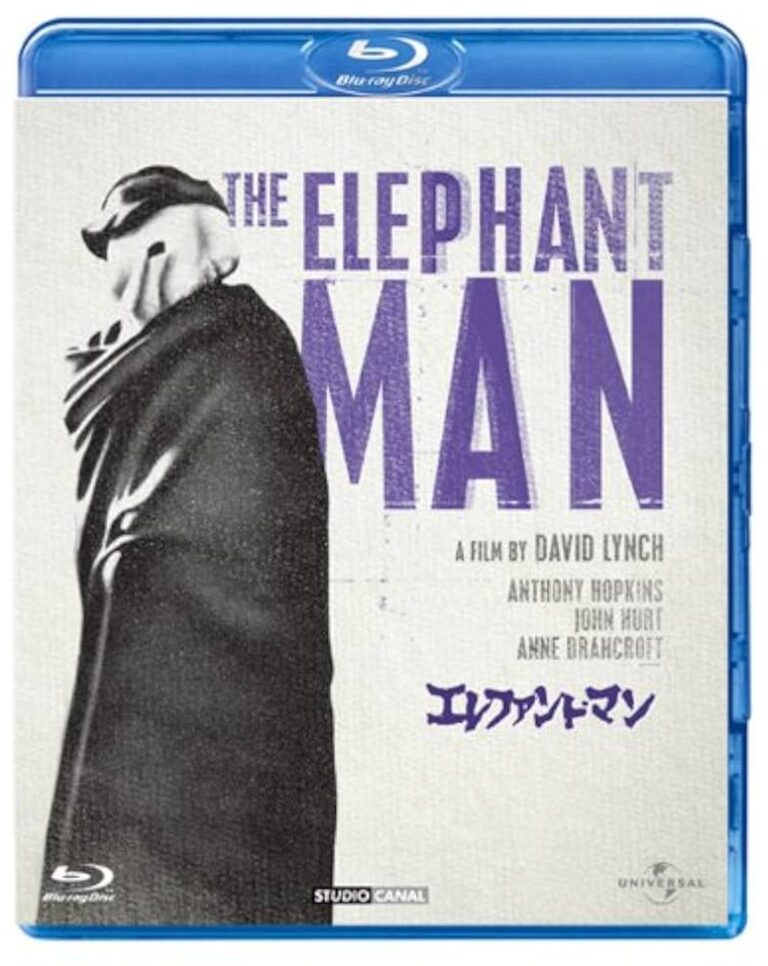『フレンジー』(1972)
映画考察・解説・レビュー
『フレンジー』(原題:Frenzy/1972年)は、アルフレッド・ヒッチコックが21年ぶりにロンドンへ戻って撮影したサスペンス。連続絞殺事件が続く中、無実の罪で疑われた男ブレイニーは逃亡を余儀なくされ、真犯人ラスクは表向きの顔の裏で凶行を重ねていく。物語は二人の動きを平行して追いながら、ロンドンの街並みや食事の場面を巧みに絡め、日常の中に潜む恐怖を際立たせていく。逃亡と捜査が交錯する中、事件の全貌は次第に緊迫した形で明らかになっていく。
ヒッチコックの変態的復活作
『マーニー』(1964年)で主演ティッピ・ヘドレンとの確執を抱えて以降、ヒッチコックは不調期に陥っていた。
『引き裂かれたカーテン』(1966年)、『トパーズ』(1969年)は興行的にも批評的にも振るわず、「巨匠も終わったのではないか」とささやかれる始末。しかし、21年ぶりに生まれ故郷ロンドンへ戻って撮影した『フレンジー』(1972年)は、そんな声を一蹴する“変態的復活作”だった。
“間違えられた男”プロットの転倒
『フレンジー』の表層は、ヒッチコックが好んで扱った「間違えられた男」の物語。本作の主人公リチャード・ブレイニーもまた、無実の罪で追われる。
興味深いのは、〈だれが犯人か〉を早々に明かしてしまう点だ。犯人当てを捨て、倒叙サスペンスに軸足を移すことで、観客は物語の“神”になる。
情報優位に立つ我々は、捜査の遅れやすれ違い、偶然の連鎖をもどかしく見守るほかない。このドラマティック・アイロニー(観客だけが真相を知っている状態)が、作品全体のテンションを持続させる燃料になっている。
さらに重要なのは、視点の“再配分”だ。ヒッチコックはカメラを犯人ラスクの肩越しに据えたり、彼の問題解決(証拠隠滅)に付き添わせることで、観客に一時的な共犯感覚を強いる。
たとえば、殺害後に証拠を取り戻すため、ラスクがトラックに積まれた荷にしがみつく名場面。ここでカメラは、彼の焦り、逡巡、そして肉体の“労苦”を事細かに追う。
私たちは嫌悪しながらも、彼が「うまくやれるか/やれないか」に手に汗を握ってしまう。犯人の「課題解決」をスリラーの推進力に据える、この倫理的に居心地の悪い設計こそが『フレンジー』の真骨頂だ。
一方で、ブレイニー側のドラマは“完全同化”を拒むように作られている。粗暴で短気、被害者意識をこじらせた彼は、古典的ヒーローの対極に立つ。
そのため観客の共感は二分化される。〈加害者への嫌悪と同時進行する、一時的な同一化〉と、〈被害者側=冤罪者への限定的な共感〉。
この二重の感情線をモンタージュで編み、時に食卓での軽妙な会話劇(警部と妻のディナー)を差し込み、緊張と緩和の振幅を意図的に大きくする。結果として、日常のユーモアと性的暴力の異常が同一フレーム内で反復され、観客の情動は揺さぶられ続ける。
演出面でも、「犯行の可視化」と「不可視化」の切り替えが巧妙だ。ラスクが被害者の部屋に入った直後、カメラは廊下へ引き返し、階段を降り、賑やかな通りへとスーッと後退していく有名な引きショット。
扉の向こうで進行する暴力を“見せない”ことで、想像の余白が最大化され、先に提示された加害者の正体が逆に生々しく立ち上がる。
以後の場面では、今度は“見せる/聞かせる”カット割り(声、息遣い、拘束の感触)で官能と恐怖を増幅。可視・不可視の呼吸が、倒叙サスペンスに独自の粘着質な快楽を与えている。
『フレンジー』は、いわゆる「テーブルの下の爆弾」理論を極端化した実験だ。爆弾(=犯人の正体)を最初にテーブルの下へ置き、観客にだけ知らせておく。あとは人物たちがその存在にいつ・どう気づくかを、時間の設計と撮影モチーフ(食べ物/都市の騒めき/室内の静寂)で徹底的に引き延ばす。
こうしてサスペンスの焦点は「真犯人を暴くこと」から、「不可避な破局へ向けて事態がどう加速するか」へと転換し、観客は最後まで身動きの取れない“道徳的な同伴者”にされてしまうのだ。
アンチ・ヒーローとしてのブレイニー
ブレイニーは“誤解された善人”ではない。冒頭で職を失い、短気でプライドの高く、観客が感情移入するには棘が多すぎる男。ヒッチコックはここで、古典的な「間違えられた男」像を支えてきた“気品”や“機知”を意図的に剥ぎ取ってしまう。
ブレイニーが粗暴で不器用であるがゆえに、彼に不利な状況証拠は増幅され、観客の心証すら揺らぐ。つまり彼の“性格欠陥”自体がサスペンスを駆動する装置なのだ。
ブレイニー像の鍵は、〈男らしさの危機〉にある。彼は稼げず、飲み、怒鳴り、他者に甘える。支配=行動力=魅力という旧来の男性像を、魅惑的なサディスト=ラスクが体現してしまうことで、ふたりの男のあいだで“英雄性”が逆転する。
この入れ替わりにより、観客は倫理的に居心地の悪い位置へ追いやられる。無実のブレイニーに肩入れしたいのに、行動能力や人心掌握の点ではラスクのほうが“映画的に有能”に見えてしまうからだ。ヒッチコックはここで、〈徳〉ではなく〈機能〉が場面を制圧するという冷酷なルールを提示している。
演出はその不快なねじれをさらに増幅する。ラスクの場面は主観的近接(顔や手元のクローズアップ、証拠隠滅の段取り)で“成功の手触り”を与える一方、ブレイニーの場面は中距離のブロッキングや雑踏の中の孤立で“無力の距離感”を刻む。
とりわけ元妻の事務所での口論後、彼が部屋を出るカット割りは、観客の記憶に「彼は短気で乱暴」という印象を強く焼き付け、その直後の悲劇に対する疑念の受け皿を用意する。人物の徳性ではなく、ショットサイズと動線が“犯罪の物語”を編んでいく――ヒッチコックらしい倫理破りだ。
物語設計のうえでも、ブレイニーは“解放の媒介”に回らない。彼は真相に迫らず、偶然と他者の行為が物語を動かす。観客は救済への能動的な期待を奪われ、冤罪者の受動性に縛られる。
ここで浮上するのは、〈正義が勝つ〉という古典的カタルシスの欠落だ。それは、70年代ロンドンの倦怠や頽廃の空気、都市そのものの疲労と共鳴する。ブレイニーは“敗者の体温”を帯びた存在として、時代の空気を吸い込む容器なのだ。
もうひとつ決定的なのは、ブレイニーが“被害者に見えるふるまい”をしないこと。ヒッチコックは、彼に謝罪も反省も長広舌も与えない。潔白の自己弁護で観客の涙腺を刺激する安全装置を外し、むしろ周囲の人間関係(元妻との緊張、友人の援助の拒絶・誤解)を通して、彼の未熟さを増幅する。
結果としてブレイニーは、“英雄不在の物語”を成立させるための中核ピースになる。善悪の軸を〈誰が正しいか〉から〈誰が状況を支配するか〉へずらし、ヒーローの魅力ではなく演出の冷徹なロジックで観客を拘束する。
『フレンジー』が放つ独特の後味――救われたはずなのに爽快ではない、疑いが抜けない、どこか腹立たしい――は、このアンチ・ヒーロー造形がもたらす“道徳的残響”に由来する。
ヒッチコックは、無実の男を敢えて好かせないことで、サスペンスを心理の奥底にまで沈めているのだ。
脱グラマー・キャスティングと猟奇性の装置化
『フレンジー』は、ヒッチコックが長年偏愛してきたアイス・ブロンド(グレース・ケリー~ティッピ・ヘドレン系)の審美から、あえて距離を取っている。
ブレンダ役のバーバラ・リー=ハント、バブス役のアンナ・マッセイは、いずれもグラマラスというよりも、生活感と実在感が先に立つ。言い換えれば、欲望の対象として記号化されにくい“ふつうのロンドンの顔”。
この「脱グラマー」が、ネクタイ殺人の残酷さを過剰にエロティックに美化させず、むしろ現実の皮膚感覚に引き寄せる。結果として暴力の異様さが、より汗ばむ具体性を伴って突き刺さる。
容貌だけではない。衣装・小道具・色調が連動し、日常の粒度を上げることで異常性の輪郭が濃くなっていく。たとえばオフィスの地味なスーツ、街のくすんだアースカラー、コヴェント・ガーデンの雑多なテクスチャ――、どれもが被害者を“特別な美女”から外れた「そこにいる人」に見せる。
だからこそ、ラスク(バリー・フォスター)の「Lovely! Lovely!(ラーヴリィィィ…)」という甘い囁きは、観念的なエロスではなく、肉体を締め上げる私的暴力の合図として耳にこびりつく。
『フレンジー』のキャスティングは、〈ロンドンの日常〉と〈私的な変態性〉を短絡させるスイッチとして機能する。スターの光沢を剥ぎ、生活のディテールを増幅し、可視/不可視の呼吸で想像を駆動させる。
この“反グラマー”的選択の連鎖が、ネクタイ殺人の場面を単なるショック・シーンではなく、倫理と感覚の両面で忘れがたい体験へと変換しているのだ。
食べ物モチーフのグロテスクな笑い
『フレンジー』における「食べ物」は、小道具の域を超えた意味論のハブである。欲望と生存を保証する〈口/胃〉の回路が、殺害の方法=絞殺によって〈喉/気道〉の遮断へと反転する。すなわち〈食べる=生の取り込み〉と〈窒息=生の遮断〉が同じ身体部位で結線され、映画全体が“食欲の倒錯”というテーマに貫かれる。
まず、警部と料理好きの妻の食卓。異国風の創作料理に眉をしかめる警部のリアクションは、単なる寄り道ギャグに見えるが、ここで描かれているのは〈中産階級の上昇欲〉の滑稽さであり、味覚の“冒険”が同時に倫理の鈍磨も生み出すというアイロニーだ。
テーブル上の品の良い会話劇と、直前直後に挿入される殺害の記憶(あるいは予感)が交互作用し、観客は“上品な食事”と“下劣な暴力”を同じ咀嚼のリズムで飲み込まされる。
フォークやナイフの触れる硬質な音、乾いたパン皮の噛み砕かれる音は、やがて絞首の締め上げ音や衣擦れの摩擦と同格に聞こえ始め、音響的にも〈生〉と〈死〉が隣り合う。
つづいて、コヴェント・ガーデンという舞台設定の機能。青果市場の雑然とした活気、木箱、泥、土埃――“生命の糧”が集積・流通する場は、そのまま死体を覆い隠す理想的なカムフラージュへと転位する。
象徴的なのが、野菜を満載したトラックの荷台で証拠を回収しようとする一連のシークエンス。乾いた皮膜、指にまとわりつく粉、崩れていく山。テクスチャの連打が“商品”と“死体”の境界を曖昧にし、身体が市場の物的連鎖に組み込まれてしまう。
食卓を支える生鮮品と殺人現場の遺物が同じ流通ラインで混ざり合うとき、観客は“日常が異常を飲み込む”光景を嗅覚レベルで追体験させられる。
モンタージュと視点設計も、食モチーフの不気味さを倍増させる。ヒッチコックは、暴力の直後(あるいはその強い示唆)の場面から、何事もなかったかのように食卓のショットへと切り返す。
被害者の身体を“見せない”引きのショット(ドアの外へ退く有名な引き)で想像の余白を最大化し、直後に“見過ぎる”ほど牧歌的な料理のクローズアップでその余白を残酷に埋める。
この〈不可視→可視〉の反復が、食べる行為を“生命の祝祭”ではなく“倫理の麻酔”へと変質させ、観客の笑いに粘ついた後味を残す。
ヒッチコック作品に広く見られる“食のサスペンス”――『ロープ』の棺桶ディナー、『サイコ』のサンドイッチ談義、『汚名』のコーヒー――の系譜に照らすと、『フレンジー』は最も肉感的で、嗅覚と触覚を直接刺激する段階に到達している。
ここでの食は、上品な暗示や毒薬のメタファーに留まらない。咀嚼、消化、排泄という生理の連鎖そのものが、絞殺=窒息によって反転され、観客の身体に“不快な同化”を強いる。
ゆえにこの映画の笑いは、ジャン=ピエール・ジュネ&マルク・キャロ監督の『デリカテッセン』(1991年)のグロテスクなユーモアと共鳴しつつ、より生々しく、より倫理的に攻撃的だ。
『サイコ』との比較と映画史的意義
『フレンジー』は、『サイコ』(1960年)と並ぶ“異常性”の極北に位置づけられる。だがその立ち位置は微妙に違う。
『サイコ』において異常は〈家〉の内部に潜む。モーテルと母屋という二重構造、母‐子関係の密室性、バーナード・ハーマンの鋭利なストリングスが刻む神経症のリズム。観客は「家庭/私性」の皮膜が剝がれる瞬間を覗き見する。
一方『フレンジー』は、異常を〈都市〉の日常へ拡散させる。ロンドンの雑踏、コヴェント・ガーデンの市場、官庁街の石畳。公共圏の騒めきのただ中で、私的暴力は平然と作動する。密室の恐怖から路上の恐怖へ。ヒッチコックは異常を“家”から“街”へと解き放ち、観客の安全地帯を消していく。
叙述設計も反転している。『サイコ』は「正体の撹乱」をサスペンスの核に据え、アイデンティティの錯綜(母/息子)を暴露の快楽へ導く。クライマックスの精神科医による“説明”は、当時の検閲下で物語を社会的了解へ回収するための装置でもあった。
対して『フレンジー』は早々に犯人を提示し、倒叙へと舵を切る。観客は神の視点を持ちながら、警察や周囲の鈍さを嘆じ、犯人の“段取り”を手に汗にぎって見守るという、倫理的に居心地の悪い座席に縛られる。サスペンスの焦点は「何が起きたか」から「どう捕まるか」へと転換し、そこには60年代から70年代への映画言語の移行が刻印されている。
制度史の文脈でも両作は対照的だ。『サイコ』は旧来の検閲の縫い目をこじ開けた挑発(トイレのフラッシュ、下着姿の持続)であり、言わば“暗示の時代”の極北。『フレンジー』は一転して“可視化の時代”に入ったヒッチコックで、露骨な裸体や絞殺の身体感覚が、想像の余白と交互に呼吸する。
見せる/見せないの振幅が広がったことで、観客の身体はより直接に巻き込まれ、笑い(警部夫妻の食卓)と戦慄が同一リズムで噛み合う。ここで食べ物=生の象徴と絞殺=窒息が、〈口/喉〉という同じ器官をめぐって反転し合う造形は、70年代犯罪スリラーの先駆けとして特筆される。
ジェンダーと視線の配置も、映画史的な差異を示す。『サイコ』の視線は“覗き見”と母性の幽霊をめぐる内的地獄へ潜行し、モノクロの抽象性が神話化に寄与する。
『フレンジー』はカラーの生活感――肌理、汗、土埃――を前景化し、女性身体を「鑑賞の対象」としてではなく「傷つき得る現実」として提示するために、可視/不可視の切り替えを戦略的に用いる。
結果として、エロティックな凝視は寸断され、代わって“見たくないのに見てしまう”倫理的負荷が観客に課される。これはのちの70年代以降の犯罪映画に広く継承される視点設計だ。
地政学的にも、両作は時代の気分を異なる角度から封じ込める。『サイコ』が戦後アメリカの繁栄の陰に沈殿した家庭の病理を露出したのに対し、『フレンジー』は産業の空洞化と帝国の黄昏を引きずる70年代ロンドンの倦怠を背景に、紳士的ふるまいの皮一枚下にあるミソジニーと暴力を曝す。だからこそ『フレンジー』の笑いは上品な風刺にとどまらず、都市の血流そのものを冷やす毒として機能する。
『サイコ』は“古典期の終章”として、暗示と撹乱でサスペンスの文法を更新した。『フレンジー』は“新しい現実主義”の入口で、倒叙・可視化・都市空間を束ね、サスペンスを観客の肉体へ接続し直した。
ヒッチコックはロンドンに帰還することで、郷愁ではなく〈母国の日常に巣食う異常〉を彫り上げ、古典と70年代の橋を架けたのである。
老いてなお変態魂を爆発させる巨匠
『フレンジー』の異常性は単なる猟奇趣味にとどまらない。熟練の職人が丹念に仕込んだブラック・ユーモアと精緻なサスペンス演出が融合したことで、「変態性」が芸術にまで昇華されている。
ヒッチコックは老境にあっても創造力を失わず、むしろ“変態性”を全面化させることで再生を果たした。これこそが『フレンジー』の最大の意義であり、観終わったあとにチキン料理を避けたくなるほどのトラウマ性もまた、巨匠が仕掛けた恐るべき魔術なのだ。
- 原題/Frenzy
- 製作年/1971年
- 製作国/イギリス
- 上映時間/117分
- 監督/アルフレッド・ヒッチコック
- 脚本/アンソニー・シェーファー
- 製作/アルフレッド・ヒッチコック
- 原作/アーサー・ラ・バーン
- 撮影/ギル・テイラー
- 音楽/ロン・グッドウィン
- 編集/ジョン・シンプソン
![フレンジー/アルフレッド・ヒッチコック[DVD]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/5108xXgXMjL._AC_UF10001000_QL80_-e1707221155669.jpg)