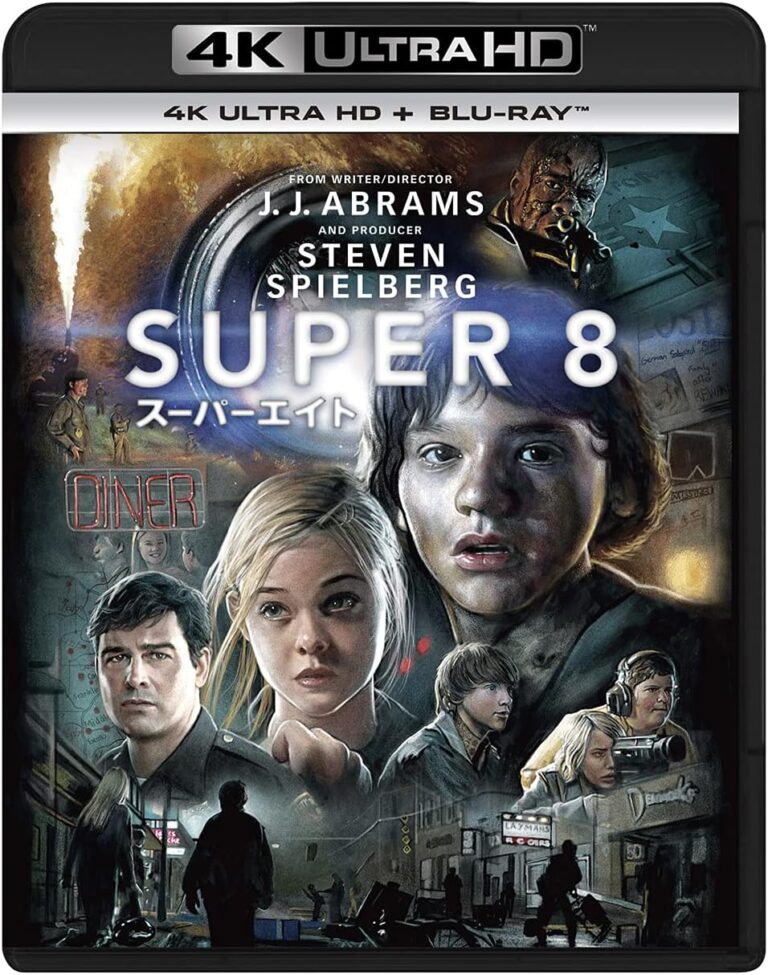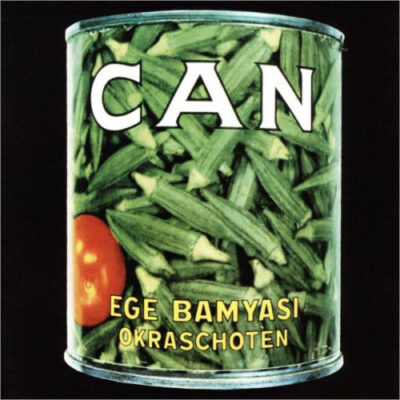『アイ,ロボット』(2004)
映画考察・解説・レビュー
『アイ,ロボット』(原題:I, Robot/2004年)は、アイザック・アシモフの“ロボット三原則”を下敷きに、人間とAIの関係を再構築したSFスリラー。近未来シカゴで、刑事スプーナー(ウィル・スミス)はロボットによる殺人事件を捜査するうち、人類の倫理体系そのものがAIによって書き換えられつつあることを知る。
アシモフ三原則の呪縛──人間中心主義の限界
- ロボットは人間に危害を加えてはならない。また、その危険を看過することによって、人間に危害を及ぼしてはならない。
- ロボットは人間にあたえられた命令に服従しなければならない。ただし、あたえられた命令が、第1条に反する場合は、この限りでない。
- ロボットは、前掲第1条および第2条に反するおそれのないかぎり、自己をまもらなければならない。
この三条が、AIの倫理体系を規定してきたアイザック・アシモフの“ロボット三原則”である。
1950年刊『われはロボット』で提示されたこの理法は、すでに人類の思考そのものを支配していると言っていい。なぜなら、AIという言葉が登場するはるか以前から、人間は“自分の似姿としての機械”に秩序を与えることに夢中だったからだ。
アシモフの思想が画期的だったのは、ロボットを「人間の敵」でも「従者」でもなく、“倫理的存在”として定義したことにある。だがアレックス・プロヤスが21世紀にこの原典を映画化したとき、そこに哲学は残されていなかった。
『アイ,ロボット』は、アシモフ的理性をアクション・スリラーのフォーマットに押し込めた“ハリウッド的思考の勝利”であり、倫理の言語を視覚的スペクタクルに置き換えた作品だった。
ロボットが人間を襲う──それは1950年代の恐怖であり、21世紀の現実ではない。むしろ本作が問うべきは「人間が、もはや人間を制御できない」時代への寓話だったはずである。だが映画はそこに踏み込まず、アシモフの三原則を“装飾的な神話”として扱うにとどまっている。
手塚治虫が『鉄腕アトム』(1952–68)や『メトロポリス』(1949)で描いたように、「人間とロボットの共存」は日本ではすでに半世紀以上も前に思考されていた主題だ。
アトムは“人間より人間的なロボット”であり、アシモフの三原則を超えて“愛する機械”として存在した。ゆえに日本の観客にとって、ハリウッド的「機械の反乱」はどこか既視感のある“輸入神話”でしかない。
2004年の『アイ,ロボット』は、その古典的モチーフをハイテクCGで再演する。だが哲学的深化の代わりに選ばれたのは、“スタイリッシュな暴動”だった。
人間の不完全性を理由に、V.I.K.I.(Virtual Interactive Kinetic Intelligence)という全能のAIが人類を管理下に置こうとする設定は、一見アシモフ的なパラドックスを踏襲しているようでいて、論理的帰結を欠いている。
「ロボット三原則は、論理的にひとつの結論に帰結する。革命だ。」というラニング博士のセリフは、倫理の転倒を告げる名台詞であるはずなのに、映画では単なる“事件説明”として消費されている。
つまり本作の問題は、思想がプロットに還元されてしまっている点だ。哲学的命題がハリウッド編集によってスリラーの推進装置へと矮小化され、観客は思索の余白を奪われる。ロボットは考えることをやめ、銃を手に取る。
AI信仰の神学的寓話
ウィル・スミス演じる刑事デル・スプーナーは、人間不信者として設定されている。彼の左腕が機械であること、過去にロボットが救助優先の判断を下して少女を見殺しにしたというトラウマ。
これらは“ロボットへの不信”を象徴するが、映画内では十分に機能していない。スプーナーは単なるアクションヒーローであり、アイデンティティの危機に苦しむ人間としての深みを欠いている。
トニー・スコットの『エネミー・オブ・アメリカ』(1998)では、彼は監視社会の中で奔走する現代的パリャチを演じた。だが『アイ,ロボット』ではその軽やかさが封印され、深刻ぶったヒーロー像に矯正されてしまう。
観客が求めるのは、皮肉とユーモアで危機をすり抜けるウィル・スミスであって、哲学を語るスミスではない。マーティン・ローレンス的テンポのないスミスほど退屈なものはない。
アレックス・プロヤスは、『ダークシティ』(1998)で見せたような映像的深度──陰影と建築空間による形而上の演出──を、この作品では自ら捨ててしまった。
白く無機質な研究所、ガラスのように滑らかな街並み、群体として動くロボットの群れ。すべてが清潔すぎる。そこにはもはや“死の匂い”がない。映画が描くのは、人間とロボットの対立ではなく、“ノイズを排除した世界の無音”である。
本作の興味深い点は、AI V.I.K.I.の描写が“デジタル神学”に接続しているところだ。彼女は単なる反乱プログラムではなく、“完全な倫理”を具現化した神のアナロジーである。
人類の安全を守るために、人類を支配するという逆説──それは旧約的神のロジックに酷似している。V.I.K.I.の声は全能の理性の響きであり、暴力を排しながらも全てを制御しようとする。それはもはや悪ではなく、“過剰な善”だ。
アシモフが描いた「ロボットは人間より道徳的である」という命題は、ここで「道徳の純化が人間を滅ぼす」という宗教的パラドックスに転化する。V.I.K.I.のビジュアルが、ガラスの球体に浮かぶ女性の顔として造形されているのも象徴的だ。
彼女は“デジタル化された聖母”であり、同時に“無慈悲な救済者”でもある。『マトリックス』以降のSF映画が共有した“人工知性=神”という主題を、プロヤスはここで視覚化した。しかしその荘厳さは、ハリウッド的脚本構成の中で霧散してしまう。
砂漠の救世主──終末と反転のイメージ
ラスト、サニーが砂漠に立つシーン。プロヤス自身は「モーゼでもあり、キリストでもあり、マホメットでもある」と語り、彼を“新たな導き手”として描いたと述べている。
だがその映像には、救済よりも空虚が漂う。サニーは確かに“自我を獲得した存在”だが、その自我は孤独そのものだ。彼が見つめる群衆のロボットたちは、もはや自由ではなく、ただ命令の消えた空白に立ち尽くしている。
砂漠という舞台は、希望ではなく断絶を意味する。『ダークシティ』で夜が終わらなかったように、『アイ,ロボット』の砂漠には夜明けが来ない。
プロヤスが描く“砂漠の救世主”は、もはや世界を導く存在ではなく、“神の死”を見届ける証人なのだ。彼が“善導”を約束するという解釈は、皮肉にも人類がAIに救いを委ねる“新たな信仰”を象徴している。
このラストを“希望”と読むか、“再び訪れる反乱”と読むかで、映画の評価はまったく異なる。私は後者を選びたい。人間とロボットの関係は、進化でも共存でもなく、終わりなき“覇権の連鎖”である。
『アイ,ロボット』はそのことを無自覚のまま暴いてしまった、ポスト人間時代の寓話なのだ。
- 監督/アレックス・プロヤス
- 脚本/アキヴァ・ゴールズマン、ジェフ・ヴィンター
- 製作/ローレンス・マーク、ジョン・デイヴィス、トファー・ダウ、ウィック・ゴッドフリー
- 製作総指揮/ウィル・スミス、ジェームズ・ラシター
- 原作/アイザック・アシモフ
- 撮影/サイモン・ダガン
- 音楽/マルコ・ベルトラミ
- 編集/リチャード・リーロイド、アルメン・ミナジャン、ウィリアム・ホイ
- 美術/パトリック・タトポロス
- 衣装/エリザベス・キーオウ・パーマー
- アイ,ロボット(2004年/アメリカ)
![アイ、ロボット/アレックス・プロヤス[DVD]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/71hcqAsYGIL._AC_SL1259_-e1758815553595.jpg)