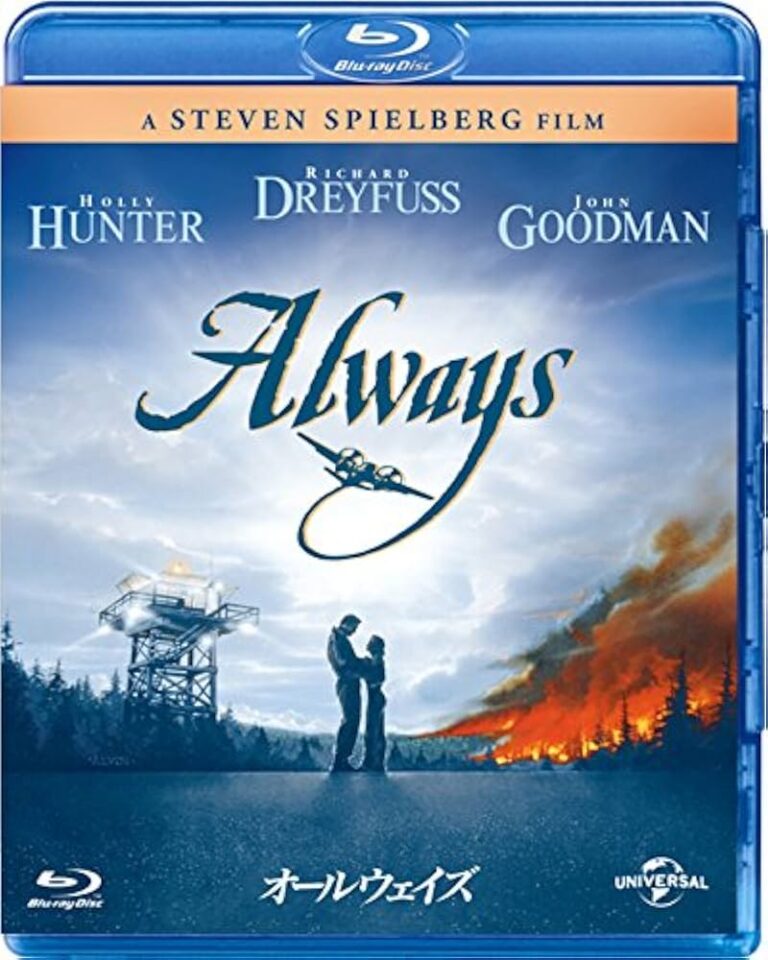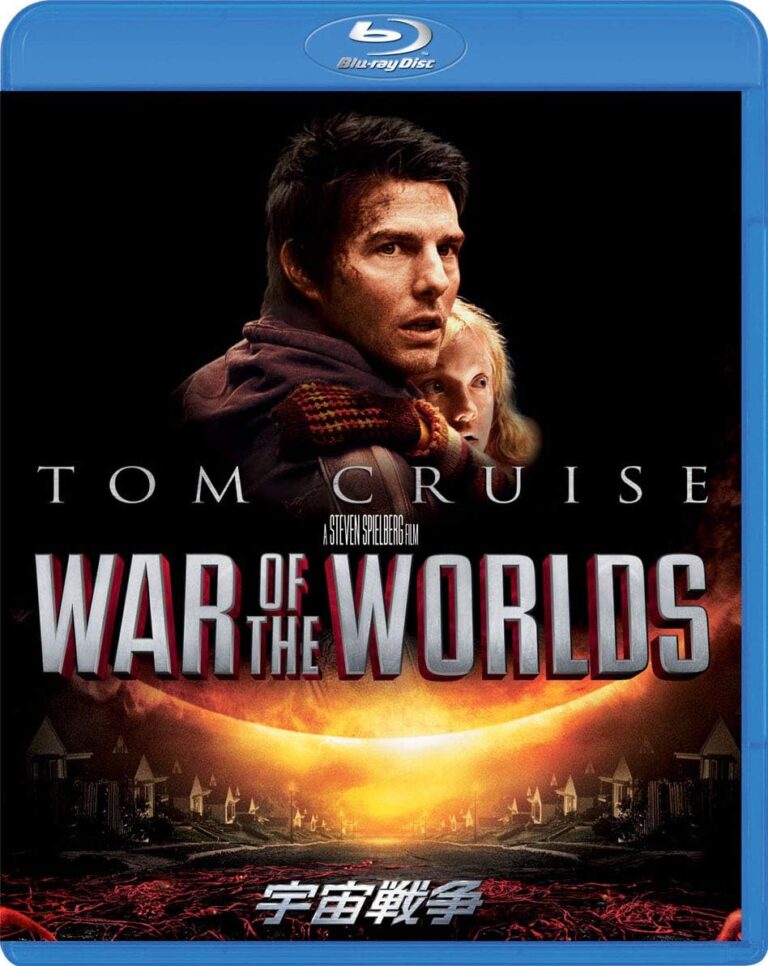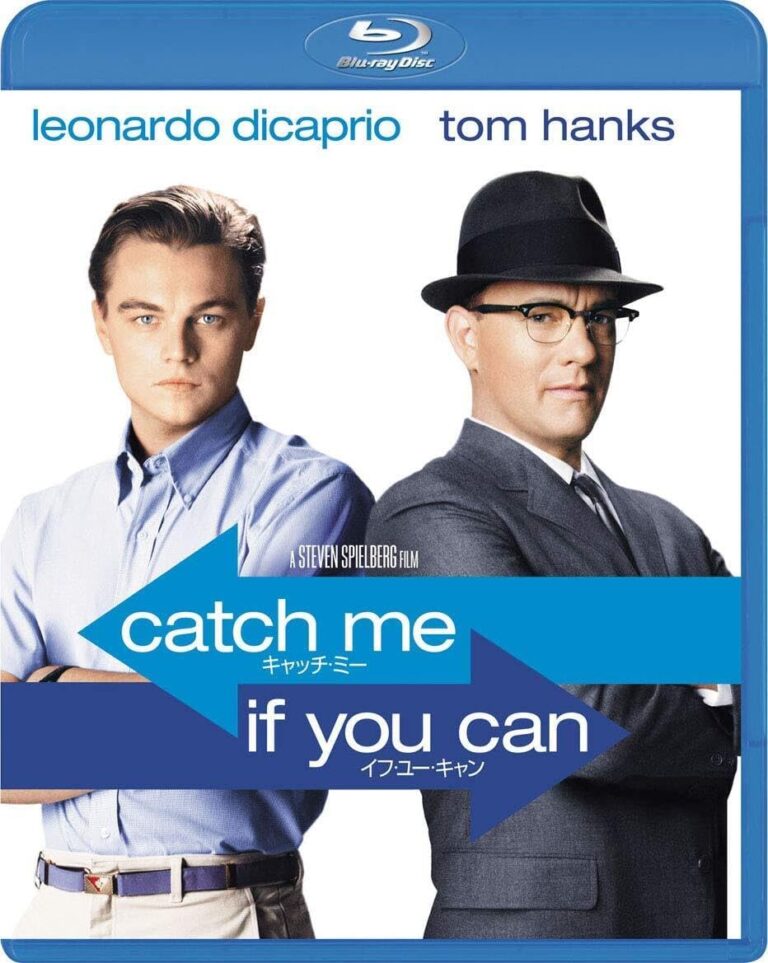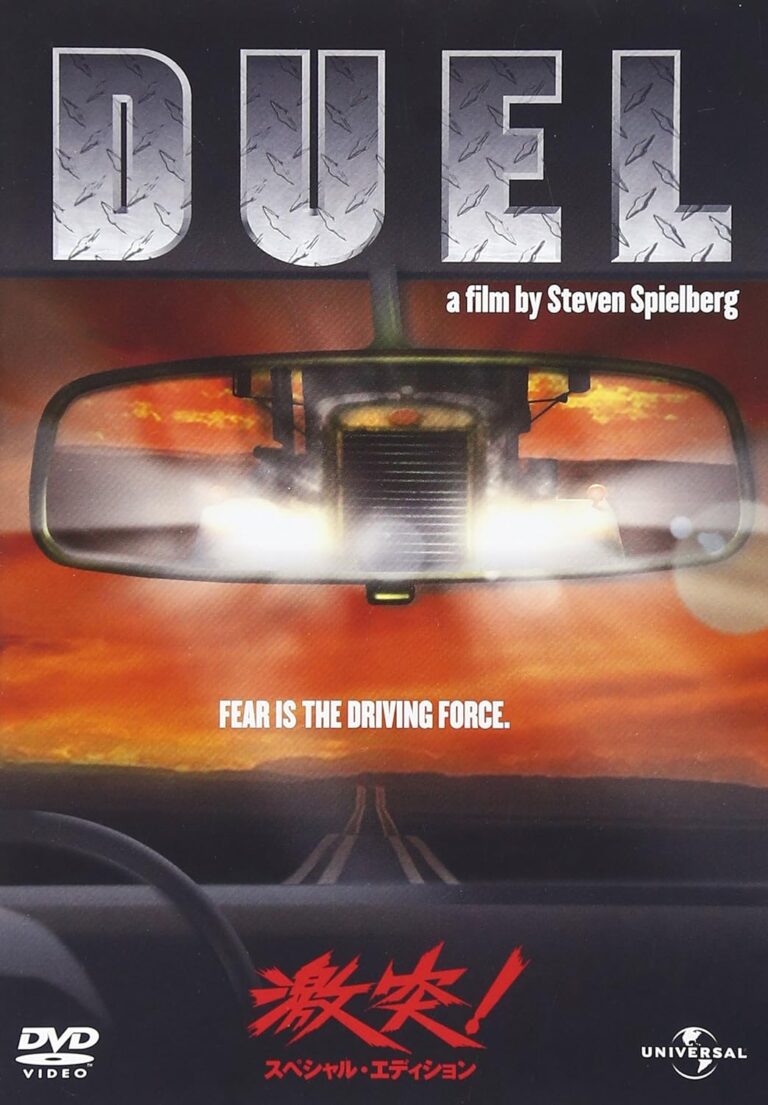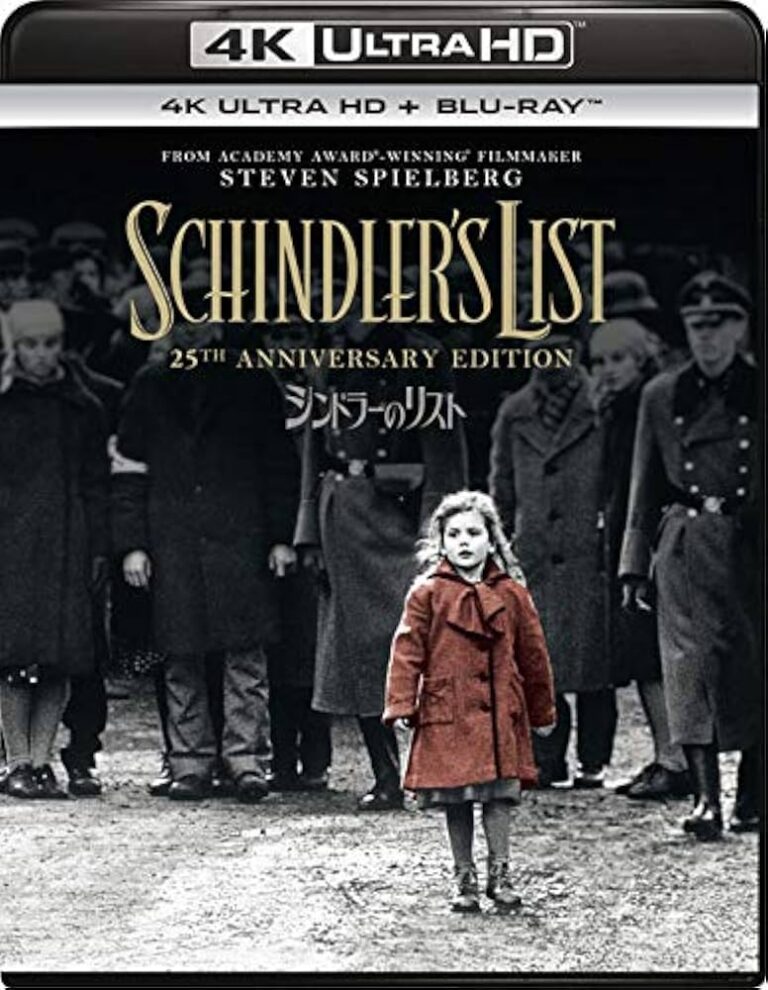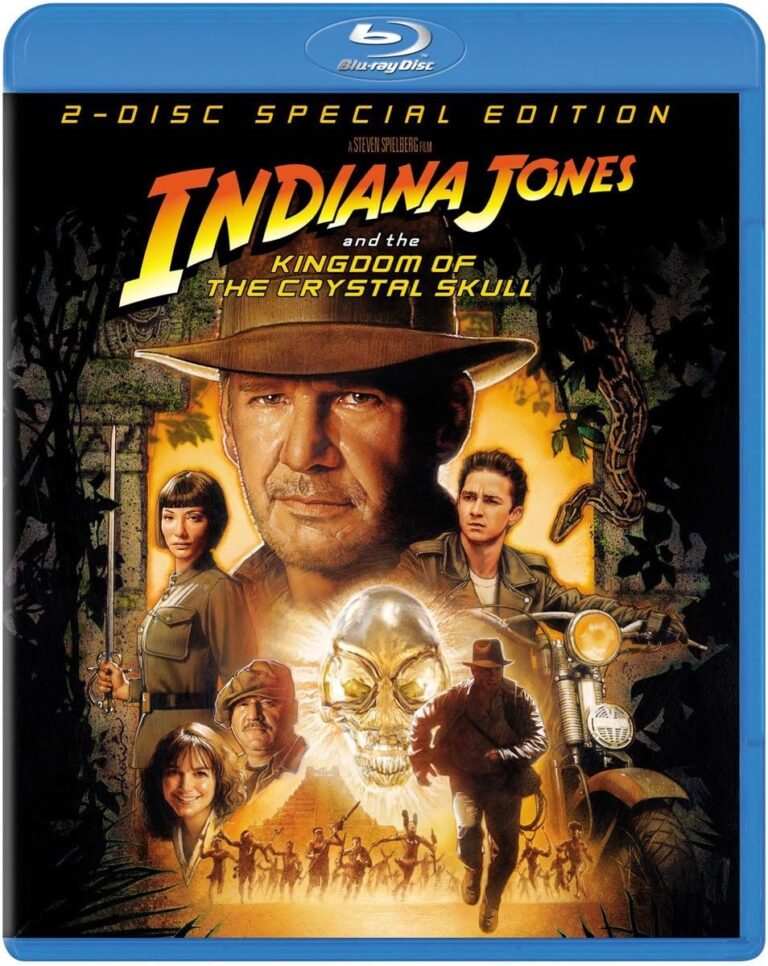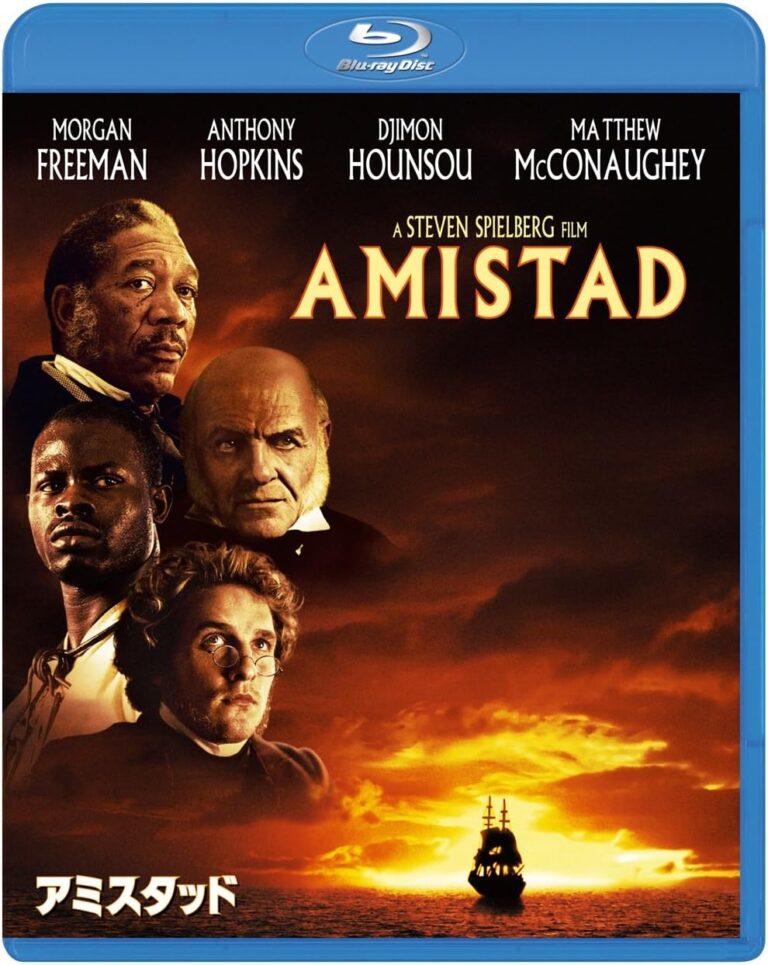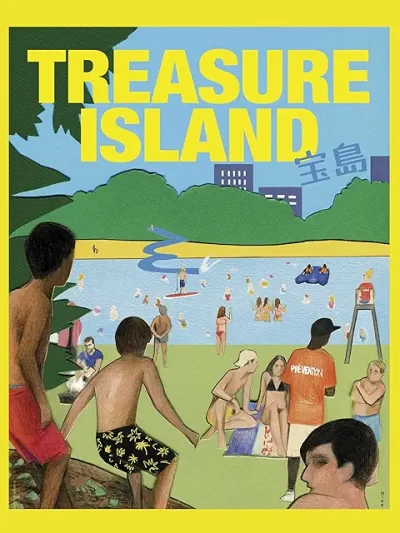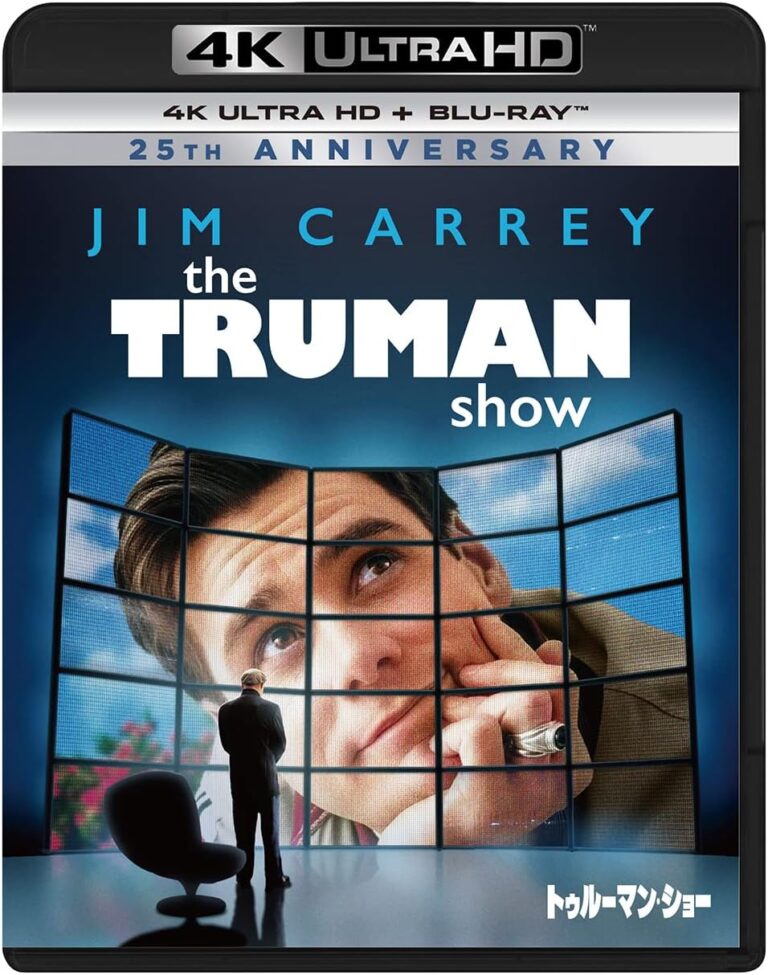【ネタバレ】『プライベート・ライアン』(1998)
映画考察・解説・レビュー
『プライベート・ライアン』(原題:Saving Private Ryan/1998年)は、スティーヴン・スピルバーグが監督し、トム・ハンクス、マット・デイモン、トム・サイズモアらが出演した第二次世界大戦を舞台とする戦争ドラマ。1944年6月、ノルマンディー上陸作戦後のフランスで、ミラー大尉(トム・ハンクス)率いる小隊が、兄3人を戦死で失ったライアン二等兵(マット・デイモン)を救出する任務を命じられ、“たった一人を救うために多くが死ぬ”という矛盾と向き合う。第71回アカデミー賞で監督賞ほか5部門を受賞した。
映像の強度だけを信じ抜いた狂気の戦場体験
スティーヴン・スピルバーグは、時に物語の整合性や高尚なテーマをあっさりと投げ捨ててしまう映画作家だ。というよりも、彼が心の底から信じているのは、たぶん映像の強度だけなのだ。
シネマという総合芸術を極限までろ過して抽出するならば、そこに残るのは映画文法のみによって構築された、観客の脳を直接ぶん殴るような純然たるイメージのみ。
リュミエール兄弟が100年以上前に開発し、パリの紳士・貴婦人たちを列車が突っ込んでくる映像で腰を抜かせた「シネマトグラフ」の根源的な映像的興奮を、彼は現代のハリウッドで最もピュアに復権させようとしているのだ。
『プライベート・ライアン』(1998年)は、まさにその極致である驚異的な映像体験だ。断言しよう、これは戦争映画ではない。観客の身体を血みどろの最前線に強制連行する、戦場映画だ。
「ママ、ママ」と泣き叫び、吹き飛ばされてちぎれた自分の腕を探して放心状態となり、飛び散る血と臓物を惜しげもなくさらしながら、無数の若き兵士たちが虫ケラのように命を落としていく。
この阿鼻叫喚の地獄絵図を、激しく動き回る望遠の手持ちカメラ、意図的にイジり倒された狭いシャッター開角度、レンズにベチャリと付着する肉片と血糊、そして機銃掃射や迫撃砲の腹に響く激しい爆音で、スピルバーグは徹底的に冷徹な視線でスクリーンに焼き付けていくのだ。
以後の映像文化をすべて変えた、伝説の冒頭24分間
映画史を語る上で絶対に避けて通れないのが、冒頭における24分間のノルマンディー(オマハ・ビーチ)上陸作戦シーン。
このシークエンスは、文字通り後続の戦争映画のルックを劇的に、かつ不可逆的に変えてしまった。実際の戦争経験者が「あとは血と泥の臭いさえあれば、これは本物の戦争だ」と震えながら語ったという逸話も、決して大袈裟ではない。
以後の『ブラックホーク・ダウン』(2001年)や『ハート・ロッカー』(2008年)といった戦争映画の傑作群、さらには『コール・オブ・デューティ(CoD)』のような大ヒットFPSゲームのリアリズム表現に至るまで、この24分間の衝撃波は現代のあらゆる映像カルチャーに波及している。
特筆すべきは、スピルバーグの長年の盟友である撮影監督ヤヌス・カミンスキーが用いた狂気のカメラ・ワークだ。手持ちの望遠レンズで兵士たちの恐怖の表情を追いながら、あえてシャッター開角度を通常の180度から90度、あるいは45度まで極端に絞り込む。これによって、爆発の破片や飛び散る土砂がブレることなく克明に映し出され、映像は異常なほどのカクつき(ストロボ効果)を帯びる。
この視覚的ショックによって、戦場のパニックや時間の断絶感が観客の身体に直接刻み込まれるのだ。さらに、レンズに付着する血糊や水滴は、従来ならNGテイクとして処理される要素だが、あえてそれを残すことで、現場の生々しい偶発性をスクリーンにそのまま固定してみせた。
音響設計の革新性もエグい。ガンショットや爆発音は、ライブラリにある一律の効果音ではなく、距離や位置関係、銃弾が空気を切り裂く音までリアルに計算されている。
とりわけ、至近距離での炸裂音の直後に、主観的な高周波ノイズ(耳鳴り効果)を挿入する演出!これによって、兵士の聴覚的ダメージと意識の混濁を観客自身に強制的に追体験させる。サウンド・デザインは単なる臨場感の演出を凌駕し、観客の身体を容赦なく戦場に晒す凶悪な装置となった。
これは、ハリウッド映画におけるリアリズムの基準点を一瞬にして過去のものにしてしまった、戦場映像の絶対的プロトタイプなのである。
無垢の崩壊と観客が陥る、共犯の罠
かつてスピルバーグは『シンドラーのリスト』(1993年)で、戦争の愚かしさやホロコーストの悲劇をテマティックに、そして道徳的に語り上げた。
しかし『プライベート・ライアン』では、倫理的なメッセージを語ることを放棄し、観客を最前線に放り投げることで、メカニカルに「戦争という暴力機構」そのものを提示してしまう。倫理を語る映画から、感覚を叩きつける映画への劇的なシフトだ。
もちろん、物語の骨格は存在する。ジョン・ミラー大尉(トム・ハンクス)率いるレンジャー部隊に、「戦争で3人の兄を失った末弟、ジェームズ・ライアン二等兵(マット・デイモン)を探し出し、母親の元へ帰還させよ」という無謀な特命が下される。
たった1人の新兵を救うために、歴戦の勇士8人が命を懸けなければならない。「人間の生命とは等価値ではないのか?」という不条理な問いが部隊から噴出する。
だが、この映画が真に恐ろしいのは、そのヒューマニズムの裏側に潜む暴力性の肯定だ。それを最も象徴しているのが、物語のラスト、通訳として部隊に同行していたティモシー・アパム伍長(ジェレミー・デイビス)が、捕虜のドイツ兵(通称スチームボート・ウィリー)を射殺するシーン。
戦闘経験もなく、味方が肉弾戦で殺されるのを階段で泣きながら傍観するしかなかった臆病なアパム。彼は常に兵士になりきれない無垢な存在として描かれてきた。
その彼が、最後に自らの意志で引き金を引く。これは一見すると弱者の成長として見ることもできるが、本質的には「戦場という狂気が、人間の無垢を完全に破壊し、暴力に染め上げた瞬間」といえる。
無抵抗の捕虜の処刑は、明確な国際法違反だ。しかし、直前にミラー大尉たちを撃ったのがこのドイツ兵であることを知っている我々は、アパムが引き金を引いた瞬間、頭のどこかで安堵し、カタルシスすら覚えてしまう。
この瞬間我々観客も、スクリーンの中の暴力を完全に肯定し、欲望を共有する“共犯者”へと引きずり込まれる。スピルバーグはこのシーンを単純なヒーローの復讐劇としては描かず、極めて残酷な形で、観客自身の倫理性を試しているのだ。
愛国心とセンチメンタリズムの狭間で輝く、異形の傑作
『E.T.』(1982年)や『ジュラシック・パーク』(1993年)で「無垢な子供の驚異」を描き続けてきた永遠の少年スピルバーグが、老成した映画作家として、アパムの変貌を直視せざるを得なくなった。ここに彼の作家性としての凄みがある。
もちろん、この映画は完璧ではない。「国家のための犠牲」と「家族のための救出」が二重写しになっており、いかにもアメリカ的な星条旗の匂いがプンプン漂う。
スピルバーグ特有の過剰なセンチメンタリズムに、この映画もしっかりと絡め取られている部分は否めない。公開当時、アメリカ国内で「英雄的戦争映画」として熱狂的に支持される一方で、ヨーロッパの批評家から「単なる愛国ポルノだ」と批判の声が上がったのも事実だ。
だが、そんなイデオロギーの矛盾や物語のアンバランスさをすべて力技でねじ伏せてしまうほどの圧倒的映像の暴力が、本作には間違いなく宿っている。批評史的にも、この映画は極めて特異な痕跡を残した。あの気難しい映画批評家・蓮實重彦でさえ、こう自虐的に語っている。
評価を超えて私が(スピルバーグ作品で)一番好きなのは、『プライベート・ライアン』なのです。しかし私たちは、この映画を好きになっていいんでしょうか?(笑)
まさにその通り。倫理的に好きになっていいのか躊躇してしまうほどの、不道徳なまでの映像的快楽。僕もまた蓮實重彦と同じく、この矛盾に満ちた異形の映画を、これからも生涯偏愛し続けることだろう。
- 監督/スティーヴン・スピルバーグ
- 脚本/ロバート・ロダット
- 製作/スティーヴン・スピルバーグ、イアン・ブライス、マーク・ゴードン、ゲイリー・レヴィンソン
- 撮影/ヤヌス・カミンスキー
- 音楽/ジョン・ウィリアムズ
- 編集/マイケル・カーン
- 美術/トーマス・イー・サンダース
- 衣装/ジョアンナ・ジョンストン
- 激突!(1971年/アメリカ)
- 未知との遭遇(1977年/アメリカ)
- レイダース/失われたアーク《聖櫃》(1981年/アメリカ)
- E.T.(1982年/アメリカ)
- オールウェイズ(1989年/アメリカ)
- シンドラーのリスト(1993年/アメリカ)
- ロスト・ワールド/ジュラシック・パーク(1997年/アメリカ)
- プライベート・ライアン(1998年/アメリカ)
- アミスタッド(1998年/アメリカ)
- A.I.(2001年/アメリカ)
- キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン(2002年/アメリカ)
- マイノリティ・リポート(2002年/アメリカ)
- ターミナル(2004年/アメリカ)
- 宇宙戦争(2005年/アメリカ)
- ミュンヘン(2005年/アメリカ)
- インディ・ジョーンズ/クリスタル・スカルの王国(2008年/アメリカ)
- 戦火の馬(2011年/アメリカ)
- タンタンの冒険 ユニコーン号の秘密(2011年/アメリカ)
- リンカーン(2012年/アメリカ)
- レディ・プレイヤー1(2018年/アメリカ)
- ウエスト・サイド・ストーリー(2021年/アメリカ)
- フェイブルマンズ(2022年/アメリカ)
![プライベート・ライアン/スティーヴン・スピルバーグ[DVD]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/71t8MElgPaL._AC_SL1250_-e1759233383404.jpg)