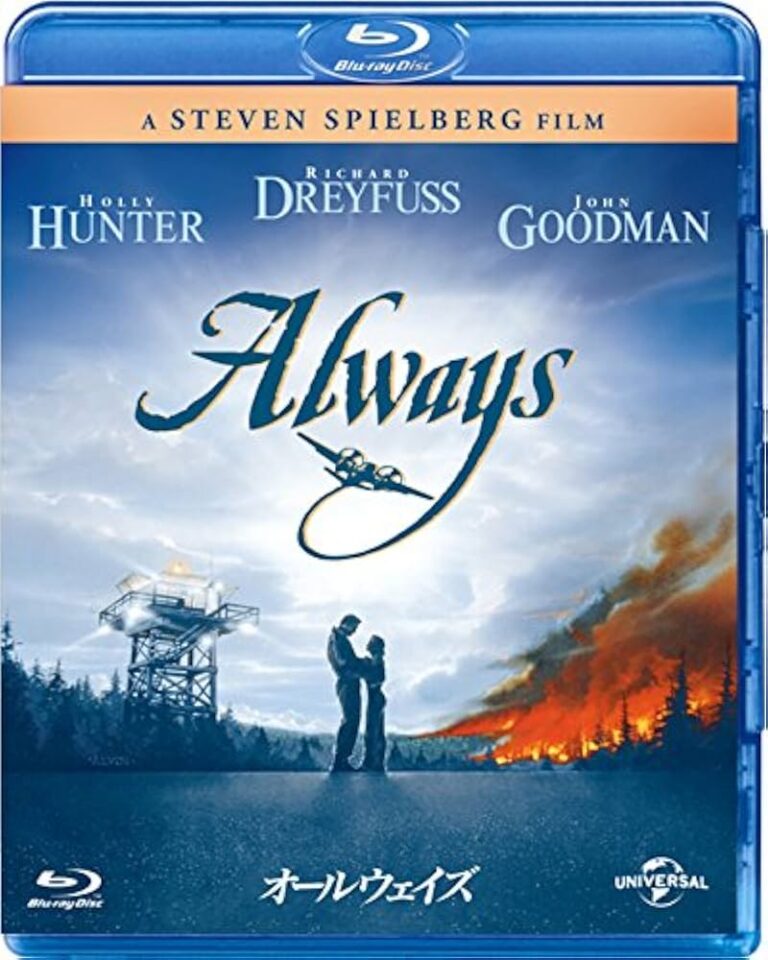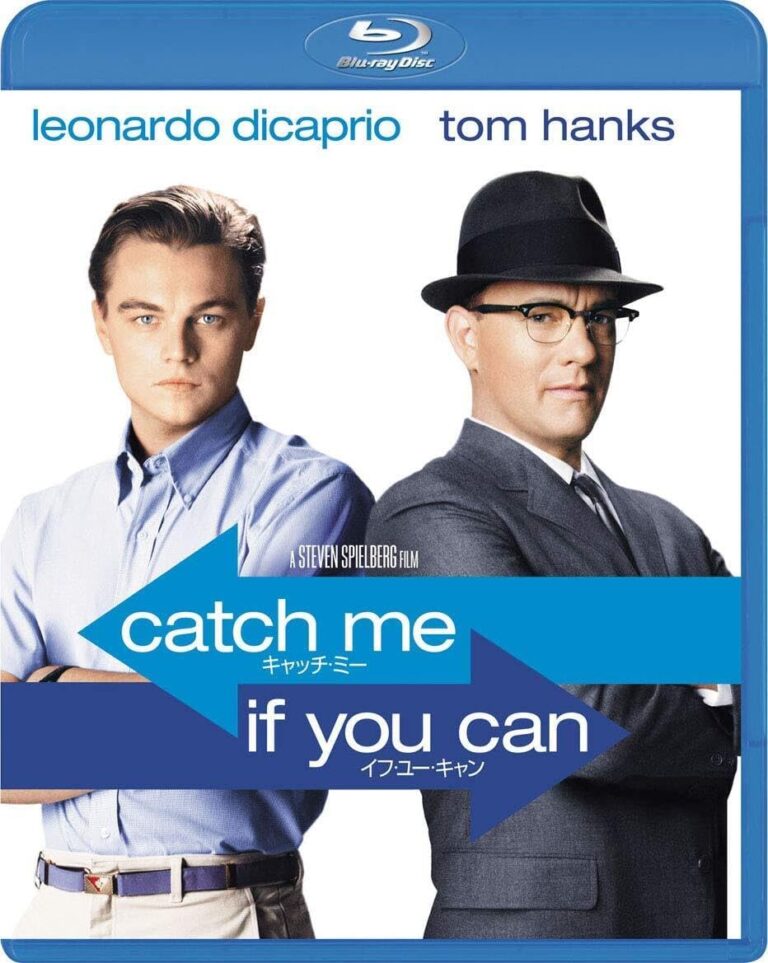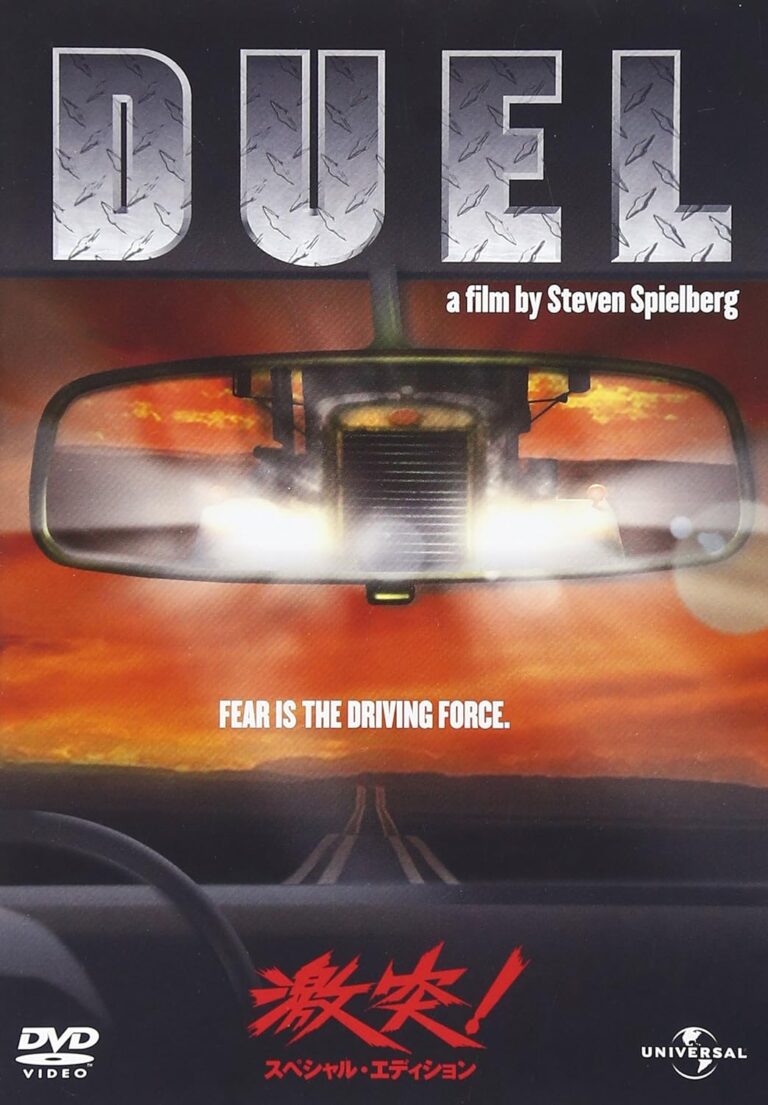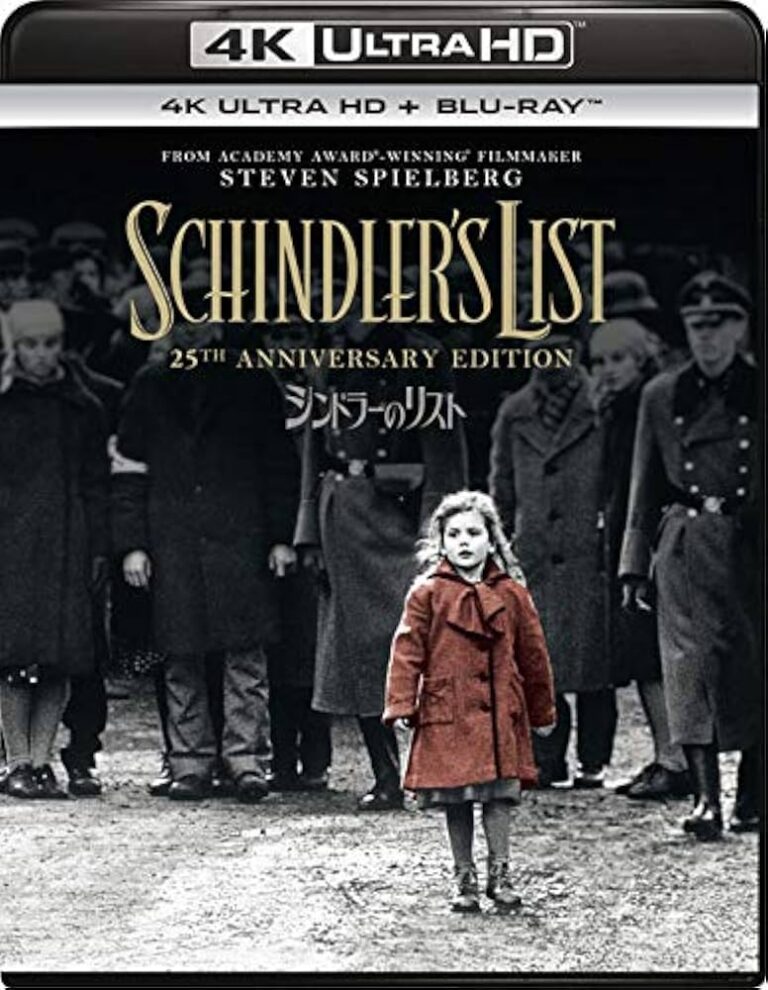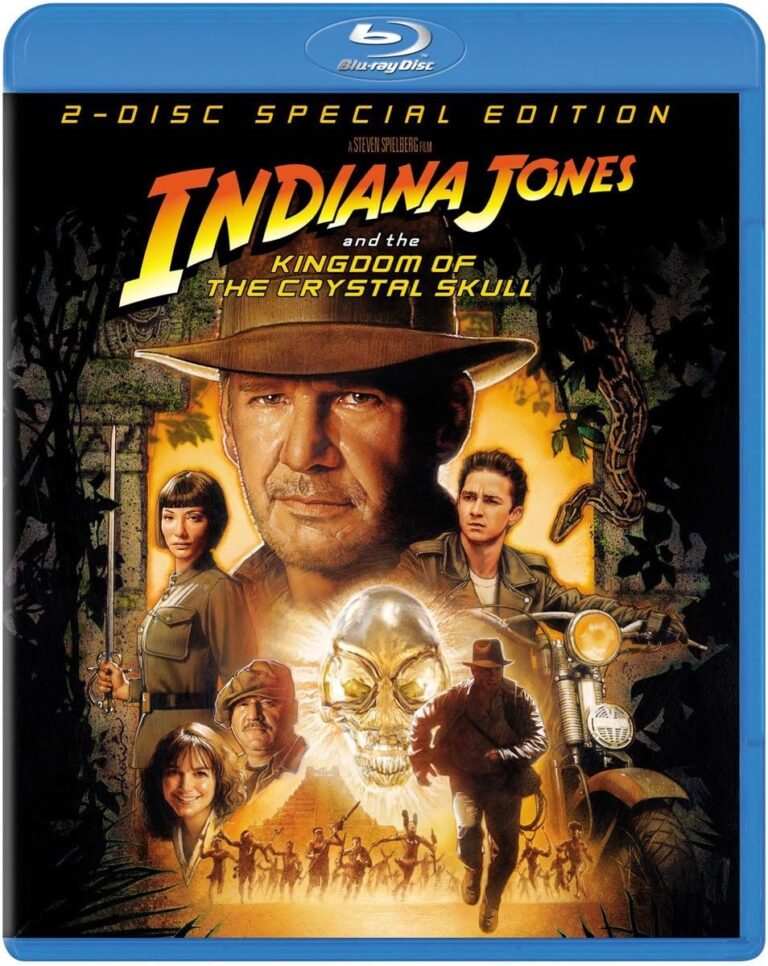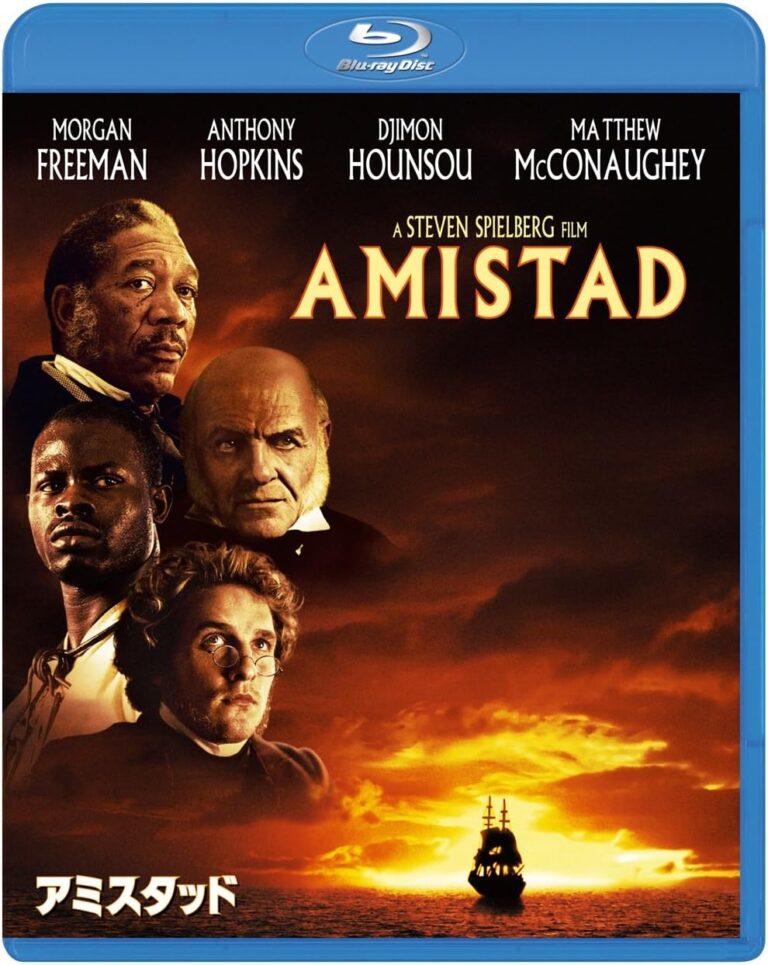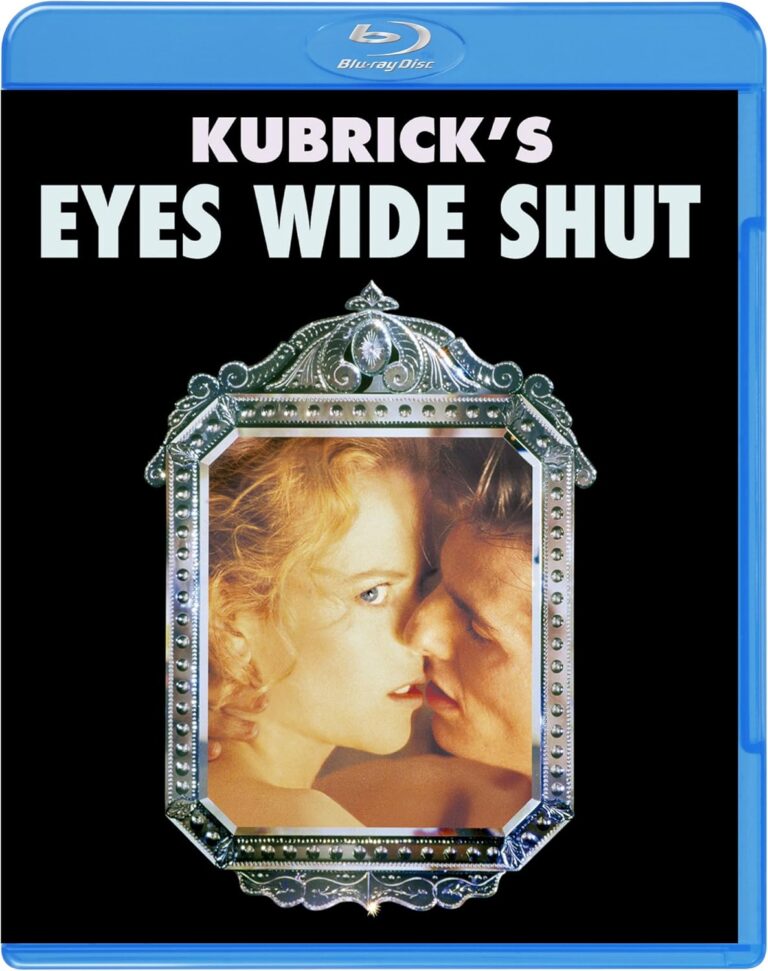『宇宙戦争』(2005)
映画考察・解説・レビュー
『宇宙戦争』(原題:War of the Worlds/2005年)は、スティーヴン・スピルバーグがH・G・ウェルズの同名古典SF小説を再映画化した作品。アメリカ東海岸を襲う謎の宇宙生命体の侵略により、父レイ(トム・クルーズ)は子どもたちを連れて逃走を始める。地中から出現するトライポッドが街を焼き尽くし、崩壊する都市で人々は恐怖と混乱の中を彷徨う。第78回アカデミー賞で音響編集賞ほか3部門にノミネートされた。
9.11の視覚的引用と衣服のホロコースト
『宇宙戦争』(2005年)は、ハリウッド史上もっとも不謹慎かつ純粋な破壊の記録である。
監督はスティーヴン・スピルバーグ、主演はトム・クルーズ。この黄金コンビが組んで、H.G.ウェルズの古典SFを映画化する。誰もが『E.T.』( 1982年)のような心温まる交流か、『未知との遭遇』(1977年)のような知的興奮、あるいは『インデペンデンス・デイ』(1996年)のような愛国的な勝利を期待しただろう。
だが、スピルバーグが我々に突きつけたのは、そんな甘っちょろい希望ではない。それは、「人間がゴミのように掃除される光景」であり、9.11の同時多発テロで世界が目撃したトラウマ映像を、宇宙人侵略というフィルターを通して再現した悪夢のテーマパークだったのだ。
なぜスピルバーグは、あえてこの時期に襲来を描いたのか?なぜトム・クルーズは一度も戦わないのか?そこには、思想よりも絵面を優先する、映画少年のまま大人になった怪物のごとき“職人としての狂気”が潜んでいる。
地中から巨大な三脚歩行兵器(トライポッド)が出現する、物語の序盤。群衆が見守る中、トライポッドは奇怪な音を立て、熱線を発射。次の瞬間、撃たれた人間は一瞬にして灰になり、着ていた衣服だけがハラハラと地面に落ちる。
この描写を見て、背筋が凍らなかった者はいないだろう。肉体が消滅し、物質としての服だけが残る。このビジュアルが喚起するのは、明らかに二つの歴史的悲劇だ。
一つは、ナチスの強制収容所に積み上げられた衣服の山(スピルバーグ自身の『シンドラーのリスト』)。 そしてもう一つは、2001年9月11日、崩れ落ちるワールドトレードセンターから降り注いだ灰と、行方不明者の帰らぬ遺品だ。
スピルバーグは、この極めてセンシティブで、政治的な文脈を帯びざるを得ないイメージを、あろうことかSF映画の特撮として楽しそうに再現してしまう。
トライポッドが光線を放つたびに、空中に舞う人体粉末のパーティクル。逃げ惑う群衆のパニック。エンパイア・ステート・ビルが崩壊する様を、カメラはまるで最高にクールな見せ場として捉える。
トム・クルーズ演じるレイが、自宅に戻り、鏡を見て呆然とするシーンがある。彼の顔と服には、びっしりと灰が付着している。狂ったように服を脱ぎ、灰を洗い流す。
このシーンの生理的な嫌悪感ったら!ここには、宇宙人への怒りなどというヒロイックな感情が入る余地はない。あるのは、他人の死骸を被って生き延びてしまったという、吐き気を催すほどの罪悪感だけ。
スピルバーグは、アメリカの国家的なトラウマを「癒やし」たのではない。それを最新鋭の映像技術で「再演」し、エンターテインメントとして消費させたのだ。これを不謹慎と言わずして何と言おう?
だが同時に、この残酷なまでの映像への執着こそが、スピルバーグを映画の神たらしめている所以でもある。彼にとって、イデオロギーや倫理は二の次。スピルバーグの無邪気な悪魔性が、画面の隅々から溢れ出している。
72日間の電撃戦と、本物のジャンボ機破壊
この映画の異常性は、その制作プロセスにも表れている。 これほどの超大作でありながら、撮影期間はなんと実質72日間(73日説もあり)。準備から公開まで含めても1年足らずという、ハリウッドの常識を覆す電撃戦で作られているのだ。
スピルバーグは「今、この恐怖を描かなければ鮮度が落ちる」と直感したのだろう。彼は脚本が完走する前から撮影を開始し、現場でのインスピレーションを優先させた。
CGのポストプロダクションを担当したILM(インダストリアル・ライト&マジック)のスタッフは、地獄のような納期に悲鳴を上げたというが、その甲斐あって、画面には作り込まれた重厚さではなく、今そこで起きているようなライブ感が充満している。
その衝動が最も顕著に表れているのが、中盤に登場する飛行機墜落現場。レイたちが隠れた家の外に、墜落したボーイング747の残骸が散乱している。
あれはCGではない。スピルバーグは、退役した本物のボーイング747ジャンボ機を約200万ドル(輸送費込み)で購入し、それをユニバーサル・スタジオの敷地内で、重機を使って実際に破壊して配置したのだ。
CGでやれば安上がりだし、修正も効くはず。そんな常人の理屈は通用しない。彼は本物の鉄の塊が持つ質量と、それが引き裂かれた時の断面の鋭利さを求めた。
セットの中を歩くトム・クルーズの表情が真に迫っているのは、目の前にあるのが作り物の発泡スチロールではなく、本物の航空機の死体だからだ。破壊への投資を惜しまないこの姿勢。スピルバーグは、映画監督である以前に、高級なおもちゃを豪快に壊して遊ぶ、巨大な幼児なのである。
音響設計も忘れてはならない。トライポッドが襲来する前に鳴り響く、あの不気味なサイレン音。「ブォォォォォォン!!」と、腹の底に響くような、霧笛ともチベットのホルンともつかない重低音。
ジョン・ウィリアムズの音楽すら控えめにし、この音を主役に据えたことで、観客はパブロフの犬のように「あの音が聞こえたら死ぬ」という恐怖を刷り込まれる。
この音響設計は、『クローバーフィールド/HAKAISHA』(2008年)や『メッセージ』(2016年)など、後続のSF映画に多大な影響を与えたが、オリジナルの絶望感は別格だ。
トム・クルーズはなぜ、ティム・ロビンスを殺したのか?
本作の主人公レイ(トム・クルーズ)は、ヒーローではない。港湾労働者で、妻と別れ、子供たちからはダメ親父として軽蔑されている。
『インデペンデンス・デイ』のウィル・スミスなら、宇宙人の戦闘機を奪って反撃するだろう。大統領なら感動的な演説をぶつだろう。だが、レイは一度もしない。演説もしない。敬礼もしない。 彼がすることはただ一つ。逃げることだ。
彼は子供の手を引き、他人の車を奪い(ここでの銃を使った脅迫シーンのリアリティ!)、群衆を押しのけて、ひたすら逃げ続ける。圧倒的な科学力を持つ敵に対して、素手や拳銃で立ち向かうのは勇気ではなく、蛮勇だ。
スピルバーグは、徹底したリアリストとして、一般市民ができる唯一の生存戦略を描き切る。ドッジボールでボールを取りに行くのではなく、最後のひとりになるまで逃げ回る。それこそが、現代における最も困難な戦いなのだ。
しかし、その逃避行の中で、唯一レイが一線を超える瞬間がある。地下室での、ティム・ロビンス演じる救急車運転手オグルビーとの対決だ。オグルビーは極限状態でおかしくなり、「地下道を掘って反撃するんだ!」と叫びだす。彼の声が外の宇宙人に聞かれたら、子供たちが殺される。レイは、娘の目を塞ぎ、ドアを閉め、オグルビーを殺害する。
このシーンは、映画全体のトーンの中で奇妙に浮いている。正当防衛とはいえ、殺人の描写があまりに軽いのだ。葛藤の時間も短く、殺害後の後悔も希薄。これはスピルバーグの弱点でもあり、同時に特徴でもある。
彼はサスペンス(バレるかバレないか)の演出には命を懸けるが、その結果生じる倫理的な重み(殺人の罪)には、驚くほど無頓着な時がある。ティム・ロビンスの死は、演出装置として消費されるのみなのだ。
だが、その軽さこそが、この映画の絶望を深めているとも言える。極限状況下では、倫理やモラルなどという高尚なものは瞬時に蒸発し、ただ「生きるか死ぬか」の動物的な選択だけが残るのだと。
ラスト、宇宙人は人間の兵器ではなく、地球上の微生物(病原菌)によって自滅する。「神が創造した最も小さな者たちが救ってくれた」というナレーションで幕を閉じるが、これはハッピーエンドではない。人間は何も勝っていない。ただ、自然の摂理によってたまたま生かされただけだ。
傲慢な人類への皮肉と、無慈悲な神の視点。『宇宙戦争』は、スピルバーグがそのキャリアの頂点で放った、最も高価で、最も絶望的で、そして最高にスリリングな人類敗北の記録なのである。
- 監督/スティーヴン・スピルバーグ
- 脚本/ジョシュ・フリードマン、デヴィッド・コープ
- 製作/キャスリーン・ケネディ、コリン・ウィルソン
- 製作総指揮/ポーラ・ワグナー
- 制作会社/パラマウント・ピクチャーズ、ドリームワークス、アンブリン・エンターテインメント、クルーズ/ワグナー・プロダクションズ
- 原作/H・G・ウェルズ
- 撮影/ヤヌス・カミンスキー
- 音楽/ジョン・ウィリアムズ
- 編集/マイケル・カーン
- 美術/リック・カーター
- 衣装/ジョアンナ・ジョンストン
- SFX/デニス・ミューレン
- 激突!(1971年/アメリカ)
- 未知との遭遇(1977年/アメリカ)
- レイダース/失われたアーク《聖櫃》(1981年/アメリカ)
- E.T.(1982年/アメリカ)
- オールウェイズ(1989年/アメリカ)
- シンドラーのリスト(1993年/アメリカ)
- ロスト・ワールド/ジュラシック・パーク(1997年/アメリカ)
- プライベート・ライアン(1998年/アメリカ)
- アミスタッド(1998年/アメリカ)
- A.I.(2001年/アメリカ)
- キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン(2002年/アメリカ)
- マイノリティ・リポート(2002年/アメリカ)
- ターミナル(2004年/アメリカ)
- 宇宙戦争(2005年/アメリカ)
- ミュンヘン(2005年/アメリカ)
- インディ・ジョーンズ/クリスタル・スカルの王国(2008年/アメリカ)
- 戦火の馬(2011年/アメリカ)
- タンタンの冒険 ユニコーン号の秘密(2011年/アメリカ)
- リンカーン(2012年/アメリカ)
- レディ・プレイヤー1(2018年/アメリカ)
- ウエスト・サイド・ストーリー(2021年/アメリカ)
- フェイブルマンズ(2022年/アメリカ)
![宇宙戦争/スティーヴン・スピルバーグ[DVD]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/717taO6dCrL._AC_SL1192_-e1758178038980.jpg)
![E.T./スティーヴン・スピルバーグ[DVD]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/51YCjb0tLxL._AC_-e1758175514300.jpg)
![メッセージ/ドゥニ・ヴィルヌーヴ[DVD]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/91XrXygp1UL._AC_SL1500_-e1706978428871.jpg)